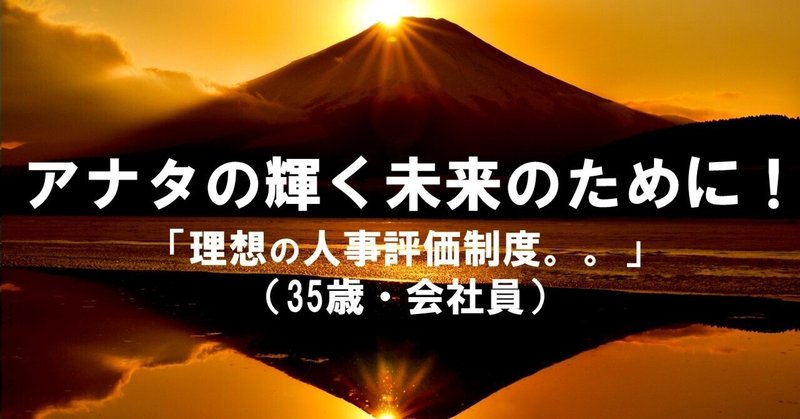
【キャリア相談】理想の人事評価制度(35歳・会社員)
世田谷区にお住いの35歳の会社員Aさんから頂いた相談を紹介します。



会社の評価制度を全面的に見直したいと考えています。
理想の評価制度とはどんな制度なのか、考えをお伺いしたい。
そこで今回はAさんのキャリア相談「理想の評価制度」を頂戴して、
「理想の人事評価制度」を「楽しみに変えるチャンス」にしたいと思います。
【私ならこうする】
組織に勤めた人なら
「人から評価された経験」
「人を評価する経験」
の有る方が多いと思います。
しかし、そもそも「なぜ評価するのか?」
このテーマについて、人事部のご担当者向けに実施するセミナーで
参加者の皆さんにお伺いすると「さまざまな答え」が返ってきます。
対策1 「原点に立ち返る」
例えば(当たり前のことですが)何かを成就させるためには、
目的と目標と手段が明確に定義されていることが必要ですが、
次の質問をすると、殆どの方の答えがバラバラです。
■評価することが何かを達成する為の 「目的」 だとしたら、
その手段は何か? その目標は何か?
■評価することが 「手段」 だとしたら、
その目的は何か? その目標は何か?
「なぜ評価するのか?」について突き詰めて議論されたことが無いまま
評価制度を運営している会社が多い」と言うのが私の実感です。
対策2「魂を宿らせる」
現在 多くの会社で、
「どうすれば社員の成長意欲と貢献意欲を引き出すことができるか」
という課題を抱えています。
この課題を乗り越えようとする時、直面するのは
「人間が抱える悩ましい岩盤志向」です。
それは人が持つ
・短期志向の強さ
・小局志向の強さ
・利己志向の強さ
です。
もし評価に魂を宿らせることが出来て、
評価プロセスを通じて全社員を
・長期視点に立たせる
・大局視点に立たせる
・利他視点に立たせる
ことが出来たら、
会社も社員も比類なく成長し発展することは間違いありません。
では評価制度をどう設計してどう運用すれば、評価に魂が宿るのか?
そして「人間が抱える悩ましい岩盤志向」を突き破れるのか?
ご参考まで、私の大学ノートに記載した私のアイデアを以下紹介します。
タイトルは「魂を宿らせる」です。
【長期視点】
①まず、相手(例えばお客さん)の力になることを考える。
②いやな仕事でもその中から自分の将来にとってプラスになる経験を見つける。
③相手(例えばお客さん)と長期に渡る関係を構築する。
④短期的な利益を追い求める社員より、
上記①②③の長期視点に立って行動している社員の方を高く評価する。
【大局視点】
①ファクトに裏付けられた自分の考えを持つ。
②自分の考えを他の人と共有する。
③②を通じて、誰も気付かなかった新しいパターンやチャンスを見つけ出す。
④目の前の小さな課題だけを追い求める社員より、
上記①②③の大局視点に立って行動している社員の方を高く評価する。
【利他視点】
「大丈夫か?」
「出来ているか?」
「〇〇に気をつけろよ」
を口癖にしているマネジャーより
「ありがとう」
「何か僕に(私に)出来ることある?」
「こんな支援が出来るけどどう?」
を口癖にしているマネジャーの方を高く評価する。
どうでしょうか?
マックス・ウェーバーの官僚制研究
最後に、
マックス・ウェーバーの官僚制研究を踏襲した
ジェリー・ミュラーの研究を紹介します。
彼は「数値では測定できない価値」の中で、
「数値による業績評価がもたらす弊害」を次のように述べています。
・数値で評価できない仕事をやらなくなる。
・数値化が可能な短期的な仕事、リスクの少ない安易な仕事にしか
挑戦しなくなる。
・パフォーマンスは運にも大きく左右されるため、
数値が能力と努力を正しく反映しているとは言えない。
以上の結果、数値による業績評価は
「イノベーションを生まない官僚的組織」と
「やる気を無くした社員」
を生み出す。
ご興味のある方は彼の著書
「測りすぎ―なぜパフォーマンス評価は失敗するのか?」(みすず書房)
をご覧ください。
何かの参考になれば幸いです。
アナタの輝く未来のために!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
