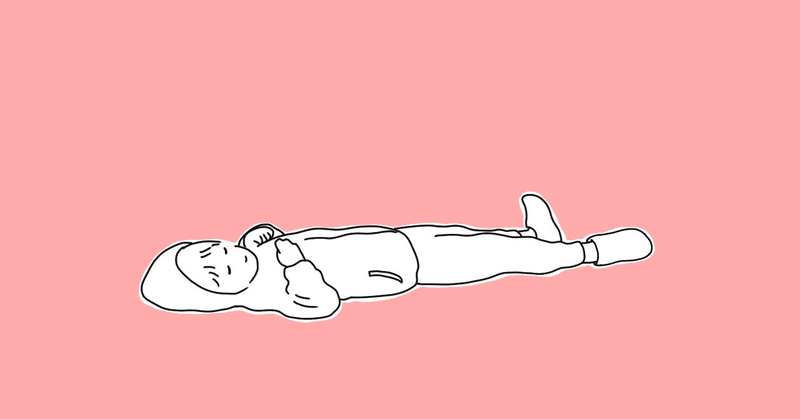
本を読む冊数と、感性という異なる2つの評価軸
乱雑な思考を整理したくて書いた自分語りです。
大学時代の振り返りと、今の課題として。
***
かなり本は読んでいたのだけれど、大学で同じ本を読んだ友人と語り合っている時に、友人の読み方の丁寧さや、独自の視点に立脚した感想の出し方に打ちのめされた事がある。数だけ読んでるだけで、上部を撫でたようなことしか言えなくて、恥ずかしくて本の読み方を変えようと思った事がある。大学3年生の後期の頃だった。
しかも、話す前はその友人のことを心のどこかで自分よりも本も読んでいないし、読解力もないだろうと、無意識に下に見ていた自分の傲慢さのようなものを突きつけられて忸怩たる思いを抱いた。
それまで、大学に入って、勉強している先輩や院生と議論をするときに「そもそも、その分野の必読書はこれだから、これを知ってないと会話が成り立たないよね」みたいなスノビズムに直面して、そんな先輩たちに追いついて意見を出したくて本を修羅のように読んだ時期があって、多分それが関係している。
不恰好ながら当時の自分の努力を擁護するとすれば、すごく雑な例を出すなら、「経済学をやっているのにケインズを知らなかったらそもそも議論の土俵に立てないよね」という価値観に染まりすぎていた。完全には間違えてはいない側面もあるのだろう。
大学に入ったばかりの僕は、ケインズ経済学が主流派経済学になっていった20世紀の不況という歴史的要請や、その中身、現在の経済学はケインジアン的な思想の否定から成り立って派閥が成立していることなど、の基礎知識に欠けていた。
だから、「それすら知らないの」という侮蔑を跳ね除けるために、がむしゃらに会話に出た必読書のリストを使って頭から消化していった。その1〜3年生前期の自分の努力を否定するつもりはない。彼はよく頑張った。
だが、基礎となる知識を丁寧な押さえた上で、自分の意見という(間違っているかもしれないけれど)瑞々しい視点を持たないと、「なら自分と同じ本を読んだAIでいいんじゃない?」ということにもなりかねない。
そして、人がAIと同じ土俵で戦ったら「絶対に」勝てない。
人間同士でも、同じ読んだ冊数など数値化しやすい分野だけで戦うと苦しいことになるのは自明の理だ。
例えば、仕事のパフォーマンスを労働時間で勝負しようとすると、気合という誰もが持つ資源で代替可能なので、チキンレースのように苦しい努力になる。
しかも歳をとって30を過ぎる頃には体力も落ちてくるから、敗退してその土俵から追い出される。
***
論文のようなある程度の分量のあるものを書こうとすると、「何がやりたいか」という瑞々しい視点や、純粋な興味に駆動されたモチベーションが求められるのも大学3年生の後期だった。
大学入学以来、1〜3年生前期まで知識の暗記や吐き出し型のテスト、テーマがかなり限定されたレポートなどでは最高評価以外を取ったことがなかった。
ときどき最高点が発表されるような科目は、決まって自分の点数が最高点だった。
しかし、3年生後期になると、傲慢にも自分よりできないと暗黙のうちに下に見ていた同級生たちが、教授から「面白い!!」と手放しに褒められるような論文を書き始めた。
性根が悪い自分は、ゼミの教授の目の付け所が悪いのだと思い込みたかったが、論文コンテストで彼の論文が旧帝大や早慶など含めた応募者たちの(その中には同じ大学所属のものもあった)を差し置いて圧倒的な1位として褒め称えられたコメントと共に受賞して、ようやく「自分には致命的に重要な何かが欠けている」と気がついた。
ここでようやく気づく時点で、自分の頭すら悪かったのかもしれない。
ゼミの飲み会で、同席したGAFAの役職者から、「モチベーションや瑞々しい感性から意見を出さない人は、課長にすらならない」とダメ出しされたとき、心が折れ掛けた。
日本企業はイエスマンしか出世できないというのは、ある水準の大企業になると嘘だと。流石に落ちたとは言え、世界でも言及されるレベルの企業の役職者に無能はいない。
それはゼミから就職したメンバーを見れば首肯できた。基本的に鳥肌の立つほど優秀な人から順に、確かに納得できる水準の仕事に就いていった。
ただ、モチベーションや瑞々しい感性なんてどうやって出せばいいのだ。僕は困惑した。
鉄緑会でも進研ゼミでも、そんなものは教わらなかったからだ。
知識を暗記して、応用して、吐き出す。
それを繰り返して18までの青春を空費してしたのに、今さらモチベーションや瑞々しい感性なんてなんて体を逆さまに振っても出てくる気がしなかった。
しかし、そんなことを言っても仕方がないから、もしかしたら既に枯れ切ってしまったかもしれない感性を探して4年生の1年間を過ごした。
卒論には間に合わずに、感性やモチベーションとは離れた、つまらないものを書いた。恥ずかしかった。
印象的な事例に着目し、先行研究を丹念に精査し、まだ言及されていなかった視点に着目して、仮説を立て、データを集め、論理を積み重ねる。
今までやってきたことだ。
「レポートとしては満点です。卒論としては零点と言いたい。」
それが卒論の評価だった。
4月から就業して、僕はどのように自らの視点や感性から意見を出せるのだろう。
それとも、すでに枯れ切っているのだろうか。
本当に分からない。暗中模索としている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
