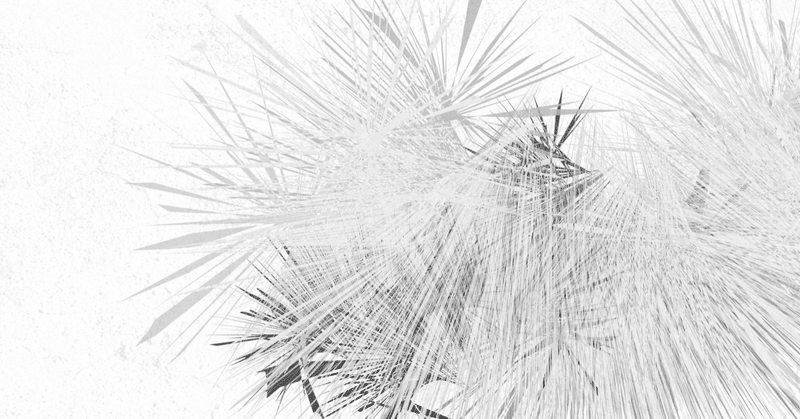記事一覧
ベキネバからの解脱 中世の多進法から学ぶ
中世の多進法中世社会では桝(一合)の容量が一定ではなかったそうです。これって、ちょっとすごいことですよね。一合の量が、あちらとこちらでは違うということ。それって、量れないということですよね。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/sehs/76/4/76_KJ00007943783/_pdf
さらに、十合=一升、十升=一斗と十進法の我々にとってはあたりまえの
動機の言語化4 クネビンフレームワーク
先月「動機の言語化」について書きました。GW後半、下記のフレームワークで、自分の置かれた状況と、これからの方針について考えてみたいと思います。
クネビンフレームワークは、VUCA時代に、ガイドライン通りには対処できない状況における意思決定のツールのひとつと言われています。
軍事領域からビジネス領域に転用され、下記のように臨床心理領域でも活用されているようです。
クネビンフレームワークをみると
動機の言語化3 ChatGPTによる童話
先月「動機の言語化」について書きました。今回は、タイトルにあるようにChatGPT4と対話しながら整理してみたのですが、その中で、童話をつくってもらったので、そちらを記載してみたいと思います。
黎明期のワクワク感何のためにやっているんだっけ? そのために自分は、どう貢献できるんだっけ?
黎明期に身を置くことのワクワク感。世界が変わる場面で、その場にいて、その動きに関わることができるワクワク感。
感覚刺激のシミュレートと解釈のアウトソース ドライビングシミュレーター・能楽・調理
ドライビングゲームの進化FORMULA1 VIDEO GAME EVOLUTION(1979-2023)という動画を見ると、懐かしさと共に、乗り物シミュレーター系ゲームの発展に目を見張ります。俯瞰視点から主観視点への切り替えは、何よりも大きな変化でした。
リアルとリアリティ以前、フェラーリのドライビングシミュレーター等の開発も行っていた某社のゲームクリエイターの方から、次のような話を聞いたこと
動機の言語化2 なぜ、今の仕事をしているのか?
先月「動機の言語化」について書きました。自分は、なぜ、今の仕事をしているのか。かつて、多くの仕事を複数同時並行で進めることを望んでいた自分が、ひとつの仕事に集中するようになったのは、どうしてか。文末に、「日常の業務に身を置きながら、深く自分に潜ってみたい。少し時間をかけてやってみようと思いました。(公開できそうな内容だったら、次回、公開したいと思います)」と書いたこともあり、今回、少し、やってみま
もっとみる習慣化は相性次第 コツコツ続かないのは自分の責任じゃない
生活習慣病生活習慣病という言葉があるように、習慣は、その人の生活そのものを左右するほどの影響力を持っています。
自分を振り返ると、ここ数年で、新しく身につけた習慣がいくつかあります。
フロスとリステリン今では、フロスを使わない歯磨きを考えられないほど、当たり前のものになっています。
口内洗浄液の使用も同様です。自宅にあったリステリンを使い始めたのがきっかけで、毎日使ううちに、なくてはならない
箱は世界を見るツール コンテナとコンテンツ 弁当〜ミイラ〜きゅうり〜人〜世界
『箱男』という小説があります。箱にとりつかれた人の話。箱の中から世界を眺める。そんな話を思い出すきっかけになったのは、TEDxkioichoを通して語られていた箱というキーワード。以前から、コンテナとコンテンツの関係について、さまざまに書いたり事業を構築してきたりした自分としても、とても面白い内容でした。
移動するコンフォートゾーン私たちの日常生活は、「箱」という単純な概念に深く根差しています。