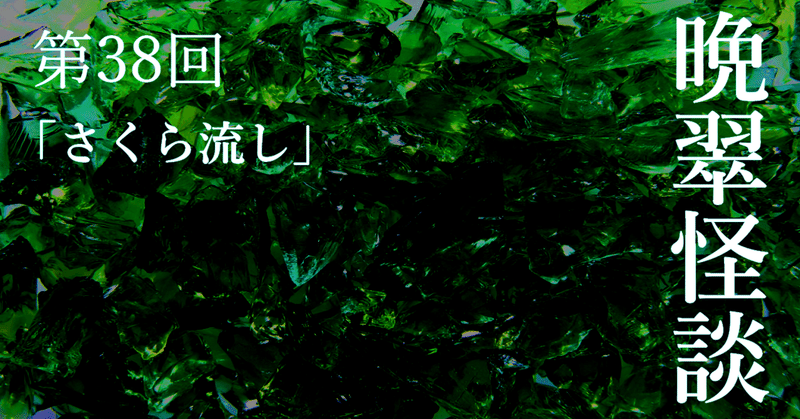
晩翠怪談 第38回 「さくら流し」
■さくら流し
我が家に市松人形が届いて、10日余りが過ぎた。
4日ほど前から人形は、仕事場の祭壇のどまんなかに、でんと構えて座っている。
極めて異様な光景なのだが、これには深いわけがある。
あの後も毎晩、箱の中で人形は動き続けた。魔祓いをかけると一時的に治まるのだが、翌日になれば再び動きだすか、さもなくば魚のボトルキャップに乗り移って暴れた。
本来ならば、一刻も早くどうにかしなければならないことは分かっていた。
けれども昼間の仕事に加え、ゲラの修正作業も忙しく、なかなか時間がとれなかった。さらには連日、人形と夜を過ごしていくうち、基本的には無害な存在と分かったことも、私の行動を遅らせる原因になっていた。
人形が動きだすのは、決まって深夜の一時過ぎだった。昼間は決して動いたりしない。だから昼間、仕事場に相談客が訪れても、業務に支障が出ることはなかった。
人形の行動パターンも限定されていた。箱の中でがさがさ動くか、魚のフィギュアに乗り移って、かたかた音を鳴らすかの2パターンのみである。他には何をするでもない。
実態が把握できると、おのずと危機感も薄まっていった。
人形の始末に締め切りはないが、文筆業には厳粛たる締め切りが存在する。
何を最優先すべきか考えた結果、人形はとりあえず放置ということになった。
そうなると、夜中に聞こえ始める物音がひどく耳障りで、煩わしいものになってきた。祓えば音はたちまち消えるのだが、いちいち立ちあがって箱の前まで行くのも煩わしい。何かいい手はないかと知恵を絞り、思いついたのが人形を箱からだしておくことだった。
あいつは箱の中にいる時だけ、がさがさ音をたてて執拗に動く。
ならば、箱からだしたら動かなくなるのではないかと思ったのだ。
なんの根拠もない実験的な試みだったが、結果は一応成功だった。
拝みの仕事が終わった夕方頃に箱から人形をだし、祭壇のまんなかに座らせたところ、その夜は生気のこもった厭な目で私を見つめるばかりで、微塵も動くことはなかった。
これはいいぞと大喜びし、人形はしばらく祭壇に座らせておくことに決めた。
しかし、祭壇のまんなかに人形をどんと座らせておくのは、さすがにどうかと思った。こんなものが祭壇の真正面に置かれていたら、相談客が怯えること必至である。
昼間は箱の中にしまっておいて、夜になったら祭壇に座らせる。
そうすれば別になんら問題はないのだが、毎晩そんなことをするのも甚だ面倒である。まんなかだったら目立ってしまってよろしくないが、端のほうなら大丈夫ではないか? ふとそう思い、人形を抱きあげて棚の端へと移動させる。
なりが大きいため、端へ行っても人形はそれなりの存在感はあった。
だが、まんなかに陣取っているよりは、だいぶ控えめな印象である。
これぐらいならば、相談客もぎりぎり許容範囲内だろう。勝手に決めつけ、満足する。
と、そこへふいに人形がぐらりとかたむき、前のめりになって倒れた。
すかさず起こして座り直させてみたのだが、数分ほどするとまた勝手に倒れてしまう。座らせ方が悪いのだと思い、微調整もしてみたが、それでも駄目だった。何分か経つと人形は前のめりになって、祭壇からばたりと倒れ落ちてしまう。
なんとなく嫌な予感を覚え、元のまんなかの位置へと座らせてみる。
すると今度は待てど暮らせど、人形はその場に貼りついたように動かなくなった。
祭壇は水平を保っているため、まんなかだろうと端っこだろうと、角度は同じである。端では倒れてまんなかでは倒れないなど、物理的に考えてありえない。
ということはすなわち、斯様な解釈をすることができる。
なるほど。VIP席がいいってわけか。このチビ助め……。
つくづく癇に障る人形である。再び箱にしまって、効きもしない魔祓いを毎晩するか、それとも祭壇のまんなかに座らせて、客から嫌がられるか。どちらか選べというわけだ。一瞬、外に引っ張りだして焚きあげてやりたい衝動に駆られた。
が、すんでのところで思いとどまった。こいつの性質を思いだしたからである。
仮に焼き尽くしてやったところで、それは単なる“外側”だけの焼失になりかねない。こいつは自分の意思で、他の人形に乗り移ることができるのだ。外側の市松人形よりも中に入っている“何か”をどうにかしないことには埒が明かない。
同じ理由で、いっそゴミの日にだしてやろうと考えたこともあったが、これもよした。もしも万が一、捨てられたことを怨んで中身の“何か”だけが我が家に戻ってきたらと思い至るなり、リスクが高過ぎてとても決行する気になどなれなくなった。
ここから先は
よろしければサポートをいただければ幸いです。たくさん応援をいただければ、こちらの更新を含め、紙媒体の新刊を円滑に執筆できる環境も整えることができます。
