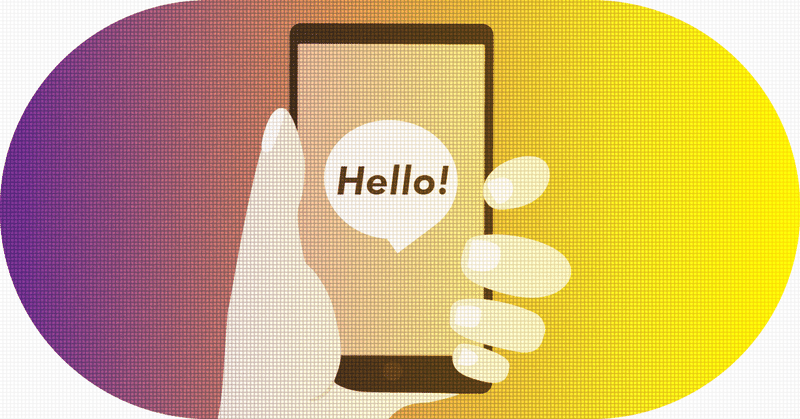
【LIFE】「立ち止まって考えてみる」ことの大切さ~誰もが持つ「三毒」とどう接するか?
タイトルはヤマザキマリさんの著書からお借りしました。私にとってヤマザキさんは「テルマエロマエ」の作者というよりも、思索家とでもいうのでしょうか。多岐にわたる幅広い知識や、異国の地での生活経験を基にした考えがとても興味深く、毎回新作を楽しみにしている読者のひとりです。さて今回は前回同様、新年の幕開けと共に私自身が考える「物事への接し方と受信・発信の仕方」について語ってみたいと思います。
【お断り】以下に関しては、賛同頂けない考え方もあるかもしれません。まずは何卒ご了承ください。もし、不快に感じた場合は、その時点でスキップしてください。ただnoteというフィールドは幅広い意見や考え方を皆さんが発表する場だと思いますので、その点に感謝しつつ、進めていきたいと思います(もちろん、何かしら参考になるようなものでありたいとは思っているのですが・・・)。
まずはケーススタディから
ベストセラー作家の百田尚樹さんがX(旧ツイッター)上で、百田さんに批判的なフォロワーの方から大量のアンチコメントが届いている、という件です。もちろん「表現の自由」の世界ですので、いろいろな意見があることはその自由が保たれているという点では、良いことなのかもしれません。が、ポイントはその後。どうなんでしょう?とても読むに堪えられないようなコメントも多く、その多くが「匿名」なんです。
批判するなら「名」を名乗りましょうよ
多くの著名人がXのみならずインスタ等でも自由に発信する時代になって久しいですが、彼らが実名なのに対して、一般人の投稿の多くが「匿名(ニックネーム)」。プライバシー云々もありますから、致し方ない面もあるのでしょうが、賛同のコメントならともかく、相手に対して「モノを申す」ような内容、さらにはもっと悪質だと「侮辱・侮蔑」するような、そのときの感情だけでまさに「書き殴る」ような表現立ったりする際には、一般人の方であってもそこは「実名勝負」するくらいの覚悟があってもいいのではないか、と思うのですが、どうでしょうか?(ちなみに私は超絶小心者の小物なので、いいねは押しますが、コメントは皆無です・・・笑)。
もっと驚愕なのが、高学歴・著名人による悪意あるコメント
上記までは「著名人VS素人さん」の場合です。まあ、これは著名人側も分かっていて、もっとも多い反応が「無視」。もしくは余裕がある場合には「(ちょっと面白がった)返答」のようなものが多いように見受けられます。(もし私なら内容はどうあれ、著名人から返信を頂けただけで舞い上がってしまいそうですが・・・笑)。
しかし、今日ここでもっと深掘りしたいのが、今回、百田さんを口撃している方々は、素人一般人ではなく、高学歴な学者さんや教授さん、または著名人として一定の地位にいらっしゃる方々だから不思議で仕方ないんです。もはや単なる言い間違いに対する揚げ足取りや、「印象」批判のような内容。現時点で私が最も悪質だと思うのは、百田さんの体調に関する侮蔑。これは本当に失礼極まりないというか、もしご自身がそんなことをされたら、どう思うのでしょうか?相手への配慮が全くなくなってしまっている、しかも繰り返しますが、社会的地位のある高学歴の学者さんや教授さん、著名人たちなのに・・・と残念に思います。
「三毒」の恐ろしさ
ちなみに百田さんはそうした方々へご自身のXで以下のような返答をされています。
「(彼らは)「恨み」「嫉み」「憎悪」が激しすぎるのです、人間、この三つが強すぎると、四六時中、そのことが頭から離れなくなり、心がゆがんで、理性が吹き飛びます。哀れな見本です。」
これを見たときにすぐに連想したのが「三毒」ということばです。この言葉を知ったのは勝間和代さんの著書でした。
勝間和代さんの『三毒追放』とは、もともと仏教用語で「貪・瞋・癡」の3つを三毒として克服するべきものとして指したものです。これを勝間さんは噛み砕いて捉えなおし、三毒をこのように紹介しています。
「妬まない」「怒らない」「愚痴らない」
勝間さんは三毒追放を意識することで『味方が増える』効果を紹介されています。ついついやってしまうこれら三毒は、そのまま妬み、怒り、愚痴として消化してしまうと、毒となるだけですが、そのまま消化せずに、成長のきっかけとする事もできます。
2019年7月3日(Shinya Oishi)より抜粋
(次元は違いますが)私にもちょっとだけ似たようなケースが
百田さんとはレベルが違いすぎて、共通のことのように持ち出すのが恥ずかしいのですが、「三毒」につながるケースが私にも起こったことがあります。
まあ、それがもとで前職と決別したというきっかけにもなったので、自分の中でも未だに(悔しいことに)鮮明に覚えているのですが、もはやそれは「嫉みだろう」という嫉妬心から、針小棒大に些細なことを大事(おおごと)として撒き散らされ、いわゆるネガキャンを張られて、それがもとになって閑職に・・・なんてことがありました(まあ、これは私の見解であり、向こうにはそうではない見解があるわけですが)。
私のケースでは、立場は向こうの方が上役なので、なんで私にそんなに敵意をむき出しにするのか(まあ、私も態度がそれほど上品ではなかったんですけどね・・・笑)、私みたいな小物、放っておけばいいのに・・・って感じでしたけどね。でも、ある種の「狂気」に駆られた時って、先ほど百田さんが書かれているように、もう四六時中そのことが頭から離れなくなっていたんでしょうね、「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」+「水に落ちた犬を叩く」勢いで、それはそれはものすごいキャンペーンを張られましたね。
ま、私の場合、私が一番大事に思ってきた部下や仲間たちはとても結束固く、そんな落ち目な私をずっと支えてくれましたし、私自身はそうした一連のいざこざでほとほと呆れてしまい、会社を去るきっかけとなり、今は新しい地でストレスなく過ごせているので、良かったと言えば良かったのですが、それでも、こうしたケースを目の当たりにしてしまうと、ついついフラッシュバックのように思い出してしまうんですよね。たぶん、これは解消するまでには相当な月日が掛かるのかなと覚悟しています。
話を戻して、「三毒」追放と「立ち止まって考えてみる」ことの大切さ
多分、私がこの話題に強い関心と共感を示したのは、上記のように自分のことがらと重ね合わせてしまったからかもしれません。やっぱり人間、どこまでいっても自分自身の経験が色濃く反映されるのでしょうね。ちなみに百田さん同様にイスラム研究家の飯山陽さんもまた、同じフィールドの研究家の方々から「口撃」を受けているようで、この場合も、本来であれば頭脳明晰の学者さん、教授さんたちなのに、なぜこんなことをするのかな・・・というくらい残念ながらあまりレベルの高くない行動を取られているのが驚きです(まあ、その驚き以上に、飯山さんが全く負けずに反論されている姿が立派すぎるのですが・・・笑)。
まとめ
話がいろいろ飛躍しているように思えるかもしれませんが、ここで前回に続き、こうした分野へのリテラシーを誰もが皆向上させていく必要があることを痛感させられました(もちろん自分への自戒も含め)。さらにどんなに地位が高い方であっても「三毒」への戒めは持つべきですし、これは誰もが罹る病であることを意識しなければならないのでしょうね。
せっかく、その分野で大成された大家でいらっしゃるわけですから、その道で私たちに役立つことを発信されたり、啓蒙活動に使われればよいところを、「三毒」に罹ったがゆえに、残念な結果になっていることは、本当にもったいない。これは現代のSNSがもたらした悲劇というか、これまでベールに隠されてきた部分が明るみになったというか・・・。とにかく誰もが発信者になれる時代だけに、心しなければと改めて考えさせられました。皆さんはどう思われますでしょうか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
