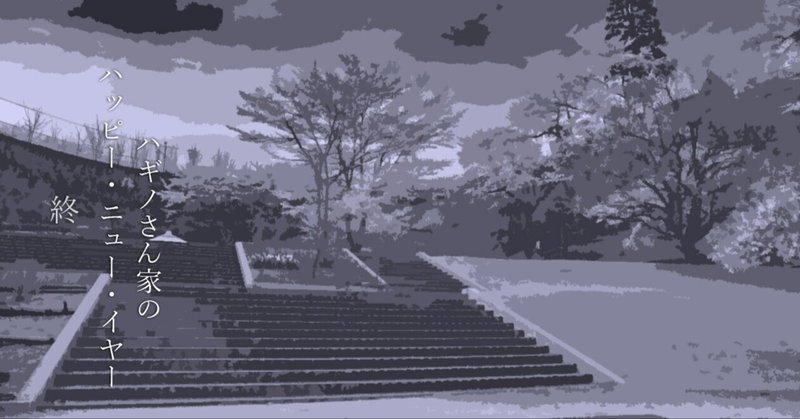記事一覧
【短編小説】カレンダーが赤い日に@3000文字チャレンジ
「エビの尻尾って、先の部分を落とさなきゃいけないんだよ」
油が跳ねちゃうから。得意げに言ったわりには危うげな手つきで、咲幸(さゆき)は尻尾の先端を切り取っていく。俺はふうんと頷き、親指ほどあるエビの背につまようじを突き刺した。
「全部切っちまえよ、面倒くせえな」
「えー、しっぽも食べるでしょ?」
「食わねえよ。そんなゴキブリの羽と同じところ」
咲幸はむっと口を曲げ、おそらく人類最凶の敵を擁
六月九日、深夜二時。浅峰駅にて(終)
下記の続き
「どうして、その呼び方を……」
なだらかな曲線を描いた顎や頬から、女の顔が露わになっていく。
かつて姉だけが使った名前を発する小さな口、薄い唇は百々子とよく似ていた。しかしそれだけだ。
「百々子さんは、そう呼んだのでしょう?」
白んでいく車内で自分を見つめる女は、記憶のどこにも存在したことのない人間だった。
朝の眩しさのせいだけではない、竹串でスッと引いたような目。鼻は
六月九日、深夜二時。浅峰駅にて③
下記の続き
千太郎を取り巻く穏やかな日々は、手を打つ一瞬の間に失われてしまった。さらさらと風に浚われていく砂のように、もう拾い集められはしない。
窓の向こうの千太郎は五歳。
オモチャを手にして、台所の百々子へと近づいていく。当時のブームは両生類や昆虫を模したオモチャで、手を開いたときの母や姉の反応を見たさに、ポケットはいつも物言わぬ生き物たちでいっぱいだった。
音のない映像に、ぐらぐら
六月九日、深夜二時。浅峰駅にて②
下記の続き
声と同時に手にした光は消え、耳障りな軋みとともに電車は入口を塞ぐ。
瞬いても瞬いても黒の世界。
たっぷり二十秒、月明かりの薄闇に目が慣れるころには、心臓も緩やかな鼓動を取り戻しはじめていた。
窓際に座る人影はいつからあったのだろう。
声は、そこから届いたようだ。
「そんなところに立っていないで、こっちへ来たら?」
女の声は友だちを招くよう親しげで、しかしつるりとした