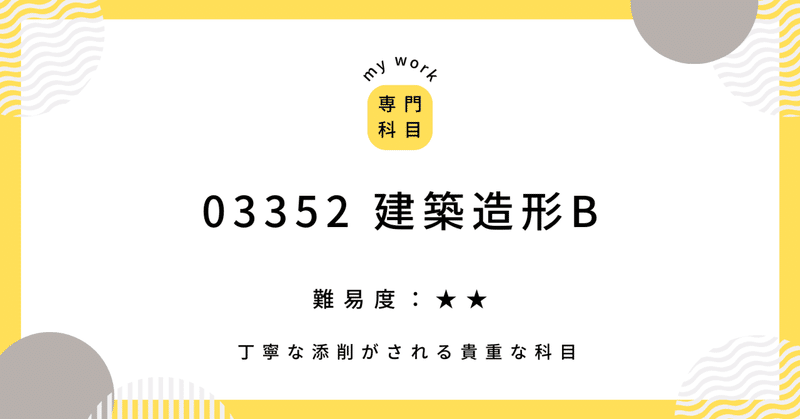
03352 建築造形B
・ソース :教科書〇、参考書×、ネット〇、現地〇
・難易度 :★
・解答作成時間:6時間程度
・オススメ度 :設計課題よりは楽
・先生 :丁寧な添削付き
・返却時間 :1か月長(採点評価)+2か月長(添削)
・ひとこと :しっかりと添削してくれて満足度高い
・課題
自分の好きな建築家の好きな建築を1つ選んで、その設計図を入手し、その図面を元に透視図(もしくはスケッチパース)を作成する。作成にあたっては現地調査を行うことを基本とする。
第1課題 外観透視図(もしくは外観スケッチパース)1枚を陰影・点景を描き込み作成すること
第2課題 内観透視図(もしくは内観スケッチパース)1枚を陰影・点景を描き込み作成すること
各課題ともその建築の持つ思想をもっともよく表す場所および画角(アングル)を選んで透視図を作成すること。また、現地調査では、図面から想像した建築空間が実際にどのような建築空間であるか体験し、図面上の寸法を確認しながら、その空間の大きさを数値的に把握すること。
【課題制作のポイント】
(1)課題では、設計者の意図を一番良く伝える画角(アングル)を選ぶこと。つまり、建築の特質をうまく捉え的確に表現すること。そして、自分がその建築の設計者になった気持ちとなり、熱意を持って制作に取り組むこと。
(2)作成した自分の作品と現実の建築を比較し、その建築が適切に表現できていることを確認してから提出すること。
(3)その建築の持つ空間が伝わるように陰影や素材感や点景を適切に表現すること。
(4)美しくあること。人の気持ちを動かすような作品をつくること。
(5)自分が選んだ建築を多くの人に伝えることを意識すること。そして制作を楽しむこと。
【課題提出の方法および補足事項】
(1)各透視図ともA3サイズのケント紙(もしくはマーメイド等の厚紙)に鉛筆(またはシャープペンシル)にて作図/陰影の描き込みを行う。陰影には濃淡をつけるなど表情をつける。着彩することも可とする。また、画面サイズを活かした画角を選択すること。
(2)各透視図には、点景として必ず人物を記入すること。ただし、その表現手法・数は自由とする。また植栽・外構・家具など、建築空間に含まれる重要な要素はできるかぎり表現すること。
(3)各提出用紙の課題裏面の右下部に「課題名、選んだ建築の名称・設計者・所在地、学籍番号、氏名」を記載し、作成した透視図の画角(アングル)を選んだ理由を選んだ建築の持つ特徴と照らし合わせながら200字程度で記載すること。
(4)透視図を作成する際に使用した図面すべて(平面図・立面図・断面図・矩計図等)をA3サイズにコピーして添付すること。
・提出物
対象建築物は建築デザイン論のために行った豊田市美術館にした。もし近くにあるなら、色んな科目に使えるのでおすすめである。コロナ禍もあって、在学中はほとんど建築巡りをしなかったので、ここしか材料がないのもあるが、全国にある建築物の中でもオススメ上位に入ると思う。正直パースはめんどくさい。なんせ時間がかかる。絵を描くのは嫌いじゃないが、苦手である。年末にやっていたので、短時間で仕上げたい…。写真はたくさん持っていたので、適当に気に入ったものを選んだ。私がやった手順は以下だ。
①写真をA3に拡大して印刷。
②A3のトレペを重ね、拾えるだけたくさんの線をなぞる。(この時に消失点を見つけて、ずれを修正できるとハナマル)
③トレペの裏に濃い鉛筆を書いた線を中心にがーっと塗って、複写カーボンみたいにする
④ケント紙の上に置いて、トレペの線をもう一度なぞって転写する。
⑤うっすらつく線を頼りに書き込んでいき、色付けして完成!
まあ、もしかしたら写真を写したものだと気づかれているかもですが…。写真ってレンズの関係でどうしてもパースが歪むらしいから。
こういうのは、とにかく濃く描く!薄いとマイナスされる。どの科目もスケッチ系は4B以上を使用して描きました。手や周囲が真っ黒になりますが…。白黒よりも、着彩があると加点されるので、色付けはしっかりしました。内観は基本的に真っ白な空間なので、光に色を付け、真っ白な窓も淡い黄色と水色に。
添付した図面は新建築データで入手。寸法が載っていないため、どうしようかと思いましたがそのまま出しました。
・先生からのコメント
「感動、印象」
外観、内観共紙面いっぱいにとてもインパクトのある絵に仕上げています。
「正しい透視図法」
外観が2点透視、内観が1点透視図で描かれています。外観はVP1が遠い位置にあるため一部VPに収束しない線がありましたがバランスは取れています。VP2に関してはさほど遠い位置ではないのですが多くの線が収束していないため整える必要があります。内観はVP、HLがしっかりと設定されていてよい感じです。内観は2階のレベルから見下ろしているため空間が捉えやすい絵になっています。
「スケール感覚」
外観、内観共建物のスケール感がおさえられています。縦横比、奥行き感も違和感なく表しています。点景の人の一部の大きさが正しくないところがありました。人は透視図においてスケール感を補完する定規となりとても重要な役割を持っていますので正確に描きたいところです。
「影や着彩」
陰影がしっかりとつけられていて建物の立体感が出ています。着彩も印象的につけられていて建物の雰囲気や素材感が伝わります。
「点景等」
人や植栽などの点景が適度に描かれていて臨場感のある絵になっています。
「コンセプト、レポート、資料」
建物の特徴を捉えてアングルや表現方法を考えて描いています。
「線、タッチ、アングル、バランス」
とてもいいタッチの線で見やすい絵になっています。輪郭は太く、目時は細くするなど線の太さを変えたり強弱を付けるとさらによくなると思います。アングルは外観は威風堂々とした建物の存在感が出ています。内観は縦長の吹き抜け空間を上から見下ろすことにより空間コンセプトがよく伝わる点がよかったと思います。


年末だったので、生徒も駆け込みで沢山いるのか、評価も講評も時間がかかっていました。
ネットで提出したので、添削データは画像が細長いためか、6個で小分けに。講評も別で1枚ついていました。
添景について、元の写真には人がほとんどいなかったので、人はオリジナル。やっぱりスケール感は感覚で描くのはちょっと駄目でした。それでも、ここまでしっかり添削してくれた先生に感動です。満足度がかなりある分、もっとしっかりやればよかったな~と思います。でも、評価はAだったのでとりあえずヨシ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
