
あいけ式ベストハンドレッド2022:どきどきバニラビート編
※1 2022年12月22日、『すずめの戸締まり』に関して追記
※2 〆鯖さん・コメント欄の方々との対話で進む動画Ver.もよろしければぜひお楽しみください(7時間ありますが……)。このnoteは「私小説あるいはエッセイ」、動画のほうは「トークイベント」という風に、異なるコンテンツとして見れるかと思います。
https://www.youtube.com/live/K_jwDS1h3Qs?feature=share
◆
水音の聞こえる世の果てで羽を休めたいと思った。
目の前よりもあさっての方向ばかり見ていた。にもかかわらず、海の向こうで放たれる砲弾の音も、白昼堂々鳴った二発の銃声も、自分の不安な鼓動に比べればずっと小さく聞こえた。元来の卑屈な性分に輪をかけて、ひどく参った一年間だった。
理由は分かっている。世界が広いことと、人とは決して理解し合えないことを思い知ったからだ。そうして瞬間ごとに打ちのめされ、千鳥足で漂っていたからだ。
偉い人はよく「知ることの喜び」を人々に説く。けれど「知ることの不幸」については誰も教えてくれなかった。諸刃の剣を使うんなら、自分の限界を理解し、欲望の在り方を、感情の切り捨て方を、十全にコントロールしないといけない。一年かけてようやく学んだ。あまりに遅く。
今年はもちろん素晴らしい瞬間だってたくさんあったし、感謝すべき縁もあったし、愛すべき作品に出会うこともできた。
けれど結局はいろんな人やコミュニティに不義理を重ねてしまったし、何のために何をやっているのかもよく分からなくなっていたし、「ちょっとくらい迷走していたほうが楽しいよね」なんていい加減言ってらんないくらいには、さまよっていた。
2023年は一度、刻むべき正常なリズムを、ミニマルな質感を、地に足のついた生の実感を、取り戻す必要がある。さもなくば鳴き喚いていられない。
だから来年はたぶんベストハンドレッドなんてものは書けない。代わりに、と言っては変だけど、もっといろんな人がこういうもの――100じゃなくても、50でも30でも15でも、各々の1年間の物語――を書いたり語ったりしてくれたらいい。そしたら僕は喜び勇んで見に行こうと思う。
んできっともう少しのあいだは楽しくやれる。
◆
ベストハンドレッドとは何か。
その年のベストコンテンツ100個をジャンルレスで選定し、ランキングを作り、それぞれについて自分の価値判断のもとで語り、文脈を紡ぐ営み。
創始者はライター・批評家のさやわか氏。僕の観測の限りでは、他にも批評等の活動をしているDiontum(米原将磨)氏がこれをやっており、今回僕も同じ形式を使って2022年を総括することにした。
当たり前だけれど中身や評価基準は人それぞれに異なる。それに僕は単純にカルチャー批評への関心の歴が浅く、前の2名と比べれば知識量・鑑賞眼ともに著しく不足していると思う。でもそれでもいい、それでもやろうと思ったのだ。
なぜなら動機はいたってシンプル。「時代の流れに掉さす自分(あるいは自分たち)の現在地を知り、なんなら突破口を探すこと」そして「Z世代としての肌感覚を含めて書き残すこと」だから。
ただし、当事者主義的に「ぼくら」を主語にして上の世代に対抗するための世代論をやる気はないし、自分(たち)の好きなものをベタに肯定するために、過剰な言葉や無理筋の理屈を使うつもりもない。そんな隘路は御免こうむる。
とはいえ文中では「Z世代」という言葉を、いささか雑になったとしてもなるべく積極的に用いている。それにも理由がある。
原田曜平『Z世代』や、最近出た竹田ダニエル『世界と私のAtоZ』などのZ世代分析を見ると(後者の本の場合、主に「アメリカの」Z世代、という留保はつけるべきだけど)、Z世代の性質はやはり「デジタルネイティブ」であることに大きく規定されているということらしい。それは実際そうなのだと思う。
ただ、今後生まれてくる人類というのは、それこそ災害や気候変動によるディストピア状況にでもならない限り基本的に「すべてデジタルネイティブ」なわけだから、変な言い方になるけれど、いま「Z世代の特徴」とされているものは別に「Z世代特有のもの」だとは言えなくなるはずだ。だから、概念としての「Z世代」について考えることは今後の人類全体を占うことにも繋がるのではないか。
上記いくつかの試みが成功しているかどうかは、文章を読んで判断していただくしかない。だからランキングそれ自体ではなく、むしろ「語り」の部分こそが重要なのだ、というのは特に強調しておきたい。
さあ。この時代の切れ味はいかほどか。短い旅を始めよう。
◆
始まりませんでした。すいません。「前置きが長くなる」という悪い癖が遺憾なく発揮されていてなんか本当にあれなんだけど、もうちょっとエクスキューズをつけさせてください。
~あいけ式ベストハンドレッド諸注意!~
・コンテンツは「誰かが言及してたやつ」を中心に見たので、チョイス自体にそこまでオリジナリティはないと思います。ていうか前もって断るけども、まあまあ保守的なラインナップだとは思います。(仮に2年後とかに、今回とはまた違った目標設定のもとでやるとすれば、きっと基準も変わるんでしょう)
・基本は「今年スタートのやつか、今年完結したやつ」だけど、厳密には違うのもあるかも(連載中のマンガとか)
・それ別に「コンテンツ」じゃなくない?ってのもあるかも
・音楽はアルバムかEP単位
・基準は「2022年のモードの自分と人類にとって良いと思った」「問題意識に照らして、批評的に意味があると思った」「これは後々のために書き残しておきたいと思った」とかいろいろ混じった総合的な判断
・なので、単純に「良いと思ったかどうか」で選んでるわけでもないです
・同じ理由で、「見たけどランキングに入れてないやつ」も多々ありますが、ランキングに入れてない=良くなかった、ってことでもないです
・ランキングに入れてるやつの中には、やたら文句つけてるやつもあるけど、基本どれも「見てよかったな」と思っているのは前提です。一応は全部おすすめです。その中でのグラデーションの話です
・「これがこんなに順位低いのはおかしい」「あれが入ってないのはおかしい」とかの意見は、カジュアルな関係や会話の中で言われるのは全然いいけど、ガチトーンで言われたら普通に「知らんわ」と返します。何かが不満であれば、あなたが自分のランキングや批評を作ればいいのです。簡単です
・2023年は燃え尽きてる予定ですが、いろいろ考えを深めたいとは思うので、このランキングを見て、後学のために良さそうな本やコンテンツがもしあれば優しく教えていただけると嬉しいです
・あと単に情報の間違いとか、「この文脈でいくならこう考えたほうがいいよ」みたいなアドバイスがあれば、教えていただけると大変ありがたいです
・今更だけど別にサブカルとか全然詳しくないので、そういうのは期待しないでください
……という次第です。ご理解の程よろしくお願いします。では、ゆるゆる、ぼちぼち、始めていきましょう。
100位 仮面ライダーBLACK SUN(ドラマ、Amazon Prime Video)

人間と怪人、差別と共存みたいなテーマのやつ。『BLACK』のリメイク。今の日本のリベラルの現在地を端的に体現してしまっている悩ましいコンテンツ。「お、おう……」感がほとばしる。
まず、平成2期=『仮面ライダーW』以降の(『電王』のノリをさらに推し進めたような)「ポップな仮面ライダー」のノリについていけず、宇宙キターとか言い出した『フォーゼ』あたりでほぼ脱落した人間としては、この手の「シリアスな仮面ライダー」はとりあえず観ることになっている。実際個別のカットやキャラデザについては面白いものはあるし、俳優も良いし、いまの時流でポリティカルな要素を入れること自体も日本のコンテンツとしてはチャレンジングだと思う。
けれど、左翼運動とアメリカ的人種差別という別種の要素を変に重ねてあるために問題系がよく分からなくなっているのをはじめ、差別や共生や「無敵の人」問題についてあまり真面目に考えていなさそうな紋切り型のTwitterリベラル感が全体的に拭えない。ていうか、複雑な問題をエンタメとしてうまく扱った『仮面ライダー555』を観て育った世代にこれをお出しされても困るんだ。同じ白石和彌監督作品なら『孤狼の血』のほうがちゃんとしてる。
何よりも、人間はかっこいいヒーローが単に戦っていればそれだけでテンションが上がるわけではない、と思った。我々がヒーロー物で感動する理由は、なぜ変身するのか?なぜ戦うのか?という人間的な葛藤と決断(『クウガ』2話)、あるいはウルトラマン的な未知の超越性のかっこよさ(『アギト』1話のアギト登場シーン)、大別すればこの2種類だと思う。前者ならキャラがよく描けている必要があるし、後者なら演出がしっかりかっこよくないといけない。『BLACK SUN』はどちらも中途半端だった。
とはいえ『アマゾンズ』よりも描ける内容の幅を広げられる方向にはなってきたと思うので、そろそろいい感じのシリアスな仮面ライダーに期待したい。頼む。ほんとに。まじで。
99位 タコピーの原罪/タイザン5(マンガ、少年ジャンプ+)

https://shonenjumpplus.com/episode/3269754496638370192
いじめ問題+家族+ループ物。SNSでなんかすごいバズってたやつ。
2022年は『少年ジャンプ』編集部に対する今までの忠誠心がそれなりに揺らいだ一年だった。本誌だと冨樫義博オマージュが変な方向性で発揮されてきて以降失速してる『呪術廻戦』なんかを見ていてもそうだし、『ルリドラゴン』もああいう感じだし、Webの『ジャンプ+』にしても、媒体として自分に親和性の高いものではないなと明確に思った。読み味がつねにこちらの想定を超えてこず、小さくまとまる印象がどれも共通している(『推しの子』とか例外はある)。
で、同じことを『タコピー』にも感じてしまった。一般的には「尖ってる」とか言われうる作品かもしれないけど、90年代の連続ドラマくらいのちょうどいい「しんどさ」消費、キャラの関係性のドラマを中心に据えつつループ要素を取り入れたことによるちょうどいい「考察」可能性、みたいなものばかりが感じ取れてまあ響かなかった。構図とか技術的には上手いから全然読めちゃうんだけども。
たぶん『まどマギ』の遠い影響なんだと思うけど、これとか『ちいかわ』とか、イノセントな「かわいい」概念を露悪的に用いればバズりますよ~と考えている悪い大人たちから我々は「かわいい」を奪還しなきゃいけないと思う。
(ちなみにこの99位は『SPY×FAMILY』のアニメを入れようか?とも迷ったけど、結局タコピーもスパイファミリーも「かわいいキャラを都合よく利用しつつSNSバズを狙う+保守的っぽい家族観が根底にあるコンテンツ」って意味では同じなので、どっちでもいい)
98位 ONE PIECE FILM RED(映画)

『アナと雪の女王』あたりから『ボヘミアン・ラプソディ』『君の名は。』『竜とそばかすの姫』を経た流れにある、音楽的要素を大きなフックとして魅せるタイプの映画。
既出の原作のストーリーを完全になぞる『鬼滅の刃 無限列車編』の大ヒットとかを考えても分かるように、「ストーリー展開云々よりも体験として楽しいのだ」というのはサブスクリプション全盛の今あえて映画館まで足を運ぶ大きな理由のひとつになっていて、今作はそれを律義にやり通している。なのでAdoが好きな人は観ても良いと思う。実際Adoは良かった。
というわけでストーリーは別に面白くない。おおよそ「社会のこととか知らないで歌ばっかり歌ってるとまずい!ドフラミンゴみたく新聞とか読もうね!」という映画です。しかし「夢vs現実」という対立構造自体、ルフィ=葛藤しない主人公の性質上うまく機能していないし、ウタというキャラ自体が文字通りあまりにも「歌の力」のみによって駆動されており、「海賊って悪でしょ?」という面白そうな論点もなんか有耶無耶になっていった。
全体的に演出下手かよ!というのも大いに惜しい。そもそも『ONE PIECE』の原作自体が歌舞伎を参照したヤクザ物の精神を継承しているのに、今作みたいな映画作品では歌舞伎の見栄やタメの要素(マンガと違って映像には見開きがない分、そういうやつ必要だと思うんだけど)を全然取り入れないことに驚いた。ルフィもさあ「ギア4」とかはちゃんといちいち口に出して言ってよ。そういうの大事だよ。
バトルについては、ゾロとかが一つずつ右腕なんかを潰してくのは良かったけど、要はキャラがいすぎる上、「それぞれのキャラに何ができるか」が明確じゃないがためにゲーム的な攻略感とかはなく、「ジャンプ作品の映画ってこういうぼんやりした力任せのクライマックスになりがちよね」という感想になった。その点『ヒロアカ』の映画2作目は緊張感をちゃんと出していて、本当に頑張っていたと思う。名作。プルスウルトラ!
97位 皆既月食(天体)
月食の日、多くの人がSNSに月の写真を上げていたわりには各々の感情も見えてこず、月を評する言葉や歌が添えられるでもなく、全体的に意味が分からなかった。エモーションもユーモアも批評も乗っけない、図像とリアリズムだけのSNSなんて無味乾燥じゃん。月食自体も、別に悪くはないけど普通に考えていつもの月のほうが綺麗だと思う。
そもそも平安時代の半ばまでは「月見」という行為自体が忌むべきものとされていたわけで、美しさとそれゆえの恐ろしさ、そして『竹取物語』の時点で前景化されていたアウタースペース的超越性、これら3つを同時に喚起するアンビバレントな存在感こそが月を風流物たらしめてきたんだし、月食なんて「恐れ」を呼び起こす最たる現象だった(西行にそういう歌がある)。しかしすべてがフラットな記号やイベントとして消費される現代という時代には、月でさえも抗えない。
ただ、僕が最も気に食わなかったのはじつはそこではなくて、端的に言えば月というのは「誰かと一緒に見るもの」ではないと思う。だから好意を寄せる他者と一緒に見ることが前提になっている「月が綺麗ですね」的パラダイムにも乗れないし、そこからロマンティシズムの成分を抜きにしたSNSのお祭り的消費に関しても同様になる。
元より月は「誰か」との空間的・時間的な疑似同期の感覚を生み出すモチーフとして連綿と歌い継がれてきた。とはいえ、たとえばポルノグラフィティの詞は「そもそも月が見えないこと」、あるいは「見えたとしてもそれが同じ像を結びはせず、人によってズレを生んでしまうこと」を重視しているし、今やそちらのほうが意味のあるものだと思う。
また近代に遡れば、夏目漱石は「月が綺麗ですね」なんて三文小説じみた言葉を残しちゃいないどころか(このページを参照)、小説作品の中ではむしろ「逡巡を経たあとのカラッとした明るい心情」を描くときに月を用いることが多い。そのときも別に主人公が「誰か」と一緒に見ているわけではない。月はただ単にそこにある。
ただ単にそこにあるものを、愛でるでもなく、内輪の誰かとシェアするのでもなく、愛の不可能性、シェアの不可能性にこそ思いを馳せる態度。それを経由する以外に今、批評的な考え方を成り立たせる道なんてあるだろうか。
96位 ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス(映画)

ドクターストレンジと謎の力を持つ少女が、家族を失って闇堕ち魔女になったワンダと戦う話。
マーベル・シネマティック・ユニバース(以下MCU)において監督の作家性が強く発揮されるのは、基本的には好ましいと思っている。今作もサム・ライミ作品としてはスリリングな演出が楽しかったし、マルチバースのサイケデリックな演出もまあ良かったし、ワンダも美しかった。
ただしキャラ物としての消費をそもそも要請されているシリーズである以上、客はキャラの扱いに関して以下のシンプルな文句を言う権利があると思う。すなわち「ワンダがかわいそうだ」と。
この作品ではワンダの喪失体験がストレンジの失恋と重ねられ、ともに「乗り越えるべきもの」として描かれるんだけど、ワンダの姿自体を批評的に描き出した『ワンダビジョン』を経るとなおさら、どう考えても重みが違うだろ!と感じる。ここでまずワンダのほうを応援したくなる。
それにストレンジはキャラとして何らかの象徴性を背負うことができていないので(アイアンマンにおける西海岸的な起業家精神、キャプテンアメリカにおける国家的正義のような)、ストレンジとワンダの明暗を分けた分水嶺とかについて思いを巡らせることも難しい。だから単なる内輪バトルだなあと思いながら観ることになる。
ブラック・ウィドウ=ナターシャが自己犠牲で死を遂げたことから始まって、『エターナルズ』では有害な男性性を象徴するキャラが安直に太陽に突っ込んで自害したり、『シーハルク』では「ヒーローではなく働く女性である」ことを強調しすぎるあまり逆にステロタイプなキャリアウーマン系女性の描き方になっていたこと含めて、少なくとも僕は「MCUは男性性や女性性のことをまじめに考えようとはしてないのかもな」と残念に思ってしまった。映画自体は面白いのに。。
95位 NOPE/ノープ(映画)

空中版『未知との遭遇』『ジョーズ』みたいな話。ジョーダン・ピールは作品に社会批評性を入れる人で、『NOPE』も多分に漏れず考察記事とかを書きやすそうな意味性に満ちていたんだけど、思ってた以上にちゃんとバカみたいな映像的スペクタクルをやってくれていたので良かった。役者もいい感じ。変な映画ではあるのでカタルシス感とかは薄いけど、退屈しない映像にはなっていた。
映画ファン界隈を見ていると、「これは傑作!絶対IMAXで観るべき!!」みたいな薦め方をする人が多かったのは気になった。いや知らんわ、と思ったので通常上映で観た。「IMAXでこそ本領発揮」みたいな作り方って、僕には技術に胡坐をかいてるようにしか思えない。
あと批評界隈では「この作品は“見る”という行為自体の暴力性を、映画の歴史を参照しながらメタ的に指摘しており」云々という論じ方をする人が多く、なぜそんなに定型のパターンばかりで踊りたがるのかが不明だった。去年出た小説の町屋良平『ほんのこども』とかもだけど、なんかそういう不幸な作品ってあるよね(なお『ほんのこども』よりは『NOPE』のが全然おもろい)。
94位 ユーフォリア/EUPHORIA シーズン2(ドラマ、HBO)
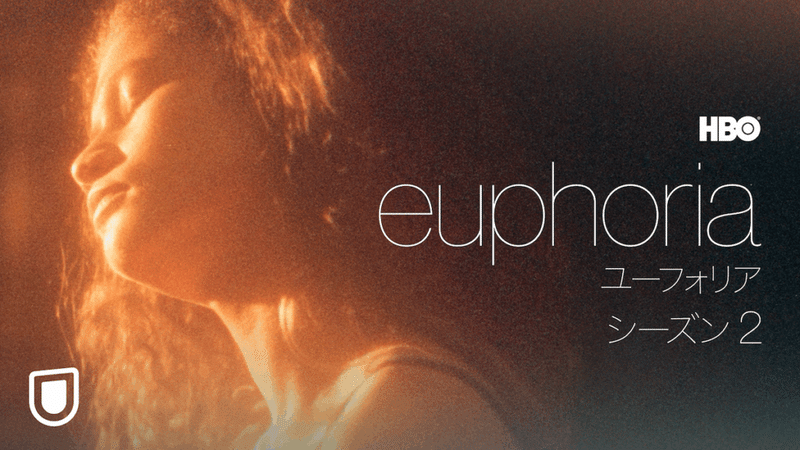
鬱とか薬物とかSNSとかいろんな問題を抱えるZ世代の生活を、主にしんどい感じで(時にコミカルに)描くドラマ。アメリカではかなり人気らしい。
シーズン1は派手な色のライトを積極的に使ったり、音楽もMVのワンカットみたくなってるシーンも多く、その掴みどころのない謎の突飛さ(それ自体がZ世代的な作りってことなんだろうか)にチューニングを合わせるのになかなか苦労したけど、シーズン2は普通にコミカルなポップ感と物語性が分かりやすくなったので観やすい。
シーズン2に関してはアメリカでは「ネットミーム狙いすぎ」的な批判もあるらしく、実際ゼンデイヤの演技も過剰になっていて、これも「しんどさ」消費じゃんと言われたらまあそうかもしれない。でも露悪的な印象をそこまで受けないのが不思議。日本のコンテンツの湿っぽさとは何かが違うんだけど、何だろう。
93位 THE BATMAN-ザ・バットマン-(映画)

3時間。長い。しかも画面がずっと暗い。そしてバットマンは弱く、憂いを帯びた彫りの深い顔がちょくちょく映り、最後には悪を倒すとかじゃなくて普通の災害ボランティアみたいなことを始める。どんな映画やねん。
でも退屈ながら、そこそこ色々面白くはある。公式も「エモい」というワードを前面に押し出してSNSプロモーションをしていたように、メロドラマ的にムードを醸し出すような作りにはなっていて、話の運び、道具立て、キャラ、フィルムノワール的演出も含めて「今時それ?」という要素の集積でできていたところがハードボイルド物としてはむしろ良かった。配信でダラダラ流し観をするのに意外と向いているかもしれない。
災害ボランティア問題については、「ヒーローが敵を倒す」という暴力に正当な意味付けを与えることについて今みんな苦労しているんだなあと感じた。冷静に考えれば暴力が良くないのなんて当たり前なので、そこはフィクションですよ、メタファーですよということで突破すればいいと思うんだけど、それができないくらいフィクションがリアルと切り離せなくなっているところに現代のヒーロー物の困難がある。
92位 ゲルハルト・リヒター展(美術)
リヒターは、写真との関係性の中で「絵画」というメディアに何ができるか?ということでフォトペインティングとか色々やってる人。展示自体はオーソドックスな内容。
リヒターの技術の妙は百も承知の上で、全体としては、ひとことで言えば「異常空間」感が足りなかった。あくまでも『美術手帖』的な整い方(客層的にそれが正しいんだろうけど)。
20世紀的なメディウム・スペシフィシティを問うたオブジェクト群に対して人々が真面目な顔で向き合っている様子自体はなかなか面白かったけども、ホロコーストの問題系を扱った「ビルケナウ」はじめ、リヒターの作品はコンセプトから手法まで「観客側が頭で考えてしまう」ことができるものなので、むしろ我々の思考を止めさせてくれるだけの圧みたいなものを演出して欲しかった。異常な過密感、もしくは逆にセカイ系的な過疎感があれば個人的にはよりグッときた可能性がある。
その点、森美術館のChim↑pom展のほうが(あれもあれで頭で図式的に理解できてしまうタイプの作品も多いとはいえ)Z世代に届くインスタ映え的な見せ方をちゃんとやりつつ、言葉を超えるやばさみたいなものは表現できていたと思う。
これはでも最終的には、単に世代の問題かもしれないし、僕が「20世紀じゃん」と思っちゃった時点で感性が働かなくなっただけかもしれない。「頭で考えてしまう」とか言ってないでもっと普通に見ろや、と言われたらそれはその通りです。
91位 セブンイレブン「アンデイコ メロンクリームソーダアイスバー」(スイーツ)
昨今は最早ブームでもなかろうけど、エモと結びついた「昭和レトロ」ブームみたいな文脈で出てきたと思われるやつ。
「これがあればわざわざポッピングシャワーのためにサーティワン行く必要がなくなる……ってコト!?」と思って食べたら、普通にポッピングシャワーのほうがおいしかった。ポッピングシャワーの本質は別にあのパチパチだけじゃなく、半分はアイスクリーム自体の食感なんだなと学びました。あと所詮コンビニスイーツは期間限定なのですぐに消えた。所詮やつらはそういうやつらですよ。
あと似た事例として、今年は近所の中華料理屋で食べたオムライスがなかなか衝撃的だった。
オムライスといえば、下北沢や表参道などでは「卵ふわふわで何ならスフレが最強」みたいな謎のマーケティング的価値観が横行しているわけだが、その近所のやつは「いや卵とかどうでもいいんで」という渋い雰囲気を出しながらうっっすい卵を纏い、しかしケチャップライスがやたら美味いのだ。つまりオムライスの本質は実はライスにあるのだと喝破している。
僕は今のところ「食」に対してまったく敏感な人間ではないけど、なんかいろいろ文脈を学んだらこれも面白いんだろうなー。と思った。今年は食生活も残念な感じになりがちだったから、来年はおいしいお店に行きたい。
90位 ちむどんどん(ドラマ、NHK)
沖縄出身の黒島結菜(アシガールの人)が料理人を目指す朝ドラ。元気のいい女性の自立の話としてはわりと普通。
男キャラがダメな男性性を普段の朝ドラ以上に発揮しまくるところにはやや現代的な特徴があり、宮沢氷魚の「一見女性の主体性を尊重しているが実際には単に責任逃れしている男」の雰囲気とか上手くて、男性としての我が身を顧みる機会をちゃんともらえるくらいの作品ではあった。
現象としては、Twitterの「#ちむどんどん反省会」ハッシュタグがトレンド入りした挙句に流行語大賞にノミネートされていたのが印象的(反省会タグ自体はちむどんどん以前からあった)。『あまちゃん』以降、朝ドラは明らかにSNSとのインタラクションによって「朝ドラクラスタ」を作ることで高い人気を保ってきたので、しょうがないといえばしょうがないんだけど、反省会タグがこんな目立つのは単純に感じ悪いなあと思った。
で、その反省会タグで観測される意見っていうのも、「時代考証が違う」みたいなやつの他には「朝からこんな、他人の都合を考えず非常識なことをするキャラを見たくない」とかが多いんですよ。つまり倫理的な論難。みんな2010年代的なポリコレを完全に内面化した結果、PTAみたいなことを言い出している。
確かに主人公は単なるワガママ少女みたくなってて、制作陣は有村架純の『ひよっこ』を100回くらい観てくれとは思ったけど、そもそも朝ドラは作品ごとにリアリティラインが違っていることが忘れられている。
要はSNSの人たちは「リアル志向で、倫理的に良いもの」を求めてるだけなのだ。たとえば近年なら『スカーレット』や『カムカムエヴリバディ』のような、ある程度リアルで繊細で、心情をじっくりと深く描くような文学性の高いやつ。でも『ちむどんどん』は序盤から上記のような作品とは違って「これはまんが・アニメ的なものですよ」という演出をちゃんとしている。ちゃんとしてるんだから視聴者側も対応してあげてもいいじゃん、と思う。
余談だけど、いま放送中の『舞いあがれ!』の脚本家交代がSNSで不評だったのを見て、反省会タグの意見は無であると確信した。交代前は毒気のない「良い人」ばかりが出てくるストレートなドラマで、ツッコミどころがない代わりに内容は正直退屈だったので、まあそういうのがみんな好きなんだろう。
特に脚本家交代後、「人の愚痴を言う舞ちゃんなんて見たくない😓」みたいなツイートが拡散されていたのには慄いた。人間もキャラも愚痴くらい言うやろ。「人を無慈悲に刺し殺す猟奇シリアルキラーと化した舞ちゃんなんて見たくない😓」とかなら分かる。
89位 犬王(映画)
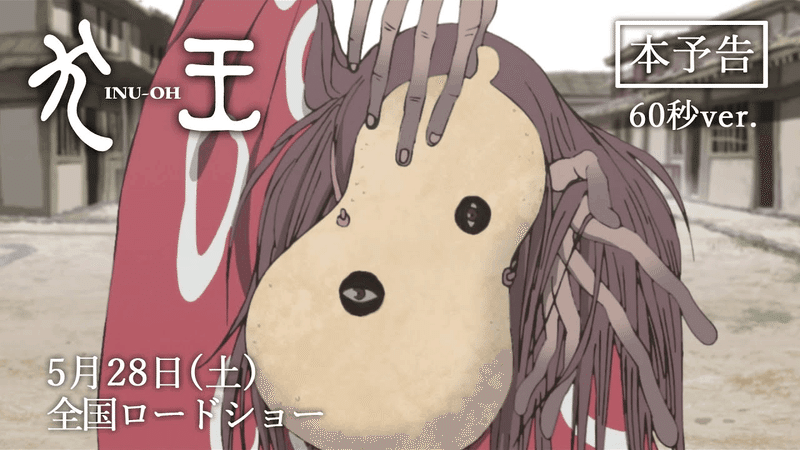
歴史には記録が残っていない室町時代の能楽師の話。『竜とそばかすの姫』みたいな歌もの。
途中少し寝たけど、それも含めて、劇場で観れてよかったと思った。これを観てて一番よかったのは「なんか現世とか色々どうでもいいな」と一瞬のあいだ思えたところ。懸命に生きた結果歴史から消されて、数百年ののち巡り合った2人のように、どうせ歴史に残らない一部なんだからと。なので居眠りだって許される作品ですよ。すべてはどうでもいいのだ。
物語は単純で、「反体制ブロマンス+物語ることの価値」みたいなリベラルが好みそうな感じのやつ。時代劇の良さって「時代性ゆえの制約」にあると思ってるので、小劇場演劇っぽい変なダンスのシーンとか、妙に現代のライブっぽい光を出すのとかはやめてほしかったけども、まあ映像は良かった。ゲーム的なカメラ演出のところとか、この世界行きたい、こういうゲームあればいいのにと思った。
ちなみに野木亜紀子(『逃げ恥』『アンナチュラル』の人)の脚本では能舞台だったものが、湯浅政明監督によってダンスとかライブとかバレエに変更されたり、音楽も当時あった和楽器(琵琶、笛、鼓、中東の弦楽器とか)でやろうとしたけど監督の意向でエレキギターが入ったらしい。ふむ~。「ギターロック=反体制」みたいな前時代的イメージを、それこそ現代劇じゃない時代物だからこそやろうとしたんだと思うけど、にしてもねえ。時代物なんで、急に反米右翼みたいなこと言うけど、だって外国のやつでしょそれ。
88位 ポケットモンスター スカーレット(ゲーム)

ポケモンの正統な新作。オープンワールド。
オープンワールドのシステム面とか処理落ちについては色々言われてるけど、そもそもオープンワールド自体に関心がなくて『エルデンリング』すら序盤で止まってる僕からすると、寄り道を楽しむタイプのゲームである『Pokémon LEGENDS アルセウス』(これも今年出たやつ)よりはシンプルなRPG形式の色が強いので、ちゃんと楽しめた。ポケモンの生態を『モンハン3』みたく垣間見れるのも良い。
シナリオは、伝説のポケモンなはずのコライドンに伝説感がまったくなく「最初から仲間になってくれる、移動に役立つデカい犬」くらいの感じで進むのが気になってたけど、これが最終的にうまく回収されたので感心した。『シンエヴァ』『ドライブマイカー』『すずめの戸締まり』的な「傷からの回復」って主題をポケモンすら扱う時代。2020年代的な想像力のデフォルトラインがけっこう見えた気がする。
ただ同時に、フィクションとしてのポケモン全体がリアル志向になっているのでは?という問題もまた気にかかる(そもそも2D→3Dという変化自体がそういうものなので、仕方ないのかもしれないが)。
1つ目が社会の問題。2019年の『ソード・シールド』はポケモンバトルをショーとして描き、『アルセウス』は異世界転生したあとに組織に所属するところから話が始まるし、今回の『SV』はあくまでも学校という箱庭の話。どうやらポケモンは「社会」を描こうとしているらしい。挙句、今回なんてジム戦の前におもんないバラエティ番組みたいな謎ミニゲームをやらされたり、ポケモンリーグで「面接」パートがあったり、ジムリーダーが他の職業との兼業だったり、明らかに現実に寄せているわけです。
ちなみに昨今『少年ジャンプ』のバトルも、組織としての集団戦・総力戦スタイルが増えていると言われてる。でも冷静に思うんだけど、どうせ我々はだいたい現実で組織に所属してるのに、なぜフィクションでも何かに所属しなきゃいけないんすかね。
2つ目が超越性の問題。今作のポケモンはナラティブでわくわく感を演出することを放棄し、オープンワールドの野生ポケモンの生態とかコライドンの扱いとか含めて、グラフィカルな「かわいい」の感性のほうに全振りしている。あえて老害として言うけども、『ルビサファ』『ダイパ』あるいは『仮面ライダーアギト』みたいなゼロ年代のコンテンツ群は超古代の想像力を導入して僕らをわくわくさせようとしてくれていて、いま思えば偉かった。
とまあ、楽しみながらもなんか色々考えちゃった。マスカーニャのデザインとかは超好きなので、もうなんでもいいっちゃなんでもいいんですけどね。
87位 あかね噺/末永裕樹、馬上鷹将(マンガ、週刊少年ジャンプ)
落語家の娘のギャルっぽいJKが最強の落語家を目指す話。どれ発祥なのか明確に言えないんだけど、こういう謎のハッタリを大真面目に効かせてくるタイプのジャンプマンガは久しぶりなので、いいぞもっとやれ、と思いながら読んでいる。大味ではない『火ノ丸相撲』みたいな感じ。『マッシュル』『SAKAMOTO DAYS』みたく変化球ですよ感を出すのではなく、かなりストレートにベタにやっていて偉い。
絵は、最近のジャンプは最初からアニメ的なデフォルメが効いたものが目立つんだけど、正直僕は『アンデッドアンラック』『マッシュル』『夜桜さんちの大作戦』とかの絵柄はあまり得意でないので、『あかね』は適度に細い線で等身高く作ってあるのも良い。あと案外こういう勇ましい女性主人公はジャンプでなかなか出てこない。キャラデザかわいい。
86位 沈黙のパレード(映画)

過去に解決できなかった事件のことが再燃したので、草薙刑事=北村一輝が苦悶の表情を浮かべながらいろいろ頑張る話。もはや伝統芸みたいな、福山雅治の「はっはっはっは」「じつに面白い」が見れる。
かの『容疑者xの献身』はガリレオ=福山の物語だけど、これは北村一輝が福山の助けを得ながら決着をつける物語で、友情ものの要素が強めに出てる。ガリレオの映画版は「名探偵=ヒーローが1人いたところで別にスッキリ解決とかしないし、みんな色々しんどいんだ」というヒューマンドラマ的な部分をちゃんと描いてくれるので好感度高い。屋上で2人が対比的に座ってる構図とか、ベタだけど、全体的にカメラワークもアベレージ以上のものを出してたと思う。ただ中盤は「日本映画やってまーす」という感じで若干だるい。
あとやっぱり柴咲コウは良い。飼われたい。
85位 Burn The Empire/The Snuts(音楽)

UKのインディーロックバンド。2010年代のロックおじさんたちは「ロック死んだ」みたいな話が好きだったけど、最近ならオリヴィアロドリゴとかロック要素あるし、フジロックでもジャックホワイトとか盛り上がってたし、若い世代でもマネスキンとかヤングブラッドとかいるし、全然死んでないじゃんと思う。2010年代に「ジャンル横断性」みたいなものがトレンドだっただけで、2020年代はむしろジャンル性が復活してるのでは?という話もあったりする。
で、このThe Snutsはそういうシンプルさを感じさせるやつの1つ。「イギリスの音楽はダサいところが良い」ってさやわか氏も言ってたけど、このアルバムとかほんとダサくて楽しい。
84位 I Didn't Mean to Haunt You/Quadeca(音楽)

シリアスなエモラップ系のやつ。サムネ、何してんのこいつ?という感じでおもろい。亡霊的でありつつ壮大な闇落ち感をコンセプチュアルに作っていてすごい。内省的・閉塞的な祈りみたいな感じで、攻撃性はないので、ケンドリックラマーの新作にも近い温度感がなくもない。でもこのふわふわした空間性ってなんかコロナ禍初期っぽいとは思う。
あとエモラップの「エモ」と日本のサブカルが言うところの「エモ」って全然違うよね。ロック以降の文脈とボカロ・セカイ系文脈(でいいのかな)の両方が分かる人にガチまとめ記事とか書いてほしい。誰か氏~
83位 Unity/Mrs. GREEN APPLE(音楽)

2010年代の邦ロックフェスの盛り上がりの中でデビューした、フェスに無限に最適化されたような、BPM早くてハイトーンで複雑なメロの爽やか系のやつをやるバンド(デビュー直後くらいのときにROCK IN JAPANで観たことある)。でもバンドサウンドというよりはEDMとかも普通に入れてくる。今作は活動休止・メンバー脱退を経て、2010年代的なポップロックの王道アップデート+さらなるポップ化みたいなことをやっていて良い。歌は上手い。ので歌によるゴリ押し感はある。
邦楽の影響がバリバリ強いんだけど、ボーカルで作詞作曲とかしてる大森元貴は影響受けた最近のバンドとしてThe VampsとかMaroon5を挙げていたり、DTMもやってたりと、当然のようにいろいろ融合してる系。だからこそ「ロックバンド」へのこだわりがないからか、ビジュアルのテイストを定期的に変えたりダンスを始めたりしてて面白い。
これとかストリーミングでもチャート入ってる。なんか最近Spotifyの日本のチャート見てると、2020年代に目立つのは「めっちゃテクニカル」か「めっちゃシンプル」かの両極で、しかも後者はやたらと素朴なラブソングが多いような気がする(ミセスは前者のほうでいける人たち)。2010年代みたく四つ打ちでとりあえず爽やかにいくぜ!とはいかないのかもしれず、個人的には楽しそうだなと思うけど、音楽の人たちがどう思ってるかは気になる。
82位 FICTION/BREIMEN(音楽)

さっきの分け方で言うと、テクニカルなほうの人たち。見るからに意識高い。カテゴリは「ミクスチャーファンクバンド」らしい。なんだかよく分からない。Suchmos、星野源以降の新しい人たちになるとブラックミュージック要素とかはもう当然の前提としてあったりするので、なんやかんや「ポップロック」とまとめられるミセスとは違ってジャンルも実際よく分からない(全部「邦楽」でいい、ってのも分かるけど)。
このアルバムはクリックを使わずに実機のみで録音したらしく、明らかにこだわりの強い人たちであることはMVを観てもすぐに分かるんだけど、そのわりに意外とちゃんとポップになってるのが今作は良い。声を張らないボーカルの感じ、なおかつ全体的に理論派のエリーティシズムを感じさせるところはKing Gnuっぽい。やはり意識は高い。
今年はポルノグラフィティ岡野昭仁×King Gnu井口理にオシャレ曲も提供してくれたよ。
81位 For./sumika(音楽)

2010年代に結成してフェスにいっぱい出てたバンドのうちのひとつだけど、BPM全速四つ打ちムーブみたいなものに全力で乗っていた印象はあまりなく、キーボードとかが目立ってて程よく力の抜けた(そしてどっか垢抜けない)ポップロックをやっている人たち。
今作は今までよりも洋楽エッセンスを明確に入れたり、打ち込みを使ったりと、尖りすぎないままに横断的な楽しさをやっているところが好き。言葉の響きをちゃんと重視するsumikaの詞の乗せ方がその方法論とバッチリハマってるようにも聴こえる。3曲目『何者』の詞とか、King Gnuをはじめとした英才教育勢への皮肉になってて良い。
『Habit』のセカオワとかもだけど、2010年代に目立ったバンドたち(その大半は自分にあまり合わないやつだけど……)が隠し持っていた別の武器を最近になって使うようになり、音も多様になっている感じはわりと楽しい。どちらかといえばシンプルなジャンル性に回帰してる英米とかの動きとは逆というか、要は遅れてるのかもしれないが、まあいいよ別に。
この1曲目とかも良いと思う。
80位 石子と羽男―そんなコトで訴えます?―(ドラマ、TBS)

最近ちょくちょくある非恋愛の男女バディもので、深刻じゃない感じのリーガルもの+ヒューマンドラマ。演出が『アンナチュラル』『MIU404』とかの人で、脚本がそこそこまあまあ普通でも演出と役者が良ければドラマは楽しく観れるのだと再確認した。社会的イシューが毎回律義に設定されるあたりはTBSらしい。あと衣装も良い。
キャラの関係性の面では、「破天荒な男性が堅物の女性を振り回し、女性側もやがて影響され変化していく」という『リーガルハイ』的なやつではなく、中村倫也側も弱さを見せながら2人があくまでも対等な関係性を築いてるところが今っぽくて良い。けっこうみんなの見たかった中村倫也が見れるやつだと思う。
79位 君と悪いことがしたい/由田果(漫画、週刊少年サンデー)
ゲンロンひらめき☆マンガ教室出身の方のサンデー連載作品。自分が恋愛物をヒーロー物の構造として楽しんでいるところがあることに気付いたので、じゃあこれはハマれるはず!と思って読み始め、見事に面白い。「憧れ」って感情をうまく見せてくれるやつはとても良いですよね。そして表情が感情を雄弁に語っている。かわいい。
こういう男女逆転のガチ少女マンガみたいなやつを今は少年誌でやれるというか、少年誌ってむしろそういうものになってるんだなあとも実感。「ラブ」だけじゃなくて弱者性みたいな要素が当然入ってくるのは、いまどきのマンガだからってことなのかな。
ところでなんか最近本当によく分からないんだけど、恋愛物って何すかね。一口に恋愛物と言っても、キュン系のやつと「人格としての自分にとってこの相手が重要なんだ」というやつは明確に違う気がするし、やっぱり後者に惹かれてしまう。
78位 モガディシュ 脱出までの14日間(映画)

ソマリア内戦に巻き込まれた韓国・北朝鮮の大使館の人たちが頑張って国外に脱出する話。韓国でめちゃヒットしたらしい映画。
韓国映画なので自動的に社会的イシューをぶちこんできつつ、普通にエンタメとしても面白いし、南北朝鮮の人たちの協力とかは王道だけど良い。しかしどうしても終盤のカーアクションがハイライトなので、するとこれは本質的には『マッドマックス』なのではないか?という疑いが自分の中で消えなくて悲しい。あと「ソマリアとにかくやべえ」という感想も残ったんだけど、ソマリアについてはそれでいいんだろうか。
これとか、あと今年だと『ベイビーブローカー』も、『パラサイト』『万引き家族』とかよりも何かしら希望を持たせる終わり方になっているあたり、「コロナ禍以降みんなしんどいんだなあ」という納得感があった。
77位 機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島(映画)

ファーストガンダム15話のリメイク。島で自給自足してる脱走兵の人VS軍隊という話。
ファーストは全話観たことはありつつも特に思い入れがないんだけど、これは感動した。最初のドアンの斧を振りかざすカットの強キャラ感とか、最後のガンダムのヒーロー感、刀を振るときのポージングとかけっこうバッチリ決まってたと思う。
なんで我々はドアンたちのように自給自足で楽しく暮らせず、クソみたいな東京でパソコンを叩いているんだろう。とく死なばや。と思うくらい、あの島での生活がドアンたちにとって大事なものなのが伝わったし、それがドアンや子供たち、引いてはアムロの戦う理由になるのだという。バトル物はやはり「戦う理由」にグッとくるのが重要で、なおかつ戦闘がかっこいいと完璧。
しかしほんと、島とかね。行きたいですよね。東京ってなんなんだろうか。ってなりました。
76位 サイバーパンク エッジランナーズ(アニメ、Netflix)

やばい人体改造がナチュラルに行われるようになってるやばい街で貧しい少年が頑張る話。世界観とアニメーション演出と軽薄な音楽のキッチュさが良い。攻殻機動隊とかじゃなく、このダサさこそが真のサイバーパンクってやつなのか!と素直に思った。
社会に虐げられてる感じの少年が主人公なんだけど、ジュブナイルにありがちな迷いや葛藤で時間を使うやつがなく、サクサク進むので好みだった。2話の医者からの脱出シーンとかいいよね。主人公の動機にもちゃんと切実さを感じられる(なお僕が『メイドインアビス』『水星の魔女』あたりがどうも苦手な理由は上記を反転させれば分かるのかもしれない……しかし苦手は克服したい)。
ただ一本調子ではあったので後半は飽きが来た。「底辺から這い上がる」って意味ではもっとちゃんと現代的な欲望の話をやってる人がいるんだ、藤本タツキという人が。デイビットは普通に成長して普通に社会化される奴ですよやはり。
75位 極道會襲名式(ヤクザバース・トランザクション)/長谷川京(小説、ゲンロンSF創作講座)
ゲンロンSF創作講座の課題提出作品。上記は課題ページ。作品ページはこちら。
ギブスン的なサイバーパンクのスタイルを感じさせる文体を、2020年代のメタバース的想像力と接続した上でエンタメにしている。「合理/非合理」というシンプルな二項対立の話ではあるんだけど、いろいろな設定に必然性が感じられる。
あとこれはなんとなくフィーリングで楽しめるところも良い。小説でしかできないことをやっているものが好きだな、と改めて思った。夏目漱石は『草枕』について「内容が分からなくても、読んだあとに良い感じのバイブスが残ればOK」みたいなことも言っている。けどまあなかなか今はそういう時代ではないのも分かる。
74位 うるわしの宵の月/やまもり三香(漫画、デザート)
まわりから「王子」と呼ばれてるイケメン系女子が、同じくまわりから「王子」と呼ばれてるイケメン系年上チャラ男子と出会って翻弄されるみたいな話。人から抱かれる勝手な属性のイメージに苦悩する「王子」たちの描き方も良いし、「美しいものは美しいんだ」とキッパリ言えてしまうあたりが、ルッキズム問題を経たあとの人間の真実という感じで良い。
これは弱者というより、「持てる者」がそれゆえに苦悩しているっていう前提のやつなので、そういう意味では今っぽいのかなあ。少女マンガの文脈が分からないので分からないけど。なんにせよ絵がいいですとにかく。ほぼヒーロー物です。
73位 シン・ウルトラマン(映画)

変な映画。長澤まさみが巨大化したり山本耕史が宇宙人やってたりする。ドラマ評論家の成馬零一氏が「30分のドラマを5本集めた感じ」と言ってて、実際『ザ・バットマン』にもその細切れ感はあったし、サブスクドラマ全盛の時代だからか「映画」というフォーマットを勘違いしている制作者が世界に一定数いることは分かった。
ただ『犬王』と同じで、「現世とか仕事とかいろいろ些末なことどうでもよくね?」と思えたので僕はけっこう好きだった。だって長澤まさみのシーンがセクハラ描写か否かについて細かい指摘をし合うSNSのツイバトルよりも、地球をゼットンから守るほうが人類にとって大事じゃん??
ジャンルとしては、ヒーロー物ではなくて超越性のやばさを味わうSFとして観ればいいので、「ウルトラマンに感情移入できなかった」的な感想はそもそも観方が違うと思った。ウルトラマンが人間を好きになる理由なんて何だって良かろうが。
CGしょぼいとかも言われるけど、同じく別にどうでもいい。CGちゃんとしてなくても『クウガ』の2話は感動するじゃん。あと最初にスペシウム光線撃つときの腕の動きのキレめっちゃ良くなかったですかね。あのケレン味だけですべて許した。
72位 流浪の月(映画)

幼少期の広瀬すずを誘拐した犯人として松坂桃李が逮捕されたけど、別に誘拐とかじゃなくて2人にとっては幸せな時間だった、そしてそれから数年後2人は再び出会い……みたいな話。横浜流星が広瀬すずのDV夫を演じていて、微塵もキラキライケメン感がなくて良かった。
構造は単純な「普通の世間/世間から異常だとされる主人公たち」の二項対立で、つまりそういう系の文芸によくあるやつなので「よくあるやつだ!」ってなるんだけど、普通とは何か?と問えるだけの強度はあったし、「暗い日本映画」をちゃんとやっていたので全力で乗れた。つらいな、この人たちに幸せになってほしいな、と本当に思えた。
撮影監督は『パラサイト』の人らしく、映像も良かった。暗いシーンのあとに白いカーテンと空がドーンと来たりとか、光と影のイメージがしきりに使われていて若干くどかったけども、ビジュアルと連動して物語が明暗どっちに転ぶのか分からない怖さがあった。
原作も一応読んだけど、原作から改変して「水」のイメージをめっちゃ使ってるのも好みですね。水と月を象徴的に使ってくるんだから文学勢は好きだと思う。画面がせっかく良いのにセリフで説明しすぎなところはあったけど、映画のあとに原作のモノローグを読むと若干ありがちでチープに感じられたりもしたので、うまくいってる映像化だと思う。
71位 Being Funny In A Foreign Language/The 1975(音楽)

UKのチャラい大人気ポップロックバンド。前作までの尖ってます感は抑制されて、ストリングスとかいろんな要素が入って丁寧で繊細な感じ、それでいて分かりやすすぎるくらいキャッチーで、パリピ感はなくて聴きやすい(今年で言えばハリースタイルズについてもそう思った)。
「少し抜け感のあるオーガニックな感じで、コロナ禍的なメランコリックな閉塞感からは脱してきてる」みたいなモードが2022年は来てるんだという話をさやわかさんがしていたけど、これなんかもそういうやつだと思うし、実際自分にもとてもハマった。疲れてるときに聴きたいアルバム。
70位 Three Dimensions Deep/Amber Mark(音楽)

アメリカのR&Bの人。「女性シンガーが歌い上げる、とりあえずリバーブがやたらかかっているシリアスでメロウなR&B」みたいなやつが基本あまり好きじゃないのだけど、このくらいクラブミュージック、テクノ、オリエンタルとかいろんな要素とビートを混ぜてポップ感も出してくれるなら楽しく聴けるなあと思った。ルーツが多国籍的なのも関係あるのかもしれない。
『Worth it』とか詞もストレートでめちゃくちゃ好き。The 1975と同じく、疲れてるときに良い。
69位 星の子/chatoe(音楽)

バンドを日々ディグりながら生きてるわけではないので、日本のインディーバンドは知り合い経由で見つけるみたいな感じが多いわけだが、イヤホンやデカい箱だけじゃなく「ライブハウスで聴きたいタイプの音」というのはやっぱりあって、このEPはとてもそういうものだった。全体にUKっぽさもありつつ、メロウやエモではなく静かな熱さを感じさせる作りは2022年っぽい。あと僕はたぶん内省的すぎない詞が好きなんですね。ほっとくと自動的に内省的になる奴だからこそ。
The 1975、Amber Markと同じで疲れてるときに聴きたいやつ。というか今年は基本的に疲れてたので、特に音楽は自然とそういうものが多くなる。でも世の中全体も疲れてた気がするので、あながち僕個人のモードってわけでもないと思うんですよね。どうだろう。
68位 ReLOVE & RePEACE/高橋優(音楽)

シンガーソングライター。ゆえに別に新しいことをしてるわけじゃないんだけど、「リアルタイム・シンガーソングライター」こと高橋優が今作はやたらアッパーな精彩を放ってるので、それだけ大変な1年だったんだなあと改めて思ったので入れた。「感情」は2020年代の大事なテーマでもあると思ってるし、アルバムのタイトル通り、ラブとピースを本当に大真面目にもう一度言わなきゃいけなくなっちゃったんですよ。
高橋優はデビュー時から一貫して「エロス=生(性)」と「タナトス=死」の両極について歌い続けてるんだけど、今までは明示的に一応別のものとして言っていた2つが、今回は境界を失ってナチュラルに融合しているのもどこか怖ろしい。
サウンドの硬質な感じと歌の乗せ方は、特に1、2、7曲目なんかは「人間ってこんな初期衝動みたいな暴れ方できるんだ?」と何か勇気づけられるものだった。アミューズを離れたのが大きいのかな。
『forever girl』のBメロの乗せ方とか良い。こういうの作ってみたい。
67位 さよなら絵梨/藤本タツキ(漫画、少年ジャンプ+)
自殺しようとしてた少年がミステリアス美少女と出会い、一緒に映画を作る話。公開時は「またSNSでの考察バズを意識してやがる」「映画っぽい!みたく褒められて満足か?」と警戒しながら読んだけど、時間をおいて2回目を読んだら普通にけっこういいじゃんと思った。
2021年の『ルックバック』は軽やかでそりゃ素晴らしい作品ではあるけど、結局のところ、『左ききのエレン』以降的な「エモ系描写と結びついた、創作および創作者の側の話」でしかないとは言えてしまう(それがあの時の藤本タツキの役割だとしたら、彼は真摯にやりおおせてると思う)。
他方、『さよなら絵梨』は「死にゆく人や死んだ人をどう思い出すのか」、そして「映画みたいな"いわゆる創作"が偉いわけじゃなく、我々の"思い出"とか"記憶"だって人生をかけた一種の尊い創作と言えるんだ」ってことをやってるので、テーマ的には『ルックバック』よりも普遍的なところまで成熟している。
作家論的には、当時は「こういう意識の高さを気取るメタ漫画みたいなやつをやり続けるならもう読まねえ」と思ったけど、最後のコマは『ルックバック』批判に対する「いやこれフィクションですよ?」という回答であり、結果的に『チェンソーマン』2部=全力のフィクションへの助走でもあったわけなので、まあいいんじゃないでしょうか。
66位 創業/ぷにぷに電機(音楽)

インターネット発の電子音のR&Bで、ジャズとかシティポップとかテクノとか色々混じってる人。まあ「混じってる」こと自体は今や別に普通じゃんという感じにもなるけど、オシャレでありつつも歌謡曲のテイストも感じさせて良い。最近の音楽は要素が多い上に、シティポップリバイバルとかが無限に続くせいでどれが何年代っぽいのかよく分からんので誰か教えてほしい。
シティポップって都会的なエモ概念と結びついて消費されてるんだと思うけど、ぷにぷに電機の3年前の曲と今年の曲を比べると、2022年現在の若者が「もはやエモでもあるまい」みたいなモードになりつつある気がする(MVもそう)。
ボーカルやってるスナネコの歌もいい。猫とか大事だよね。
65位 アオのハコ/三浦糀(マンガ、週刊少年ジャンプ)
青春部活ラブストーリー。それ以上でも以下でもない。
一応「恋愛マンガ」ということになっている。しかし『いちご100%』的な「誰ルートにいくか?」を楽しむやつじゃなく、単に負けヒロインの負けっぷりを楽しむマンガ。というかそれ以外の読み方がもはや分からなくなっている。連載スタート開始は今年じゃなくて2021年なんだけど、今年あった負けヒロインの告白シーンがあまりにも無慈悲な脈無し感を放っていて感動したので、ランキングに入れた。
あとジャンルとしては「ラブコメ」でもない。青春っぽい少女マンガのモノローグを減らして限界までシンプルにした結果、雰囲気だけでサラーっとすべてが進んでいく、みたいなやつ。これも「エモ」に入るんだろうか。エモに詳しい人教えてください。
64位 MAD/DAOKO(音楽)

ネットカルチャーから出てきて、ボースティングとかじゃなくて文学性の高い不思議少女系の詞(セカイ系感もある)でラップをしてる人。今まであんまり分かってなかったけど、今年出たつやちゃん『わたしはラップをやることに決めた』を読むと、色々な方面に影響を及ぼしてるらしいことが分かる。
今年のEPはトラップでクラブカルチャーっぽく、なおかつちゃんとポップスになってて聴きやすく中毒性がある。ポピュラーな場でラップをやる人はどうしても「歌うかどうか問題」みたいなことで色々言われたりするんだと思うけど(素人目からはそう見える)、DAOKOはと言えば2020年以降ラップ色がまた強くなってきたとか言われつつ、今年の『MAD』『燦光』を合わせて聴くと「そもそも別に何のジャンルにも対応できるし?」という無限の自由度と凄みを感じるので大変良い。
「狂騒」と「ヒーリング」という、僕の勝手に思ってる2022年の2大テーマをひとりで体現している人。
63位 鯉姫婚姻譚/藍銅ツバメ(小説、日本ファンタジーノベル大賞)
人魚に求婚された男が、昔の御伽噺を語ることで(人魚との共生なんて無理なので)求婚を諦めさせようとする話。ゲンロンSF創作講座出身作家の、ファンタジーノベル大賞受賞作。文体がきれいなので純文学的な楽しみ方ができる。
昔話を引用して構造を何度も何度も重ね合わせた果てに、共生だとか共存だとか、ジャンプ本誌の『ルリドラゴン』的な令和の優等生っぽい正しさをせせら笑うように、ダンディズム男とメンヘラセカイ系人魚はアクションを起こす。その過程と結論が反時代的で良いと思ったし、最後の数ページは小説読んでて久方ぶりに本気で胸が躍った。めちゃめちゃ良い。日本の古層的なものを継承しようとする作家、って意味でも貴重だと思う。
62位 春火燎原/春ねむり(音楽)

激しいポエトリーリーディングの人。ポエトリーリーディングって僕も素人ながら小規模イベントのオープンマイクに参加したことが数回あるけど、特に日本語のやつなんて国内ローカルのものだと思ってたので、春ねむりが海外で人気と知ってびっくりした。
過去作ではわりかし勢いのある生命力を感じるけど、今作はポストアポカリプス的なヒリついたプログレッシブ感があって、オルタナティブ感・アートロック感は増している。サビも「歌」という感じではなく、シャウトとか、絞り出すような歌い方とかで、この切実さが素晴らしく2020年代っぽい。『春雷』とかポップ感強いやつもあるので聴きやすいとは思う。
音に加えて壮大なジャケット写真・MVのせいかもだけど、聴いてるとなんとなく「『シンエヴァ』以降の世界だなあ」と感じる。セカイ系的な自意識と承認の話はもう終わって、あとはこの「元々狂ってる世界」(by『天気の子』)にどう立ち向かうか。ボースティングではなくてライオットガールとしてのアジテーション。良くも悪くもダイレクトな表現。あと作品自体には関係ないけど、SNSとか見るとTwitterリベラル感が凄まじいので、「Twitterリベラルだ!!」とはなる。
(そういえば、『最終兵器彼女』が好きで、だからこそセカイ系の乗り越えは意識してる、みたくどっかのインタビューでも言ってた。)
MV的は表題曲のやつがいいけど、曲はこっちのほうが好き。
61位 極主夫道 ザ・シネマ(映画)

元ヤクザの玉木宏が川口春奈の夫になって主夫やってる話。テレビの延長線上なので、映画である意味は特にないし、まあチープではあるけども、コメディ系の小劇場演劇の良いやつくらいには良かった。記号化された「ヤクザ物感」をギャグとして使うやり口のため、玉木宏が意味もなく脱ぐことが可能だったりして面白い。
「ヤクザが主夫をやってます」という現代的フラット感を必要以上に押し出してないのも良くて、当然こういう世界もありえるよねと思える優しい世界観。家を守る、コミュニティ=居場所を守るという役割をみんなが懸命にやっていて、それが男性性の発露にもなっていない。この世界の中に行きたいと思った。みんながリスペクトしあいながらバカにしあう世界。疲れてるからほんとこういうのでいいんだよ。
それと川口春奈といえば今最も活躍している人間の一人で、YouTubeの「はーちゃんねる」とか当然チェックしてるわけですが、「石原さとみとかガッキーみたいなロールモデル感ある人たちと違って、2020年代はこういう時代なんだな」と感じる。気取らないナチュラル感というか。清原果耶とか上白石萌音とかも。
60位 ソー:ラブ&サンダー(映画)

目的を一度見失ったソーがまた頑張って戦う話。最近の窮屈なMCU及びそのファンダムへの疲れを表明したかのようなバカみたいな単純な映画。ブラックウィドウとワンダに続いてまた女性が死んでるし、「喪失とどう向き合うか」というフェーズ4的なテーマも言うほど掘り下げられないけど、まあソーがソーらしくかっこよくコミカルに撮ってあるから良いか!と思いました。
ただソーのダンディズムへの解決に関しては、意外とちゃんとやってくれたなと思った。「女性のジェーンがヒーローとして、男性のソーを助けに来てくれた」ことの背景には、そもそもソーの日常の中の愛や祈りによってジェーンにムジョルニア(斧)への適性が生まれたからで、だからタイトル通り日常的なミニマルな「ラブ」が重要だっていう話ではあるんですよね。ソーの日常が出るところもこの作品は楽しい。
しかし家のモニターでもう一回観たいとは別に思わないあたり、これも体験型の何か、という感じがする。
59位 「おかあさんといっしょ」ファミリーコンサート ~たいせつなもの、なあに?~(イベント)

ファミリーコンサートは縁があって何回か観に行ってるんだけど、今年は新任のまやお姉さんの初めてのツアーで、前任のあつこお姉さんもゲストで出てくるので、継承の話になっていて良かった。「好きなものが見つからない」って悩んでるまやお姉さんに、あつこお姉さんが「私はみんなと歌ったこと」って言うんですよ。最高じゃん。思い出をちゃんと大事にしたいなと思った。
おかあさんといっしょのコンサートの何がメタ的にグッとくるかというと、連れて来られてる子供の年齢層がかなり低いので、彼らが大きくなったら「このコンサートに来た」ということ自体をもしかしたら忘れてるかもしれないところ。幼稚園・保育園以前の記憶って実際曖昧ではある。
ただ、幼少期に限らず人生のあらゆることにおいて、やがて忘れてしまうかもしれないからといって「何もしなくていい」ってことではないのだ。そういう空間で継承の話をやられたので、もう感動的だなと思ったわけです。
58位 おいしいごはんが食べられますように/高瀬隼子(小説、『群像』初出)
芥川賞とったやつ。性格悪い小説。「いわゆる女性的で体調崩しがち=かわいそう=かわいい」系の職場の女性、つまり周囲から「配慮」されるべき弱者性を持った存在に対して、いや分かるけど頭痛薬飲んで頑張ったりしてもいいんじゃん?いや分かるけどさ?とまわりの人がモヤモヤするみたいな話(実際にはもう少し複雑な群像劇にもなってる)。
著者は「日常の小さな違和感」みたいなところから話を展開する傾向がある人で、そりゃ芥川賞向きですな、と思う。二回目をわざわざ読もうとは別に思えないあたりも芥川賞っぽい。
「食べる」というモチーフやキャラの対比がきれいに機能してる感じもしないし、歪ではありながらも、視点の移動とかうまいので読ませるし、「マジョリティ男性の意地悪い内面」といういま描きにくいテーマをやってるのはすごい。
あとこの描き方だと、当の職場の女性が単に厄介な「他者」になってる=内面が描かれてない、のだけど、「他者感」を排除するかどうか問題はけっこう難しい。
つまり「この女性を他者化してしまっていて人間としての複雑さを描けてない」みたいな昔ながらの批判っていくらでも可能なんだけど、ここでへたに彼女の内面とか描かれても「技巧的ですね~多面的でえらいですね」としか思わなかったかもしれない。実際リアルにおいては人の内面なんて分からないわけだし。と、そんな感じで、ちょうどいい塩梅で成立してるところも面白い。
57位 こちらあみ子(映画)

田舎のちょっと変わった(アスペルガーとかそういうのだと思われる)女の子がいろいろ頑張るが、周りとは全然波長が合わずしんどい、という話。青年マンガっぽい「イノセント系」(多分さやわかさん命名)。なお作者の今村夏子は『花束みたいな恋をした』のクソサブカルカップルこと菅田と有村が言及する感じのタイプの作家。上質だけどしゃらくさいやつです。
周りとズレちゃうあみ子が平坦に、ユーモラスに、愛らしく描かれてるんだけど、やがてそれが笑えなくなってくるという仕組み。これが原作小説だとあみ子に寄り添う三人称視点のモノローグ的な地の文なので、ユーモアは感じづらく、最初からシリアスに内省的に読んじゃうんですね。だから小説のほうが普通に感動できるんだけど、映画のあみ子は「他者」感がすごいのでそれこそ無責任に笑えてしまうし、ベタな「泣き」は遠ざけられる。
内省的な深刻さを「文学っぽさ」と仮に呼ぶなら、映画はむしろ文学っぽくなくて分かりにくい。そして、あみ子は終盤で「大丈夫じゃ」とか言うんだが何もこの先大丈夫そうではない(泣きというより、そういう意味での悲しさは感じられる)。
あみ子は観客にとって「他者」だから面白いんだけど、「他者」だからこそ観客とあみ子の距離は一定程度離れたままで、しかしその距離がまたユーモアの発動条件でもある。これは夏目漱石や柄谷行人がこだわっていた問題にも直結するので、個人的にいろいろ考えさせられるものだった。まあそれ抜きにしても普通に良い映画。
56位 サマータイム・アイスバーグ/新馬場新(小説、小学館ライトノベル大賞・優秀賞)
トンマナが自分に合うかどうかで言えば合わないながら、珍しく読んだガガガ文庫。青春SF。夏だし単にエモい系なのかな?とか思いながら読むと、むしろ「夏っぽい(セカイ系っぽい)青春もの」という構造自体を利用して別のことを描こうとする作品になっていた。「恋愛ものはくだらない」とか、「何かを家族のせいにしてしまう自分が嫌い」とか、そこに描かれるのは最早いろんな問題の相対化を終えたあとの葛藤で、社会派要素も入っていて良かった。
この作品が何をやろうとしているかについては、新馬場先生ご本人出演のPodcast「やんぐはうすらじお」第4回(めっちゃ良い回ですこれ。90年代生まれにおすすめ)と、神山六人さんのおたよりを読めばだいたい分かるので、もう語ることはあんまりないんだけど、90年代~ゼロ年代的なものを真っ当に乗り越えようとしてるのはやっぱり尊敬できる。『君の名は。』以降、セカイ系の再来みたいな話がまた色々言われちゃってる時代なだけに。
55位 ウ・ヨンウ弁護士は天才肌(ドラマ)

法廷お仕事もの。社会性をオミットせずむしろ主人公の自閉症設定とか含めて積極的に入れるのに、クジラの謎演出とかも相まってふわふわ気楽に観れる。ウヨンウ頑張ってくれ~とも素直に思える。法曹物にありがちな「ヒーロー的な主人公像」じゃなくて、ダメなところもある身近な人なのが良い。観てると若干たるいなと感じるところもあるけど、まあネトフリドラマってそういうもんか。
冬ソナ純愛ブーム的な『愛の不時着』、半沢直樹的な『梨泰院クラス』、デスゲームの『イカゲーム』だけじゃなくてこういうものも日本でけっこう観られてるみたいで、この感じは日本のドラマも普通に真似してほしいなとか思うけど、難しいんだろうか。
54位 Mmaso/Ecko Bazz(音楽)

ウガンダのラッパー。アフリカやばい、すごい!という気持ちになれる(というこの視線自体がオリエンタリズム的な何かを含んでいるかもしれないけど、でもこういう風にしてリスペクトが募る分には良いと思う)。コンシャスラッパーらしいけど歌詞はまったくわからない。しかしグライムでUSヒップホップ感があり、言葉の乗せ方が気持ちいいことだけは分かる。ざわざわっと、都会の仮面の下に隠れた生命力を呼び起こしてくれる。
53位 BORN PINK/BLACKPINK(音楽)

ヒップホップだろうがエレクトロだろうが、「今とりあえずバキバキのかっこいいやつが聴きたければKPOP聴けばいい」くらいのことは知ってるので、NewJeansでもKep1erでもLE SSERAFIMでも逆になんでもいいんだけど、モードとして合うのはBLACKPINKだなあと思った。アートワーク含めて、オリヴィアロドリゴとかに親和性のある悪ぶった感じのパワーを感じる。でもKep1erとかのコミック的な明るさのほうがトレンドにはなっていくんですかね。
しかし「パワー」って言うとなかやまきんにくんなので、なんか別の言い方を探したい。実際今年のキーワードのひとつはパワーだとは思うし、きんにくんもすげー流行ってるけど。JKとかが真似してるらしいですよ。
52位 《エンキリディオン Enchiridion》——山上徹也容疑者の未発表論文「哄笑」を読む/壱村健太(批評、「週末批評」)
批評というかなんというか、樋口恭介編『異常論文』に入ってるやつの文化社会批評版みたいなやつ。荒唐無稽に見えつつ弱者男性の問題系をちゃんと扱ってる、と思うんだけど、どうだろうか。「倫理的に無理」という人もいるかもしれない。
僕は、特に杉田俊介という批評家に関してはこういうコンテクスト含めた読み方が必要だというのは頷けるし、「ありえたかもしれない可能性」自体を陰謀論にも似たフィクションとして提示してるので、危うくも怪しく魅力的に感じた。「結局俺こういうの好きなんだな~」と残念な気持ちにもさせられる論考。というか自分がこれをほんとに読解しきれてるかどうかも謎。
読んでるときの「なんかよく分からんがとにかくやばいものを読まされている!」という強度の出し方は徹底していてすごい。テクストの引用とか絵画の挿入ってのはこう使うんだよ!と全力で殴ってくる。体験型アトラクションだと思う。こういう謎文章が存在しうるのも確かに批評というジャンルならではだよなあ、とか考えさせられるやつ。
51位 青春とシリアルキラー/佐藤友哉(小説、『HB』『すばる』初出)
太宰治がリアリティショーをしつつ自分の語り(地の文)のリアリティ自体を延々疑い続けるクソめんどい面白メタ小説こと『道化の華』を、きわめて現代的に、きわめて軽いノリで継承している!というところにまずビビる。
青春と90年代的な露悪性のことを考え続けているユヤタンだからこそ「中年男性の問題というのはつまるところ青春との折り合いがついてない問題なのでは?」ということを書けるし、個人的には舞城王太郎のやってることよりピンとくる。舞城のことが分かる舞城力はまだ僕にはない。
しかしこれは若者にとってはある種絶望の書でもあって、たとえ家族ができて「父」になったところで別に成熟なんてできないし、どこか満たされない感覚ってのは残るもんだぞ、と告げられるので、まじかよ……ってなる。しかも太宰のようにロマン主義的な最期を迎えるわけにもいかず、だらっと続く生活の中で我々はどうするか。どうしましょうね。
50位 ディスコ エリジウム ザ ファイナル カット(ゲーム)

トマスピンチョンっぽいポストモダン文学の雰囲気と、TRPGっぽい形式を借りながら、疲れた中年男性が立ち直っていく様を描くゲーム。Netflixドラマ『ベターコールソウル』が人間の崩壊の過程を描くものだとしたら、『ディスコエリジウム』は壊れて以降の過程を描いたもの、と言っている人がいて、我が意を得たりと思った。……と言いつつまだエンディングまで見れてないんだけど。とにかくムードが最高なんですよ。テキストは「中二っぽい」を超えた謎の何かなんだよな。何だろう。
49位 NEEDY GIRL OVERDOSE(ゲーム)

地雷系メンヘラ女子を彼氏兼配信者として育てる美少女ゲーム。メールの返信が少し滞っただけで過剰にヘラってくるのも面白いし、逆に好感度をめっちゃ高くキープするように苦心してたら「メンヘラの愛の重みに耐えきれずゲームオーバー」とかになって爆笑した。SNSや裏垢の空恐ろしい感じも妙にリアルで良い。にゃるらさんの観察の賜物。
これははっきり言って倫理的に批判することはいくらでも可能なゲームで(美少女ゲームな時点でそれはそうだけど)、実際調べると批判はいくつも出てくる。ただ、自分の接し方次第で相手がハッピーにもアンハッピーにもなる、その選択肢をプレイヤー側が握っていて、コミュニケーションも思い通りにいかない……というほどの複雑さは感じさせるものだし、『メタルギアソリッド:ピースウォーカー』で平和のための戦いをしていたはずのプレイヤーがやがて軍拡競争のピースのひとつになっていたのと(少なくとも構造的には)同じ。フィクションが現実の何かを簡単に「助長」するほど、人類って愚かなものだっただろうか。
48位 vs./valknee(音楽)

ギャル系ラッパーの人。病み系ではない。令和の幕開けである2019年はギャル雑誌『egg』が復刊したり、ファッションではなくマインドとしてのギャル概念を広めたkemioの『ウチら棺桶まで永遠のランウェイ』が出たりと重要な年だったけど、valkneeが活動を始めたのもまさに2019年。
そこからZoomgalsとかを経て、今年のEPはニコ動的MAD感をやりつつ急激にSpotifyのいわゆるハイパーポップ(音数多い、BPM速い、攻撃的、ノイジー、マキシマリズム、みたいな)方面に舵を切ったのが面白いと思った。エモではなくそもそもキッチュなことをやってきた人なので、親和性があって良い。詞も今っぽい。知的っていう褒め方は好ましくないかもしれないけど、知的だなと思う。
valkneeは普通に会社員として働いている「OL」としてのアイデンティティも使っていたり、美大出身だったり、アイドルオタクだったり、といろんな属性が混在してるところがギャル概念の現在地をよく表してると思う。つまり「ギャルマインド」というのは現実の属性云々よりもひとつ上のレイヤーの話なので、その前提さえあれば、一見対極のように見られるギャル性とオタク性だって当然のように融合しうるのだという。
47位 Un Verano Sin Ti/Bad Bunny(音楽)

プエルトリコの人で、ラテン系ヒップホップとかをやる。Spotifyのグローバルチャート見てるとこのアルバムが長いことトップ50に大量に入ってて、トライバルなもの+狂騒的に盛り上がれるものってことでみんな好きなんだなあと思った。夏っぽいし。同じく今年話題だったラテン系のレゲトンのロザリアの新作とか、あとアフロビーツのAsakeとかも良かった。
こっちの『Yonaguni』は2021年の曲だけど、この曲のアウトロ、俺がいま中学生だったら友達と一緒にリピートして無限に爆笑してたわ絶対
46位 Familia/Camila Cabello(音楽)

元々グループ活動してたので、若いけど活動歴やたら長い人。これも今年人気だったやつでラテンっぽいアルバム。かわいい。テイラースウィフト~オリヴィアロドリゴ的な(やたらこの人の名前出ますね、好きなのかなオリヴィアのこと)、メタファーを使うとかではない直接的なリアリティショー感のある歌詞。
そしてアルバムタイトルはスペイン語で「家族」の意味らしく、アートワークもそういうテイストだし、SNS休止宣言とかしてたりしてなんか全体的に冷静で意識高い感じ含めて、もうどこをどう見ても「2020年代のアメリカのZ世代」ってイメージなんだけど、僕のこのイメージ合ってるのでしょうか。
45位 The Gods We Can Touch/AURORA(音楽)

ノルウェーのシンガーソングライターの天才少女系のZ世代の人。大自然のなかで育ったらしい。そしてほんとに大自然っぽい(?)音楽。ちょっと前のやつ聴くとかなりファンタジー色が強いんだけど、今回のアルバムはギリシャ神話が参照されつつも同時代的なメッセージ性を感じさせるものになってる。あとメロディアスなので歌謡曲っぽく聴けると思う。癒し。このMVはなんか「ペンギンダンス」としてTiktokでバズったらしい。知らんけど。
44位 浅煎りコーヒーと自然派ワイン Typica「いちじくのパフェ」(パフェ)
ガチ勢には遠く及ばないものの、最近ちょくちょくパフェを食べるようになった中で、これはやっぱり完成度高かった。フルーツをどーんと載せるフルーツパーラー系よりも、Typicaみたくスイーツ的・物語的な構造で工夫するパティスリー系のほうがそもそも好みっていうのもあるけど。食感とか、食べるスピードまで含めて計算してるんだろうなと思わせるやつ。
このパフェだと「揚げいちじく」とか入ってたり、まだ食べれてないけど果物じゃなく野菜とかをメインにした「オードブルパフェ」なる品もあって、食材のオルタナティブな魅力を提示するフォーマットとしてパフェは機能しやすいんだろうなと思った。一定の形式さえ守ってれば(世界には最早それすら守ってないやつもあるが)他はすごい自由にアレンジできるから。
43位 かんみ:旬の柑橘の食べくらべの定期便(柑橘)
11/26(土)-11/27(日)で全ての対象者の方に『かんみ』11月号を発送しました🚚
— かんみ|かんきつのサブスク (@KANMIofficial) November 27, 2022
ブラックフライデーと重なり、配達の遅延も発生しているようなのですが届きましたらぜひ #かんみ でご感想を呟いてみてください🍊 pic.twitter.com/DNJT7QmqGj
東大みかん愛好会創設者で「株式会社みかん」代表の清原優太氏の立ち上げた、柑橘の定期便。1年続けると合計82種類が届くらしい。オリジナル解説冊子も付属。
柑橘に限らずフルーツ全般において、「いろんな種類がある」「いろんな方向性の魅力がある」と知らせることまではわりと簡単でも、「じゃあ自分に合っているものを選びましょう」というところまではなかなか進みにくいのが現状。
そんな中「とりあえず申し込めば毎月めっちゃ多様でおいしい柑橘が届く」というパッケージを作ったのは重要だし、清原さんが生産者ではなく「いろんな生産者とつながりのある一消費者」だからこそできることでもある。いつ何を届けるのか含めて、このパッケージを作ること自体が柑橘批評の実践だとも言えるわけです。日本には素晴らしい柑橘があふれている。
と言いつつ僕は12月号からの申込なので、書いてる時点ではまだ食べられていません。全体的に、「いくしかない!」ってタイミングを昔と比べて平気で逃しちゃうようになってきた。でもいくしかない時はいくしかないんだ。
42位 ハケンアニメ!(映画)

新人アニメ監督の吉岡里帆と天才監督の中村倫也が切磋琢磨しつつ頑張る話。辻村深月原作。ウェルメイドで面白い。中村倫也と柄本佑がやたらエキセントリックな演技をしてるんだけど、「単にそういうキャラだから」ってことじゃなくてそこに役割意識というか理由があるのもいい。
雨のなか走って倒れてカバンの中身ぶちまけるとか、やりがい搾取みたいな問題は特に言及されない感じとか、今時そんな!?というベタな展開や演出が目立つけど、終盤で「中村倫也が自作の露悪的な展開(登場人物全員殺すみたいな)を書き換えてストレートなことをやる」という展開があることからも、これは「ベタの力」を再確認させるための映画なんだと思う。そこが良い。ベタと言っても、台詞回しが過剰に分かりやすいわけでも、役者の力でゴリ押すわけでもなく。
あとこれは「集団制作の現場を描く」という現実的な設定ゆえに、クリエイター物にありがちな「エモ的描写と過剰に結びついたクリエイター幻想」みたいな描写に抑制が効いているのも評価したい。
人々のあいだで信じられる共通の価値観がなくなった今、「創作は尊い」という考えだけは揺らがずに(むしろ強化されて?)残っているというのは宇野常寛氏が指摘する通り。ただ、「創作は尊い」と大真面目に言うことはそりゃ簡単だけど(で実際僕だって「尊い」とは思うけど)、それは「クリエイターでもない奴が創作物への批評をするのはおこがましい」みたいな価値観とも表裏一体なわけで、結果、人々はファンダムの内側に閉じこもって楽しく考察遊びをしたり、「推しが尊い」と言うだけの自動機械になっていくんじゃなかろうか。
(だからって創作物に対してガンガン「批判」しましょう、倫理的な正義感を振りかざして叩きましょう、ってことじゃないよ。念のため。)
41位 暁/ポルノグラフィティ(音楽)

僕はポルノグラフィティのことを、基本的に飽き性な人たちだと思っている。だからいろんなタイプの曲がある。
サウンドや歌い方はトレンドの前線に乗っかるタイプではないけれど、特に2011年以降はプロデューサー本間昭光ではなく曲ごとに若い多様なアレンジャーと組むようになり、「歌謡曲的な安定した様式美は基本崩さないまま、アレンジはいろんなタイプのものが聴ける」という面白い状態になっている(初めて買ったCDが『メリッサ』だという米津玄師の、ポップソングの振り幅のちょうどいい保ち方は、ポルノのそれに非常に似てると思う)。
「ポルノの特徴は良い意味での偽物感」と本人たちがどこかで語っていたように、彼らはつまり、邦楽としての聴きどころを纏ったまま「○○風」の色を出すことだけをずっとやってきたとも言える。初期の『サウダージ』『アゲハ蝶』だってガチなラテンではなくラテン「風」だし、デビュー曲の『アポロ』はデジタルロック風。
で今作もアニメOP風の『暁』、ヘヴィロック風の『Zombies are standing out』、UKロック風の『ナンバー』、ソウル風の『ジルダ』、ミュージカル風の『証言』などなど、節操のなさを楽しめる。最近の若いミュージシャンのアルバムってシングル曲多めだとしてもトータルの色が相当統一されてるような気がするので、そこも反時代的。それでいい。
あとポルノの聴き方としては、歌詞を聴いたり読んだりしても楽しいと思う。近年は現代詩的な意味での文学性が強いというよりは、思考の跡を感じさせるタイプの詞も多くなっている。特にギターの新藤晴一(今作は全部この人の歌詞)は、村上春樹のデタッチメント感・ダンディズム感をポップロックの文脈に乗せることでうまいこと昇華させ続けていると思う。
「他者とは分かり合えない」「明日が今日よりいい日かどうかなんて分からない」というリアリズムが前提にあった上で、あくまでもロマンを感じさせるフィクションあるいはファンタジーとして隠喩的に語ること。
今回のアルバムで言えば『暁』『カメレオン・レンズ』なんかは今日的なカオスな状況を特に反映しているし、サウンドの面でも詞の面でも「信じられる大きな物語がなくなった時代で、過去の自分や歴史との対話によるセルフエンパワメント」みたいなことをずっとやってる人たちでもあり……まあポルノについてはそのうち書きます。
たとえばこの3曲がこの順番でアルバム内で並んでるわけなので、ほどよく楽しいと思うし、逆に「確かに今そんな流行る感じではないよな」というのも分かっていただけるかと思う。
40位 漱石を語る午後(イベント)

90年代~ゼロ年代半ばにかけて夏目漱石研究を主にテクスト論の立場から牽引してきた(=近代日本文学研究全体をかなりの程度ブーストすることにも繋がったはずの)小森陽一・石原千秋コンビがたぶん十数年ぶりに聴衆の面前で行った対談。これが盛り上がること自体、下の世代がまだこの2人を超えられていないことの証左でもあるけど、それでも次の時代のための燃料になるイベントではあった。
簡単な経緯としては、2005年にめっちゃ喧嘩した結果、2人で編集していた雑誌『漱石研究』も終刊になり、ところが2017年に編集者の仲介で再会して久しぶりの対談本を刊行。そういうアツい経緯を知る人間としては、もはやキャラの関係性のみを楽しむダメなオタクみたいな見方で堪能しました。
もちろん普通に刺激も受けた。お互いが何をどう論じてきたかを知り尽くしているからこそトークの掛け合いも面白いし、研究対象=漱石への熱量を生で浴びるのは良い経験だった。そもそも僕が文学や批評に興味を持ったスタートは小森陽一なわけだし、『漱石研究』はかの『批評空間』の磁場のもとに作られていた雑誌なので、もう一度原点に立ち返っていろいろ繋げて考えてみたいと思った。
読者論的なテクスト論というのは、「作者の考え」や「作者のバックボーン」といったいわゆる実証的なコンテクストをいったん考慮せずに作品を解釈し、そしてその解釈は「読者=『読解の当事者の自分』がそう解釈しうるのだから正しいのだ」という強硬な感じになりがちなんだけど、めちゃくちゃざっくり言えば、いまTwitterで人の揚げ足取りみたいなことをやってる人文系アカデミシャンの背景には大体こういう素朴な思想があると思う。
テクスト論はあくまでも「作者という要素をいったんは考えないようにする」というメタな態度を取りながら成立すべきものなのに、メタがベタに転化した結果、「批評はコミュニケーションなのだ」みたいなポジティブな批評礼賛的な態度と共に世に出回るようにもなり(2021年に出た北村紗衣『批評の教室』とかが典型)、一定の思想を共有した人々のあいだだけでその「解釈」がグルグル回るようになった。
そういうSNSや(外から見た限りでの)アカデミズムの状況を見るにつけても、日本で言えば少なくとも小森・石原に立ち返って考えるべきだと思うのです。
面白すぎるせいで自分がいくつかの道を踏み外すきっかけになった石原千秋・小森陽一の漱石対談本が文庫になっていた。感慨深い。みんなも読もう pic.twitter.com/01beOip6fz
— あいけ (@aike888g) March 11, 2022
まあそれはそれとして単に面白いので、みんな読もう!
39位 エルピス—希望、あるいは災い—(ドラマ、フジテレビ)

テレビ局のタブーとか含めて扱う社会派ドラマ。画面とか演出とかフジテレビが急に本気出してきたやつ。このくらい社会派でありつつ骨太な面白さなのはすごい。
眞栄田郷敦が残念キャラを全力でやってるおかげでユーモラスで観やすいし、会社組織の男社会に抑圧されつつも戦う長澤まさみがリアルで良い。キャラ造形も「単純な正義」という感じではない。演出は大仰だけど、まあそれくらいやっちゃっていいのではみたいな。
ただ、実在の事件を複数合わせてフィクション化するときの手つきとか、社会の悪や真実の描き方においてはどうもポストトゥルース以降の複雑さには対応してなくて、現実の後追い感がある。で、調べると「TBSでボツになった企画が6年を経てフジテレビで通ったやつ」らしく、そりゃ2010年代中盤感があるわけだと納得。というわけで「2010年代のドラマとして」すごく面白いです。
38位 黄金比の縁/石田夏穂(小説、『すばる』掲載)
人事部の採用チームにいる主人公が、会社への反発から「ダメな人材を採って会社に復讐するのだ」とか考えて色々採用の基準とか試行錯誤する話。終盤はちょっと落ちるのと、時系列も分かりにくいけど、語りがユーモラスなのでめっちゃ面白い。小説という文字媒体の快楽のひとつはやはり「なんか面白いやつが面白いことを語っている」ことに尽きますよ。
作者は2021年芥川賞の候補になった『我が友スミス』の人で、身体性とそこから生じる不平等、みたいなテーマが一貫してる人だと思う。何よりも、今回は「弱者」側ではなく「強者」側を描こうとしてるのも良い。性別に本当にまったくこだわらないで見ていたら、むしろ女性を自然と優遇することになってしまったりとか、最終的には「顔」という身も蓋もないことを言い出したりとか。
これは単に反ポリコレやバックラッシュってことじゃなく、構造的な「社会的強者(ここでは採用担当)」の側がルッキズムの問題と真剣に向き合ったからこそ反動的なアウトプットが出てしまうこともある、それを踏まえてどうするべきか、という2020年代的な重要な話だと思う。早川書房の『「社会正義」はいつも正しい』に脊髄反射的にキレてる人とかに読んでほしい。
37位 Dr.STONE/稲垣理一郎、Boichi(漫画、週刊少年ジャンプ)
今年完結したSFマンガ。全人類が石化して文明が滅んだあとの世界で、蘇った天才科学者が発明の力で再び人類をなんとかしようとする話。
国内SF小説がハードな要素や科学要素を失ってどんどん純文学化・ファンタジー化している昨今(僕はそれ好きではあるけど)、この規模のSFをまじでやり抜いたのがすごいし、最近のジャンプはこれとか『トリコ』みたいな世界観構築がしっかりしたデカい作品が少ないので、ありがてえありがてえ~と思いながら読んだ。Eテレ感があるのはご愛嬌。
とは言ってもジャンプなので、読み味としては異世界転生的・俺TUEEE的なロマンをしっかり感じられて良い。最後のほうで、達成目標が非現実的であるがゆえに頭悪いSF感が増していくあたりも最高。アツさでは決して『三体』シリーズにも『プロジェクトヘイルメアリー』にも負けないと思う。
36位 初恋の悪魔(ドラマ、日テレ)

坂元裕二のミステリ×恋愛もの。毎回の事件とは別に大きな謎がひとつの軸を貫いてるやつ。坂元裕二特有のこっぱずかしさみたいなものはありつつ、毎話事件を解決するスタイルだしコメディ色も強いので見やすい。『こちらあみ子』と同じで、林遣都の変人キャラはふつうに笑えるんだけど、それを笑えるのって「まともな人間」側だからだよね?という批評性は当然入れてくる。テーマとしては、今っぽい「多様性」概念を人の内面にまで広げたという感じ。普通にいい話。
『anone』で名言切り抜き消費を、『花束みたいな恋をした』で固有名大好きクソサブカル人間を皮肉ったように、今回はSNSやYouTubeでの「考察」ブームへの皮肉にもなってる。いいぞいいぞと思った。
さらに、「反物語」と言うと文芸批評で使い古されたワードになっちゃうけど、すべてがパチンときれいに収まる野木亜紀子的な「気持ち良い物語」へのアンチテーゼも明らかに提示している。つまり事件の背景とか別に分からなかったり、色々回収されないまま終わったりする。
そういうシナリオの細部とか「考察」とかより、この四人の関係性や恋愛や人生が重要なのだ、というミニマリズム的な(=ミステリと言いつつ結局は普通に坂元裕二的な)見方を提示していて、観てる側も自然と乗っかれるようになってる。
なお松岡茉優は私の人生において大変重要な概念なので、単に執着心はある。
35位 君のクイズ/小川哲(小説、『小説トリッパー』初出)
SF作家ということになっているがSF以外のほうを多く書いている作家こと小川哲の中編。これもSFではなくてクイズプレーヤーが主人公で、「早押しクイズで問題文が読まれる前に回答して(つまりゼロ文字押しで)優勝できたのはなぜか」という謎を追求していく話。
小川哲はロジカルに小説を組み立てる人で、とりわけモチーフAとモチーフBの構造を重ね合わせることによって浮かび上がる美しさみたいなものが魅力だけど、今作は「競技クイズ」「ミステリ(謎解き)」「人生」の三重構造。とくに最後の「人生」が効いていて、結局、実存からしか人は何かを始められないし、そうだよね観念的なロジックばかりこねくりまわしてる場合じゃなくて人生って大事ですよねえ……という気持ちになって反省して感動した。僕は4つ目の層として「批評」を勝手にイメージしながら読んだ。
なお直木賞候補になってる『地図と拳』は、外連味も構造もなにやら中途半端に感じ(このテーマで今ここまで書けるのはすごいと思うけど)、僕には小川哲は『嘘と正典』とか短編のほうが良いように見える。
34位 今、何処/佐野元春&THE COYOTE BAND(音楽)

ブルージーなポップロックみたいな言い方でいいのかな。個人的には佐野元春に今まで思い入れがなかったけど、ハードボイルドでありつつ、いまの世を冷静に俯瞰して柔らかくアウトプットしたならこういう言葉になる、という詞になっててすごい(書いたのはコロナ禍以前らしい)。
曲はわりとオーソドックスだけど、「この曲のこのタイミングで、この言葉を強調して聴かせたい」みたいな技術をめちゃくちゃ感じる作り。ポルノとかにはこれは備わってないやつ。
33位 フィールダー/古谷田奈月(小説、『すばる』初出)
オンラインソシャゲとリアル世界の二軸で進む、社会派お仕事物小説。たぶん骨太すぎるので芥川賞にはノミネートされてない。社会問題にタッチしつつも、もうちょいぼんやりしてるほうが今の芥川賞向きなのかな。
芥川賞をとった2020年の宇佐見りん『推し、燃ゆ』は、ある事件で推し=偶像が崩壊して、その真実が分からないままの世界でどう生きるか?という話だったけど、これはアイドルよりもう少し身近な(=コミュニケーション可能な)偶像の話であり、真実が分かってしまったあとにその相手および社会とどう接するか?というところにまで及んでいる。
すると必然的に、特に3・11以降問われ続けてる「当事者」と社会正義の問題系に抵触することになり、リベラル的言説の欺瞞だとか、出版社という情報発信側の人間である主人公がどのように倫理を守るか?という話にもなってくる。表紙の帯にも書いてある通り、社会的イシュー大盛り(大盛りすぎて胸焼けはします)。でも文体はサラッとしてて読みやすいし、設定とかキャラ造形にも破綻を感じないのでまあ面白く読める。
タイトルの意味は、フィールドワーカーではなくフィールダー、つまりフィールドを走り回る「当事者」ということで、主人公も基本的には正義感に基づいて当事者たろうとして動いている。けどそれだけじゃなくて、「かわいい」という私的な動機でも動く。
特定の対象を「かわいい」と思ってしまうことはは暴力的なことでもあり、しかし人間にはそういう面があり……と、いろんな側面や登場人物を(単一の価値観でジャッジすることなく)並立させて描くことができるのはひとえに真面目で平易な文体の力。逆に、大人のリアルをリアルに描こうとしたらこのくらい真面目な文体にならざるを得ないってことか。難儀。
32位 ネオン/水曜日のカンパネラ(音楽)

パフォーマンス力というか表情筋というか上半身のコントロール能力どうなってんだよ、となるファーストテイク。
基本ダンスミュージックっぽいトラックで、ネタ要素多めの変なラップをする人たち。サブカルっぽい。けど2021年以降はボーカルのコムアイが脱退して2代目・詩羽(うたは)が入ることでよりポップ方面に振れていて、そんなにサブカルっぽくもない。ハイパーポップ的要素とギャルマインド的価値観もマッチしているし、わりと普通めな歌ものもある。
『織姫』という曲は「織姫がもしギャルのラッパーになったら」のifストーリー。実際詩羽はギャルマインド概念についてもインタビューで言及していて、自分をギャルだと自己規定してるらしい。やっぱり2020年代はギャルなんですよ。
そして詩羽によれば今は「エモい」ブームは終わってて、「アツい」とかの時代らしい。いい話。
これは、ちゃんと今までの路線も健在だぞ、という曲。
31位 LOVE ALL SERVE ALL/藤井風(音楽)

なんか色々すごい人。宗教との関係で色々言われてるけど別にどうでもいいと思う。サウンドは王道ポップスだけど力の抜けたチル感もある。
この『まつり』の詞なんて本当すごいですよ。コロナ禍以降のZ世代が世界に絶望しないためには、競争を遠ざけ、終わりなき日常を肯定し、根拠はなくとも疑似的な祝祭を仮構するしかない、という話。
これはTiktokの影響で今年世界でバズった曲。死ぬのがええらしい。
30位 our hope/羊文学(音楽)

サブカルの人たちに好かれてるオルタナロック系バンド。3ピースなので音はシンプル。前作までよりもポップに振りつつ、シューゲイザーっぽいやつとかざらざらしたロック色強いやつとか色々あって楽しく、全体的には清涼感・癒し感を感じさせる。
『光るとき』はアニメ『平家物語』の歌。僕は平家物語の原作厨である自覚があるのでアニメはまだ観れていないんだけど、確かにゆったりと滅びゆく平家および令和の日本にもピッタリな祈りの歌でもある。
29位 Queendom/Awich(音楽)

いやこれはさすがに入るだろ、と思ったいくつかのうちの一つ。フィメールラップの女王、というか性別関係なく今一番すごい感じの人。ポップ寄りではなくあくまでハードなヒップホップ感。ボースティング的な要素が強めのゴリゴリ系男性ラッパーには僕はどうにも乗れないので、Awichに限らず今年はフィメールラッパーを聴くことが多かった。
私小説的・キャラ的に消費しすぎるのはもちろん良くないとはいえ、最近のメディア露出とかからも、メジャーの場においてAwich自身の背負っている何かの責任感みたいなものを感じるし、それがサウンドにもリリックにも反映されていて(同時に内省的でもあって)なんかもうすごい。
28位 Killer in Neverland/4s4ki(音楽)

ハイパーポップの不思議少女系の人。2020年とかのやつ聴くと、ストリート感、高音の声から来るエモ感を感じるんだけど、そこから徐々に色彩含めてマキシマリズム的なキッチュ感のほうに寄せていって世界観が強くなり、2021年末~2022年にかけて仮想空間的想像力と完全に融合を果たしたのが面白い。VTuberとか『スプラトゥーン』以降の世界のデフォルトラインという感じがする。
なんか淡々と低音使ってきたり、掠れ感あるのも良い。でもDAOKOみを感じる部分もある。2010年代のDAOKOから2020年代の4s4kiへ、というラインは、時代精神を考える上で何かある予感がしている。
あと海外のハイパーポップ系って単にうるさくて全然好きじゃないんだけど、この人は普通にメロディアスに歌ってくれるので個人的にはわりと聴きやすい。
27位 チェンソーマン(アニメ)

底辺の少年がなんかヒーローっぽい力を手に入れ、よく分からん美女に懐柔され、少しずつ良い生活を目指すことになっちゃう話。
『少年ジャンプ』に連載された原作のバカなポップさ(ひとえに藤本タツキのマンガ技術によるもの)よりも、劇映画っぽいリアリティある空気感のほうをおしゃれに強めに押し出したアニメ化。実際原作にあった見開きのパンチ力とかが弱くなってはいるんだけど、アニメアニメしたトンマナにあまり肌が合わない僕にはこれがちょうど良い。原作厨とかがSNSで色々批判してるけど全無視でいいと思う。
「やんぐはうすらじお」出演時にも話したけど、連載立ち上げ前に「冴羽獠、ぬ~べ~みたいな性的欲求を求めるジャンプ主人公が最近は減ったよね」という話を藤本タツキと林士平(ジャンプ+で無双してる編集の人)がしていたらしく、だからこれは「自分の欲望の在り処を問い直せ」と1990年代生まれの若者に向けて言っている作品なわけです。そして欲望が本来的に、性欲みたいな非倫理的なものや、現代の病とされる承認欲求とも切り離せないんだという話。こういうことをやってくれるポピュラーなコンテンツは今時なかなか少ない。
あと米津玄師のOP主題歌『KICK BACK』。平成のセンチメンタリズムを終わらせ、大衆的な邦楽を引き受けつつも令和的メランコリーの幕開けを告げたのが『Lemon』だとすれば、『KICK BACK』はモー娘=平成のポップな側面を引用しながらコロナ禍以降のきたるべき狂騒感を一手に引き受けている。『少年ジャンプ』のジャンプ性を継承しつつもアンチテーゼを提出した『チェンソーマン』と米津がここで合流するんだなあと、勝手に感動した。
26位 Unlimited Love/Red Hot Chili Peppers(音楽)

レッチリが今年2枚アルバム出したうちの1枚目のほう。ジョン・フルシアンテ復帰作。レッチリについて色々うるさいレッチリおじさんたちは「こういう地味でハッピーな安定感をレッチリに求めてない」とかなんとか言ってたりしてて大変そう。僕はスローでメロウでミニマリズムっぽくて(そしてなんか懐古的で)良いと思った。ただ今年の2枚目のほうの『Return Of The Dream Canteen』のほうが分かりやすく良いのは分かる。
25位 トップガン マーヴェリック(映画)

「若者たちが不甲斐ないせいで、引退したはずの教官トムクルーズが頑張る」という20世紀的・白人男性的・懐古的なやつ。
鑑賞時のメモに「アツい!!!」としか記されてないせいでディテールを何ひとつ書けないんだけど、とにかく映像も音もすべてがアツい映画。今こういう父性的なマッチョな話がここまでウケるんだな~とびっくりした。世界のポリコレ疲れを感じる。まあでもおじさんたちが全力で没入できるコンテンツって今あんまりないので、デトックス的な意味でも大事なやつですよ。おじさん予備軍としては。
「敵が何者なのか」という外部の事情とかをまったく描かないという、『エースコンバット』のゲーム部分のみを取り出したような作りは、余計な(とあえて言ってしまうけど)社会性を排除してトムのかっこよさを満喫するための仕掛けとして最高。こういうのもっと作ろうぜ。
ちなみにこれは「鑑賞時の気持ちよさ」って意味では、ベストハンドレッド5位以内には入って来る作品なんだけど、でもそういうことじゃないんです。
24位 リコリス・ピザ(映画)

ポール・トーマス・アンダーソンの、ロサンゼルスの70年代を描いた青春恋愛もの。普通に懐古的なのでまあ『トップガン』みたいなもの。長回しが多く、ナレーションもなく、どこかダメな人間たちを描き、起承転結とか伏線回収とかは特になくエッセイみたいなノリで進む、けど演出とか画面が良いので観れる。
「サブスクのTVシリーズ隆盛の中、映画にやれることはストーリーではなくなっている」と宇野維正氏も言っていたけど、確かに『トップガン』『ONE PIECE FILM RED』的な映像音声スペクタクルor『リコリス・ピザ』的なエッセイっぽい作品、という感じで二極化していて、中間のものが目立ちにくくなっているとは思う。
キャラの描き方としては、ダメな男性性を描きつつも、主体的な女性像を描けてはいた。全体的に話がとっちからっていたおかげで、「大人の女性に少年が導かれて成長する」みたいなありがちなやつからは抜け出すことができてて感心した。
23位 N/A/年森瑛(小説、文學界新人賞受賞)
金原ひとみが「欠点がないこと以外の欠点が見当たらない」と含みのある褒め方をするくらいにはよくできたZ世代文学。
全体のなかで自分の状況すら俯瞰しながら「カテゴライズは良くないよね」と思っているリベラルで賢い主人公が、しかしカテゴライズの暴力性・利己性の中から抜け出せていないことが分かる(でもバッドエンドってわけでもなくて救いもある?)、という話なので、何重にも正しい。正しいだけじゃなく文章もうまいので、読ませる。
というか「正しい」と書いたけど、それ自体は別に重要じゃなくてもうただの前提条件なんですね。作者もこれ別に「正しさをめぐる話にしよう」とかじゃなくて生理の身体性みたいなところから書き始めたらしく、だとしたら、意識せずともフラットにこれが出てくるというところにやっぱりZ世代のリアリティがある。(作者インタビューを100%鵜呑みにするのも若干あれだけど。)
いまどき文芸誌に載ってるやつも、2010年代的なパラダイムを経て、単純なポリコレや傷つきに対するシニカルさみたいなものは標準装備になってるものが多い気がしていて、(面白いかどうかは知らないが少なくとも倫理的には)けっこう良い感じなんじゃないかと思う。マイノリティ意識を前面に押しだすんじゃなくて「生理で血が出るのが単に嫌だ」という主人公の「傷ついてなさ」や、対応のそつのなさは、「深さ」を無条件で良しとする人文的な価値観へのカウンターとしての「浅さ」になっていて、良い。
22位 くるまの娘/宇佐見りん(小説、『文藝』初出)
ストレートな家族もの+ちょっと旅もの。あのキャッチ―な『推し、燃ゆ』の作者にこんな近代文学みたいな中上健次もどきみたいなフック弱いやつ書かせてる場合じゃないだろ、という意見も分かるけど、オールドスタイルなものを作っていくのも文芸誌の役割だとしたら(それは半ば諦めでもあるが)僕は単に作品の強度を評価したいと思った。
『かか』よりも乾いた自然な文章で、『推し、燃ゆ』よりもレトリックが鼻につかない。このレベルで文体をチューニング可能なのかこの人……と驚嘆した。文学、宇佐見りんだけいれば十分じゃん。と一瞬思ってしまうくらい。
基本とてもミニマルな家族の話で、外のなにかが介入したりせず、家族にも何も起こらない。問題も解決しないまま日常が続く。「傷つけてくる相手からは逃げろ」という巷の耳障りのいい、今っぽくてポリティカルにも「正しい」言葉に、主人公は違和感を覚える。むしろ家族が単なる「嫌なやつ」だったら思い切って逃げられるかもしれない。けれど現実はそこまで単純じゃなかったりする。『N/A』はその複雑さを描くためにある技巧を必要としたんだけど、『くるまの娘』はそのへんの複雑さを前提として含んでいる。
車という、『ドライブマイカー』的な共存の場にも、心中の道具にもなる乗り物を使っているのも良い(残念ながらきれいに活かされてるとは言い難いけど)。ネガポジどちらのルートもまだありえる。いま生きているのは、今までたまたま死ななかったから、というだけ。
いくらZ世代だなんだと言ったって、フラットに(『N/A』のごとく)、スマートに、ポストモダンになんて我々は所詮生きられないんだ、と宇佐見りんは1作目からずっと言っている気がする。だからこそ僕は「優れた近代文学」として『くるまの娘』を評価したい。
あとテーマ的には、今やもはや大事なのは「父殺し」なんかじゃなく、「母性との対峙」でもなく、父も母も勝手に死んでいくんだなあと思った。
21位 リコリス・リコイル(アニメ)

かわいい女の子2人がバトルとかを頑張るアニメ。「世界や社会の大きな悪をどうするか?」という天下国家の話になりそうに見せかけて、「世界は変わらないのでミニマルな関係性を大事にしよう」という話(実際作中でも悪役のやつが「現状を維持するやつ」ってセリフ言ってくるし)。『まどマギ』的なでかい話に対する2020年代的な回答として優れてると思った。アメリカのZ世代には政治的にコンシャスな感じがあるかもしれないけど、日本のZ世代にはもうミニマリズムしかないんですわ。
で、それらのテーマ性を扱えるのも、我々がちさと・たきなの関係性を素晴らしいものだなと思えるのが前提なので、単に尊い~と思いながら観ればいいんだと思う。9話とか最高。
リアリズムのバランスがちょうどいいし、全体的に演出に抑制が効いているのも観やすい理由のひとつ。真島によるリコリス狩りもだけど、たきなの傷に絆創膏とかがちゃんと貼ってあるから彼女らは「死ぬ身体」なんだなあ、と思えるのもいいよね。ちゃんとドキドキできる。5話の人工心臓のくだりとかも、尺使ってオーバーにやったりはしないのが上手い。
20位 Beatopia/Beabadoobee(音楽)

イギリスのシンガーソングライター。バリバリZ世代の人。このアルバムのビートピアってタイトルは「7歳の beabadoobee が想像の中で作り上げ、それ以来持ち続けている、ファンタジックでありながら深く個人的な世界を表現しています」ということらしい。そらそんなの好きだわ。
アメリカの若いやつは聴いてるとなんか強すぎて疲れる感じがあるので、やっぱイギリスでいくしかないですよ。かわいいウィスパーボイスと暖かいアコギ。一時期ほんとうに鬱々としていたとき、このアルバムしか聴けない時期というのが2~3日あった。
19位 Wet Leg/Wet Leg(音楽)

ミニマルなカントリーっぽいインディーのUKロックの人たち。Z世代よりは年上。憂いを帯びているんだけど癒される声、淡々としてるんだけどキャッチ―で激しい。90年代ロック好きにノスタルジー的に刺さってるところがあるらしい。
Spotifyのいわゆる「サッドガール」的な感じもなくはないんだけど、ガチな内省的な暗さではなくあっけらかんと自虐・ユーモアを織り交ぜながら歌っていて、実際サウンドもそうなってる。
あと2人ともワイト島っていう島の出身らしいですよ。ほぼポルノグラフィティ(広島の因島出身)じゃん。出身地とかをサウンドと紐づけすぎるのもあれだけど「都会的な鼻につくスマートさがない」というのはどっちも共通してるので、自分はそういうのが好きなんだなと思った。
なんかもうさっきからエピソードの話しかしてないダメなおじさんと化してるわけだが、「大学時代から親友だったふたりが楽しく過ごした夏の日々を何度でも繰り返したいと、その気分に相応しい曲を作ろうとしたらWet Legの音楽になった」らしいよ。そんなことある???
18位 TITANE/チタン(映画)

ジャンルはボディホラーって言うらしい。すぐ殺人とかしちゃう主人公の女が他者(知らんおじさん)との共生で更生する話。そして家族の拡張の話であり、なにかを支配して繋ぎ止めたいと思ってしまう男性性の話でもあり、ただし「キャラが時間をかけて変化する話」という意味では超絶王道。うまい。うますぎる。ラストは母性+自己犠牲みたいな要素が入るので、賛否両論ある。まあ確かにねえ、とは思った。
ジュリア・デュクルノー監督は1作目『RAW 〜少女のめざめ〜』もカニバリズムの話だし、『TITANE』も痛そうな描写がまじで痛そうすぎて何回か帰りたくなった。主に音とシチュエーションのせい。それも含めて、ちょうど小説のことを色々考えてた時期だったこともあり、映画はこういうことできるからずりーな~~と思わされる要素が多々あった。
具体的には、同じ役者が言葉もナレーションもなしに、心を開きつつあるのを表現できたり。人を殺していたその手と道具が、似たような視覚的・反復的モチーフとして、しかし今度は人を救うものとして使われたり。踊り子だったときの音楽という要素を、バトルやら心肺蘇生やら女性性表現としてのダンスやらで使ったり。ずるー。どれも文章でやろうとすると説明的になりすぎちゃうやつ。
テーマ的には、異常な殺人衝動にどうやら理由がなさそうなのも重要ですよね。世代的なものなのかな。トラウマだ何だと、悪に理由をつけて語る『ジョーカー』という映画もこの世にはあるらしい。
17位 ミズ・マーベル(ドラマ、Disney+)

マーベル好きなオタク女子が突然ヒーローになる話。それと家族の問題、民族の問題が絡み合ったやつ。
全体通してポップな演出も良いし、元が一般人の少女設定だから「成長」を描きやすくなっていて、2話の少年助けるシーンとか、6話の手作りコスチュームのくだりとかもう本当に素晴らしい。とはいえ中盤は急に世界史の資料集読まされてる感が出てきて(そのせいで評価落ちるのはめっちゃ分かる)、学園もののままやってくれたほうが個人的な好みではあった。
他にも主人公の「マーベルオタクで空想に耽ってばかり」というキャラがあまり活かされなくて残念とか、キャラが次々出てきてお前誰やねんとか、いろいろいびつではあるけど、SNSドキュメンタリー感の使い方は今っぽいし、「もはやヒーローは個の力でいくのではないのだ」という『ヒロアカ』感もある。カマラがピンチになったときの両親の反応とかもいちいちぐっとくるし(家族の問題を正面からやっててすごい)、「ミズ・マーベル」のタイトル回収も良いです。
16位 映画クレヨンしんちゃん もののけニンジャ珍風伝(映画)

しんのすけが実は忍者の里の子だった!?という話。家族、アイデンティティ、ムラ社会、女性の能動性、災害、父性的ダンディズム、みたいなイシューてんこ盛り映画。よくできてる。
家族の問題がそれにとどまらず共同体の問題につながり、最終的にはカスカベ防衛隊がわけわからん超越的センスオブワンダーみたいなノリで解決するのが良い。「わけがわかるもの」だけ摂取してんじゃねーよ、という気概を感じる。
明確に泣かせに来てやがるシーンはひとつだけあったことはあったけど、クライマックスを「泣き」じゃなく「笑い」で彩るあたり、全体としては『オトナ帝国』的な安易とも言えるセンチメンタリズムへのカウンター精神はあったと思う。あと複数のキャラが明確に「自分の感情や弱さと正直に向き合い、抑圧から自分を解放する」という構造で動いていて、2020年代のやつだ!と思った。
今回はしんのすけの描き方が良い。物語が家族の取り違えの問題から始まったがゆえに、今までとは違ったアイデンティティクライシスの不安が出てきて、ひとりで過ごしてるときにしんのすけが静かに泣くんですよ。しんちゃんのいつもの悪ふざけっていうのは「そこに他者がいるから」こそ発動するもので、一人だったらしんちゃんだって普通の子供なんだな、そしてうわーんとかではなくしんみり泣いてしまうんだな、と思った。切ない。良い。あと川栄李奈が声優うまい。
15位 長谷川彰宏 個展「よもぎとコンプ」(美術)
モギケンも絶賛の、若手の画家で僧侶の資格も持つ長谷川彰宏氏の初個展。
特に地下1階の作品が白眉。アクリル板をうまく使うことで、デジタルのスクリーンの発光の感じをアナログで表現し、仏教美術の本来の(たとえば如来像の螺髪が鮮やかな青色をしていたように)ケバケバしい異世界感を21世紀的・デジタルネイティブ的な想像力のもとに復活させる。
まあでも論理的に云々というよりは、単純に観ていて癒されるところがまずは良い。絵すげ~ってなる。人の顔があるのも大事。
そして、傷つきを癒すためには結局は「時間の経過」が重要だというのは『シンエヴァ』『ドライブマイカー』など2020年代のコンテンツ群が指し示す通り。で長谷川氏の絵もまた、重層的な塗り、具体性・抽象性の共存、見る角度によって変化する光などによって、「時間の経過」に耐えうる強度をそもそも構造として孕んでいる。というか要するにずっと観ていられる。昨今言われるマインドフルネス的なカジュアルなスピリチュアル消費でなく、ガチ仏教美術の、しかも「触視的平面」(東浩紀の議論を参照)の時代における超越性の回復の契機がここにあると思う。
あと光の性質上、この絵はスクリーンの画面を通したときよりも、自分の目で観たほうが発色がきれいに見える。ポストモダンの世界は、近代の「見る/見られる」的な二項対立、あるいはそれに基づいたテクスト論的な解釈可能な奥行きが失われたと指摘されて久しいけれど、長谷川氏はスーパーフラット化した世界において「わけのわからない、新しい奥行き」を復活させようとしているように見える。
風景にはあまり興味ないらしいけど、この青い絵なんかは写実的な人物画ではないからか、人間の身体と背景(バーチャルな風景のような)の境界は曖昧なように見える。基本的に風景派(?)の人である僕がグッとくる理由もたぶんそこにあると思うんだけど、このへんはもっと考えたい。
14位 井の頭自然文化園 アムールヤマネコ(動物)

2022年5月13日、井の頭公園(吉祥寺の近く)の敷地内にある動物園で、絶滅の恐れがある希少種のアムールヤマネコが4頭生まれた。で、やつらが10月末から公開飼育されているので、見るべき、という話。現代思想系の人たちも「ポストヒューマン(キリッ」とか言ってる場合じゃなく、まず絶滅しかけのヤマネコとか見たほうがいい。
いまアムールヤマネコが見れる動物園は日本で5つらしい。関東地方では那須どうぶつ王国(栃木)とこの井の頭自然文化園だけで、しかも幼いやつが見れるのはたぶん井の頭だけなんじゃないでしょうか。ヤマネコも大人になるとトラみたく「縄張りエリアをひたすら往復する」みたいな謎の動きをし始めたりするので、自然なあどけない動きが見れるのは今のうちだけなのかもしれない。
しかも今は4頭一緒に展示されてるのだけど、いずれ成熟しちゃうと繁殖の管理とかの都合上、分けて飼育せざるを得ないので、いつ頃まで一緒に暮らせるのかは不明とのこと。つまり4頭が固まってわちゃわちゃしているのを見れるのも今がチャンス。
ちなみに井の頭自然文化園はリスが無限に放し飼いされてる無秩序な謎空間があったり、いいところだと思います。人類にとって大事なのは別に中央線とかじゃない。吉祥寺が重要。
13位 3級(映画)
次に何を起こすか分からない(唐突にれいわ新選組の代表選に出馬するなど)、「ふーんおもしれー男」を地で行く人間こと古谷経衡氏によるドキュメンタリー映画。これはぜひまっさらな状態で初見を終えて、シラスの延長部分まで観てほしいやつ。
古谷さん本人含めて精神疾患の当事者を扱ったものなんだけど、正常と異常の境目、リアルとフィクションの境目、最終的にすべては攪乱されるのだった。独特のリズムによってユーモラス感が出ているのも良い。
12位 ファイトソング(ドラマ、TBS)

TBS火曜は『逃げるは恥だが役に立つ』『恋はつづくよどこまでも』『私の家政夫ナギサさん』の枠。つまり社会的イシューを明確なテーマにしたり、しなかったりしつつ、ストレスなく見れる感じの恋愛ドラマ枠のやつ。
人生が停滞してる清原果耶と、落ち目になって再起を図るバンドマンの間宮祥太朗が、曲を書くためという名目で恋愛をするんだけど最終的にガチで好きになっちゃう系パターンの話。
主人公は恋愛もしたことないし、事故で夢破れて挫折状態(+いずれ手術で聴力を失う可能性がある)にあるんだけど、その不幸をことさら強調するでもなく、自意識に苛まれるでもなく、ナチュラルに道を見失っていて特に展望もない、しかしそのまま平坦にぼちぼちやっている、みたいな感じが2020年代っぽい。
そしてこれも「自分の感情と向き合い、頑なな心をほぐし、弱さをちゃんと吐露できるようになるまでの物語」なんですよ。失われたものは失われたままなんだけど、それでもまた歩いていく。喪失と再出発。それでいてほっこりできる。最高。かんそうさんの感想記事じゃないけど、間宮おまえ…!!とか、風磨ぁ!!とか思いながら観ました。ええ。
これ「Z世代的」と言っていいと思うんだけど、ナチュラルに相手の気持ちを尊重しようと努めるのが現在のコミュニケーションの基本形になっていて、それゆえに「相手を尊重するがゆえに身を引く、我慢する」みたいな態度がデフォルトで搭載されちゃってる気がする。このあと言及する予定のもう一つの恋愛ドラマにもそれを感じる。
で、そこを突破するにはある種のバカみたいな能動性が必要で、だから終盤の間宮が急に「いわゆるラブコメ」みたいなベタなことし始めるのがほんとに良いんですよ。このドラマが1話から「恋愛に負けたくない」「ラブコメみたいな展開はやだ」とか謎にメタ的なことを言い続けたのはこのためだったのかと。
「メタからベタへ」という言い方は批評とかでは基本悪い意味で使われることが多いんだけど、メタな立場に立ってるだけじゃ何もできないのもまた確かだよなあ、と思った。反省しました。Z世代のひとりとして。「メタを経由した上で、メタを一旦オフにする」のが来年の目標。
11位 カムカムエヴリバディ(ドラマ、NHK)

朝ドラ。母娘3代の、偶然性を孕んだゆるやかな継承と、トラウマからの回復、家族の回復、日米交流の回復の話を、メタ朝ドラ視点を入れながらやる話。
僕は1週目くらいの時点で「これはグローバリゼーションとナショナリズムの話になるに違いない!」とかひとりでバカみたく盛り上がってたけど、別にそんなことはなかった。そしてそうならずに抜群に面白かった。
第1世代=上白石萌音、昭和の朝ドラ的な高度成長ラインの崩壊。第2世代=深津絵里、戦後日本のアメリカナイゼーションの明暗と、自己実現の不可能性。第3世代=川栄李奈、日米の架け橋の再構築と日常の肯定。
……とか図式的にまとめられはするんだけど、これは何よりも「自己実現をできなかった敗者のための物語」になってるのが良い。江藤淳~加藤典洋ラインの、結局アメリカの属国みたくなってるじゃん問題は温存されるんだけど、まあいいんだそんなことは。朝ドラなんだから。
第1・第2世代それぞれの傷を、第3世代が歴史との接続によってケアする。しかしそれは第3世代の重荷としてではなく、時間の経過の中で自然と癒えていく+第3世代の能動的なアクションによって為される。
朝ドラへのメタ言及も、嫌味にならない程度にうまくやってて感心した。第2世代のオダギリジョーがずっと朝ドラを観る人だったりとか、第3世代の本郷奏多が時代劇のスタジオで「毎週放送するドラマなんかで、いい作品作ろうなんて思ってる奴はいない。単にいつも通りやってればいい」みたいなこと言ってて、これ完全に朝ドラのことなんですね。
それに対して川栄李奈が「毎週同じ展開だとしても、うちは時代劇を夢中で見てた」と。毎回同じような展開だとか、保守的だとか言われたとしても、それでもその枠の中で続けることに意味があるのだ、という意思を感じるし、「ポップであり続ける」というのはそういうことだよなと思った。
10位 スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム(映画)

スパイダーマン過去作の敵とか味方とかがドバドバ出てくるやつ。MCUがマルチバース的想像力を正しく上手く使ったほぼ唯一の例。
過去作をリアタイで熱く追ってた人間じゃないのと、歌舞伎的なケレン味のあるカットが少なかったためにそこまで全力では乗れなかったんだけど、単なるお祭り映画ではなくてトムホランドの覚悟ある選択にしっかり胸を打たれる。
悪を「ケアする」という表現については、すべてを医学的に「病=治してあげるべき対象」だと捉えてしまう現代の捻れだとかなんとか巷間言われてたけど(45位のAURORAの『Cure For Me』とかもそういうのへの反対意思の曲)、結局「悪を暴力で倒す」こと自体にMCUはどうやら疑問を持っているようで、いやでもフィクションだからね?とは思う。
9位 すずめの戸締まり(映画)

セカイ系の人こと新海誠の、天皇スピ土着リアルファンタジー。
脚本は詰め込みすぎてて混線してるし、キャラへの感情移入も絶妙にできないんだけど(特にすずめ・草太の感情の根拠の描けてなさ自体がセカイ系の残り香っぽいとは思った)、アニメーションの良さと、「観てる人それぞれの中で、散りばめられた様々なテーマ性のどれかが響けばいい」みたいな力技によってなぜか感動させられたりする謎映画。
いやまじで謎映画ではあるんだけど、でもこのぐちゃぐちゃな「わけのわからなさ」を意識的に作れてるんだとしたらほんとにすごいと僕は思うし、支持したい。それに天皇制とか、細かい設定の小出し感とか、考察勢にも配慮がされてるので、無のような素朴な『すずめの戸締まり』論が世に溢れることによって宣伝になることも織り込み済みだと思う。
中身については、「第三者=非当事者=観客」の位置を代表する芹澤というキャラが魅力的に描けてたのは、震災映画であるこの作品にとって素晴らしいことだと思った。あと僕はすずめ・たまきさんのくだりで普通に感動した。たまきさんの「好きな人のところに行きたいってことね」というセリフ。「好き」みたいな単純すぎる感情に集約させずに倫理的な動機を設定する、というのは今の現実のリベラル界の常識になってると思うんだけど、でもなんだかんだ突き詰めると人の動機ってそういうことだったりもするよね?と思わせるものがあった。
芹澤といえば、草太のことに言及して芹澤が「あいつは自分の扱いが雑すぎるんだよ」と言うシーンは、世界を救うヒーローがしばしばやりがちな自己犠牲を戒めるもので、「おっ」と思った。実際、特にアメリカを中心に個人のメンタルヘルスの問題が深刻化している現代において「自己犠牲」ほど役立たずな概念はないし、北米・韓国ポップカルチャーなどでも2010年代後半から言われるようになったセルフケアの問題系にも繋がるのかな?と。
ところが、草太こそそれで「生きたい」みたくなったにもかかわらず、今度は草太を救いたいすずめが「私が!要石になるよ!」とか言い出したのでビビった。問題の単なる先送り。まあ日本ってそういう国だしなあ、と勝手に納得もした。
そして結果、ダイジンが自己犠牲的に要石になる。「よく分からないがなんだかんだ大丈夫」みたいなこの結末は先送り感の最たるもの。
で、ここで強調したいのが、あまり批評の文脈ではちゃんと言われないけど、ダイジン、普通に可愛くないですか? ジブリとかポケモン映画とかドラえもん映画とかの謎マスコットキャラクターよりも全然かわいかったよ。内面が見えないからだと思う。
ただ実のところ、あれを「かわいい」と感じてしまうこと自体が罠かもしれないのだ。ある程度は友好的なインタラクションが見込める犬と違って、あの猫的なかわいさは「よく分からなさ」「意図の読めなさ」つまりは「存在が謎であること」「一定の距離感が保たれていること」ゆえのかわいさだから(これは夏目漱石~柄谷行人的な写生文とユーモアの問題系とも直結するやつ)。
つまり「なんだかよく分からないが最終的には要石として世界のバランスを保ってくれる」という意味でも、よく言われるようにダイジンは間違いなく神=天皇的な存在ではあって、大塚英志『少女たちの「かわいい」天皇』じゃないけども、あなたたちはこれを「かわいい」という親しみの感覚で消費してますよね?これの本質を考えないようにしているからこそ、「かわいい」とかに疑問を抱かず、「何となく」エンディングで感動してしまえるんですよね?という問いに繋がるわけです。
だから意地悪な作品だとも思うし、『ちいかわ』みたく「かわいい=かわいそう」ラインの問題を露悪的に示すより、良い話をしつつ、よく考えたら嫌な気持ちになる『すずめ』のほうがちゃんとやるべきことやってると思う。
ということで総合的には良い映画。最終的にトラウマや怯えを乗り越えるには「過去の自分」「未来の自分」を粗末にせずに対話することで時間性を導入するしかないし(ポルノグラフィティがやってることに近い)、芹澤が「闇ふけー」とだけ言って踏み込まずにいたり、風景を見たときのリアクションも温度差があったり、コミュニケーションはつねにいくらか不全なんだけど、そういうものだよね、という。
余談。同世代と話してると、意外なほど『天気の子』が普通に好きって人が多い。でもそれ要は街を雨に沈めたいやばいやつってことだぞ!とは毎回言うんだけど、「やばい」とも思ってない人がわりと多い。ということ自体がなんだかいろいろ示唆的。ちなみに僕も『天気の子』普通に好きです。ファックザワールド感。
追記
セカイ系を受け継いだ新海誠の作品の良いところは、おそらく観たあとに好き嫌いがわりと明確に分かれるだけに、「これを肯定する/否定する自分の感性とは何だろう?」と自問できるところなんだと思う。
なんらかの作品を見てもやもやしたとき、おおよそ、人のとれるアクションとしては「自分の感じたもやもやを『正しい』と規定し、それに基づいて作品を批判する」「もやもやしているこの自分の認知や倫理観って何だろう?と自問する」の2種類がある。(作品に限らず、社会のあらゆることに関して本当はそうなのだが。)
そして『すずめの戸締まり』はとても変な映画で、要素がいびつにごちゃごちゃ詰め込まれているからこそ、後者のような問い直しを可能にする機能を持った作品だと僕は思った。
けれども多くの人は(とりわけ「批評」を好んで行うような人は)前者に基づいて、自動機械のように色々な事を言う。しかしそれでは新海誠の掌の上なのである。僕はそこから脱したい。言うなればこのベストハンドレッドの実践自体が自己分析でもあり、ひとつの態度の表明でもある、と思う。
8位 鎌倉殿の13人(ドラマ、NHK)

鎌倉幕府2代執権・北条義時が主人公の大河ドラマ。和製ゲームオブスローンズ+ゴッドファーザーみたいな「ドロドロ権力闘争デスゲーム群像劇コメディ歴史ホームドラマ」です(なんだそれ)。前半はわりとストレートに面白い大河ドラマで、後半になると『イカゲーム』『デスノート』色を強く感じる。
「ホームドラマでキャラに愛着がわけばわくほど後半が地獄」という、大河ドラマの構造を知りぬいた三谷幸喜の大河ファン力を感じる。大泉洋はSNSでの反応も当て込んでの起用っぽくて若干どうだろうと思ったけど、けっこう良い頼朝だった。全体的にキャラもモチーフの反復も画面もよくできており、これまたファンダムによる「考察」の欲望にも完璧に対応している。対応しすぎていて少し鼻につくレベル。
大河ドラマは、2002年『利家とまつ』あたりで一昔前の合戦メインのマチズモからの脱却を試みた結果、①今度は単なる朝ドラ的ホームドラマじゃんみたくなったり、②女性主人公を無理に活躍させようとして史実をガン無視して批判を浴びたり、③「リーダーシップ」みたいなビジネス概念と謎の結合を果たして「きれいでまっすぐなヒーロー(なお中身は特にない)」としての主人公像が提出されて全然面白くなかったりと、それなりに受難というか、出来の良し悪しが激しい時代が続いた。
ところが2016年『真田丸』あたりからはけっこう良いものが続いていて(『西郷どん』は役者パワーによるゴリ押し系だったが)、2020年の『麒麟がくる』は壮大な承認欲求の話(光秀・信長のセカイ系二者関係)をインスタ的な彩度の借景的画面でやり、2021年の『青天を衝け』は明治維新=近代化の光と影を問い直す二面性の話で(つまり司馬遼太郎史観へのオルタナティブの提示でもある)、それぞれに現代性もあった。
で、『鎌倉殿』は、『新撰組!』『真田丸』と敗者側の物語を描いてきた三谷幸喜がついに「権力者サイド」の話をやっているのが良い。
上に挙げた3つの問題点に対しても、①ホームドラマの形式を利用することで逆にその崩壊を印象づけること、②怒られないようにちゃんと史実を尊重すること、③主人公を聖人ヒーローにしないこと(むしろ小栗旬=北条義時はヒールとしてすら描かれる)、という完璧な対策も準備してあり、つまりここ20年ほどの大河が陥ってきた隘路を全力で回避した上でむしろ逆手に取っている。時代劇がどんどん観られなくなっている中、大河ドラマを本格的に復権していこうというNHKの意思も感じられるので、応援したい。
ついでに、これは自己犠牲的ヒロイズムの話にもなってるのが良いんですよ。北条義時はすべてを一人で抱えたまま闇に堕ちようとする。「頼朝への忠義」という呪いのために、弱さを人に開示できない。それへのホームドラマ的回答(義時が能動的に動くとかではない)は終盤の47話にしてついに提出される。実衣「気持ちが悪いのよ。そうやって一人で格好つけてる感じが」。政子「大丈夫。格好良いままでは終わらせません」。良いんだこれが……。
あと書評家の三宅香帆氏が「『半沢直樹』くらい社会現象になってもいいのに」と言ってたけども、なんでそこまで流行らないかというと、端的に「暗いから」だと思います。ただそもそも大河を1年のあいだ観続けるのって修行みたいなものなんで、みんなでもっと修行しよう。
7位 窓辺にて(映画)

稲垣吾郎が、妻の浮気に気付いてるのに何の感情も起こらない自分に悩み、玉城ティナとかと喋ったりして色々考える話。文芸っぽいやつ。
監督の今泉力哉といえば『愛がなんだ』を想起する人も多いかもしれないけど、あれほど強烈なキャラは出てこないし、なんなら今作はもっとウェルメイドだし(サブカル感も抑制されてて良い)、「もはやそういうエモ若者系映画ではなく中年男性を描くフェーズに入ったのだ」という監督の意識が感じられる。総じてとにかくリズムが心地良い。登場人物はみんな「少しだけ」何かに疲れていて(この極端じゃない感じが今の社会っぽくもある)、その疲弊感に寄り添うヒーリング効果がある。主人公が「正直に何かを言っちゃう人」なのも良い。
「parfait=完璧な」の名を持つくせに、いつも食べきれず残してしまう、完璧な存在とはいえないパフェ(と玉城ティナが言ってただけです。僕はつねに完全に完食してます)。必要以上に当たりまくるパチンコ。大衆受けを狙ってそのままベストセラーになる小説。どれも「満たされているはずなのに満たされない」ことの象徴。けれどその状態にさえ、正直に向き合うのが一番いい。結果何かが変わってしまうとしても。だからこれも、「自分の内面をもう一度見つめ直す」というコロナ禍的流れと関係あるとは言える。
男性の描き方はファンタジーっぽかった。そもそも今泉作品って「リアリズムを突き詰めたように見せかけたファンタジー」みたいなものが多い印象あるけど、今作でも稲垣吾郎は性的欲望を持たないし、玉城ティナとも別に恋愛的なことは何もなく終わる。もちろんそのアロマンティック的な欲望のなさというのは現実にありうることなので、「ファンタジー」と言ってしまうこと自体にも暴力性が伴うわけで、ここでは役者の力と会話のウィット等によって漂白された「きれいな」男性性、という言い方をしたい。
欲望の在り処が分からなくなっていること自体はきわめて現代的な問題意識でもあると思うけど、『すずめの戸締まり』でも新海誠的なキモさが完全に脱色されていたことも考えると、いま男性はそのようにクリーンにしか描けない時代にはなっているのかもしれない。その意味では、いまどき下世話な欲望を扱う『チェンソーマン』がいかに稀有なものかという話。
6位 シン・サークルクラッシャー麻紀/佐川恭一(小説、破滅派)
サークルクラッシャーによってクラッシュされた文芸サークルの部長の、その後の人生と文学の話。バカおもしろ小説。自称・童貞文学評論家のいとうせいこうは今すぐこれを読むべき。
インディーズ的な動きをしてる人たちにはインディーズならではのことを求めたいと常々思っているけど、この作品はまさにそういうものになっている。けれど「純文学的なもの」への単なる露悪的なカウンターではなく、初期の漱石をも思わせる優しいユーモアとペーソスのようななものがつねに機能しているので、陳腐な言い方だけど、むしろ屈折した文学愛に満ちていると思った(佐川恭一氏がそもそも文学賞の出身)。
「文学」という概念が、特に90年代後半以降、もはや効力を持たなくなっているがゆえに逆に狭い界隈(+アカデミズムとの結託)の中でリベラル的な権威化を推し進められ、在野研究者の荒木優太氏が「今の純文学の評価は減点方式になっていて、みんな"減点されないもの"ばかりを書くようになっている」みたいな皮肉を言うくらいの状況の中、「文学にはこういう可能性もあったのだ」と思わせてくれる作品は今日日貴重です。
5位 浦沢直樹×さやわか×東浩紀「戦後日本とマンガ的想像力──万博、五輪、テロ」 (イベント)
日頃から色んなイベントやっているゲンロンカフェの、いわゆるレジェンド降臨回。単に「あの浦沢直樹がこんなに長時間喋ってますよー」というだけではない内容に当然なっている。聞き手2人の力と浦沢先生の圧倒的サービス精神が生んだ上質エンタメ。俺たちみたいな(と僭越ながら複数形で言わせてほしい)ひねくれ者が、それでも世界に開かれたことをやり続けようとする、というのはどういうことなのか。その矜持を教えてもらった気がする。
最初のロックとかボブディランの話とか、世代論みたいな話も途中ちょくちょく挟まれるので、「歴史を参照しながら我々は物語を作っていくのだ」という話にもなっていて良い。
4位 わたしは最悪。(映画)

北欧の文芸系映画。主人公がいろんな人生の選択をするんだけど、つねにその選択には満足しきれない感覚があり、、というのを繰り返すだけの話。そして主人公の不安感や焦燥にはさしたる理由もない。
「とりあえず満たされてはいるのにどこか不安である」みたいな感覚がとりとめのないカット移動や章立ての作り方によってあまりにも活写されすぎていて、やめてくれ!死ぬ!みたくなった。つかみどころのない映画だから人を選ぶ。
なお上の世代に感想を聞くと「ピンと来なかった」、同世代=Z世代に聞くと「刺さった」みたいな回答が来ることが多かった。これが年齢の問題なのか世代の問題なのかというと、「選択肢の多さゆえの漠然とした不安感」ということを考えるとやっぱり世代の問題な気はする。分からないけども。
3位 silent(ドラマ、フジテレビ)

フジテレビが急に本気出したやつその2(観れてないけど吉沢亮の『PICU』がその3らしい)。Z世代がTVerでめっっちゃ観てて民放の何かの記録を塗り替えたらしいドラマ。
川口春奈が高校時代の元カレの目黒蓮(今は聴力を失ってる)と再会し、お互いがもう一度コミュニケーションをとろうと頑張る話。つまり喪失=変化と向き合う話であり、コミュニケーションの話なので、聴覚障害が本質でもなければ、恋愛が本質なわけでもない。と思いながら観てる。
(ただ、「過去に付き合ってた」という設定に頼ってすべてを突破しようという強引感はあるので、「関係性の変化」は描けてても、いわゆる恋愛ドラマ的な「関係性の構築」はまったく描けていないとは思う。そして残念ながらそれ自体が、結果的にコロナ禍以降の「新しい人間関係の構築」が難しくなった状況の反映でもあると感じてしまい、観ているとなんだか寂しくなる。)
韓国のリアリズム系恋愛ドラマの影響を感じさせる作りで、撮り方も韓国映画の『はちどり』とかを参照してるらしく、まず単に美しい。テレ東の『うきわ』にも似てる。あとアイテムとか色とかを象徴的・反復的に使ってくるので、恋愛ものでありながら考察動画とかも作りやすくなっている。
脚本は20代の新人の人(!)。坂元裕二に影響を受けているようで、実際やたらファミレスが出てくるので「坂元裕二じゃん!」となるんだけど、坂元裕二ほど「今うまいこと名言を言いましたよ感」みたいな雰囲気は出さないので普通に観やすい。スピッツとか使ってくる平成ノスタルジー感も、ネトフリの『First Love 初恋』よりは全然キツくない。
この作品の特徴的なところは、まじで『トップガン』ばりに「社会=外部」を描かない点(だから当然批判もいくらでもできる)。というか近年ヒットした他の日本の恋愛ドラマが中心に据えていた要素――たとえば『逃げ恥』的な社会性、『ナギサさん』的なお仕事もの要素、『恋はつづくよどこまでも』的なキラキラフィクション感――を『silent』はいずれも完全に排し、ひたすら恋愛を描いている。そしてZ世代にヒットしている。Z世代はコンテンツ消費において「外部」など必要としていないのかもしれない。いろいろ示唆的な現象だと思う。
(ちなみにSpotifyのチャート見ててもやたらストレートなラブソング多いし、『おっさんずラブ』『僕の心のヤバイやつ』『愛の不時着』ラインを経て2022年は何度目かの「純愛ブーム」と呼んでもいいんじゃないでしょうか。)
もう少し言うと、恋愛という概念を、ヘテロ的な非対称性も用いずに、不自然にキラキラもさせずに、漫画的なキャラにもせずに、お仕事恋愛ドラマ的な社会性も排し、その上でリアリズム「風」に全力で描くと、今日それはもう必然的にひたすら「コミュニケーション」あるいは「他者と共に生きること」の話になるんだ、ということを誠実にやっている。だから普遍性を持っているし若者にウケてるんだと思う。仕事とか人生設計とか憧れの人とかそういうことじゃない、単に「関係性」を描くんだ文句あるか、という逆ギレ感すらある。
一応他に家族の問題も扱ってはいるんだけど、これにしても「家族の問題もやりますよー」ってことではなく、「恋の問題はつまりコミュニケーションの問題なので、当然まわりの人たちも関係あるよね」という感じでナチュラルに描いているのが良い。
だから「ちょっと昔の少女マンガ感」も正直ある。でもそれはおそらく「外部のない純愛」というファクターによってそう見えるだけであって、実際描かれてるコミュニケーション様式は心底「Z世代的」。
まず、90年代のドラマみたくやたら元気溌剌みたいなキャラとかは一人もいない。反対に、明確に暗いキャラもいない。そして比較的ポジティブに描かれている川口春奈含め、若いキャラはほぼ全員がデフォルトでめちゃくちゃ他人に気を遣う。『ファイトソング』のところでも書いたけど、だからこそ気遣いの結果として自ら身を引くみたいなことが普通に起きて、それが泣ける。その中にあって夏帆は少し例外的な意地悪なことをするキャラではあるけど、にしても極力抑制されている。そのバランス感覚がすごいと思う。
あとこれ、リビングで家族で観る用にはあんまり作られてなさそう。無音が続くシーンとかもけっこうあるから単純に喋ってる場合じゃないし、基本シリアスに観るしかないやつなので、「観ながら喋る」のではなく、終わったあとや翌日に同世代の人と学校・SNSで話すという行動様式を想定しているはず。Clairo、PinkPantheressとかの音楽がダンスフロア的な喧騒と無縁の「ベッドルームミュージック」と呼ばれるように、『silent』は部屋に閉じこもって観るパーソナルかつミニマルな「ベッドルームドラマ」としてある。
まあしかし日本の恋愛ドラマの明確なゲームチェンジャーになるかどうかは微妙というか、劣化『silent』みたいなやつがポコポコ出てきても単に困るので、たまーにこういうのが出てきてくれると良いよね、というテンションでいたい。
2位 RRR(映画)

1920年代、イギリス統治時代のインドで2人の英雄が頑張る話。神話『マハーバーラタ』と『ラーマーヤナ』を偽史として作り変えた結果、ふたりの英雄の完璧なブロマンス劇が爆誕してしまった作品。『バーフバリ』の監督だけど、『バーフバリ』ほどフィクショナルな神話感はなくてむしろ観やすいかも。時代設定が実際に近代だからだと思う。
この映画はとにかくベタなことを、ベタに実直にやる。しかしスローモーションの使い方が異様に上手いキレキレ演出、生命力あふれる音楽、演技とダンス超うまい筋肉ムキムキのキャスト、そしてインド映画史上最高額とされる無限の予算によって、そのベタは我々の人生史上最も素晴らしいエクストリーム・ベタと化す。本当にそういうやつ。
一般的に「インド映画」と言ってイメージされる通り、『RRR』には踊りも歌もあるのだが、それはまったく唐突なものではなく、脚本が上手すぎるのですべてに必然性が付与されている。特に踊りの場面は「イギリス統治下におけるインド人の立場を描く」「主人公2人の友情・関係性の強化」「抑圧された女性たちの本心を垣間見せる」「めちゃくちゃ楽しい」と何重もの意味を持っていてすごい。
『RRR』は神話的ナラティブを借りながらもヒーロー物っぽさを感じさせる作品でもあるので、これを観たことで正直、粗製乱造モードに入りつつあるMCUとか、内輪の事情か何かで一生グダグダしてるDCをわざわざ熱心に観る必要はないのかもしれない、と思ってしまった。ヒーロー的役割のキャラが陥りがちなロマン主義的自己犠牲ムーブと、友情によってそれを止めるところまでもちゃんと描いている。
ということで、総じて最近のMCUとかぬるいハリウッド映画に不足しているものをすべて持ち合わせていると思う。ので2位。もちろん一口にインド映画と言っても玉石混淆なんだろうし、「アメリカのコンテンツだからこそ描ける現代的テーマ」とかがあるのも分かるけど、来年以降の自分の観測範囲は色々と修正していきたい。そのくらいのインパクトが『RRR』にはあった。
SNSでの消費がデフォルトになった今のコンテンツらしく、キャラ造形や象徴性の使い方もめちゃくちゃよくできているので(いわゆる「解釈違い」なんて万に一つも起きないような)、「ラーマ ビーム」とかでツイート検索すると活きのいいオタクのツイートもたくさん見れる。楽しい。というかこれもやはりファンダム形成が重要になった最近のコンテンツにはわりとあることだけど、ファン語りによる補完の欲望を促す「隙間」みたいなものさえ意図的に作り込まれてると思う。
1位 ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー(映画)

MCU。前作『ブラックパンサー』の主役=俳優のチャドウィック・ボーズマンが亡くなってしまったこともあり、因縁ある民族とのバトルの中で、ブラックパンサーを妹シュリが継承する話。そして喪失からの回復の話。アメリカだと「MCUはもう追ってないけどブラックパンサーは観てる」って人がけっこういるらしくて、それで正解だと思う。
何度も言ってきた通り、今年は本当にしんどかった。プライベートなこともだし、世間的にもそうだった。戦争が起きた。元首相が殺された。尊敬する言論人は些末なきっかけで世の批判を浴び、「もう疲れた」と嘆いていた。あらゆる綺麗事が無意味に思えた。この映画を観るまでは。あのシュリの気高い姿を観るまでは。僕にとってはそのくらい素晴らしい作品だった。
歴史が忘れられた結果の、起きなくてもよかったはずの戦争の話。ちらつくヨーロッパ諸国の問題や他のアベンジャーズとの関わりなど「外部」の要素はオミットされ、そういう意味ではひたすらミニマルな話。
でも今は、2022年はそれでいいんだと思った。ミニマルな問題を片づけないまま、世界のことを考えても仕方ない。僕たちはシュリのように、喪失と向き合えず、自分の感情を制御できず、時に道を誤る。けれどこれからまだやり直せる、かもしれない。
あとヒーロー物にとって重要なのはやっぱりバトルシーン自体ではないんだな、と確信した。この映画はバトルシーンはむしろ少ない。そしてオコエとか脇役が魅力的に描かれてたのも良い。アイアンハートにもそれを感じたけど、「ユーモアがあって景気良くて実際強い」というトニースターク感はワカンダで一番継承されてるのでは?と思った。で映像も素晴らしかった。わくわくする海底の帝国とか大事だよね。ポケモンの『ルビサファ』を思い出した。
決して派手な作品ではないし、さすがにこれは前作を観てからのほうがいいかもしれないけど、平和を祈るくらいしかできない今の情勢の中で観るものとして、大変良い映画だと思います。
超ざっくり総括
①パワー系=マキシマリズム=狂騒
(トップガン、RRR、バッドバニー、チェンソーマン、black midi、水曜日のカンパネラ詩羽、4s4ki、ワンピースFILM RED、ビヨンセ)
コロナ禍的(2020年~2021年)な内省感・閉塞感からはすでに抜け、そのストレスを晴らすかのようなアグレッシブなもの、過剰なものが目立った。
②ヒーリング系=ミニマリズム=喪失・回復・自己の感情の受容
(ブラックパンサー、silent、ファイトソング、すずめの戸締まり、クレしん映画、藤井風、ポケモンSV、The1975、宇多田ヒカル、カムカムエヴリバディ、羊文学)
シンエヴァ、ドライブマイカー的な「傷」の問題は、90年代~ゼロ年代的な自意識や内省やトラウマ、あるいは2010年代的な災害や性差や戦争、いずれをも引き継いだ形で扱われ、しかし2020年代にはそれが「正しさ」のみによって解決できないことも明らかになっているため、時間性・歴史性に基づく他者や過去の自分とのコミュニケーション(あるいは祈り)、ひいては自分の感情を抑圧から解放し受け入れることによって解決がなされる。それに伴って、「外部=社会」を描くべき、というパラダイムも今や必ずしも共有されなくなっているように感じる。
③「強者」の弱者性系
(鎌倉殿の13人、窓辺にて、私は最悪。、黄金比の縁、青春とシリアルキラー)
④外部なき純愛ミニマリズム系
(silent、僕ヤバ、SaucyDog、優里、Novelbright、wacci)
ついでに2022年あいけWorks
・文芸同人誌『現代人』創刊、「マリトッツォの鎮魂」寄稿
「近代文学的な要素を踏まえた上で、現代人に向けた文学を作ろう」というプロジェクト。僕はサクッと読める7,000字くらいの短編をサクッと書きました。
買っていただいた方は、冊子の巻頭言と巻末作者コメントを見ていただけると分かるのですが、この小説は少なくとも3つの仮想敵「夏目漱石(の小説)」「Twitter」『silent』には勝とうと思って書きました。だって「マリトッツォの鎮魂」よりも漱石のほうが面白けりゃ漱石読めばいいし、Twitterのほうが面白けりゃTwitter見ればいいし、『silent』のほうが面白けりゃ『silent』見ればいいじゃん、と思うので。普通に。
小説よりも面白いものがいっぱいある世の中で、「小説だからこそできること」って何なの?というのは考えてるし、今後も考えたいなと。
なお、『現代人』はKindleとかで読めるようにするつもりなので、リリースされたらここに追記します。(今のところ僕が死んでいるので作業進んでない
僕らが文フリで販売する同人誌『現代人』の詳細について、noteに書きました。
— 銀杏派『現代人』 @文フリ東京C-22 (@ichou_gendaijin) November 13, 2022
各作品の概要を示しつつ、一部の本文を 抜粋しています。#文学フリマ東京 https://t.co/1K3pOcPUq3
・Stray Beep新曲『パサージュ』ストリーミング配信
歌詞を担当しました。曲調はラテン系で、それに合わせたからか、今風のストレートな言葉にはしなかったというか、ならなかった。
・Podcast「やんぐはうすららじお」ゲスト出演
ゲンロンSF創作講座の、第2の非公式Podcast。ギャルとかチェンソーマンとか色々アツく語りました。他の多くのゲストの方と違って別に作家デビューとかしてないし業界人でもないので、創作論に行くのではなく、「とにかくアツくしたい」というのを目指して頑張りました。で実際にアツくなったと思う。
・Podcast「あいけ式不要不急インタビュー」スタート
いろんな人と真面目な話をしてみる機会を設けたくて、始めた。11月ごろから僕が色々しんどかった結果、普通に滞っているぜ
・ゲンロンSF創作講座の感想
受講生の皆様の梗概などを読み、僭越ながらたまに感想を書いています。どういうことを書けば受講生の方々のため、世界のためになるんだろうな~とか思いながら書いてるけど、結局は自分のためかもしれない。
・徳谷柿次郎『おまえの俺をおしえてくれ』刊行記念エッセイ寄稿コンテスト佳作
お世話になった、ローカルとインターネットを無限に行き来する狂人・柿次郎さんの自伝的書籍の刊行記念ということで、批評っぽいエッセイっぽい謎の文章を寄せました。「言葉は大切」という人文系にありがちな価値観をどう考えるか、って話をしてるので、けっこう良いと思います。
・シラスレビュー
トークイベントや1人配信などなど、観てきたいろんな番組につけたレビュー(感想というか推薦文というか)がここから見れます。最近は「レビューしないよりはしたほうがマシやろ」くらいの感じでやってるので、以前より絶妙にやっつけ感が出てきているのが伺える。うむ。
・ブログ
今年も地味に、ぼちぼち書いたり書かなかったりしてます。ある意味最も気負わずにナチュラルに書いたアウトプットが載ってますが、少なくとも読んで元気になるような内容ではないので、読む必要はないです。
おわりに
おわりました。去年も「2021年振り返り」みたいなnoteは書いたのですが、それは今見たら、7000字ですって。どんなぬるい世界なんだ。
……とか言って文字数の多さを誇るようになると滅びの道へ突入してしまうので、2023年の年末は適当に140字くらいだけ書くようにしたい。
「今年ベストハンドレッドを書く」というのは年始からじつは決めていました。とりあえずやってみようと。
なので「だって年末にどうせ全部書くし~」と思い、SNSではコンテンツへの言及はわざと少なめにしたりしていました。そのあたりのマゾヒズム感含め、けっこう良い経験になったと思います。
そして、読んでくれたり観てくれたりした方にとっても、何か意味のあるものになっていればいいなと。
来年は100個はやりません。やったとしても30個くらいでしょうか。ポップカルチャーを追うというよりは、ルーツに立ち返って文学とかのことを考える1年にしたい。ていうか、頭も使いたくないし、お金も使いたくないし、なんもしたくないし、無になりたい。無を愛したい。
というわけで、無の2023年も何卒よろしくお願いいたします。
おわりに、の裏に
これくらいでざっと5万8,000字分ほど。
いろんなことに関心がある、ふりをしてきた。うまくいってるんだろうか。
いや、関心はあると言えばある。前置きでも書いた通り、ランキングに入れたのは全部「いいな」とか「気になるな」と思ったやつばかり。そこに嘘はない。そんな嘘をぶちこめる余裕はない。
でももっともっと根本的なところにおいては、本来、別に、カルチャーにも、社会にも、歴史にも、政治にも、スポーツにも、お笑いにも、他人にも、たぶん何にだって興味ない奴なのだ。それが悲しい。悲しいから、ちょっと無理をしてでも変えようとしてみている。このnoteは本当はそういう文章だ。それでこんな分量が必要だったのだ。
人と比較して勝手に負い目を感じてちゃ世話はないとはいえ、SF小説にせよ、マンガにせよ、音楽にせよ、学問にせよ、「新しくて面白いものを見たら即座に食らいつく」という、純粋なエネルギーを持った人たちってのが確かにいる。
けれど、そういう力は僕の中からは湧いてこない。どうしたって、湧いてこないもんは湧いてこない。この「湧いてこなさ」って何だろう。とか思う。
『BLEACH』が好きだ。ずっと好きだ。文脈なんて知らねえ、新しいかどうかも関係ない、ほんの一瞬かっこよけりゃそれで勝ち、その後は消えてしまってもそれでいい、あれはそういう精神性によく似合う作品だから。
それに今回のベストハンドレッドの中にも、明らかに「2020年代的でないもの」、言い換えれば、わざわざ「2022年の」ランキングに入れる必要がないものが明らかにいくつか入ってたと自覚している。
別にそれを意図したわけじゃない。けれど、「ダイナミックに蠢く同時代」なんかには乗れない、俺は自分の愛着の持てる世界の中だけに閉じこもりたいと、ランキングそのものが雄弁に語ってしまっているのかもしれない。
今ここで挙げたいくつかのこと。なんとか誤魔化せてたらいいのにな、と願ってる。
けど僕は何にでもすぐ飽きてしまうから、「誤魔化そうとすること」自体にもそのうちまた飽きてしまうかもしれない。それじゃ悲しすぎるけど、まあどうせ飽きる日が来るんだろう。
それだから、このnoteの冒頭で僕は言ったのだ。「もう少しのあいだは」楽しくやれる、と。
であれば。
せめてその「もう少し」を、ささやかなリズムを、高鳴る拙速なビートを、一緒に繰り返させてほしい。これからざっと無限回ほど。
消えそうな火に薪をくべるように。止まりかけの心臓へ酸素を送り続けるように。泥に足をとられて沈みながらも、次なる一歩を踏み出すように。
十の夢を見る。百の夜を数える。千年に一度の花と微笑む。いつかそれが永遠になる。人はそんなものを歴史と呼ぶ。物語と呼ぶ。
俺がくたばって羽を休めてるときは、あなたが別の何かを紡いでほしいし、逆も然り。どうせ徒然続くだけの日々、一人じゃ祭りもぶち上げられない。
それだけでいい。それについてさえ互いに頷き合えりゃ、ここで最初の一頁を終えることにもう何の躊躇いもない。まどろみからほんの少し目を覚ましたとしても、いつだってすぐ戻ってこれる。
また会いましょう。暁の灯りをついに数えきれなくなったその時に。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
