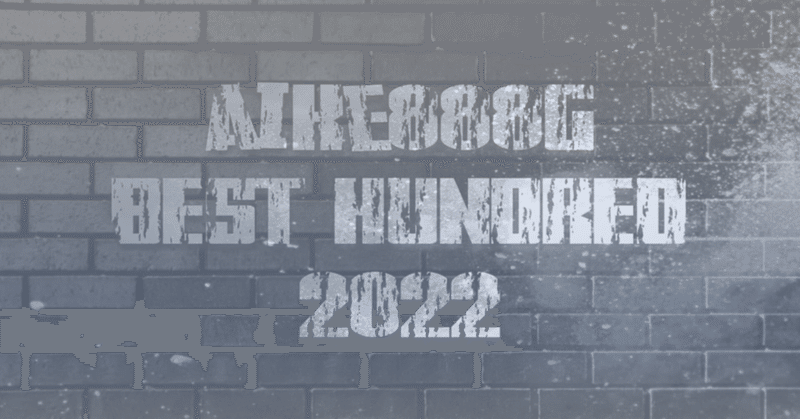
afterBEST100:今その言葉は怯えているか?
自分の握る剣に怯えぬ者に、剣を握る資格はない。僕はそう教わった。
過日、「2022年のコンテンツを100個ランキングにして全部に批評を加える」という企画をやってみた。疲れた。
それで改めて理解した。「何かを言うこと」「何かに言及すること」にはつねに怯えが伴うべきだ。今回僕が疲れたのも、別に実務的な作業量が一番の理由なのではなく、それが怯えとの戦いでもあったからだ。
作品について何かを言うということは、同時に、自分の倫理観や価値観を表明していることにもなる。どんなに「自分」の表出を抑えたとしても、必然的に何かが滲み出てくる。それは当然、怖いことだ。
そもそも「何に言及するのか」というセレクトの仕方ひとつとっても、「こいつはどんなクラスタに属しているのか」という値踏みの視線を想定しながら考えないといけない。
実際、ランキングを作るにあたって1年間、いろんな人たちを観察していた結果、同じようなイデオロギーやクラスタの人たちはみんな同じような作品を褒めるし、同じような作品を、同じような口調で批判する傾向がある(もちろんあくまで「傾向」の話)。これは本当にそうなのだ。
そしてそれは、作品に限らず、社会のあらゆることに関して言える。
何について、どんな口調で、どんなことを言うか。その端々にパーソナリティが宿る。社会的属性が、価値観が、思考の跡の深度が宿る。どうしようもなく宿ってしまう。
言葉そのもののレトリックは別に重要ではない。問題なのは、その後ろにどんなロジックが働いているのか。後ろにどんな背景があるのか。たとえ井の中の蛙だとしても、自分のいる井戸の場所を認知できているのか、いないのか。
でもそういうことは基本的に、人にはうまく伝わらない。
とりわけ経験上、「言葉は大切だ」という文学的な、耳ざわりの良い標語を支持するタイプの人たちには伝わりにくい。彼ら彼女らにとって大事なのは言葉の表面上の手触りと瞬間的な悦楽だけであって、「長い目で見たときにそれが何を表しているか」ってことではないから。
人文系の人と関わっていたとき、僕はその狭さがとにかく嫌だった。だから今回、抵抗手段のひとつとしてベストハンドレッドを編んだ。というか、コンテンツ100個の力を借りながら、あれは基本的に「何かへのプロテストを表明し続けている文章」だ。
そんなわけで今回、「批評家」と呼ばれる人たちの気持ちがほんの少しだけでも分かった気がした。徒労。孤独。そしてディスコミュニケーション。もちろん批評家と言っても、場当たり的に何かを言うタイプの人たちのことではなく、ちゃんと信念をもって何かをやっている人のことをここでは指している。
そして畢竟、僕は何かに怯えている人が好きなのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
