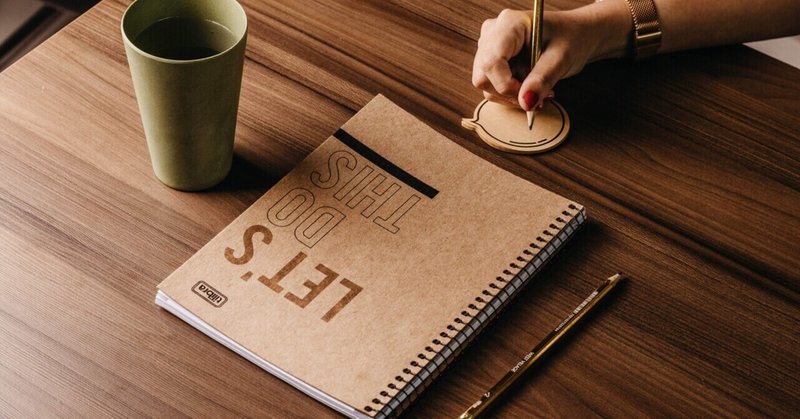
法務若手失敗談
久しぶりの投稿です。
私は、新卒で大手のメーカーに就職して、司法修習に行ってから、IT企業の法務部で働いてます。
Twitterで、法務に入ってくるロースクール卒生、司法修習明けの新卒の弁護士について、社会人基礎力的なものが足りない、、って記載をみました。
私自身も振り返ると、法律の専門知識も足りてなかったし、社会人の基礎力も、本当になかったなと思います(今も日々精進です)。
上司からかけてもらった言葉とともに、自分自身の失敗談を振り返ってみたいと思います。悩んでいらっしゃる方のお役に少しでも立てたらいいなと思います。
【伝えたいこと】
スケジュールを引く・タスクの解像度を上げる
神は細部に宿る
自分の仕事に責任を持って、やり切る
想像力を働かせる
即レスが安心感を与える
スケジュールを引く・タスクの解像度を上げる
上司からの言葉
スケジュールの引き方が甘い。タスクの解像度が低い。いつまでに何をやれば終わるか、完成形が何か考えて仕事しなさい!スケジュール引いたら、頭の中でロールプレイしてみなさい。
これ言われた時に、ショックでしたね。。。
自分なりにはスケジュール引いてるですよ…
ここで、上司は一緒にスケジュールを引き直してくれました。
何がゴールか、いつまでにやるのかというところから逆算していくんだと、すごく大切なことを実感させてくれました。
大タスク・中タスク・小タスク・期日・着手日・達成されているゴールをイメージして記載していく(できるだけ、「これをやる」じゃなく、「これができている状態を作る」という表現になるようにタスクを分解しました)。ここで、自分だけでは終わらない仕事を優先的にスケジュールの中で、優先順位を下げてしまっていたことに初めて気がつきました。
他部署にお願いしたり、上司や先輩にレビューしてもらったり、ここは余裕を持っておかないとお尻がどんどん詰まっていきます。
適切なタイミングで関係者を巻き込んで、誰かにお願いするところのスケジュールには余裕を持って、かつ、レビュー後の修正にも余裕を持ってスケジュールを組み立てるようにしましょう。
スケジュールを引けたら、タスクリストと共に、上司と認識すり合わせましょう。
これでやっと仕事に着手できます!
過去のプロジェクトとかのWBS確認してみて、先輩にどこでスタックしてしまったかとか、困ったところはどこかなどをヒアリングしておくと、スケジュールで余裕持たないといけないところが見えてくると思います。
あとは、タスクの全体像を把握するために、関わるプロジェクトに関連する本を読んだり、ざっとググって調べたりしてました。
神は細部に宿る
上司からの言葉
誤字脱字、名前間違い、資料のインデントやフォントが揃ってない。
神は細部に宿るから、細かいことでもバカにせずに丁寧にやりなさい。
誤字脱字が働き始めてから、ずっと止まらなかったんですよね…
何回確認しても、ずっとミスがありました。。。
今なぜか減ったんですよね…具体的にやっているのは以下の3つなんですが。
①全体を一気に見るのではなく、パーツ・段落ごとで読み返す
②声に出して、赤ペン入れる
③1日明けてからもう1回読み返す
意識の方では、アウトプットも完成形のイメージを持つようにしたこと・自分が何を伝えたいのか、根拠は何を意識しながら見返すようにしていることが効いているのかなと思っています。
漠然と見返しているとダメで、実質的な内容を確認しているのか/形式面を確認しているのか、チェックの目的を持ちながら確認すると誤字脱字に気づきやすくなった気がします。
「神は細部に宿る」という言葉を聞いて、「形式面なんて…意味ないやん」とかって調子に乗っていた自分を叱ってやりたいです。
・形式が整っているから、読みやすいし、伝わりやすい
・誤字脱字がない・スケジュール守る・ホチキスが綺麗・資料が綺麗だから、安心して仕事を任せられる
全て「信頼」につながっているんだと思います。
「こいつに任せておいたら、安心だ。自分の脳みそのスイッチをオフにできる」
この感覚を働く仲間に持ってもらえるようになるのが非常に大切で、神は細部に宿っていて、信頼関係を紡いでくれているのかなと思います。
自分の仕事は全て自分が責任者のつもりで対応する
上司からの言葉
担当している君以上に、この事案を詳しく理解している人はいない。
君の報告が曖昧だと、上司はもっと曖昧な事実関係をもとにしか判断できない。
自分が判断する側で、どんな情報、どんな報告、どんな相談が必要かを考えて仕事しなさい。
ほんとに、これはその通りですよね。
上司や役員へのレポートする際に、全部の情報を伝える時間はないし、ミーティングにも全部出てもらえる訳じゃない。
そんな中で、上司や役員に判断を仰がないといけない。
そのためには、「自分が責任者だったらどんな情報が必要か」「どんな事実関係か」「ポイントや論点は何か」「自分の仮説は何か」「根拠や文献はあるのか」などなどを意識して仕事をしないといけません。
事案と論点の解像度を上げられるように、丁寧にヒアリングして、リサーチして、仮説を持って、報告を簡潔に作らないといけないなと思っています。
この過程の中で、1番大切だなと思っているのは、「自分なりの仮説を持つ」です。
最初、上司にレビューしてもらう時って、上司が答え持っていると思っていたんですよね。上司は答えなんて持っていない、上がってきた情報に基づいて、適切に判断する。
これが決裁者の役割なんですよね。
上司が適切な判断できる状態に持っていくのは、担当者の責任。
けど、ここで忘れちゃダメなのは、上司の中にも一定の方針があります。
きちんと対話をして、上司の疑問点を聞き出して、事業部とのコミュニケーションが必要なら追加でミーティングをして、リサーチが必要なら追加でリサーチをする。
独りよがりなアウトプットを出しても意味がなくて、決裁者が判断できるアウトプットを出すのが大切だなと思います。
コミュニケーションが結局大切なんですよね。
結局レビューされるんだから、上司に任せておけばいいや…とか、先輩や上司の顔色伺いすぎて、自分の意見を曲げちゃう…なんて無責任なことはせず、自分なりの結論を持つことを心がけていけば、自分の意見も自信を持って伝えられるようになってくるかなと思います。
具体的に、過去上司が判断したSlackのやりとり・過去の決裁資料等を振り返ってみて、上司が気にするポイントがどこかを把握しておくのはすごく有用かなと思います。
あとは、本当に困ってるなら、すぐにSOSです!
プロとして、自分1人で抱え込んで、約束守れないのはよくないと思ってます。助けてと言えるように、細かめに報連相が大切ですね。
想像力を働かせる
上司からの言葉
誰が読む資料なのか、きちんと想像して、資料作成して、ロールプレイして説明するイメージを固めなさい。
決裁資料・議事録などを作成するときに、誰が読む資料なのかを考えて、その人の立場に立った時に何が必要か、何は不要かなどを徹底的に考えて、作成する。
これは、文章の量・内容を決める上で非常に重要な視点だと思っています。
役職だけでなく、それぞれのパーソナリティにも注目して、資料作れるようになると仕事がぐっと前に進む印象です。
また、スケジュールを引く時、タスクの解像度を上げる時にも想像力は役に立ちます。
何が仕上がっていればいいのかは、レビュワーの目線でゴール設定するべきですし、他部門にタスクを依頼するような時にもどういうパスを出せばうまく引き継ぐことができるのかを考えることも有用だと思っています。
契約書のレビュー時もコメントも、契約相手型の営業・法務の目線、社内の営業・営業の部門長の目線、法務の上司の目線などを想像して、どこで落とし所をつけるのか、どんなコメントをすれば一回のラリーで終わるのかを考えることで、仕事がスムーズに進むように思っています。
どんな仕事も1人でやっているわけではないですし、受け取り手の気持ちや考えを想像して、資料を作成するというのはとても大切なことだと思っています。
即レスが安心感を与える
先輩からの言葉
社内外問わずに仕事ができる人って即レスだし、時間とか約束は絶対に守るよね。
これ、本当にそう思います。
忙しすぎるはずの人ほど即レスだし、社長からの返事が1番早いこともありました。
そんな人と仕事していると本当に安心して、仕事できるんですよね。
決裁もスムーズに進むし、ネクストアクションも明確になってくる。
法務の日常の仕事に当てはめると、事業部の方って何かしら解決してほしいことを法務に持ってきてくれています。
「契約を締結したい」の裏には、売上のKPI達成しないと…
「お客様からクレームが発生しちゃいました」の裏には、怒られないかな、早く終わらないかな…
法務のお仕事の一つに、「肩の荷物を下ろしてあげる」というのがあるのかなと思っています。即レスするだけで、安心感を持ってもらえたり、そのおかげで信頼してもらって案件解決がスムーズに進んだり。
即レスにはいいことしかないように思っています。
これは、考えが浅いままに回答にするということではなく、
「月曜日までにお返事するので、お時間頂戴しますね!」「いつまでに確認すれば、スケジュール大丈夫ですか?」とか、カジュアルにコミュニケーションをとっておくだけでいいと思っています。放置されているときが1番不安だと思うので、それだけは避ける。自分がされて嬉しいことをするだけなのです。
その他
他にもあるのですが、少し長くなってきたので、箇条書きでまとめたいと思います。
「他部署の〇〇部長から、クレームはいったんやけど、どんな説明したの?」
→ 相談してくれる事業部からしたら、1年目とか関係ないので、ばんばんビジネスの相談されちゃうと思います。自分の意見が一人歩きしちゃってクレームになることもあるかもしれません。そんな時には、一回持ち帰ってきていいから、その場で回答するのは控える。落ち着いて、上司と相談してからで全然OK!実は過去に回答してたことと矛盾しちゃうとかあるから、部内での過去の回答方針とかはきちんと確認する。「結局事業部は何したいの?これは何を解決すれば終わるの?」
→何が論点なのか、自分は何を達成しようとしているのかということから逃げない!案件を終わらせるために、何が論点なのかという意識を持つ。上司に説明してる時に「結局何言いたいの?俺にどうして欲しいの?」と言われる
→「相談したいのか、決裁して欲しいのか、軽く雑談したいのか」を自分の中できちんと決めておいて、何のつもりで話しかけているのかは上司に伝えてあげる。予測可能性がないと、上司も困っちゃう。感覚で説明せず、事実を解釈を分けて、結論→理由→例示→結論の順に説明する(PREP法がいい!)。「ちゃんと、社内の規程・オペレーション確認した?この経費の申請間違ってるよ。」
→社会人1年目の時に、予算とか経費とかよく分かってなくて、よく失敗しちゃってました…。あとは、事業部は達成しないといけない予算や目標があるという感覚を持っておくのが大切。「このミーティング何のためにやってんの?」
→ミーティングは雑談するためのものではなくて、何かを決めて、ミーティング後から動き始めるようにするためのもの。目的をきちんと持って。ミーティングの終了5分前には合意事項の確認とネクストアクションの確認をして!「わからんことをわからんって言いなさい!何にもできないのに偉そうに語るな。素直になりなさい!」
→「実るほど頭を垂れる稲穂かな。」前職の上司が大切にされていた精神です。
謙虚に誰からでも学びとるという姿勢を大切にして、ミスした時には素直にごめんなさいをできるようにしましょう。「過程を褒められたいはやめろ、アウトプット出してたら評価されるから。」
→目の前の仕事のアウトプットを出していたら、結果はついてくるから落ち着いて一個ずつ頑張れ。過程は自分から言わなくても、誰かが見てくれてるから。
夢ばっかりデカくて、目の前の仕事が瑣末だと思ってしまうのは危険。
神は細部に宿ります。「条文、ガイドライン、信頼できる根拠に当たったのか、事実を確認したのか、一次情報に当たったのか!!!」
→何よりも事実!そのあと、条文・ガイドライン!公式資料から考える。一次情報を確認することを怠らない。(番外編)自分の身は自分で守る。
(番外編)精神的に強くなって(受け止めすぎず、受け流して)、周りに心配をかけすぎないようにね。けど、困ったら絶対頼るんだよ。プロとして、周りを頼ってでもやり切らないといけないよ。
(番外編)肩の力抜いて働くんだよ。
(番外編)酒は飲んでも飲まれるな。
おわりに
今回記事を書くにあたって、振り返っていて、
たくさん失敗して、怒られてきたなと思いますが、振り返ると温かい言葉ばっかりでした。成長を期待して、たくさんの言葉をかけてくれていたんだなと思います。
みんな、こんな感じでゆっくり階段登っていくのかなーと思います。
私は、本当に素敵な上司や先輩と出会ってきました。そして、前職の会社と法務のMVVは今でも大切にしています。
法務パーソンとして大切な考え方を教えてもらったと思うので、これからも胸に刻んで仕事に励みたいと思います。
失敗談を通じて、どなたかのお役に立てれば嬉しいなと思います。
最後に、おすすめの本をご紹介させてください。
社会人一年目の教科書
コンサル一年目が学ぶこと
希望の法務
日本語の作文技術
逆引き法務ハンドブック
仮説思考
イシューからはじめよ
超箇条書き
伝わる揺さぶる!文章を書く
遅考術
Chatter 頭の中のひとりごと
おわり
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
