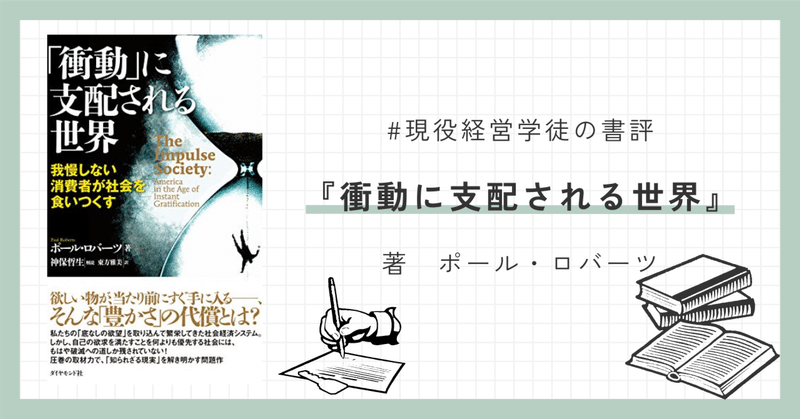
#24 【書評】 衝動に支配された世界
最近日本では様々な「ハラスメント」が問題になっている。
以前までは言っても「セクハラ」とか「パワハラ」程度のハラスメントしかなかったが、最近は「カスハラ(カスタマーハラスメント)」とか「モラハラ(モラルハラスメント)」とかとにかく色々な種類が出てきている。
ただ私の体感としてこれらは全て一つの理由に収束されると思っている。
それは「過度な自己中心的価値観」である。つまり、相手のことを考えずに自らの都合のみで言動をすることに対して、何も感じない価値観が形成されてしまっていることが全ての理由ではないだろうか。
そして、私がそう思っているときに出会った本が今日紹介するポール・ロバーツ氏の『衝動に支配された世界』である。
本書はジャーナリストである著者が、現代の衝動に任せた行動が激化した現代のアメリカ社会に対して警鐘を鳴らす一冊になっている。
あくまで本書はアメリカに向けたものとして書かれているが、内容としては特にアメリカに限定されてものではない。日本にも十分当てはまるものである。
インパルスソサイエティの危険性
本書を通して一貫して語られるのは「インパルスソサイエティ」の危険性です。インパルスソサイエティとはその名の通り、人々が自らの短期的な欲望や衝動をもとに行動する社会のことであり、それが続くと社会は大変なことになると筆者は述べている。
インパルスソサイエティの危険性は大きく分けて二つ、「人々が長期的な利益を大切にせず、今しか考慮しないこと」、そして「誰もが自己中心的にしか物事をとらえなくなり、自らの利益のみを追求する」ことにある。
この短期的かつ自己中心的な考え方は、一見合理的かつ正しい判断に見えるが長い目で見るとそれは間違っている。社会のコミュニティの強さは失われ、社会的なつながりは希薄化していく。
実際にアメリカではその影響が随所で見られているという。ゲーム中毒になり、社会から隔絶されたため、更生施設に通うもの、医者に対して自分に合った治療ではなくとにかく最新の治療を求めるもの。どれを見てもとても正常とは言えないものばかりである。
ここからは、どうしてこのような自己中心的かつ短期的志向に陥ってしまうようになったのかを考えてみたいと思う。
長期と短期のジレンマ
まずどうして人は短期的な思考になってしまうのかを考えてみようと思う。
例えば、今10000円あげます、と言われた場合と一年後に20000円をあげると言われた場合、普通に考えれば20000円の方を取るはずである。しかし、なぜか人は本来もらえたはずの金額の10000円も少ない金額を受け取る。これが長期と短期の合理的の違いである。(ファイナンスの現在価値計算を考慮すると実際はもう少し差は小さいが今回はそんな細かいことは考慮しない)
短期的な目で見れば、10000円を今すぐ受け取ることが合理的であるが、その目線が一年後まで伸びるとするとそれは20000円を受け取る方が合理的であることはよくわかる。
こんなことは小学生でもわかるはずなのに私たちはその判断をすることができない人があまりに多い。これは別に個人に限った話ではない。かの有名なクレイトン・クリステンセン教授が提唱している「イノベーションのジレンマ」もまさにこの短期と長期のトレードオフを失敗した時に起こるものである。
この理由として筆者がすごく面白い言葉を言っているので紹介しようと思う。
人間は利益はすぐに手に入れたいが、痛みは先延ばしにしたい
もうこれ以上の説明は必要ないと思う。我々が短期的志向に陥らないためにはこの人間の原理とも言える特徴を意識しておくしかない。逆に言えば何かを判断するときに少しでもこの意識が出てきて一度立ち止まって考えてみることで少しは改善できるかもしれない。
過剰な自己中思考
最近思うのが、日本に蔓延る社会問題の根底には総じて『自己中心的な考え方』があるのではないかと思う。
例えば冒頭挙げたハラスメント系の問題に関してはこれがわかりやすい気がする。お店の店員さんに対しての態度が悪いことの背後には、『自分は客なんだから自分中心で話して良い』という前提があり、パワハラに関しては『自分は上司なのだから部下に対しては強く出ていい』という前提があるのだろう。
しかしどうしてこのような前提が生まれてしまうのだろうか?
私の考える理由は『共感する力が欠けているから』である。
この共感という概念はそれについて詳しく書こうとするとそれ一つで記事になるレベルなのでここでは詳しい説明は割愛するが、わかりやすく言えば『相手の目線に立って考える』という力と言える。
よく『自分がされたら嫌なことはしない』と子供に対していう親がいるが、私はこの指導は最も共感力を削ぐものだと感じる。この言葉にはさまざまな行動を判断するときに全て『自分ならどうか』という自分の価値観をもとに判断するという問題が背後にはある。
共感については話し始めるとそれだけで一冊の本になるくらいなので、最近読んでよかったおすすめの本を紹介しておく。共感について知るにはおすすめだ。
短期思考と自己中思考から抜け出すために
ここまで紹介してきた思考から抜け出すためにはどうすればいいのだろか?
考え方はそう簡単に変わるものではない。そもそも考え方というのは自分が間違っているということになかなか気づけないし、そんな自覚はない人間がほとんどである。(もちろんかくいう私もその一人である)
そうなった時、大切なのは常に自分自身を疑ってかかる一種の懐疑主義的な思想だろう。別にこれは自分のことを信用するなとかそういう時ではなくて、時々自分の行動や考え方が偏ったものになっていないかをよく考えることが重要だということだ。
それが今現在我々にできる唯一の方法なのではないだろうか。本書を読んでいてそう思った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
