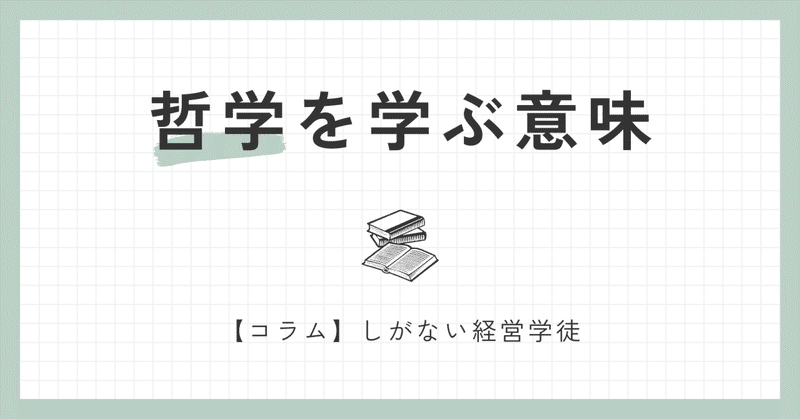
【コラム】 哲学を学ぶ意味
こんにちは!
三日ぶりの更新になってしまいすみません!!
ちょっと色々バタバタしていまして、前のように毎日更新ができなくなってしまうかもしれませんが、なるべく更新していくのでこれからも読んでいただけると嬉しいです!!
さて、今日は『哲学』というものの話題について話していこうと思います。
みなさんはこれまで『哲学』に触れたことはあるでしょうか?
大学生だと一般教養で哲学の授業があったり、文学部には哲学科があったりするので、すでに知っている人も多いかと思います。
ただ、なかなか日々の生活の中で根付いているものではないですよね。
なんだか難解な言葉をたくさん使いながら、難しい説明をしていくようなイメージがありますし、『哲学を学んだからといってなんになるんだ』と思われている方も結構いますよね。
なので、今日は大学から哲学を学びはじめた私が哲学を学ぶ意味について書いていこうと思います。
そもそも哲学とは何か?
哲学について話していく前に、そもそも哲学というのはどういう学問なのか?ということを明らかにしておきたいと思います。
哲学とは『生そのものについて疑問を投げかけて考えること』という定義ができます。これだけ聞いてもよくわからないと思うのでもう少し噛み砕くならば、「どうして我々は生きているのか?」とか「私たちはどうして存在しているのか?」といった生きていることに対する根源的な問いを立てて、それを考えていくのが哲学なんです。
この『哲学とは何か』ということに対しては有斐閣アルマから出ている『はじめての哲学史』という本がすごくわかりやすく解説しているのでもっと詳しく知りたいという人は買ってみてください。リンクも載せておきます。
ここまでで哲学というものが一体何をしているのか、ということがわかりました。
なので、ここからは哲学が果たす役割について私なりの意見をまとめていこうと思います。
前提を覆そうとする姿勢
私が哲学という学問を知ったことで、最も役に立っているのは「ある問いに対して簡単に答えを断定しない姿勢」であると言えます。
哲学という学問のもっとも大きな特徴として、「これまでに積み上げられた前提を完全に崩して考え直す」ことが挙げられます。
どういうことかというと、例えば私たちは算数を学ぶときまず「足し算」という知識を学びます。その後「引き算」とか「掛け算」とか計算方法を学んでその先の図形問題とか複雑な問題を解いていきますよね。
これは別に算数に限らず英語だってまずアルファベットを学びますし、もっと突き詰めればまず私たちは日本語という方法を学んでからその先の学問を学びはじめます。
このような考え方に対して哲学という学問は「いや、日本語がそもそも正しいかどうかわからないから日本語を使うのはやめて他の言語を考え直そう」と考えてしまう。
つまり、それまで信じられていた「前提」を吹き飛ばして、一から考え直そうとする姿勢が哲学にはあるのです。
この考え方は我々の日常とは相容れないものです。普段の生活の中ではたくさんの前提を共有しながら生きていますし、その前提をいちいち崩して考えていたら生活できません。
ただ、私も含めて多くの人は本来なら考え直さなければならない問題も前提として見逃してしまっている可能性があります。この見逃してしまっているたくさんの問題を捉えるために哲学は大いに役立ちます。
論理的に考えること
先ほど哲学は「生とは何か?」という問題を問うことと言いました。しかし、実は宗教というのもこの「生とはなにか?」という問題に答えを出すために作られたものです。
哲学が「論理」で世界を説明しようとするのに対して、宗教というのは「物語」で世界を説明しようとする営みです。
ただ、この物語というのは知っている人同士なら理解できますが、一度その物語を知らない人に出会ってしまうと急速にその効果を失ってしまいます。
同じアニメを知っている人同士ならその話は通じますが、知らない人からしてみたら「なんのこと?」となってしまうのと同じです。
この宗教の欠点を哲学は論理で乗り越えます。直感的にもわかると思いますが、我々が備えている論理性というのは物語と比較して、色々な人に通じやすいですよね。
つまり、論理には「万人に通じやすい」という大きなメリットがあります。色々な人に通じやすいとそれだけ説得力も増しますし、相手を納得させやすいです。
この論理性を身につけることができるのも大きな魅力の一つです。
思考体力がつく
先ほど哲学には論理的に考えるという魅力があると言いました。
しかし少し哲学を知っていくとわかりますが、哲学の論理というのはかなり厳密です。そしてその論理を厳密にしていくには、重箱の隅をつつくような問題に対しても深く考える必要があります。
この厳密な論理を構成するには、「思考体力」が不可欠です。思考体力というのは、その名の通り施行するにあたっての体力、つまりどれだけ深く考えることができるか?を示します。
哲学を扱っていくとその内容を理解するには、理解できないところを何度も見直して考える必要があります。そう簡単に理解できないからです。
このようにたくさんの哲学に触れて、複雑な論理にたくさん触れていく中でより厳密に考える頭の体力がついてきます。
そんなにそんなに「堅い」ものではない
ここまで三つの魅力をお伝えしてきましたが、最後に伝えたいのは哲学とは決して「お堅い」ものではないということです。
もちろん私の専門は哲学でもないですし、まだ入門すらしていないような初心者ですが実際に哲学というものに触れてみると思っていたよりも身近なものであることに驚きました。
哲学というと難しそうと思ってまだはじめていないのならとってももったいないと思います。最近はわかりやすい入門書も多いですし、ネットでも調べるとたくさんの記事が出てきます。
ぜひまずは一歩踏み出して哲学の世界に入ってみてほしいです。
ではまた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
