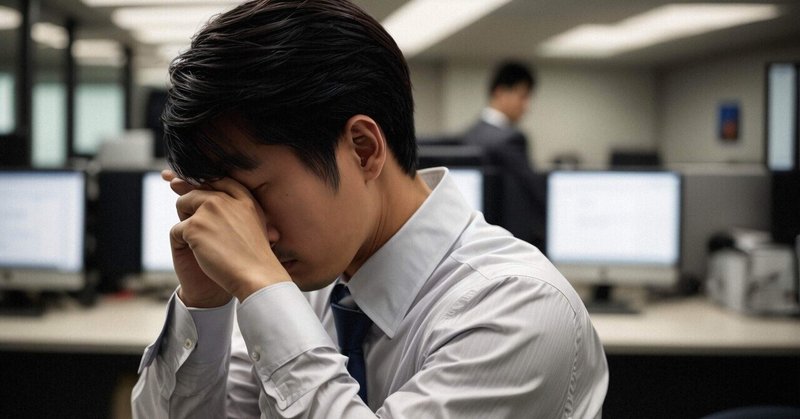
無資格でも設計はできる〜建築士資格は必要ない!?〜
5月になり、私の会社では新人研修を終えた新入社員が配属される時期になりました。
新入社員の自己紹介・抱負では、皆が口を揃えて「一級建築士を取ることが目標です!」と言います。
かくいう私も同じことを言っていましたが、先輩方を見渡すと無資格の人が案外多いという事実に驚いたことを覚えています。
この記事では、無資格でも建築設計の世界で生きていくことができる理由とそのリスクについてお話しします。
建築士になろうと頑張っているものの結果が出ていない方、試験勉強のモチベーションが上がらない方にはぜひ読んで頂きたいと思います。
【建築設計実務の裏側】
建築物の設計は建築士の独占業務であり、資格を持っていなければ設計ができないことが建築士法で定められています。
しかし、設計実務では無資格者が設計・作図したものを建築士がチェックして押印することで、「建築士が設計した」という体を成すケースが頻繁にあります。
「それって法令違反では?」と思うかもしれませんが、建築士が責任を持ってチェックしていれば法令違反にはなりません。
これには設計という行為の特性が関係しているのですが、具体例として運転免許と建築士免許を比較して説明します。
無免許の人が自動車を運転しているとします。
免許を持っている人が助手席に座って指導をしたとしても、事故や違反は一瞬のできごと。
起こってしまったら、もう取り返しがつきません。
そのため無免許の人が運転することは絶対に許されません。
これに比べて建築士免許はどうでしょうか。
自動車免許の例と違って、設計は時間が許す限りいくらでも修正・やり直しができます。
無資格者が建築基準法に違反する設計をしてしまったとしても、図面が世に出る前、つまり建築士がチェックする段階で修正すれば違反は無かったことになります。
そのため無資格者が設計を行った場合でも、建築士が責任を持ってチェックをすることで、建築士が設計したとみなされて法令違反にはならないのです。
このロジックが成り立つため、無資格でも建築設計の世界で生きていくことができ、無資格の人が案外多い業界となっています。
【資格と実務能力は別もの】
無資格者の設計を建築士がチェックすることで、法令違反にならないことを説明しました。
これは当然ながら、建築士が無資格者よりも設計に精通していることが前提となっています。
しかし、設計実務ではこの前提が逆転していることも少なくありません。
どんな資格にも言えることですが、資格の有無と実務能力の有無は別ものです。
「資格を持っているから実務能力が高い」とは限らないし、「資格を持っていないから実務能力が低い」とは限らないのです。
そもそも、資格試験は実務能力を測る試験ではありません。
試験元が決めた、資格を保有するに見合うだけの知識や技能を持っているかを測る試験です。
建築士試験は学科試験・製図試験の二部構成となっていますが、そのどちらにも同じことが言えます。
学科試験は意匠・構造・設備・施工といった、建築に関連する幅広い分野から様々な問題が出題されます。
しかし建築実務は専門分化しているため、全ての分野で主体的に業務をしている人はおそらくいません。
そのため、専門分野に関して深い知識・豊富な経験を持つ人であっても、学科試験の対策を行わない限り専門外の分野からの出題に対応できず、不合格となります。
また製図試験に至っては、未だに手書きの作図技能が求められます。
CADソフトによるパソコンでの作図が常識になっている時代に、日常的に手書きで作図している人はおそらくいません。
そのため、CADを使って素早くキレイに図面を描ける人であっても、手書きで図面を描く練習をしない限り思うように図面が描けず、不合格となります。
このように建築士試験に合格するためには、実務とは別に試験対策としての知識・技能を身に付ける必要があります。
こんな試験のために時間・お金をかけて勉強することは無駄と捉え、資格を取らずに実務に集中するという生き方を選択する人もいます。
実際、無資格であっても実務能力が非常に高い、ブラックジャックのような設計者も実在します。
【無資格でいることのリスク】
ここまで話をしてきましたが、「建築設計に資格は必要ない」と主張しているわけではありません。
資格を取らないという選択をする以上、無資格でいることのリスクを知ったうえで相応の覚悟を持つ必要があります。
ここからは建築設計者が無資格でいることのリスクについて説明します。
[自分の責任で設計ができない]
無資格で設計をする以上、いかに完璧な設計だとしても最終的には建築士にチェックしてもらい、その建築士に責任を負ってもらう必要があります。
経験の少ない若手のうちはそれでいいのですが、ある程度キャリアを積むとそのチェックを煩わしく思うことが増えてきます。
設計の世界に絶対的な正解はありません。
自分と建築士の設計方針が対立することもあります。
「自分の方が実務に精通していて、顧客とコミュニケーションも取っている。自分の設計方針の方が顧客のニーズにあった建築物になる。」という場合でも、自分の意見を曲げて建築士の意見に従わざるをえません。
なぜなら、表向きの設計者は建築士であり、その設計に対して法的責任を負うのはチェックした建築士となるからです。
資格が無いということは自分の設計に責任を持つことができないということで、当然ながら独立開業して事務所を構えることや、組織の設計責任者になることはできません。
[転職活動で不利になる]
資格の有無と実務能力の有無が別ものであることは周知の事実ですが、転職活動においては資格を持っていることが有利に働くこともまた事実です。
限られた時間と情報の中で合否を判断される採用面接において、資格は自身の能力を客観的に証明してくれる心強い味方です。
建築士という国家資格を持っているということは、目標達成に至るまでの戦略を立て、それに向けて努力を継続できる人間であることを、国が保証しているということなのです。
これはどんな仕事をするにしても重要な素養であり、採用面接において大きなアピールポイントとなります。
実際に建設業界の転職市場では、応募条件に「建築士資格の保有者であること」を掲げていたり、「建築士資格の保有者は優遇」と記載している企業が数多くあります。
無資格で転職活動を行う場合、業務実績・筆記テスト・面接で相当な高評価を得られない限り、有資格者を差し置いて採用を勝ち取ることができないのです。
[有資格者に対する引け目を感じる]
建築業界の実状がどうであれ、世間一般の認識は「設計者=建築士」。
これは紛れもない事実です。
資格を取らずに設計の仕事を続けていると、日常生活の中でふとした瞬間に有資格者に対する引け目を感じることがあります。
顧客との打ち合わせで名刺交換するとき、名刺に書ける肩書きが無くて説得力に欠ける…
会社で昇進して部下を持ったとき、部下が有資格者だとバツがわるい…
会社から資格取得を勧められたとき、正当な理由がなくて断りづらい…
同窓会・合コンで「設計ってことは建築士ですか?」と言われたとき、即答できずに何とも言えない空気になる…
これらは全て、当人から聞いた体験談です。
他人にとっては些細なことかもしれませんが、無資格であることの引け目を感じながら生きていくことになります。
【まとめ】
無資格でも建築設計の世界で生きていくことができる理由とそのリスクについてお話ししました。
資格試験の勉強をしても思うように結果が出ず、諦めたくなることは何度もあります。
諦めるための言い訳ならいくらでも浮かんできますが、どうか諦めないでほしいと思います。
建築士資格を持っていなくても建築設計の世界で生きていくことはできますが、それには相応の覚悟が必要です。
逃げの理由で無資格の道を選ぶことだけはしないでください。
自分はどんな風に生きたいのか、なぜ建築士を目指しているのか、あらためて考え直して頂くキッカケになればと思います。
この記事が面白かった・役に立ったという方は、スキ・コメント・フォローをお願いします。
次の記事を書くモチベーションが上がります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
