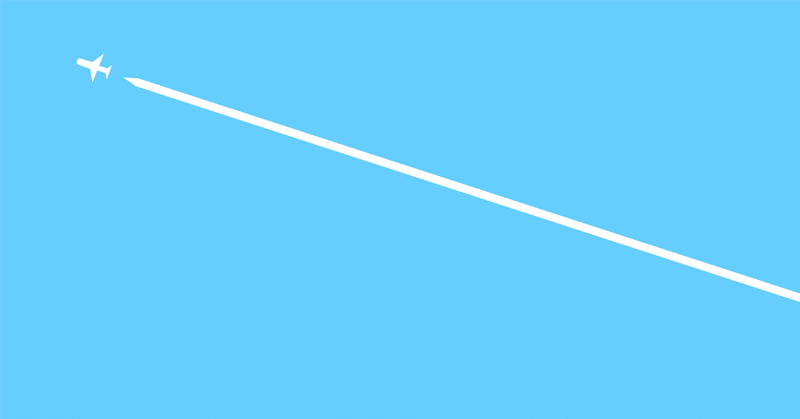
【エッセイ 日記?】 夏の入り口(2023.7.21)
夏の入り口、という割にはもう世界は茹だるような暑さの真っ只中で、キラキラ光る爽やかな夏というよりは外出を嫌ってしまう閉鎖された夏の有り様だ。僕は仕事には行ってるけど、休日は部屋にこもってアイスばかり食べている。1日に3本食べている。ちなみに好きなアイスはしろくまだ。
そんな日常のなかでも僕の心には夏の入り口に対する明瞭なイメージがあって、それは大学時代に行った自転車で巡る北海道1周の旅(旅行会社の謳い文句みたいだな)での記憶だ。あろうことか初日に僕は崖の下にテントと寝袋を落としてしまい、綿密に立てた計画は北海道に足を踏み入れてものの数時間であっけなく崩れ去ってしまった。
草っきれのなかで眠るわけにもいかないし… と思って結局僕はバス停で野宿をすることにした。北海道のバス停は寒さを凌ぐための工夫が施された雪国ならではの作りで、小さなバス停でも小屋になっていて引き戸もついている、ちょっとしたログハウスだ。
最終便の時間が過ぎてからバス停にお邪魔しベンチで眠る。朝は始発便がやって来るまでに荷物をまとめて旅を再開する。そんなふうに野宿をする日が1ヶ月の旅の間で何度かあった。いつも夜明けに目覚める。バス停の入り口からは四角く切り取られた朝の光が溢れていて、その光をくぐって1日が始まることに心躍っていた。自分の足でどこへでも行けたし、時間は贅沢にあった。今日は何が起こるのかな、なんて入り口の先に広がる未知に対する高鳴りを、夏が始まると思い出す。
家にこもってるって言ったけど、今年の夏は会いたい人にたくさん会える夏だ。読みたい本も描きたい物語もあるし、行きたいところにも行ける。両手から溢れそうな予定を落とさないように抱えながら、今日が大学の前期最終講義であった。
僕の授業では最初に音読をする。車座になって一人一文交代で読んでいく。読んだ本はサン=テグジュベリの「人間の土地」だ。限られた時間のなかで読めるのはほんの数ページでその文章の機微を捉えるには短すぎるけれど、学生と一緒に読んで、この本を選んでよかったなと思った。
講義終わりに熱心な学生が「文章が難しくていまいちわかりませんでした」と言いにきてくれた。「僕も大学時代に読んだ時はまどろっこしい表現に挫折して読み通せなかったよ」って素直に答えた。それから続けて「今は理解できなくてもいいから、死ぬまでに一回読み通してみな」なんて伝えた。
極端なことを言うけど、理解するなんて年寄りのすることだと思う。わからないということをたくさん経験できることが、子どもや青春時代の特権だ。返せば、理解できない未知に向かい続けていれば人はずっと若々しくいれるのだと思う。サン=テグジュベリだって幾度もの夜間飛行を通して世界を、自己を拡張し続けた。尽きることのない好奇心は夏の入り口につながっている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
