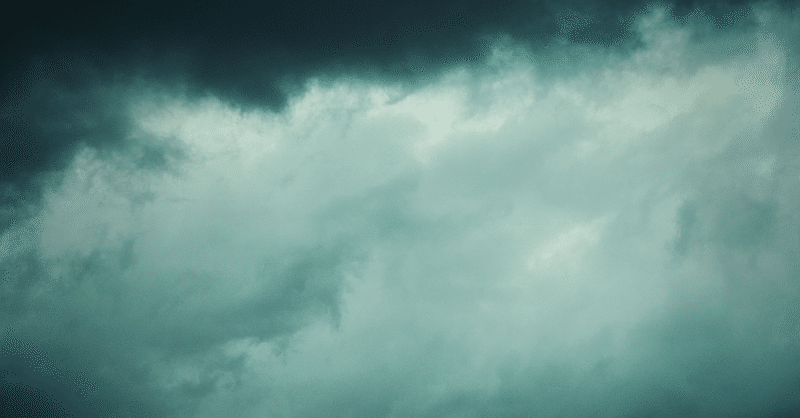
「自殺憎悪」 斎藤茂吉
※素人が、個人の趣味の範囲で入力したものです。
※一通り見直してはいますが、誤字脱字等の見過ごしがあるかもしれません。悪しからずご容赦ください。
※自殺に関する描写があります。ご留意ください。
※今日の社会において不適切と思われる表現が使用されている箇所がありますが、底本のまま掲載しました。
自殺憎悪 斎藤茂吉
この自殺憎悪といふのは、他が自殺することに対する憎悪。或は自殺する者に対する憎悪といふ意味で、羅典語か希臘語ででも書けば勿体がついていいのだらうが、それが私には出来ないから差当りかうして置いた。
この自殺については、世人は余り痛切に感じてゐない。家人に自殺者があつても、惜しいことをしたと云つて歎けばいい。他人ならばただお気の毒だぐらゐでよし、さもなければただの話題の材料にしていい。
然るに精神科医の吾々には、さう簡単に行かぬことが多い。自殺する者は勝手に自殺するのだから、法律からいつても何も吾々に罪は無いのだが、家人などいふものは一から十まで吾々に罪があるやうな顔付をすることがある。
私が巣鴨病院に勤務してゐた時にも、受持の中に幾たりか自殺者を出した。丁度明治天皇が崩御あらせられた日の朝、一人の患者が看護人の部屋から鋏を盗み出し、それで喉のところを目茶苦茶にはさみ切つたのを、丁度当直の私が不馴な手附で縫合したことがある。この時も家人が彼此いつて難儀した。この患者は幾度も幾度も看護人の注意保護で自殺未遂に終わつてゐたが、三年ばかり経つてとうとう自殺してしまつた。
それから、巣鴨病院で患者娯楽会のあつた時、患者出入のいそがしかつたほんの僅かの隙に一人の患者が便所で自殺した。呉院長は私を呼んで患家に弔問に行くやうにといふことで、私は出掛けた。患者の家は本所の奥で、溝川に沿うたあたりで、道は悪く電車から降りて人力車で行くにもまたその家を捜すにも一通りではなかつた。また何故私が弔問にやらされたかといふに、その時分私は医員ではもう一番古く医局長をつとめてゐたからである。さてやうやくにして患者の家を見附けて、院長からの香奠などを出し、くどくどと詫びを云つたものである。然るに家人はどうかといふに鼻もひつかけない。そして香奠を私に突返して、さていふに『いま弁護士に頼んだところですからいづれ御挨拶しませう』云々。
こんなことはその一例に過ぎない。巣鴨病院時代はただ職員の一人で責任者に院長が居るから、まだ気が楽な点があつたが、自分が院長になつて見るとまだまだ気苦労である。そして自殺する者の具合を見てゐるに、やる者は何時かは遣つてしまふのが多いし、何でもなくやる者がある。世間の健康な人達が常識で考へるやうなものではない。
私はそのころ、一面は注意上の心配をすると同時に、自殺者をいつのまにか憎むやうになつた。如何にしてもいまいましくて叶はない。彼等は面倒な病気を一つ持つてゐて、医者も看護人も苦心惨憺してゐるのに、なほそのうへ勝手に死んで心痛をかけるといふのが、いまいましくて叶はんのである。自殺憎悪症ともいふべき心の起こつて来てどうしても除れないのはそのころからである。
そしてこの憎悪症ともいふべき稍病的な心状は精神病者の範囲のみならず、それを越えて普通人のあひだに対してまでひろがつて行つた。それだから新聞の三面記事に載るものでも、いまいましくおもひ、『勝手な真似をしやがる』。『余計なことをしやがる。』『生意気な真似をしやがる』等ともいふべき下等な言葉を以てあらはし得べき心を持つやうにもなつてゐたことがある。芥川龍之介さんの死んだ時にも、ふとそんな心が湧いて私は強くそれを制したことがある。まだその時分には憎悪症ともいふべきものが心の隅に残留してゐたためであつたらう。
さうかうしてゐるうち、私は自殺者防禦に全力を尽した期間がある。実にいろいろのことをした。為てみると自殺者の数は前年に比して少くなり、或る年には一例もなくなり、次の年も次の年も一例もないといふ状態になつて来て、いつといふことなしに憎悪症が薄らいで行つた。或るときなどは、Odiumといふ羅典語をさがして、この心境を書いて見ようかなどと思つたこともあるが、この心境の薄らぐと共に、そんなことを書かうとする要求もなくなつてしまつたやうなわけである。
つまり憎悪(Odium)といふ証状をば直接取りのぞかうとはちつとも努力はしてゐない。併し、自殺が減つて行つたときにおのづとこの証状が薄らいで行つた。この事は極めて当然且つ平凡な事だけれども、ややともすれば気づかないことがある。
底本:斎藤茂吉選集 第十一巻 随筆四 1981年11月27日第1刷発行
1998年10月7日第2刷発行
初出:『改造』昭和12年1月 「癡人の随筆」より抜粋
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
