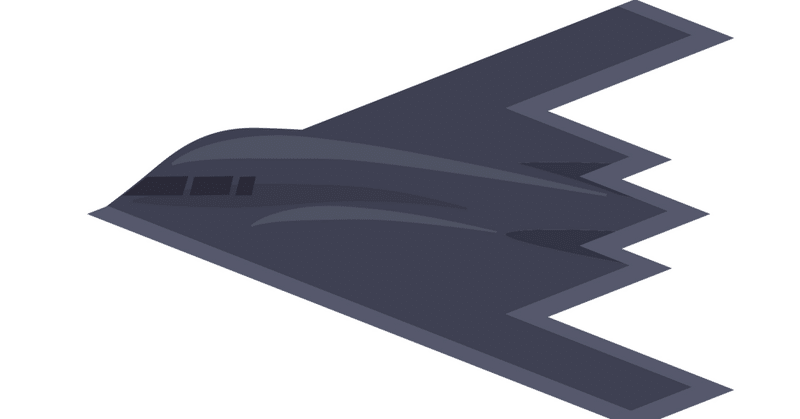
ローカルコンテンツの広報で避けたいこと
僕が編集長を担当しているオウンドメディアは、立ち上げから8年目。
このメディアは制作マンが書いている「番組ブログ」、イベントや特番告知などの「トピックス」、そして「番組記事」の3つに大別されます。
このうち「トピックス」と「番組記事」が僕の領域となっています。
いつの間にか1万本超え
「番組記事」は、ブロガーにはおなじみのRSSでLINE NEWSやスマートニュースなどのニュースメディアに展開しています。
記事数は1日平均で4〜5本配信、延べで1万本を数えます。
「番組記事」に関わっている社員は僕ひとりですが、記事の執筆はライターさんたちに依頼しており、ヘッダー画像の大半は元同僚の主婦が付けているなど、社外のスタッフたちに支えられています。
僕の役割は、ライターの皆さんに担当番組を割り当て、送られてきた記事の校正や見出しの推敲をすることです。
我ながら極度な飽き性なのによく続いてるもんだと感心しています。
8割がエリア外から
最近は180万ページビューを稼ぐ記事もあり、月間アクセス数も数百万ペースで推移しています。
Googleアナリティクスで見ると、8割近くがニュースメディアでの閲覧で、放送エリア(愛知•岐阜•三重)外からのアクセスがやはり8割を占めています。
つまり、自局リスナーが購読しているわけではありません。
このオウンドメディアは、当初からニュースメディアに送り込むことを画策して作りました。
ニュースメディアは日本のどこでも読むことができます。
そして番組も2016年秋からradikoエリアフリーで、日本のどこでも聴くことができます。
だからこそ、サービスエリアにこだわってないのです。
radikoエリアフリーには、指定日時のリンクURLを生成できる特徴があります。
このURLを記事のエビデンスとして記事末尾に付ければ、ノンリスナーが番組に接する機会が増えるのではと思いつき、ニュースメディア各社と交渉しました。
脱エンタメ
2017年3月にメディアを立ち上げ、4月にはスマートニュース、7月にはLINE、9月にはグノシーとの連携を始めました。
ニュースメディアとの交渉の場で、先方から期待されたのは、主にパーソナリティを務める地元エンタメ勢の記事でした。
一応「はいはい」とは言ったものの、僕の狙いはまったく別のところにありました。
職場では、時事ネタや生活のTIPS(シモネタ含む)を扱う番組が多く、当事者や専門家に電話を繋いだり、ディレクターがあらかじめ話題や事件の概要をレジメでまとめるなど、ひと手間かけています。
それゆえ「ニュース性が高いメディアになる」と考えていました。
キー局にもその手の番組から派生した記事はありますが、どちらかと言えばパーソナリティのタレント性が重視されているので、生活ネタならこちらの方が優勢だと確信していたのです。
WhoとWhatのせめぎ合い
僕の中で記事をバズらせるために決めた、ある意味冷酷なルールがあります。

これはスマートニュースの当社チャンネル画面ですが、記事にはある法則があります。
それは「見出しにパーソナリティ名を極力使わない」ということです。
現在、主要都市圏ではラジオのセッツインユース(メディアそのものに接触する割合)が5パーセント前後という低迷ぶりです。
原則としてこの調査はリアルタイムで聴いたことが前提なので、実際にはもう少し多くなるとは思いますが。
ただ、やはりラジオ村から出れば、ニッチメディアであることに変わりありません。
そもそもラジオは「何を話したか」よりも「誰が話したか」がウエイトを占めるメディアです。
だからアウトプットがテキストに変わっても、主語がパーソナリティになると考えるのが自然です。
しかしニュースメディアというのは、ラジオ村から見れば他流試合の場です。
ラジオに見向きもしない読者が圧倒的多数を占めています。
そんな不利な状況にパーソナリティ名で勝負を挑んだところで、おそらく手応えを感じることは少ないでしょう。
たとえ有名であれ芸能人の記事なら、スキャンダルネタをはじめ週刊誌•スポーツ紙の独壇場なのです。
だからこそ、見出しには「誰」ではなく、「何」を見出しにすることが最重要だと考えたのです。
「ネット戦略」の使い分け
実はオウンドメディアの立ち上げから半年ほど経ち、1日のPV数が2万を超えた頃、パーソナリティ名を見出しに入れた記事と、話した内容をタイトルにした記事を同時に出したことがあります。
その結果、後者には前者の30倍近いPVがついたのです。
この業界には「出演者ファースト」という風潮が強く、当初は番組スタッフからこの点を問われたこともありましたが、この実験の話をしたところ、早々に理解されました。
またこの20年、業界では「ネット戦略」も並行させるのが常識となっています。
もちろん、音声だけのポッドキャストなどは、パーソナリティ名を前面に出す方がいいと思います。
サムネイルが最初の接点となる動画コンテンツも同様です。
ただ、いずれも関心のない人は通り過ぎていくだけなので、結局パーソナリティの潜在的なファンの数に左右されるわけです。
著名ユーチューバーも無名の頃の主役は、発売されたばかりのスナック菓子やカップ麺、最新のガジェットなどの「商品」だったのです。
所詮キー局にはなれない
我々ローカル局には、よほど強い縁がない限り、知名度の高い芸能人などブッキングできません。
だからローカルの制作マンはとことんアタマを使って、内容の濃い番組、また聴きたくなるコンテンツを作るしかありません。
いま自社のオウンドメディアで記事化している内容も、「サンマが高い」だの「おっぱいがどうした」だの、リスナー目線で取り上げられたものがほとんどです。
でもそういう記事の方にこそ、何十万PVという反響があるのです。
予算も時間もない中で、せっかく知恵を絞って面白い番組にしようと努力してるんですから、その知恵をアピールした方がいいと思うんですよね。
他局が取り組んでいるテキストメディアを見ていても、ほとんどが出演者ファーストなんですよ。
僕自身、ラジオ村の住民ではありますが、タイトルのパーソナリティやゲストに興味がないと、やっぱりスルーしちゃうんですよね。
自画自賛じゃないんですけども。
とは言え、おっぱいネタは程々にしたいところではあります。
ラジオ局勤務の赤味噌原理主義者。シンセ 、テルミン 、特撮フィギュアなど、先入観たっぷりのバカ丸出しレビューを投下してます。
