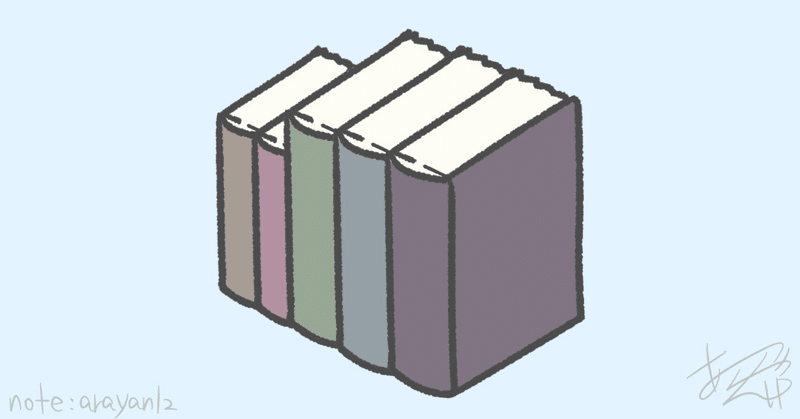
受験の季節
大学受験の話題がSNSから聞こえてくる。今年も全国の受験生が1年間の勉強の成果を発揮する季節がやってきた。それと同時に、日本の受験制度や学校での学習内容に対する議論も活発になる。古典など、日本特有の科目に対してはその必要性を含めて、特に議論が白熱しているように感じる。私はSNS上で意見できるほどの人間ではないから、ここで密かに独り言を。
結論から言えば、私は日本の大学受験および、高校の学習カリキュラムが好きな方である。日本の受験は努力が評価されるところが良い。受験にちゃんと向き合って勉強すれば、自分に合った学力の大学にきちんと入学できる。『平等なチャンス』が一定の水準で保証されている。
高校での学習内容が、受験勉強になってしまっているという指摘をたびたび目にする。それは否定的なニュアンスであることが多いが、私は、それの何が悪いのかと思う。入学試験が、学校のカリキュラムに上手く対応しているだけのことだ。私は、入学試験がIQテストのような、その場の瞬発力のみで回答できるものだけになったとしたら、その方が問題だと感じる。
つまり、多くの大学は、『高校の学習内容をいかに蓄積できたか』を重視しているということだ。大学で研究を齧ると、恐ろしいことに、専門分野に特化するために必要な知識量は、高校での全科目分の知識量を遥かに超えることが分かる。それらを長い研究生活の中で蓄積していく力は、研究機関である大学が学生に求める能力のひとつである。
また、『自分の知らないことにいかに興味を持てるか』も、研究においては重要な能力だ。高校での学習内容は文系理系の両方を含んでいる。広く雑多な情報に触れ、興味を持って知識を吸収する能力が研究には必要なのだ。古典の中に科学を見出すことができれば、その人は研究者として末長く飯が食えるに違いないのである。
「受験勉強なんか意味がない。はやく学問の楽しさを感じたい。」という受験生の愚痴をよく聞く。私もかつてはそう考えていた。しかし今になって、受験勉強も楽しめないようでは、研究など出来はしないのだと気づいた。受験期は知識を吸収する時間だ。その過程が楽しめる人間こそ、研究に向いている人間なのではないか。大学で学ぶことは、その先にある研究に嫌でも繋がっている。受験生諸君には、受験を通して、『大学での学び』に耐えうる能力を培って欲しい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
