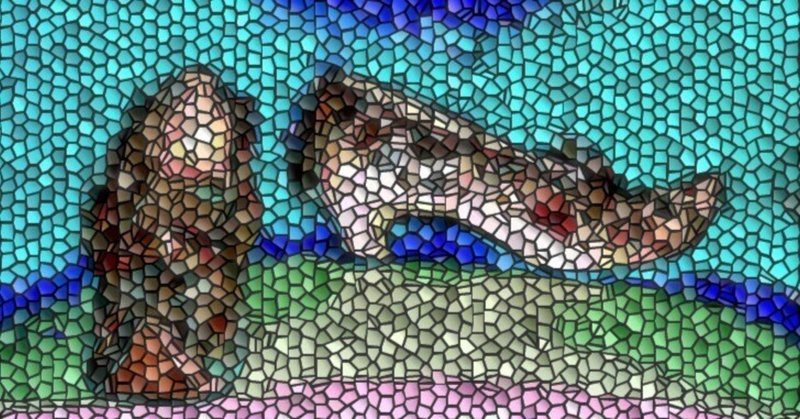
魔法の靴⑱それでも仕事がありました!
第十章
希美とぜんぜん連絡がつかない。LINEは返って来ないし、電話はどうやら着信拒否されているようだ。
香奈恵は途方に暮れた。
希美と別れた最後の場面を何度も反芻する。演奏会のあとの短い会話。香奈恵の言葉は、希美の心を逆なでするものだったのは、間違いない。ソロを担当すると聞いていた後半に、希美の姿がステージになかった時点で「よかったよ~」と言ってはいけないことに気付くべきだった。
きちんと謝りたい。でも、希美が鉄の壁の向こうに引きこもってしまうと、香奈恵は途方に暮れるしかない。
そうだ。1人、鉄の壁の向こうと香奈恵がつながる可能性がある人物がいる。拓也だ。
でも、香奈恵が拓也に直接、連絡するのは気が引ける。これまで一度も、希美の知らないところで接触したことはない。
大好きな希美の彼氏だからだ。
希美が香奈恵に嫉妬する可能性はないはずだ。きれいで才能があって輝いている希美と、平凡で目立たない香奈恵では月とすっぽんにすぎる。でも、希美の頭越しに香奈恵が拓也に連絡するのは、面白くないかもしれない。1ミクロンでも希美に嫌な気持ちをいだかせたくない。
とはいえ、ほかに方法はない。
希美、ごめん。1回だけ。
香奈恵はベッドに正座して、拓也に「お手透きの時に連絡ください」と、丁寧にLINEを送った。
10分もしないうちに、スマートフォンが鳴った。香奈恵はベッドからもぎ取るようにスマホを取り上げた。
「はい! 香奈恵ですっ!」
「……おお、びっくりしたぁ。どうも~、拓也です~」
拓也の間延びした声は、いつもと変わらない。香奈恵の肩から力が抜けた。
さっそく、あの日の出来事を聞いてみる。
「あたし、希美に謝りたいんです」
「ああ」。拓也が電話の向こうで長いため息をついた。「こっちこそ、ごめんね。香奈恵ちゃんのフォローをしておくべきだった」
「いえ、そんな」と、恐縮する。
「演奏者じゃないとわからないことを、香奈恵ちゃんにあたっても仕方ないのに、希美ときたら」。拓也の力ない笑い声が聞こえる。
「やっぱり、なにかあったんですか?」
「あの日、希美のヤツ、本番直前にリードをだめにしちゃったんだよね。それで音が出なくてね」
「リード?」
「そう。オーボエは音を出すのに、口元に当てる『リード』っていうパーツが重要なんだ。リードが合わないと、いつもの音が出ないのよ。本当にめんどくさい楽器でねぇ。いい音が出るかどうかは楽器のご機嫌次第。手入れや管理にものすごく気を使うんだ。演奏前のチューニングで希美が吹いた音、いつもと違うと思わなかった?」
「そういえば。はい」。音大の卒業演奏会で聞いた音とはぜんぜん違って、なんだか頼りないと感じた。
「リードは完成品も売っているけど、希美くらいのレベルになると、これはもう手作りなんだ」
「手作り、ですか?」
「そう。細い彫刻刀みたいなナイフで、材料を少ぉしずつ、削って作るの。消耗品だから、どんどん作らなきゃいけない。オーボエ奏者って忙しいよね。練習しながら、リード削って、楽器本体も温度や湿度の変化に弱くて壊れやすいし。希美はデート中も、暇さえあれば無言でリード削ってるよ」
拓也は短く笑った。
「そんな大変な楽器だなんて、ちっとも知りませんでした。そういうの、ぜんぜん話してくれなくて」と、香奈恵は少し恨めしくなる。
「そりゃ、こういうのは演奏する仲間うちの話だ」。拓也は軽くいなした。「で、話を戻すと、オーボエのリードはね、吹く前にも水に浸さなきゃなんない。これがまた、漬けすぎるとダメになるし、水分が足りなきゃ困るし。気が抜けないのよ」
呆然とする。舞台で華やかなドレスを身につけた希美しか見ていなかった。希美が奏でるユーモラスでふくよかな響きを聞くだけだった。裏でどんな準備をしていたのか、香奈恵は考えたことがなかった。
「希美はあの日、本番用のリードを水に漬けて準備していたんだけどね。何かの拍子で容器が倒れて、リードが床に落ちた上に、どうも踏まれたみたいなんだな。リードが乾いて割れていた。気づいたときには、もう間に合わなかったんだってさ」
「それで、音が出なかったんですか」
「そういうこと。チューニングも希美が担当するはずだったが、ちょっと吹いた音を聞いて『これはだめだ』と、隣にいたオーボエのトップ奏者が判断した。だからすぐトップ奏者が音を出しただろ」
確かに。あのとき、希美のオーボエから細い音が響いたのはほんの一瞬で、すぐに隣の奏者の音が力強く加わった。そしてすべての楽器がチューニングを始めたのだった。拓也の話は続く。
「そんなだから、希美はとてもソロをやれる状況じゃなくてね。オーボエのトップが、後半は別の団員が代役で出るから、希美は休めと言ったんだ。予定していたソロはトップがやった。あいつはオレと一緒に、自分が演奏するはずだったメロディを舞台袖で聞いていた」
拓也のため息は、深く長く悲しげだった。
「まあ、スペアのリードを家に忘れたことも、容器が倒れたのに気づかなかったことも、希美の凡ミスなんだけどね。デビュー戦に思い入れがあっただけに自分のミスが許せないみたいでね」
「そこに、あたしが『よかったよ~』なんて言っちゃったんですね」。背筋が寒くなる。
「香奈恵ちゃんにあたったのは、本当に申し訳なかった。間が悪かった。どっちかというと『夢がかなった日だ』って言われた方が、逆鱗にふれたみたいだな」
「……そんなこと、言いましたね」。顔から血の気が引く。夢がかなったどころか、正反対。希美にとっては、最悪のデビューだったわけだ。
「まあ、一回の失敗でダメになるわけじゃないし、大丈夫だよ。希美は音大時代に最初のコンクールで失敗した後も、かなり荒れたけど立ち直ったしね。今回だって、すぐ持ち直すさ。連絡が付かないのは、自分が悪いのに香奈恵ちゃんにあたっちゃって、決まりが悪いからじゃないかな。オレからも香奈恵ちゃんが心配してるって言っておくけど、もう少し、そっとしておいてくれるとうれしいな。とばっちりで、ごめんね」
拓也は、どこまでもにこやかに電話を切った。
香奈恵は沈黙するスマートフォンの画面を見つめた。
最初のコンクールの失敗? そんな話、聞いたことがない。大学3年生のときに全日本コンクールで3位に入賞したことは知っているけれど、失敗なんて、一体いつだろう。ピアノを諦めたのだって、ついこの間まで知らなかった。
いつも落ち込むのは香奈恵で、希美は「よしよし」と慰めてくれる。困ったときに話を聞いてくれるのは希美で、親に言えない失業も希美には打ち明けた。
希美は一度だって、香奈恵に落ち込んだ姿を見せたことがない。自信たっぷりに、順調に歩いている姿しか、表に出さない。
「あたしは挫折したことがないと思っていたの? まあ、そのほうがかっこいいから、いいけどね」
そう言っていた。香奈恵の前では、常に希美は「かっこいい」成功者だった。
地元の名士の娘で何不自由なく育った希美が夢を次々とかなえていく裏で、どんな努力や挫折があったのか。香奈恵は何も知らなかった。
「なんでもいいからハッピーエンドが夢だとか言ってる、お気楽で半端な甘ちゃん」
希美は香奈恵のことをそう言った。反論できない。
大好きなピアノを諦めて、オーボエを毎日何時間も練習し、気難しい楽器の手入れをし続けた。コンクールに挑戦して失敗して再挑戦して、全国3位でも就職できずに欠員を待ち続け、大学院で限られた学生しか出られない卒業演奏会で演奏できるほどに腕を磨いた。
ひきかえ、香奈恵はどうか。毎日のんびりすごせればよくて、何かを頑張った記憶はほとんどない。希美がしてきた努力の百分の一……いや、一万分の一さえも、覚えはない。夢がないから。見つけようとしなかったから。
自分の怠惰に愕然とする。
香奈恵がしてきたのは、舞台の上の希美や、拓也とのラブラブなデートを羨んで、憧れることだけ。
やりたいことを探そうとすると、脳味噌がフリーズする。それはつまり、なにかになる可能性を、心の底で最初から諦めているからだ。
そのほうが、楽だから。最初から諦めれば、努力が報われず挫折を味わうこともないから。
なにかを目指す障害はなにもなかった。慎太みたいに死ぬこともなく、誠一のように親の手で夢を折られることもなかった。小倉少年のように家業を継ぐよう強要されることもなく、治彦のように兄と差別されて育つこともなかった。それがどれだけ幸運なのか。
幸運に気づきもせず、ただ羨んで憧れるだけ。24歳にして「とにかくのんびり幸せに暮らしたい」って、ご隠居思考。
希美は、そんな香奈恵に、ずっと苛立っていたのではないか。
考えるほど、空恐ろしくなる。
こんなあたしが、誠一に夢を目指してもらうために10年前の心の傷を掘り返すなんて、そんな資格はどこにあるのか。
香奈恵は肌掛けの下に逃げ込み、ぎゅっと目をつぶった。

働いていてよかったと思うのは、落ち込もうが絶望しようが、仕事に行かなきゃならないことだ。悩みだけ考えて一日過ごしたら、きっと簡単に引きこもりになっていた。
香奈恵は重い心と体をとりあえず棚に上げ、蛇口を全開にした水を勢いよく顔にかけた。洗面台が水浸しになるが、放っておけば乾くだろう。歯を磨いて気合いを入れる。最低限の化粧をした最後に、ほっぺたを両側から平手でばしんと叩いた。
「っしゃぁ! 今日も一発、ぶちかますぞぉ!」
開店準備では普段以上に走り回る。「それ、あたしやります!」「手伝います!」
威勢の良さに、山際チーフが目を細めて口をすぼめた。
午前中はいつもよりずっとハイテンションで接客した。
それが、どうも、仇になった。
「軽いジョギングをなさる程度なら、始めのうちは、底が薄く柔らかい靴は避けたほうが、足にはいいですよ。そちらとデザインは違いますが、初心者には、こちらのラインの方が」と、誠一になったつもりで、若い女性客の商品選びをお手伝いする。
と、女性客は眉を寄せて、香奈恵の手を払いのけた。「うるさいなあ。好きに選ばせてよ。モデルのリナちゃんがホノルルマラソンで履いたのは、このモデルなんでしょ?」
「でも、リナさんはフルマラソンを何度も走っていて、これからジョギングを始められるお客様とは……」
「う・る・さ・い! ちょっとあんた、余計なお世話だよ。どういう教育されてんの。店長呼んでよ、店長!」
女性客はとがった声を張り上げた。
背後から、ぱたぱた足音が近づいてきて、香奈恵の肩越しに明るい声が聞こえた。
「お客様、どうかなさいましたか?」
山際チーフだ。とびっきりの笑顔で、背筋をぴんと伸ばしている。
女性客はチーフの頭のてっぺんから足先までじろじろ見て、鼻を鳴らした。
「あんた、責任者?」
「はい。私、スニーカー売場の責任者で、山際と申します」
「ちょっと、部下にどういう教育してるか、教えてくれる?」と、女性客は香奈恵を勢いよく指さした。香奈恵の肩がびくっと跳ねた。
「こいつ、あたしが選んだ靴にけちをつけてきたのよ。あたしが履くには百年早いとか言ってさ」
「そ、そんなこと言ってな……」
香奈恵のかすれた声は、山際チーフがひらりと動かした手で止まった。チーフの声が香奈恵に被さって朗らかに響く。
「ご不快に思われましたら、誠に申し訳ございませんでした」
90度に腰を折った山際チーフに、女性客は勢いをそがれたようだ。香奈恵も反射的に深く頭を下げる。山際チーフは絶妙の呼吸で客に大きく一歩近づいた。
「お客様はこちらのスニーカーをお求めなんですね。はい、すばらしい靴で、サイドのデザインがおしゃれですよね。モデルでアスリートのリナさんもご愛用で、人気です。サイズはよろしいですか? お選びいただいて、ありがとうございます。お箱にお入れいたしましょうか?」
「……そうしてくれる?」
女性客は面倒くさそうに手を振った。山際チーフは女性客の背中を抱くようにしてレジに誘導し、ちらっと香奈恵にウインクした。
香奈恵は山際チーフの後ろ姿にぺこりと頭を下げた。
女性客を最敬礼で見送って、山際チーフは香奈恵のところに小走りで戻ってきた。
「で、何やったの?」
香奈恵はしゅんと肩をすぼめた。「すみませんでした……あのお客様は、これからジョギングを始めるっておっしゃったので。走った経験がほとんどない人が、いきなりフルマラソンを走り慣れている人と同じような底が薄くて柔らかい靴を履くと、逆に走りにくいんじゃないかと思って、底が厚手の靴をお勧めしたんですが……」
「村瀬さんは、機能重視派だもんね」。山際チーフは、こくこくうなずいた。「でも、あのお客様は、機能よりデザイン重視のタイプだったんだね。だから、食い違っちゃったんだね」
「すみませんでした……」と、また頭を下げる。
山際チーフは、にかっと笑った。
「お客様にはいろいろなタイプがいるからね。機能的にぴったりなのをお勧めしたい村瀬さんの気持ちはよくわかるけど、お客様の好みがはっきりしている場合は、自分の意見は控えめにしたほうがいいね。お客様と話をしながら、どんな靴があうかだけじゃなく、どんなタイプの人なのかも、見極めるようにしようね」
「ありがとうございます。融通利かなかったです。気をつけます」
自分がものすごくダメなやつに思えてくる。夢さえ持てない女が、はっきり「この靴が欲しい」と言い切れるお客様にダメ出しするなんて、百年早い。不覚にも、鼻の奥が熱くなる。
山際チーフが香奈恵の顔をのぞき込んだ。「どした?」
「なんでもありません」
香奈恵は目をそらして天井を仰いだ。あほか、あたしは。職場で泣くな。
山際チーフが腕時計を見た。「お、こんな時間か。今なら店内も空いてるし、二人で昼食に行こ!」
有無をいわさず香奈恵の腕を引っ張ってバックヤードに連れ込み、香奈恵のエプロンのひもを器用にほどいた。
「はい、ばんざーい」
つられて両手を上げると、山際チーフはするすると香奈恵のエプロンを脱がせてしまった。続いて自分もぱっぱとエプロンをとる。
「山際と村瀬、2人で、お先に昼食休憩いただきま~す」
明るく声をかけ、山際チーフは香奈恵の手を引っ張ってショッピングモールのフードコートに連れ去った。
山際チーフはお好み焼きコーナーでイカ玉、香奈恵は丼コーナーで親子丼をチョイスし、テーブルを確保する。
「で、ほかに何があった?」
山際チーフの問いかけは、いつもすっぱりシンプルだ。真っ正面から聞かれ、香奈恵の心の扉がすかっと開いた。
希美のこと、誠一のこと、自分のこと、お客様のこと……すべてが怒濤のように扉の向こうから渦巻いて飛び出してきて、ごちゃごちゃの取っ組み合いを始める。ぐっと押さえようとしたら、鼻がまた、つうんと痛んで、下を向いたら涙がぽたぽたと親子丼を直撃した。
「どしたん?」 山際チーフの声が、包み込むような温かさを帯びる。がさがさ音がして、目の前にティッシュが差し出された。
「すみません」。香奈恵は受け取って、目と鼻を押さえた。耳が赤くなっていると思う。
心の中の大混乱を押さえ込む間、山際チーフは待っていてくれた。お好み焼き、冷めるから食べてくれていいのに。
「あたし……あたしって、ダメなやつですよねぇ」
笑ったつもりが涙声になってしまった。
「どして?」
初めて聞く山際チーフの滑らかで柔らかい問いかけ。堰は崩れ、香奈恵はティッシュで涙と鼻水を盛大に押さえた。
「あたし……あたし……夢とか目標とか、ないんですよね。見つからないんです。自分が何をしたいのか、何を欲しいのか、ぜんぜん考えずに、その日がよけりゃいいやって、お気楽で半端な甘ちゃんで生きてきたんですよね。山際チーフ、あたしの面接の時、正直、やる気あんのかと思ったって言ってましたね。やる気なんか、どこにもなかったんです。そんな自分が嫌で……就職決まんなかったわけですよ。こんなんじゃ、どこだって採用されないわけですよ。甘えて、努力もしないで諦めるくせに思いこみが激しくて。ダメダメですよ。だから、今日だって、お客様を怒らせちゃうんですよ」
もはやびしょびしょのティッシュで瞼をぎゅっと押さえる。
と、頭に温かくて柔らかい感触が乗った。山際チーフの手だ。そうっと撫でてくれる。
「村瀬さんは、努力してるよ」
あったかい声。
「最初は、正直、やる気がなさそうでトロそうだと思ったけど、すぐ商品の品番を一生懸命覚えて、それぞれの商品ラインの特徴もつかんだでしょ。1ヶ月もしたら貴重な戦力になっていたよ。努力したから、お客様の目的に合う機能的な靴を、自信を持ってお勧めできるようになったのよ」
止まりかけた涙が、また盛大にあふれだした。
さっきは涙で胸がぎゅっと苦しくなったけど、今度の涙は不思議なことに、胸の固まりを溶かして押し流してくれるみたいだ。肩の力がふうっと抜けて、体がほぐれていく。
「おやまあ、ほらティッシュ全部使っちゃいなさい」
山際チーフが差し出してくれたティッシュは、和柄の女らしいティッシュケースに収まっていた。
「かわいい」。ようやく、少し笑うことができた。
涙を止めたら、残り時間で丼をかき込み、洗面所に走って徹底的に顔を洗う。午後はすっぴんだが、いたしかたない。
山際チーフは香奈恵の横でしゃかしゃかと歯を磨き、香奈恵をせかして売場に戻ると、さっさとエプロンをつけて店頭に走り去った。きちんとお礼を言う暇もない。香奈恵もあわてて後を追う。
早番のシフトが終わる頃合いに、香奈恵は山際チーフに呼ばれた。振り向くと、山際チーフの隣に立っている男性に見覚えがあった。
名前は忘れたが、2回くらいスニーカーを売った記憶がある。父親と同世代と思われる。
「村瀬さんをご指名なの。あとはよろしくね」。山際チーフはウインクして身を翻した。
香奈恵は戸惑いつつ、精一杯明るく「いらっしゃいませ。いつもありがとうございます」とお辞儀した。
男性は今回は、通勤に履いても目立たない黒のスニーカーを買いにきたとのことだった。「村瀬さんに勧めてもらったスニーカーの履き心地が大変良くてね。この際、三駅先の会社まで、徒歩通勤するか! と思い立ってね」
「ありがとうございます!」 元気よく頭を下げる。幸い、このお客様に勧めた商品とサイズは、頭に入っていた。バイトを初めて以来、売った商品をメモする癖がついている。
「お客様が前回お求めになったのは、こちらのラインでしたね。サイズは……27センチですよね」
「よく覚えてるね」。男性客が目を細めた。
黒の在庫を調べにバックヤードに戻り、目指す箱を抱えて男性客のところに戻る。
「念のため、試しに履いてごらんになりますか?」
「そうだね。履いてみよう。うん。大丈夫。この間、買ったのと同じで、いい感じだよ。これをもらおう」
男性は商品の自宅配送を希望した。座って宅配伝票を書いてもらう。住所や名前を慎重に確かめながら、男性は言った。
「村瀬さんのおかげで、歩くのが楽しくなったよ。今じゃ、あてもない散歩が趣味になった」
「あてもなく、ですか?」と、香奈恵。
「そう。行く先を決めないで、とりあえず歩き出すんだ」
「わあ、すごいですね。あたしだったら、行き先が決まってないと歩き出せないかも」
ふと「行く先が決まっていない」という自分の言葉にひっかかった。夢を持てないあたしは、要するに人生の行く先が決まっていない。あてもなく歩いている状態ってわけね。軽く落ち込む。
男性は短く笑った。「肩に力を入れなくてもいいのさ。そりゃ、目的地が決まっている方が、わき目もふらずに歩けるけれど、歩くことそのものが楽しいんだよ」
「楽しいですか?」 つるっと口から疑問がこぼれた。
「うん。楽しいよ。桜が散ってツツジが咲いたな……一雨ごとに緑が濃くなるな……川の水量が今日は多いな……見所満載だ。そうして歩いているうちに、今日はあの公園の池を見に行こう、なんて、目的が決まったりするもんだよ」
「そうなんですか」
「意外だな」。男性はいたずらっぽい口調になった。「君は、こんなにいい靴を勧めてくれたのに、歩く楽しみを知らないのかい? 僕に歩く楽しさを教えてくれたのは、君なんだよ」
「あたし?」
「そうだよ。君だよ。また、君から買いに来るよ」
男性は、笑いを残して店を後にした。
「ありがとうございました!」 香奈恵は腹の底から声を出し、深々とお辞儀をした。
なかなか頭を上げられない。嬉しくて、お腹の中がむずがゆい。
また、あたしから買いに来るって! あたしが、歩く楽しさを教えたんだって!
小走りでレジに戻って、今の男性が書いた宅配伝票の名前を確かめた。「中川晃」さん。この次にいらっしゃったら「中川さん」って呼びかけよう。
(続く)
/////////////////////////////////////////////////////
最初からお読みになりたい方はこちらからどうぞ!↓↓↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
