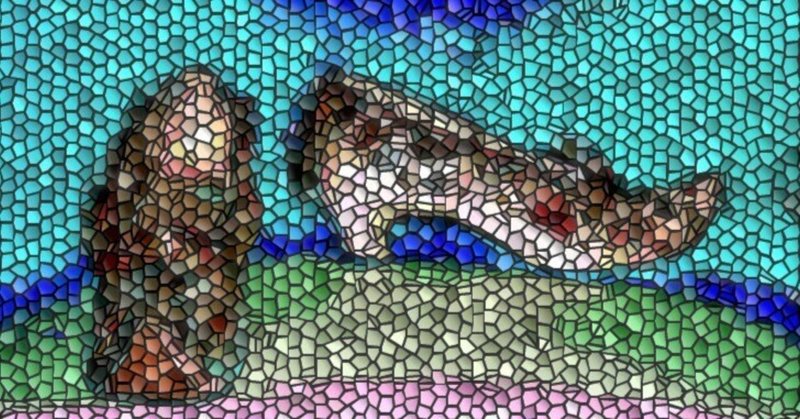
魔法の靴⑰親友にキレられました!
第九章
希美の演奏会は、都心から少し離れた駅前の大型ホールが会場だった。改札口で拓也と待ち合わせる。
拓也が見慣れない背広にネクタイ姿だったせいで、香奈恵は、本人が3メートル先にいるにもかかわらず、きょろきょろする羽目になった。拓也からスマートフォンに電話をもらうまで気づかなかった。
「拓也くん? 今、どこ?」
「目の前だっつの」
肉声が斜め前から聞こえて、ようやく拓也の存在に気づいた。香奈恵が90度の最敬礼で謝ると、拓也はひらひら手を振って笑ってくれた。
「見違えるほど、いい男だってことだよね? よっしゃ希美が惚れなおすぞ!」
ガッツポーズ。その手には巨大な花束が握られている。あまり見かけない渋い赤茶色の優美なバラが何本も。花には詳しくない香奈恵でも、高価な品種だとわかる。気合入ってるな。
客席に落ち着いてパンフレットを広げる。前半はボロディンの「だったん人の踊り」と、ムソルグスキーの「はげ山の一夜」。休憩を挟んで後半は、リムスキー・コルサコフの「シェーラザード」だ。
「はげ山の一夜」は、あの、おどろおどろしくけたたましい、モンスター登場シーンにぴったりなやつだろう。あとの二曲は香奈恵は知らないが、拓也は「聴けば必ず『これ知ってる』って思うよ」と、右手でイイネ!を作った。
場内の照明が落ち、舞台だけが明るくなった。
舞台下手側の扉が開き、赤みの強いブラウンが艶やかなバイオリンを無造作にぶら下げてコンサートマスターが現れた。拍手が起こる。
コンサートマスターが席に着き、会場は静かになる。舞台中央で、細い楽器がかすかに動いた。楽器の金属部分が鋭く輝く。香奈恵の目線はそちらに移った。
希美のオーボエだ。
「おっ、スターターか。希美、すげぇじゃん」
拓也が隣で呟いた。
「オーボエは始まりの楽器なんだよ」。希美はそう言っていた。
希美がオーボエを構える。吹いた。細い細い音。
音大の卒業演奏会で聴いた希美のオーボエ協奏曲は、もっとふくよかな音だった。今日は響きが違うな……と、香奈恵が思った瞬間。
「あれっ」
隣で、拓也の声が小さく裏返った。見ると、拓也は口をぽかっと開け、顔色が蒼白だ。
「希美、どうした?」
拓也がささやくように息を吐き出す。何か異変があったようだ。
舞台では、希美の隣の男性が、落ち着き払って希美と同じオーボエを構え、吹いた。希美のオーボエに音が重なり、響きがしっかり安定する。
続いて、コンサートマスターが立ち上がり、大きな身振りでバイオリンを弾き始めた。4本の弦を次々に引いて響きを確かめる。まもなく、舞台のすべての楽器が響き始めた。
チューニングだ。香奈恵はようやく思い出した。
「演奏会は、オーボエのAから始まるの」。希美はオーボエを始めた中学時代、誇らしげに語っていた。「オーボエのAの音程にあわせて、オーケストラ全員が音を調節するんだよ。オーボエから、すべての演奏が始まるの。だから、始まりの楽器だよ」
今日も、希美の音から、すべての演奏が始まるわけだ。細い音だったけど。
ひときわ拍手が大きくなり、体をやや前に傾けて、指揮者が急ぎ足で現れた。小柄で白髪、体中から水分が抜けた感じの男性だ。水分を失った代わりにエネルギーをぎゅっと凝縮したような熱さを感じる。
指揮者が台に上る。指揮棒を持った腕が上がる。
香奈恵の席から見ると、指揮者があげた肘が希美と重なって、その姿を隠した。
指揮棒が、そよ風に揺らぐように柔らかく動き始める。男性が構えたオーボエと、フルートが響き合う。耳になじむ旋律が、滑らかにホールに流れた。緑の柔らかい草が風で波打って白く翻る、草原の光景が目の前に広がる。
あ、知ってる。この曲、好き。香奈恵は微笑んだ。
指揮者が身をよじり、希美の顔が現れた。
あれ? と思った。白い白い顔。もともと色白だが、あれでは「今日は顔色が悪い」と言いたくなる。照明のせいか? 隣をちらりと見ると、拓也が真剣に希美を見つめ、引き締めた唇に緊張が走っている。
曲が盛り上がり、戦士たちの勇ましい踊りを思わせる響きが、テンポを早めて勢いを増す。高揚して曲は終わった。
拍手と一瞬の静寂の後、金管楽器が緊迫したフォルテを響かせる。さっきまで草原だったホールの風景は一変し、険しい岩山から怪物や魔物がぞわぞわと姿を現す気配になった。さあ、見てはいけない夜の異世界の宴、「はげ山の一夜」が始まる。
希美の顔は、ずっと白いままだ。目に生気がない。あんな顔、始めてみた。
魔物たちの饗宴は、爽やかな朝日とともに差し込んできた鐘の音で終わりを告げた。
休憩時間、拓也は、無言でそそくさと消えた。トイレを我慢してたのかな? 首をかしげ、香奈恵はパンフレットを改めて読み直した。
後半の「シェーラザード」が、本日のメーンの曲だ。リムスキー・コルサコフの音楽は、極彩色の絵巻が目の前に広がるような楽しい曲だという。様々な楽器のソロが次々に出てきて、見せ場が多いそうだ。「若手団員のフレッシュな音を、お楽しみください」とある。
希美のソロが楽しみだわ。香奈恵はパンフレットを握りしめた。
しかし、後半の舞台に、希美の姿はなかった。オーボエの配置が前半と違うのかと、舞台を隅から隅まで見渡したが、やはり見つからない。オーボエは、先ほどの男性と、もう1人の若い男性の2人だけのようだった。拓也も、客席に戻ってこない。
ブザーが鳴る。舞台が明るくなり、客席の照明が落ちる。シェーラザードの物語が、音で始まる。
威圧するような金管楽器の重々しい響きにつづき、美しい姫君の哀願が甘いバイオリンのソロで浮かび上がる。音の重なりが一気に広がって、舞台の上に青く澄んだ海が広がった。ティンパニの奥に、湘ガ浜で見た水平線が広がっているように感じる。まさに物語絵巻を耳で「見て」いるようだ。
でも、希美と拓也がいないのが気になって、香奈恵は集中できなかった。
アンコールが終わって、客席が空になっても、拓也は戻ってこなかった。電話をかけても電源が切られたままだ。
ため息をついて、香奈恵は立ち上がった。客席を出て、人が少なくなったホールの入り口へゆっくり歩く。
と、背後で聴きなれた声がした。振り向くと、拓也と希美が脇の通路から出てくる。
どこ行ってたんだよ、もう。2人に急いで歩み寄る。
希美が香奈恵に気づいた。香奈恵は明るく声をかけた。「おめでとう! 希美、よかったよ~。スターターだったんだね、すごい」
希美は下を向いた。拓也が慌てたように、香奈恵に右手の手のひらを向ける。何か、制されたような感じだが、香奈恵はその意味がわからず言葉を継いだ。
「今日は、希美の夢がかなった日だね! お祝いしなきゃ……」
「うるさい」
その言葉が、希美の口から出たものだと気づくまでに、数秒かかった。
下を向いた希美の唇がふるえている。
「……どしたん?」
下からのぞき込もうとしたとき、希美がまっすぐ顔を上げ、香奈恵をにらみつけた。
「うるさいよ! 夢がかなった? あんた、何、聴いてたのよ! なにもわからないくせに!」
「希美っ」
拓也が希美の前に立ちはだかった。
その一瞬、香奈恵はあり得ないものをみた。
希美の大きな両目から、澄んだ液体が筋を引いてあふれ出ている。
なんだこれは。希美、泣いてるの? うそ、あり得ない。そんな光景、長い付き合いで見た記憶なんかない。いつも余裕で、勝ち気で、まっすぐ前を向いて、女王のようにまぶしい希美が、こんな悔しそうな、くしゃくしゃな顔で、泣くなんて。
拓也の大きな体の向こうから、希美の高い声が空気を切り裂いた。
「夢だって? 夢なんか……どんだけ情けないか、香奈恵には、わかんないんだよ! あんた、何かを死ぬほど頑張ったことないでしょ? 命懸けても絶対にやりたいことなんか、ないんでしょ? あたしが、今日のためにどんだけ頑張ったか……ピアノ諦めてオーボエにどんだけ打ち込んできたか……なのに……あんたにはわかんないよ! なんでもいいからハッピーエンドが夢だなんて、お気楽で半端な甘ちゃんのあんたには、永遠にわかんないわよ!」
「希美、やめなさい。いい子だから……」
拓也が希美の目をふさぐように、細い体を抱きしめる。
目の前でそんな光景を見せつけられても、香奈恵の心に一筋の嫉妬すらわいてこない。
それより、心配で。
「希美……どしたの?」
自分の声が高くなるのがわかる。
拓也が器用に首だけねじって香奈恵を見た。こんなに困った顔の拓也も、見たことがない。
「ごめん。香奈恵ちゃん、今日は帰ってくれる?」
ゆがんだ顔で悲しそうに笑って言われたら、そうするしかない。香奈恵はゆっくり体の向きを変えた。
まばらになった人々の視線は、香奈恵たちに集中していた。そりゃ、気になるわ。何の騒ぎが起きたのか。あたしにも、わからない。
あたしには、希美の今の気持ちがわからない。こんなこと、初めてだ。20年以上もの付き合いなのに、初めてだ。
どうやって家にたどりついたのか、記憶は、香奈恵の頭からすっぽりぬけ落ちていた。
翌日の月曜日、バイトは上の空で、ミスをしないように気をつけるので精一杯だった。希美に打ったLINEは未読のままだ。
火曜日にも、希美からの返信はなかった。

水曜日は、バイトが終わってから誠一とデート……いや、誠一の叔父様とお会いする約束だ。希美が心配なのに、気分が高まるのが後ろめたい。足元はもちろん誠一のローファーだ。早起きして念入りに磨きあげる。
待ち合わせたのは、都心のシティホテルのカフェラウンジだ。ロビーの豪華なシャンデリアにおののく。隅の方にラウンジの入り口があった。全面ガラス張りの窓際のローテーブルを囲むソファに誠一の白髪を発見した。隣に、額が広い黒髪の男性が座っている。
恐る恐る近づくと、男性が先に香奈恵に気づいた。何事かささやかれた誠一がこちらを振り向き、笑って左手を上げる。
香奈恵は就活でたたき込んだマナー通りに四五度のお辞儀をした。
「初めまして。村瀬香奈恵と申します。誠一さんには、いつもお世話になっております」
男性は立ち上がって軽く頭を下げた。太い眉に二重瞼。誠一には全く似ていない。真下の工房で見た慎太の写真と通じる面差しだ。
「村瀬香奈恵ちゃん? 初めまして。岡野治彦です」
口調が、ゆったり心地よい。香奈恵はほっと背中をゆるめて、空いたソファに腰を下ろした。体が深く沈み、上半身がよろめいて焦る。
「お疲れ。好きなもん食えよ。おじさんのおごりだってさ」
調子よく誠一が言うと、治彦は苦笑いした。
「まったくコイツは……いや、遠慮しないで何でも食べてね。ここはパンケーキが名物だが、食事がよければサンドイッチもカレーもいけるよ」
香奈恵の胃が高らかに鳴った。誠一が爆笑し、香奈恵の顔が赤らむ。
「今さら『紅茶だけでいいです~』とか言ったら笑うぞ」
「もう笑ってるじゃん」
ぼそっと口答えして、香奈恵はありがたくチョコバナナパンケーキと紅茶をいただくことにした。
「話というのは、佳乃さんのこと?」
治彦が笑みを絶やさず、ずばりと本題に入る。香奈恵は誠一をちらっと見て、うなずいた。言葉を探して何度か口を開く。誠一が首を振って、身を乗り出した。
「母さん、ビストロカフェ・オカノだった建物で、そのままカフェをやってるんだな。しかも『オカノ』って名前で。もしかして、あいつら復縁して再婚してた? だったらオレ、覚正誠一じゃなくて岡野誠一かな?」
治彦はコーヒーをすすった。ブラックコーヒーをたしなむ姿が、大人の男って感じだ。
「いや、再婚していない。おまえは覚正誠一だ。私にはどっちでもいいが」
「じゃ、母さんには、あの店の権利はないよな」
「私が、佳乃さんに貸しているんだ。店の名前は彼女がつけた」
「なんで? あんなやつ、田舎に帰せばいいじゃん。もう、おじさんと関係ないんだから」
「関係ないことないさ。兄の元妻で、君のお母さんだ。言葉遣いに気をつけなさい。だから、誠一には知らせなかったんだ」
誠一はむっつりそっぽを向いた。治彦が苦笑して香奈恵に話しかける。
「誠一はずっと、兄夫婦のことは全く耳に入れたくないという感じだったんだ」
話しぶりが温かく包み込むようだ。
「なんで母さんに店を貸したの?」と、誠一。
「一言で言えば、世話になった恩返しだな」と、治彦は答えた。「兄さんが動けなくなって、看病してくれたのは佳乃さんだ。佳乃さんが看てくれたから、私も妻も、兄の世話をしなくてすんだ。なのに相続権がないからって何も残さないのは、人としてどうかと思ってね。佳乃さんが店をやりたいと言ったとき、すぐ賛成した」
「あそこで母さんが店をやったって、客なんか来ねえだろ。息子殺しの噂の主なんだから」
香奈恵はびくっとした。「息子殺しの噂の主」……誠一の口から聞くと、心に刺さる。
治彦は、その刃をあっさり受け流した。
「近所の客が来なくても大丈夫なんだ。ビストロカフェ・オカノは近所の常連客が主だったが、あそこは観光客やサーファーがひっきりなしに来るから。全国の作家がギャラリーとして使っていて、生活には困っていないみたいだよ」
「オヤジの生命保険金で食ってるんだろ」と、誠一はまた、毒を塗った刃を吐き出す。
「そりゃ佳乃さんの正当な権利だ。兄は離婚しても最後まで、保険金の受取人を変えなかった。感謝していたんだろう」
生命保険金! 香奈恵は、全身がけいれんするのを感じた。
家族が死ぬと、保険金が入るんだ。佳乃は、心ない噂に耐えるけなげな母親だと思っていた。だけど……
「佳乃さんのまわりで、三人が死んだ」
真下が重く語った事実を思い出す。最初の夫と、慎太と、2番目の夫である慎太の父。最初の夫が死んだときも、生命保険金を受け取ったのだろうか。慎太のときはどうか。
佳乃のはかなげな白いうなじ。たおやかな細い体に隠された心は、どんな色なのだろうか?
運ばれてきたパンケーキを無意識に一切れ口に運び……香奈恵の思考は一瞬で飛んだ。
「おいしい! 何これヤバすぎ!」
声がラウンジに響きわたった。
誠一と治彦が、そろって爆笑した。血がつながっていないのに、笑い方はそっくりだ。
「タバコ吸ってくるわ」。誠一が身軽に席を立った。
「誠一さん、タバコ吸う人だったんだ」。香奈恵は驚いた。
「最近、ちょっとね。喫煙席はどこだろ」と、店員を捜す。
ラウンジは全面禁煙で、誠一はロビーの反対側の喫煙ルームに歩いていった。
残された香奈恵は戸惑った。無言で誠一を待つのもマナー違反だよなあ。呼び出したのは香奈恵なのだ。治彦はブラックコーヒーをすすっている。しわが刻まれた頬が渋い。
「あのう」
意を決して声をかける。
「不躾だと思うんですけど……誠一さんと、すごく仲がいいんですね」
治彦は口角をきゅっと上げた。「そうだね。うちは子供がいないんで、誠一が息子みたいなものだ。手が掛かるヤツだけどね」
「あの、ほんとに失礼で恐縮なんですが……誠一さん、お父様、つまりええと、お兄様と仲がよくなかったみたいですよね? 気にならないんですか?」
「思い切ったことを聞くね」。治彦はコーヒーカップをかちゃりと置いて、目を見開いた。
「すみません」と、香奈恵は恐縮して下を向く。
「いいんだよ。そういう勇気は悪いことじゃない。それに、私は、あいつの気持ちがわかるんだよね。兄に反発する気持ちが、ね」
「え?」
「昔の話だが、うちの親は、いわゆる長男教でねぇ。新潟の古い農家でずっと長子相続で来たから無理はないが。兄と私はずいぶん待遇に差をつけられて育ったんだよ。食事はまず兄から配膳され、一番おいしい部分や珍しい食べ物は全部、兄のもの。学校も、私の方が成績がよかったが、兄が浪人して東京の私立大に進学したので、私の学費が足りなくてね。私は地元の公立大に、奨学金を借りて進学した。奨学金を返すのに何年もかかったよ。俺様の兄にお仕えした経験が、誠一と通じるんだろうな。結局、兄は実家を継がず、大学を出たはいいが職を転々として、最後はシェフになっちまったから、親としちゃ複雑だったようだ。私にもグチグチ言ってきたが、こっちは、知るかって話でね」
「でも、誠一さんだって、まあお兄さんですよね?」
香奈恵が言うと、治彦は意外そうな顔をした。「誠一がお兄さん? ああ、君、誠一が医者になるのを諦めた話を聞いてないのか」
「聞きました。それって慎太くんが亡くなって、変な噂が流れてご両親が離婚したのがショックで、誠一さんが家出して高校に行かなくなったからじゃ……」
「ちょっと違うね」。治彦は、さらっと言った。「あいつが医者を諦めたのは、兄が医学部受験を許さなかったからだ」
「高校は県でトップの進学校で理系コースだったのに、許してくれなかったんですか?」
香奈恵は首をひねった。それだけ優秀な息子なら、現役で医学部合格だって十分期待できるだろう。喜ぶ親はいても反対なんて想像もつかない。
「慎太がパイロットになりたがったからなんだ」。治彦の声には笑いが含まれていた。「パイロットは特殊な仕事で、慎太が目指すなら、いろいろお金がかかりそうだろう? 兄の店の売り上げでは、息子2人をパイロットと医者の道に進ませることはできない。だから、誠一に医者を諦めろと言ったんだ」
「ええっ」。香奈恵はのけぞった。「待ってください。慎太くんは幼稚園児ですよね? 幼稚園児の『パイロットになりたい』と、きちんと勉強して大学受験を見据えて進学校の理系コースに進んだ10代半ばの人生設計と、並べちゃいます?」
「普通は、そう思うよね。幼稚園の頃は、私だって『宇宙飛行士になりたい』と言っていたが、もちろん本気で受け取る大人はいなかった。実際、私も将来を真剣に考える年齢になったら『宇宙飛行士』なんてもう考えなかった。子供の夢なんてそんなもんだ。実現は関係なくて、何でも言うだけ言えてしまう。大人は『いいねえ』と、聞き流す。普通はね」
「誠一さんと慎太くんのお父様は、違ったんですか」
「うん。違った」。治彦は大きくうなずいた。「結局、兄にとって、息子は慎太だけだったんじゃないかと思うね」
「え……」
「慎太という名前を、よく考えてごらんよ。もう誠一がいるのに、自分の血を受け継いだ子供が産まれたからって、わざわざ『太』という漢字を使うかね? しかも兄の名前である慎治の一文字をとった『慎』との組み合わせだよ。誠一は頭がいい子だ。それがどんな意味を持つのか、わかっただろう」
「でも、誠一さんは、慎太くんをかわいがっていたでしょう?」 香奈恵はすがるように反論した。
「うん。誠一は本当にできた子で、自分の立場を理解した上で、心から慎太をかわいがっていた。だから弟の教育費を潤沢に用意できるよう、高校は学費が安い県立しか受験しなかったし、国立大の医学部にストレートで合格する計画を立てていた。十分可能だったろう」
「それなら、やめさせなくても」
「同感だね。だが、誠一が高校に合格して間もなく、兄は突然、誠一に言ったんだ。『慎太がパイロットになるのだから、おまえを6年も大学に行かせる金はない。医学部は許さん』とね」
香奈恵は言葉を失った。
「最初から夢を目指す権利を放棄するなんて、事情があって諦めなければならないヤツや、死んだヤツに失礼だろ」
真下の工房で、誠一はそう言った。それは、死んだ慎太のことだと思っていた。
でも、違ったんだ。誠一自身のことだった。本気で目指していた夢を、突然、諦めるよう強要されたのは、誠一だったのだ。
「命懸けても絶対にやりたいっていうこと」
一昨日、希美が泣いて叫んだ言葉。誠一には医者だった。希美のオーボエと同じように、誠一は医者を目指して着々と歩みを進めた。高校進学で大きな一歩を踏み出したそのときに、父親の手で、その夢を折られたのか。
「だから私は、誠一の気持ちがわかる。事故のときに慎太が家を抜け出すのに気づかなかった佳乃さんにも怒りを感じたようで、母親ともこじれていたしね。ただでさえ難しい年頃に、いろいろあったねえ」
治彦は、長いため息をついた。
「もう一つ、いいですか? 佳乃さん、離婚したのに、どうして岡野さんのところへ戻って来たんでしょう?」
治彦は、つるりと額を撫でた。「ありゃ、兄の自分勝手だよ。肝臓を悪くして、体は動かなくなるわ、不安になるわで、追いだした妻にすがろうとした。どこまでも俺様だ。佳乃さんは快く、再婚を条件にせず戻ってきてくれた。本当に感謝しているよ」
香奈恵はパンケーキの残りを機械のように口に運んだ。どんなときでもおいしいものはおいしいのが救いだった。
「お待たせ。おい、なんだか通夜みたいだな。香奈恵、おまえ、オレがいないと知らない人と話もできな~い! ってキャラじゃねぇだろ。聞いてくれよ、叔父さん。こいつ、初対面のオレに向かってパンプスを蹴り出してきたんだぜ」
軽口とともに戻ってきた誠一は、明るい。
「蹴り出したんじゃないもん。すっぽ抜けちゃっただけだもん」
香奈恵はほっとして、誠一をたたく真似をした。
2人を見る治彦が、父親みたいな笑顔になった。
(続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
