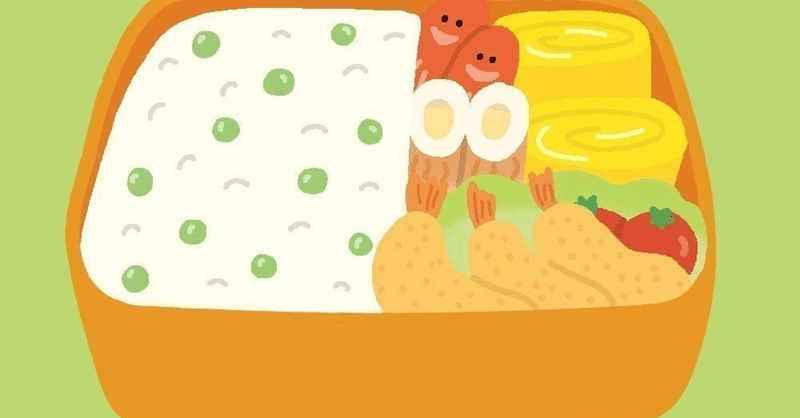
父が作った不倫弁当
ここは平成の片田舎。隣の家の鶏がコケッコと鳴きわめく前から父は目覚める。毎朝、アタシと母のためにお弁当を作ってくれるのだ。
元々板前を目指していたことがあって料理が得意だということらしいが、自分も働きに出るというのに毎朝お弁当を作るのは素直に偉いな、と思う。
「今日はお前らの好きなナス炒め、入れておいたぞ」
「え、やった」
父が作るお弁当の具材は冷めてもおいしく、むしろ冷めてより味が増すように仕上げられていた。
クラスメイトがよくつまみ食いしにきたし、先生にまで褒められたことがあったほどだ。
でも、これを食べていいのだろうかと幼いアタシは悩んでいた。
父が嫌いとかそういうことじゃない。
父はホントの父ではなかった。
アタシが最初に出会った頃は母と不倫を続ける男性で、わざわざアタシたちのためにお弁当を作るためだけに、早朝ウチにやってきていた。
なんでこんなことをしているのか? 向こうの奥さんはどう思っているのか? そんなことは聞けなかったけれど、いつまにか胃袋を掴まれた母は再婚を決めた。
父も向こうの奥さんに不倫を認め、晴れて独身になってアタシたちの家に住むようになった。
壮絶だったと母は平然と言うが、罪悪感はないのかと他人ごとのように思っていた。
高校生になって、学食でお弁当を広げているときのことだ。
今日もお弁当は絶好調においしい。
ふと、アタシのお弁当をまじまじと見てくる人がいた。髪の長い女性で美術の非常勤講師の方だった。まだ1年も経っていないはず。
「……おいしそうですね」
羨ましいとは別の感情がこもった冷たい声が耳に残り、ピンときた。
父の元嫁だ。この人がそうだ。確か、アート関係の仕事をしていると母が言っていた。
「え、あ。ありがとうございます」
驚いたことを隠しながら小声で返し、なんとなく程度の会釈をした。女性は何も言わずに去っていった。
お弁当にいつも入っている塩味のとり天。母もアタシも別に好きなおかずではなかったけれど毎日入っている。
もしかしたら。もしかすると、あの方の好物だったのかもしれない……。
アタシはお弁当を持ったまま走って、髪の長い女性を追い越して振り返った。長い髪が揺らぐ。
「…………」
何も言えずに立ち尽くし、お弁当を見せつけているアタシ。
不思議そうな、困ったような顔をしている女性。
最悪だ。何をしているんだ、あたしは。
「……あの。――ごめんなさい」
アタシがそう言うと、女性は微笑むようにつぶやいた。
「残さないであげてくださいね」
アタシはその意味がよく分からず、ただただ申し訳ないことをしたとだけ思った。
今。
アタシは大学生になった。珍しいけれど大学に入ってもお弁当を持参している。
父の不倫弁当は、今日も最高においしい――。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

