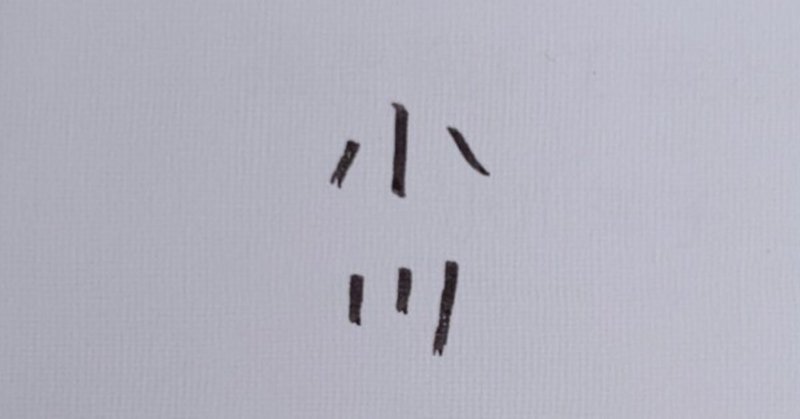
私と洋子さん
小川洋子という作家が好きなので、noteに記しておく。
イタい公開ファンレターなので読み飛ばして良いパート
無礼で烏滸がましいと承知している。
私なんかが彼女の名前をお借りして良いはずがない。
それでも大好きで、尊敬していて、愛していて、アナタに出会っていなければ今の私は存在しないので、SNSのハンドルネームを「小川」にしてしまっている。
いつの日か洋子さんに懺悔せなければならない。私のような人間が名乗って良い名前ではないのだから。
私は小説家・小川洋子のことを「小川洋子先生」とは呼ばない。「洋子さん」と呼んでいる。
小説家としても敬愛しているけれど、トークショーやサイン会で、「洋子さんそのもの」に触れる機会があり、作品だけでなく、彼女のことが大好きになってしまったのだ。
プレミアムシートを買っているほど阪神タイガースが好きなところ。
芥川賞を受賞するまでの執筆活動について、あけすけなくカラッと語るところ(割と毒舌だった。そんなところも好きだ)。
サイン会で初めて対面した時、咽び泣き、嗚咽し、しゃくりあげ、会話どころではなかった私を、穏やかに、優しく受け止めてくれたところ。
すべてが大好きだ。
世界で一番好きな小説家が、サイン会で私の名前をフルネームで書いてくれる。その場で泣かないなんて、私には無理だ。
それにしても泣きすぎていたので、洋子さんの隣にいた出版社の人が助け舟を出してくれた。
サイン会の参加者は、洋子さんに向けてメッセージカードを書き、彼女に渡せる仕組みとなっていた。出版社の人が洋子さんに「素敵なメッセージを書いてくれていますよ」とパスを出してくれた。
せっかく助け舟を出してくれたのに、愚かな私はずっと涙を流しているばかりで、結局お話しすることが叶わなかった。
私の番が終わっても、他のファンの方とにこやかにお話している洋子さんの姿を目に焼き付けたくて、その場から立ち去れないでいた。
書店員さんからしても、あまりに無惨な私が、見るに耐えなかったのだろう。全員のサインが終わったのちに、「泣きの一回」をくれて、もう一度対面することができた。
そこでようやく、一言二言、些細な言葉を、ボソボソと頼りなく発した。
「父が本棚に置いていた『博士の愛した数式』で洋子さんの本を初めて読んで、それからずっと大好きです」みたいなことを言った。
本当に伝えたいことはそんなことではなかったのに、そんなことしか言えなかった。
あの時の書店員さんには感謝している。名刺をいただけたので、その日のうちにお礼のメールも送った。書店員さんに、気持ちが少しでも届いていたら嬉しい。
サイン会での立ち振る舞いは、あまりにも不格好だった。敬愛する人の前で大失態を冒してしまった。
しかし、心の底から愛している小説家の手から、私の名前が紡がれる瞬間を目の当たりにして、感極まるのは仕方のないことだとも思う。
世界から零れ落ちてしまいそうな私を、美しい文章で掬い上げてくれる人が、よりにもよって私の名前を、手書きで、書いてくれたのだ。泣くしかない。泣くしかないのだ。
結婚のため改姓してしまい、一番残念に思うことは、洋子さんからのサインの時に書いてもらったフルネームと、今の私のフルネームが異なっていることだ。洋子さんに紡いでもらった名前のままでいたかった。
主人には、「私が死んだら、棺桶に小川洋子さんのサイン本を入れてほしい」と頼んである。私の名前を添えられたサイン本は、2冊もある。
なんと恵まれた人生だろう。もちろん2冊とも連れて、私はあの世に行くつもりでいる。
私は天国に行けるのだろうか。愚か者なので、地獄に送られる可能性が高い。
そもそも死後の世界があるのかさえ、死んでみないと分からないのだが、私の死体は洋子さんのサイン本と一緒に燃やしてもらいたい。
彼女の本と一緒に灰になることができたら、それだけで「幸せな人生だった」と思えてしまう。
それくらいには、好きなのだ。
私は涙脆い。
洋子さんは私より年上だ。「洋子さんが私を置いて死んでしまったら、その先どうやって生きていけば良いのだろう」と途方に暮れ、泣いた夜が何度もある。
洋子さんのお住まいは芦屋にあるらしい(当時のトークショーより)。
私は芦屋駅を通過する度、手を合わせて祈る。「私の寿命を、どうか小川洋子さんに分けてください」と願う。
残酷で押し付けがましい願いだが、洋子さんには永遠に、物語を紡いでいてほしいと思ってしまう。洋子さんの物語によって救われる人はたくさんいるから、永遠に物語を紡ぎ続けてもらいたいのだ。
なんて傲慢なファンだろうか。あまりに残酷と言わざるを得ない。「人間」が「人間」に対して祈る内容ではない。
こんなグロテスクな祈りを捧げる私は、きっと地獄行きだ。
だが行き着く先は地獄で良いのだ。洋子さんの本を連れて行けさえすれば、地獄は天国と同じ形をしているはずだから。
ここまで、随分と気持ちの悪い公開ファンレターのようなものを書き連ねておきながら、こんなことを表明するのはおかしな話だが、私は別に、このnoteを読んでくれている稀有な人々全員に、洋子さんの作品に触れてもらいたい訳ではない。
「私にとっての洋子さんのような小説家……『人生のお守りになるような小説家』が、アナタにもいますように」とは願うが、アナタに洋子さんを読んでもらいたいとは思わない。
「私」を理解したい物好きがいたら読むべきではあるが、そんな人は存在しないし、主人でさえ洋子さんの物語を読んだことはない。
私を深く知る人が洋子さんの物語を読んだら、「それにしても染まりすぎだろ!」と爆笑するかもしれない。「私」の内面を知っていて、さらにその上で爆笑したい人は、洋子さんの本を読んで損はないかもしれない。
私の文章や、根底に流れる考え方は、笑えくるらいに「洋子さんのまがいもの」だという自覚がある。私の文章力や表現力や着眼点なんかは、勿論彼女の足元になんて到底及ばないのだが、自分で自分の文章を読み返す際に、「いくらなんでも……」と思ってしまうくらいには、彼女の影響を感じてしまう。
それでも洋子さんを、小川洋子の小説を読んでみたいと思う人がいるならば……私は下記の3冊を推薦したい。
洋子さんの文体は癖があるし、グロテスクだし(血とか暴力描写とかではない類のグロテスクなので、更にタチが悪い)、いわゆる毒親表現(主に母から娘)も多い。苦手な人はトコトン苦手な作家だと感じる。決して万人受けはしない。
そんな中でも万人受けしそうな3冊をピックアップ。この3冊を読んでもらって、それで大丈夫そうなら、もっともっと洋子さんの文学の海に飛び込んでもらいたい。
「死のにおい」がする作家だ。私はずっと彼女の物語を追いかけていて、すっかり慣れきっているので、何とも思わない。それどころか、そのにおいに救われている。しかし、『今は「死のにおい」を嗅ぎたくない・嗅いだら嫌な予感がする』という人は、どうか避けてほしい。私が愛しているのは、そういう一面を持つ作家だ。
①『博士の愛した数式』
第一回本屋大賞受賞作。後世まで語り継がれるべき名著。
実写映画?はて、なんのことでしょう?(※すべてが台無しなので、本当に観ない方が良いです。)
『博士〜』は洋子さんの小説の「入門編」として、「入り口」として相応しい。なんて豪華で、それでいて気取った態度をしていない、凛とした、美しい門なのだろう。
あまりに面白すぎて、中学生の朝読の時間に5周連続で読んだ。
それまでに読んできたヤングアダルト小説(『バッテリー』や『DIVE!!』など)も面白かったが、きめ細やかで繊細な文章、物語全体に流れる優しさに、「こんな世界があるんだ!」とワクワクさせられたし、跪くしかなかった。
クラスメイトからは「またその本読んでるの?」と驚かれたが、何回も何回も読み返したくなる魅力が、この物語にはある。
この一冊が私と洋子さんの出会いである。そういう人は多いのではないだろうか。
この物語が無理なら、おそらく洋子さんの紡ぐ世界観はすべて無理なので、「合わない作家なんだな」と諦めるべきだ。「合わない作家」の文章を読むことほど苦痛なことはない。
私が書くと陳腐な言葉になってしまうので、あらすじはAmazon等で確認してほしい。
②『はじめての文学/小川洋子』
文藝春秋から刊行されている「はじめての文学」シリーズ全12巻のうちの一冊。他には村上春樹、村上龍、重松清、よしもとばなな、川上弘美などが名を連ねる。
『はじめての文学』シリーズは、ヤングアダルト層に向けたものであり、紙面レイアウトが特徴的だ。
行間や余白がたっぷりと取られていたり、活字サイズが大きかったり、振り仮名が多用されていたりするので、読書体験の浅い人にもオススメだ。
あくまで若者に向けた単行本である。そして掲載される短編の選定を、筆者自らが行っている点もポイントだ。
洋子さんが選んだのは、『冷めない紅茶』、『薬指の標本』、『ギブスを売る人』、『キリコさんの失敗』、『バックストローク』。
なんて痺れるラインナップ!
中学生の頃にこの本を読んだ時は、『薬指の標本』に衝撃を受けた。弟子丸氏に恋をした。
『薬指の標本』で、私から洋子さんへの愛は決定的なものになった。
今でも読み返す。
洋子さんがこの5作品を選んだ意味について想いを馳せる。
『冷めない紅茶』からスタートしているところがニクいし、『キリコさんの失敗』が選ばれているという事実だけで涙が出そうになる。
『薬指の標本』に関しては、「若者の人生をめちゃくちゃにする気か!」と叱りたくなるが、実際にめちゃくちゃにされているので文句は言えない。
割と初期の作品が多いし、「はじめての」というだけあって、文体や物語の展開的にクセやアク、エグみのあるものは少ない(気がする)。
『薬指の標本』はちょっとアレだと思うけれど、まあ、中学生くらいで一回、弟子丸氏に恋をしておくのも良い経験だと思う。
『薬指の標本』はフランスで実写映画化されている。とても気に入っているので、フランス版の弟子丸氏に会いたい人がいたら是非。サブスクでは配信していなさそう。TSUTAYA DISCASとかでなら観られるのかな。私はTSUTAYA DISCASで観た……というかこのために入会した。
問題点が一つだけある。
文庫版がない上に、今となっては流通していない。Amazonにあるのも中古品ばかりだ。
そもそも単行本なので、若者が手を伸ばしづらい価格設定なことも難点だ。シリーズまとめて、まるっと文庫本化してくれ!
おそらく図書館のヤングアダルトコーナーに並んでいると思うので、そこで借りることをオススメしたい。
『はじめての文学』シリーズは、各作者の「若者へのまなざし」が垣間見えるので、どの著者のものも読んでおいて損はない。
企画そのものが素晴らしいし、この中に洋子さんが選ばれたことを、ファンとしては誇りに思う。
③偶然の祝福
②で『バックストローク』が出てきた以上、次に薦めるのは『偶然の祝福』と決まっている。『盗作』が載っているからだ。『バックストローク』と『盗作』は、両方を読んで初めて成立する作品なので、どちらかを読んだからには、もう片方も読まなくてはならない。
『偶然の祝福』は連作短編集で、②の内容とダブりもある。
しかし『はじめての文学』で、「独立した形」で読むのと、『偶然の祝福』で「連作という形」として読むのとでは、受け取る印象も大きく異なるだろう。
なので是非、『偶然の祝福』としてパッケージされている中にある『キリコさんの失敗』にも触れてもらいたいのだ。
私はこの物語がとても好きで、何度も勇気付けられてきた。BOOKOFFの100円の棚に並んでいると「この本を売るなんて!」と怒り、「この本に100円の値札を貼るなんて!」と怒ってしまう。「それなら私が大切にしてあげるよ!」と、プンプンしながら、何冊も何冊も連れて帰ってきてしまっている。
後日、何冊も同じ本が本棚に並んでいる様子を冷静になって見返すと、「うわあ」と思わなくもないが、BOOKOFFに並んでいるよりは、私の家の本棚に並んでいる方が、この本たちにとっても、まだ少しは幸せなんじゃないかと自惚れている。
一番好きな物語は冒頭の『失踪者たちの王国』。
「何かを表現して、誰かに見てもらう」という機会が何度があった。
大学生の時の地獄の作文トレーニング。好きな人(友人だったり、芸能人だったり、美術館の館長だったり)へのお手紙。このnote。
書くときは楽しんで書いているのだが、「出す」となると、途端に怖くなる。自分だけのものではなくなるからだ。
「やっぱり出すのを辞めようかな」と怯えているときに、この物語に何度背中を押してもらえたことか。
背中を押してもらえたことで、私の世界は広がった。
そんな感謝も含めて、私は『失踪者たちの王国』を愛している。
まあ全部好きなんですけどね
所謂「入門編」として3冊を挙げてみたが、まだまだ紹介したい物語はたくさんあるし、上記の3冊がハマらなくても、私とアナタの感性は違うので、別の物語に感銘を受けるかもしれない。
『妊娠カレンダー』、『ミーナの行進』、『夜明けの縁をさ迷う人々』、『人質の朗読会』……。
若手時代、中堅時代、ベテラン(芥川賞の選考をしている方なので「ベテラン」と称して問題はないはずだ)時代、洋子さんが見せる色は少しずつ異なって、そしてぜんぶが愛おしい。
どれから読んでも、きっと、刺さる人には刺さる。
しかし「最初」を「ホテル・アイリス」にするのは、避けたほうが良い気がする。
「そういう作家」だと知った上で読むには面白いけれど、なんの前知識もなく、いきなり『ホテル・アイリス』を読んだらトラウマになる可能性がある。
ふと調べてみたら、『ホテル・アイリス』は設定をガラッと変えて、映画化されていた。
私にとって大切な部分がガラッと変わっていたので、私は観ないけれど、映像化されるくらい魅力的な物語ということだ。
この映画から入って、「じゃあ原作はどうなんだ?」と怖いもの見たさで原作に触れるというルートも面白いのかもしれない。原作に触れてしまっている私には、絶対に辿れないルートだ。ある意味では羨ましい。
ちなみに私の「揺るぎない一等賞」は『猫を抱いて象と泳ぐ』だ。
当時、あんまり洋子さんの新刊の特集を組んでくれていなかった印象のある『ダ・ヴィンチ』でさえも、『猫を抱いて象と泳ぐ』は「これは凄い本だ」と、わざわざページを割いてくれた。あの号の『ダ・ヴィンチ』はまだ手元に残っている。
洋子さんの物語は基本的に一人称視点で進んでいくが、『猫を抱いて象と泳ぐ』は伝記物……第三者の視点で進んでいく。少し毛色の違う物語だ。
優しくて、哀しい「彼」の人生を綴った本。私は「彼」が大好きだ。
図書館で借り、単行本で買い、文庫本でも買った。
今の文庫本の表紙は、こんなことになっているのか!
「この小説に出会って出版社に入ると決めました」。うん、分かるよ、分かる。そうだよね。
このカバーを書いたのは誰だろう? アナタと友だちになれる気がするから、このバージョンの文庫本も買おうかな。
番外・「今」小川洋子を読むということ
凄惨な事件があった。宗教に絡む事件で、人間が死んでしまった。今でもこの問題で苦しんでいる人がいる。
私は宗教二世の話題が出る度、「小川洋子の小説を読んでみては?」という結論が出ていないことを不思議に思っている。
テレビなどではもちろん、私が構築したSNSのタイムライン上でも、そのような意見は見つけられなかった。私が見つけられなかっただけで、そういう意見はきっとある筈だ。
洋子さんの物語には「毒親」が出てくると書いた。その毒親は「宗教にのめり込む母親」であることが多い。小川洋子をWikipedia等で調べれば、彼女がどういう家庭に生まれたのかも、なんとなく察することができる。
洋子さんの物語において、「主人公」は「母親」を切り離している。「血縁関係にあるだけで、別の人間である」と割り切っている。
娘である主人公から、母親へアプローチはしない。母親への目線は常に冷めている。「独立した人間」だと線を引いている。
その関係性が正しいのかは分からないが、その描写で何かヒントを得られる人がいてもおかしくない。
私は宗教二世ではない。彼ら、彼女らの苦しみは分からない。
しかし私が幼少期・青年期に自我を形成していく中で、「自分と両親は、あくまでも他人である」と気付かせてくれたのは洋子さんであり、早い段階でその気付きを得られたからこそ、人生が楽になった。
盲目ファンの戯言だと言われればそれまでだが、「今」、洋子さんの著書に触れることは、何かの「キッカケ」になるのではと思ってしまう。
それくらい好きってことで
私の人生と洋子さんは切り離せない。
「好き」とか「愛している」とか、そんな言葉で片付けられない気持ちを抱えながら、ページを捲っている。
別のnote(例えばヨーロッパ企画の作品を薦める記事)で「観てみたけど、つまらなかったぞ!時間を返せ!」と苦情を入れられたら「申し訳ないです」と謝るが、洋子さんに関して「つまらなかったぞ!」と感じたら、そっと胸にしまっておいてもらいたい。
「洋子さんがつまらない作家である」と「私」に伝えることは、私の内面のほとんどを否定しているということになってしまう。
つまらなかったら、「つまらなかったな〜」で処理してほしい。
こんなふうに面倒な人間になってしまったのも、洋子さんの影響は否めない。
しかし、それくらい、大好きなのだ。
私がサイン会のメッセージカードに添えた言葉。
それは「洋子さんの言葉で、私を標本にしてもらいたいくらい好きです」だった。
洋子さんの出版物を知らない人からしたら、意味が分からないだろうし、伝わらない言葉だろう。
しかし、洋子さんの隣の出版社の方は、私の言葉を「素敵なメッセージ」と捉えてくれた。
「小川洋子」にとって「標本」とは、特別な存在なのだ。
残念ながら、洋子さんは私を標本にしてくれない。そんなことをする暇があったら、別の物を標本にしたほうが彼女のためであり、読者のためである。
なので、私は私の力で、私を「標本」にする。
私のnoteには、そういう側面もあるのだ。
キショいでしょ〜(←これがヒカリゴケの漫才のツカミからの引用であると見抜けた人、握手してください)。
捻れた愛だ。捻れてるけど、愛だし、洋子さんのお陰で乗り越えられた夜が何度もあるから、どうか見過ごしてほしい。
私にとっての洋子さんのような存在が、アナタにもいることを願っています。
そうやって他者とともに生きていくことは、誰かに支えてもらって生きていくことは、決して悪いことではないと思うから。
「依存」とかではなく、「道標」としての「他者」は、存在しても良いと思うから。
いただいたサポート代はすべて「楽しいコンテンツ」に還元させていただきます!
