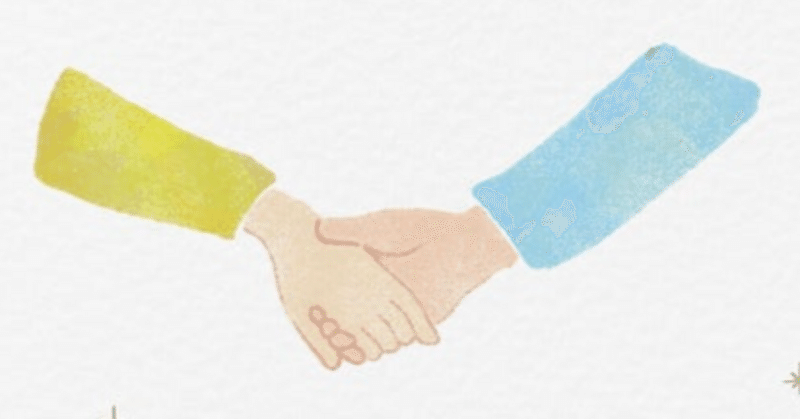
東日本大震災のボランティアに行った話
大切なこと
※地震や津波に関する話があります。この記事を読んで嫌な記憶がフラッシュバックしそうな人や、読むことで心が苦しくなりそうな人は、読むことを避けてください。
※あくまでも「私個人の体験」に基づいた話です。この記事が「正解」ではありません。様々な情報や意見に触れて、最終的には「自分の判断」で行動してください。
はじめに
以前『深夜特急』を読んで旅に出たということを記した。
「旅」と称するのは失礼な話だが、私は沢木耕太郎に背中を押してもらい、東日本大震災の被災地へ、ボランティアに行った。
今回はその体験を書こうと思う。
しかし、ボランティア先の方々には個人情報がある。すべてを無許可で書くわけにはいかない。
ある程度、特定出来ないようにボカして書く。
だがそこに嘘はない。
そもそも被災地とはどこか
「東日本大震災の被災地」をどこまでとするかは判断が難しい。
帰宅困難者が溢れた首都圏は被災地ではないのか?
揺れを感じて怖さや不安を感じた人は被災者ではないのか?
ほとんどのテレビが震災についての報道に切り替わり、ACジャパンのCMばかりを浴びせられて苦しんだ人に対して、被災者ではないと言い切れるのか?
非常に難しい問題であるので、そういった議論は有識者の人に丸投げする。
この記事では便宜上、津波による被害を受けた地域を「被災地」とさせてもらう。「あくまで便宜上である」ということを念頭に読み進めてもらいたい。
行くまでに2年かかったし、動機が不純
私が被災地へボランティアに行くまでには、2年の歳月を要した。ボランティアに行きたいと大学の教授に相談したら「遅い」と叱られた。当然だ。
「どうして今なんだ」、「就活の履歴書に書きたいから行くのか」、「お前は『そこら辺にいる大学生』に成り下がるのか」と責められた。
「あの被害を直接見ることが怖く、ずっと二の足を踏んでいたが、ようやく決心がついた」、「津波の被害に遭った地域を見たい。ただ見るだけなのは嫌だ。せっかく行くなら力になりたいから、ボランティアもやりたい」、「テレビ局や新聞社の入社試験を受けたいと言っている人間が、被災地に行ってさえいないのは恥ずかしい。そんな人は、メディアの採用試験を受ける資格すらない。私は資格がほしい」と正直な気持ちを伝えた。
教授は顔色を変えなかったが、すぐに「彼が信頼しているボランティア団体」へ、私を紹介するメールを出してくれた。
今でも振り返る。「めちゃくちゃ不純な、しかしある意味では誠実な動機」だと思っている。
当時、メディアの門を叩こうとしていた私が、被災地に足を運んでいないなんて有り得ないし、恥ずかしい。私はバラエティや情報ワイドを担当したかったが、報道担当になる可能性だって十分あった。
まあ、落ちたのだが。
見る人からしたら、私は被災地を利用しようとしていたとも捉えられかねない。それで良かった。だからこそ私も、被災地に、被災者に利用されたかった。互いに利用し合うことが、せめてもの罪滅ぼしに思えた。
2年後に見たもの、やったこと
夏休みに2週間だけ、被災地に行った。まだ電車が全面的には復旧しておらず、辿り着くにも困難を要した。
私が「被災地」に着いて最初に見たもの、それは「広大な原っぱ」だった。海から駅くらいまでの距離は、全部「広大な原っぱ」。
そこにはかつて家があり、人が住んでいた。「暮らし」があった。
津波によって「暮らし」が流され、当時はまだそこに家を建てる人はおらず、しかし瓦礫の処理は済んでいたため、「広大な原っぱ」だけが残されていた。この「広大な原っぱ」という景色を、私は一生忘れないだろう。
2年も経てば力仕事なんかは残っていない。求められるものは、もっと細やかなサポートだ。
私はその地域でスクールボランティアをした。
教員免許を持つための勉強をしていたので、その役割が適任ではと、チームから割り振られた。
仮設住宅は狭く、仮の住居では学習環境を整えられない児童・生徒はたくさんいた。
夏休みの宿題に家で取り組むことが困難な子どもたちのために、学校が開放されていた。私はそこで彼ら・彼女らの宿題を一緒に取り組んだ。
勉強を教えたり、子どもたちの言葉に寄り添ったりすることが、私のボランティア活動だった。
学習時間中、余震が何度もあった。震度5の地震もあった。「机の下に潜って!」と指示をする。しかし子どもたちは指示に従わない。震度5程度の余震には、馴れてしまっていたのだ。
この感覚のズレに戸惑い、そして胸が傷んだ。彼ら・彼女らにとっての「当たり前」は、私にとっては全然「当たり前」ではなかった。
児童たちには「先生はビビりすぎ」とからかわれたし、2週間ずっと、私は被災地の人から見たら「余震ごときに驚きすぎている人」だったのだろう。
結局、ボランティアの期間中、余震に馴れることはなかった。
ボランティアとしてはスクールボランティアが主だったが、私はもう一つ心掛けていたことがあった。「地元のものを食べること」だ。
大学生の私が毎日たくさんの飲食代を被災地に払うことは難しかった。コンビニのご飯で済ませた日も、もちろんあった。
しかし、その土地の魚や肉や野菜を食べ、お酒を飲むことは、ほんの少しだが、役に立っている行為だと信じて、消費活動をした。
その地域の海産物はどれも新鮮で美味しく、というか食べ物は総じて美味しく、地酒もスイスイ飲めるものばかりだった。
風評被害になんて負けてほしくない。
今でもたまに(たまにしか出来ない自分の財力が悲しいが)その地域の海産物や地酒を取り寄せている。
これが私の行ったボランティアだ。
些細なことだ。私なんて行っても行かなくても、被災地に変わりはなかっただろう。
自己満足だったのかもしれない。
しかし余震を体感し、子どもたちと漫画の話をし、勉強を手伝い、その土地の食べ物をその土地で食したことは、私の財産になっている。
財産にさせてもらっているから、その地域に、細々と募金を続けている。その後、観光にも行った。
支援・援助をしたいというよりは、お世話になったのだから恩返しをしたいという気持ちで、私はその地域のことを特別視している。
もちろん私が足を運べなかった「被災地」にも寄り添いたいので、「東日本大震災」全体にも募金をしている。雀の涙のような金額だけれど、無いよりはマシだと信じている。
ボランティアに行きたい人へ
2024年1月現在、胸を痛めるニュースが流れている。力になりたいと思う人もいるだろう。
すぐに駆け付けることでしか、出来ないこともある。しかし少し日を置いて被災地へ行くことも、無意味ではない。焦らず、自分に出来ることがありそうなタイミングを見計らって、足を運べば良い。経験上、私はそう考えている。
そして単独で行くよりも、母体となるボランティア団体に属した方が、適した役割を振ってもらえたり、寝床を確保してもらえたりと、馴れていない人にとっては安心・安全に活動が行える。
「シッカリしていそうなボランティア団体」を見極めることは難しいかもしれないが、周囲の人の知恵を借りたり、自力で調べたりしてから、ボランティア活動を始めることはとても大切だと考える。
これは個人的な考えだが、「帰る日」をキチンと決め、周囲に宣告しておくことも大切だ。
被災地にはたくさんの苦しみや哀しみがある。
それらを見てしまうと、寄り添おうとしてしまうと、「自分だけが安全な日常の世界へ帰ること」に後ろめたさを感じてしまうことがある。
「帰れなくなった人」を見てきた。「帰らない」という選択も否定はしないし、その覚悟は美しいと思う。
しかし、「一生その地域と寄り添って生きる」ことは並大抵のことではない。自分が元々住んでいた地域の人たちや、家族なんかの理解を得ることは必要不可欠であるし、もともとボランティアとしてその地域に入ってしまっている以上、どうやって生計を立てていくかについても、熟考する必要がある。無料のものが有料になったら、反発が起きるのは当たり前なので、ボランティアをしながら、それとは別の働き口を見つけなければいけない場合もあるだろう。しかしその働き口を外部の人間が手に入れてしまうと、被災地の人々の職を奪うことにも繋がりかねない。
「見てしまった」以上「帰りたくなくなる」のは仕方のないことだ。私にも、帰ることへの罪悪感はあった。
しかし帰ることによって新たな視点が生まれたり、新たな支援が出来たりもする。帰るという行為を責めすぎず、期間をしっかり決めて、後ろ髪を引かれようが、何があろうが、「この日に帰る」と決心してから、被災地に向かうことを、私は薦めたい。
一旦帰って、また行きたいと思えば、そのタイミングで行ったら良いのだ。
ボランティアに行けない人へ
「その土地で力になる」ことがすべてではない。
自分の今いる場所で出来ることは山ほどある。
まずは自分が心身ともに健康に暮らすこと。己の生活の基盤が整っていない状態で、他者に手を伸ばそうとすると、グシャグシャになってしまう。
まずは自分を大切にするべきだ。
震災の報道から目を逸らすことは悪ではないし、自分の趣味にお金を使うことも悪ではない。
募金や義援金なんかは、余力があれば行えば良い。
被災地が復旧したら(「復興」するのは時間を要するので、「復旧」を目安にするのが良いと、私は考える)観光に行くことだって、立派な支援である。
自分を責めず、毎日の生活を大切にして生きていくことが、支援の一番の基礎だと感じている。
そして災害をキッカケに、防災グッズの見直しを定期的に行うことも、とても大切なことだ。
さらにもう一つ。私は一番よく滞在しているXのアカウントで、「災害時」というリストを作ってある。

個人情報なので鍵は必須
リストに入れてあるのは、政府や(自分や親族が所属している)自治体、NHKの防災アカウントなど。このリストを作っておくと、有事のときは「それに関する正しい情報のみ」を手に入れられるのでストレスが減る。「自分だけの災害時リスト」をカスタマイズしておくこともオススメしたい。
持ちつ持たれつ
今回触れたのは、主に地震や津波の被害に遭った地域の話だが、日本は災害大国である。大雨も降るし、豪雪地帯もあるし、台風も来る。
東日本大震災や能登半島地震以外にも、たくさんの被災地が日本には存在する。
私の地元は海が近いので、「いつか」の話を何度も何度も聞かされて育った。訪れた被災地に、地元を重ねたこともある。
私は不順な動機でボランティアに行った。
そんな日は来ないでほしいけれど、私の地元もボランティアの人に助けられることがあるかもしれない。
不順な動機で構わない。偽善だって善だ。
災害が起きてしまえば、どんな地域でもマンパワーが必要な時期は必ずある。動機は何であれ、「行く」ということでしか出来ないことがある。
「行ける」人が行ったら良いし、「行けない」人(私もそうであるように、ほとんどの人は「すぐには行けない人」なのではないだろうか)は自分の住んでいる地域で出来ることを見つければ良い。どちらが偉いとかはない。「気に掛ける」ことが大切だし、ありがたい。
「忘れられてしまうこと」「風化してしまうこと」を被災地の人たちは不安に思うと、身をもって体感したので、毎日いつまでも……というのは難しいが、「折に触れて、色んな地域について想いを馳せること」が大切な気がする。
どこに募金をしたら良いか分からないケースも多々ある。
投じたお金は、本当に全額が被災地に届くのか。正しく使われるのか。不透明なこともある。
もしこの記事を読んで、寄付したい、募金したい、義援金を送りたいと考えた人がいたら、まずはお金を送る先について、丁寧に調べることから始めるべきだ。
「このnoteに投げ銭をしてくれたら、そのお金は全額寄付します」とかはやらない(ので、この記事に関しては投げ銭サポートをしないでください!)。まずnoteに取り分が生まれてしまうし(会社なので当然である)、不特定多数のお金を預かれるほど、私は知識も経験もない。
参考までに、日本赤十字社の寄付のページのリンクを貼っておく。
日本赤十字社は災害だけでなく、コロナ禍の支援から献血まで幅広く行っている団体なので、「特定の地域だけでなく、困っている人をサポートしたい」という人には向いているのではないだろうか。Amazon Payからの寄付も可能だ。
「特定の地域だけをシッカリと確実にサポートしたい」という人は、各自治体のアナウンスに従うのが最適解だと「私は」思う。
これは全部「私」の話
冒頭でも注意書きをしたが、このnoteは私の経験だけに基づいて書かれたものだ。
鵜呑みにしすぎないでもらいたい。
間違っている部分があれば(私の実体験のパートに間違いはないが)指摘してもらいたい。
一人でも多くの人が、安心して眠れる日が来ますように。
余談と懺悔
本当は3.11に載せようと温めていた記事を急いでまとめてたので、足りない部分や至らない部分があります。それでも、なるべく早く載せたほうが良いと考えたので、今、載せました。
正直、遅いです。
でもこの速度が、私の出せる最高速度でした。申し訳ありません。
重ねてになりますが、あらゆる災害に遭った方が、一日でも早く、一人でも多く、安心して眠れる日が来ることを祈っております。
いただいたサポート代はすべて「楽しいコンテンツ」に還元させていただきます!
