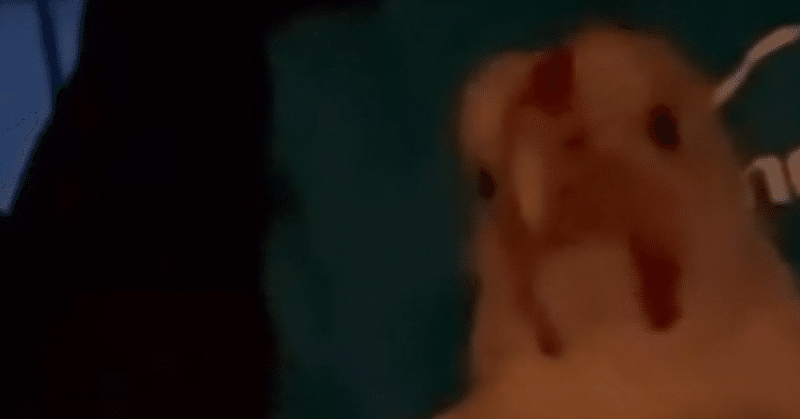
にわとりの出荷
わたしは大学3年生の時、とにかく畜産の世界を知りたくてあらゆる人脈を使って農家の皆さんにお時間をとって頂き、話を聞きに行きにいった。
その養鶏農家さんのところに行ったのも、最初はお話を伺うのが目的だった。鶏舎の中に何千羽いる鶏たちの前で、ヒヨコが届いてから出荷に至るまでの細かな流れから餌のこだわりなど、あれやこれやについて詳しく教えていただいた。
大学では牛の勉強がメインだったので、初めて生で見るブロイラーはとても新鮮で、お話をきくのもとても楽しかった。
ブロイラーとは、短期間で急速に成長させることを狙って作られた肉養鶏のことだ。基本的に大きな鶏舎に何千羽単位で平飼いされている。スーパーで売っている鶏肉のほとんどはブロイラーだ。ブロイラーとはもともと孵卵後3ヶ月以内の肉養鶏を指していたが、品種改良の結果、45日~50日程度で出荷されている。私たちが普段食べている鶏肉はほんの50日前まではひよこだったと考えると畜産とはなかなかすごい世界だと思う。実際、とある食鳥加工メーカーを訪問した際も、コメや果実などの農作物は1年に1シーズンしか収穫期がこないことも多いことに対し、養鶏は2ヶ月あれば出荷できる、出荷の機会の多い産業だということを教えてもらった。同じ畜産物でも例えば黒毛和種牛(黒毛和牛)であれば出荷までに2年近くかかることや、豚でも最短で6ヶ月弱程度かかることを考えると、養鶏業は畜産業の中では圧倒的にサイクルがぐるぐると回っていることがわかる。
養鶏業で多く行われているのは「オールイン・オールアウト」という方法である。これは1つの大きな鶏舎に何千もの雛を一気に放ち(オールイン)、一気に育て上げ、一気に出荷するのだ(オールアウト)。
そのため、何千・何万羽を一気に出すブロイラーの出荷はとても大がかりになる。
出荷に関するお話を伺っているときに、農家さんが「出荷は大変だよ~。今度鶏の出荷、手伝いにくる?」と言ってくださった。そんな滅多にない機会、やらせていただきたいに決まっている.
ふたつ返事で「是非っっっ」と答えた。
そして本当に参加させていただけることになり、丁度見学に行かせていただいた日の日齢から、10日後、午前2時半にまたここで。ということになった。私は楽しみで仕方がなかった。
ついに出荷の日となった。9月の降旬、日中はまだ暑さが残るものの、深夜2時ともなれば空気はひんやりと湿っていた。
つくと、屈強な男性が10人ほどいた。聞くと養鶏農家さんたちはお互いに協力し合い、お互いの出荷の日はお手伝いをしあっているらしい。
その時の私の服装は長そでのインナーとジャージ、その上からウインドブレーカーを重ね着していた。あとはマスクをして、帽子をかぶり、分厚い軍手と長靴を着用していた。
そして、いざ、鶏舎の中に入る。明かりはぽつぽつとある豆電球のみで殆ど真っ暗だが、目が慣れてくるとニワトリの白がしっかりとわかるようになる。3000羽以上いるニワトリみんな人間がぞろぞろ入ってきているのに、ほとんど動きがない。ニワトリはいわゆる鳥目であり、暗所では眠ってしまうからだ。
鶏舎の中には大きな箱がたくさん配置してあり、そこに鶏を7羽ずつつめて、7羽つめたら箱のふたを閉じて次に行く。それをひたすら繰り返していく。
丸くなっているニワトリを捕まえると鈍く声を上げて脚と羽を使ってバサバサと暴れる。それを箱に入れてしまえば何事もなかったようにまた静かに眠ってしまう。とにかく捕まえる。入れる。捕まえる。入れる。捕まえる。入れる。1羽2羽ではない。1人何百羽の単位で進めていくのだ。2キロの温かくて暴れる地面に落ちているものをひたすら箱に詰める作業の大変さはやってみなければわからないと思った。とにかく腰に響いてくるし、体が熱くなってきて汗が頬を伝う。でもニワトリたちとひたすら格闘しているとだんだんコツをつかんでくるもので、どんどん鳥を捕まえてから入れるまでのスピードが向上していくのを感じた。2羽一気に箱に入れるおじさんの技術を見よう見まねで習得して2羽同時に捕獲にもチャレンジした。
もう夢中だったのでどのくらい時間がたったかわからないが、出荷できるすべての鶏が箱に収まったところで休憩が入った。
ペットボトルのお茶をいただいて、みなさんの談笑に混ぜていただいた。その時ふと見上げた空に浮かぶ月がきれいだったことを覚えている。
汗が少し引いたころで作業が再開された。
ここからの作業で、私は私の力のなさ、どうしてこの場に私しか女性がいないのか、ということを痛感した。私は女性の中では力がないほうではないと思っているが、皆さんの前では本当に非力な女子大生だった。
ここからの作業は、私がほぼほぼ触れられなかったのでざっくりと書くが、さっき詰めた1箱7羽の箱を3段につみ、それを連結させてレールに乗せて運び、ひたすらトラックに積載して固定するというものだ。
単純計算で1羽(2kg)×7×3=42kg 絶対に持てないほど重たいわけではないが、とにかく素人の非力と玄人のムキムキでは圧倒的にスピードが違うのだ。捕まえて箱に入れるまではなんとかできても、それ以上先は厳しかった。足をひっぱるわけにはいかない。それにその42kgの箱を連結させて押す作業は、本当に私には物理的にできないのだ。ここにいる人たちのムキムキさの理由がよくよくわかった。筋肉こそ正義だ。
ふと鶏舎を振り返るとこないだ見学に来たときは鶏がところせましといた鶏舎はがらんとして、淘汰の子(小さすぎる子は出荷できないので淘汰される)だけがぽつぽついるだけだった。私はなんとなく足元にいた淘汰の子を抱っこしててきぱきとトラックに積み込まれていく様子を見ていた。淘汰の子はきょとんとした顔で一緒にその様子を見ていた。

どでかいトラックを見送りながら、淘汰の子の弱いけれど確かにあるぬくもりを感じていた。淘汰の子の足は曲がっていて、お腹がすいても餌場までなかなかたどり着けず、大きくなれなかったことは容易に想像できた。
今トラックに揺られている大勢の子も、少なくとも今日の夜にはこの世にいない。小さくてガリガリだけどぽかぽかと温かいこの子も、私が家に帰ってひと眠りして起きたらもうこの世にはいない。頭でいくらわかっていても、手の中にある温度がそれを非現実的なものにするのだ。
淘汰の子をそっと地面におろすと、その場で眠り始めた。もう夜が明ける。この子の最後の眠りが安らかであることを祈ることしかできなかった。
農家さんや、お手伝いに来てるおじさんたちに何度もお礼をいい、私は養鶏場を後にした。本当にいい経験ができた。知らないことがたくさん知れた。よかった。農家さんたちに、ニワトリたちに、そしてこの経験を支えてくれている両親に感謝の気持ちでいっぱいだった。
髪の毛も服もなにもかも、これでもかというくらいニワトリのにおいがして笑っちゃうくらいだった。結局私はこういう自分が1番好きだなと思った。帰り道、海から昇ってくる太陽がとっても綺麗で、いい朝だったことを覚えている。
おしまい
あとがき
シャワーをがっつり浴びても、ずっとトリくさくてうれしかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
