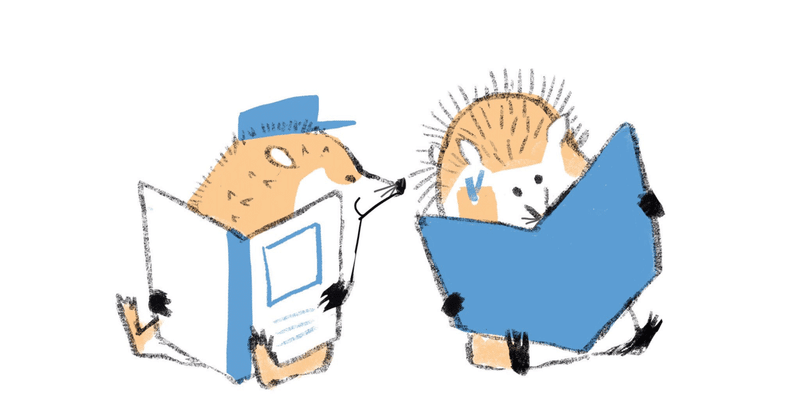
「”問題解決型”母ちゃん」と「”共感型”父ちゃん」子どもへの声かけを比べてみたら
どうも。アスピー母ちゃんの千四里(せんよんり)です。以前こちらの記事でもご紹介したように、私は41歳でASDと診断されました。そして私にはふたりの小学生の息子がおり、ふたりともASDと診断されています。
今日は、自分の思考タイプを「問題解決型」だと考えているアスピー母ちゃん(※実母からもお墨付き)と、私に比べて「共感型」(と私が感じている)父ちゃんの、息子たちへの声かけの違いを通して、実際にあったふたつのケースを例に気づいた点をまとめてみたいと思います。
ケース①:長男くん、南米フェスの会場で踊り出す

先日家族で遊びに行った先で偶然、「南米フェスティバル」が開催されていました。会場は軽快な南米ミュージックが流れ、踊る人、一緒に歌う人、その様子を見に来る人でごった返しています。賑やかな雰囲気が大好きな長男くんも、音楽に合わせ楽しそうに踊り出しました。
その様子を見た父ちゃんと母ちゃんが、長男くんに言ったことは…
父ちゃん:「もう~やめてよ。恥ずかしいなぁ…(;´Д`)」
母ちゃん:「踊りたいなら、もう少し人が少ない場所に移動しよう。他のお客さんにぶつかったら危ないから」
長男くんは父ちゃんの発言にちょっと不満そう。私はそんな彼を会場の隅に移動させ、他の人の邪魔にならない場所で好きに踊らせることにしました。父ちゃんは退屈する次男くんを連れ、屋台のある方へ消えていきました。
「恥ずかしさ」を感じるのは他者の視点を意識できる証?
ひとつ誤解してほしくないのですが、私は父ちゃんの言動を批判したくてこの記事を書いているわけではありません。彼がとっさに長男くんに「恥ずかしいからやめて」と言ったのは、ある意味「他者から見た自分」を自然に認識できるからとも言えます。
一方の私は、ノリノリで踊る長男くんを見て「楽しそうやなぁ(*´▽`*)」とは思っても「恥ずかしい」とは全く思いませんでした。
こんな風に親の予想外の行動をとった子どもに対し、「恥ずかしいからやめて」と私が声をかけたことは、恐らくほとんどないと思います…というか、「子どもたちの行動に、自分が恥ずかしさを感じる」ということが、いまいちピンとこないのです。
以前こちらの記事でもご紹介したように、私の母も父ちゃん(私の夫)も、長男くんが街中でひとりごとを言い始めたら、割とすぐ止めようとします。しかし私は正直その必要性をあまり感じないので、ふたりに比べ長男くんのひとりごとを止めようとする回数は少なめだと思います。
もちろん私も長男くんにひとりごとを控えるよう注意することはありますが、それは静かにすることが必要な施設――例えば病院や図書館、電車やバスなどを利用しているときくらいです。ましてや賑やかな街中の歩道で、小声でひとりごとを話す程度なら、「問題ない」とそのままにしておくことが多いです。
一度母の行動を不思議に思って「なんでそんなにしょっちゅう、長男くんのひとりごとを止めようとするの?」と母に聞いたところ「だって周りの人がビックリするでしょ!」と返ってきました。それを聞いて私は「…まぁ多少はビックリするかもしれないけど、一瞬すれ違うだけの人のこと、そんなに気にする必要ある?」と思っていました(口には出しませんでしたけど…^^;)。
ケース②:次男くん、目の前で転んで大泣き

これまでの出来事を読んで、皆さんはどのように感じたでしょうか?もしかしたら人によっては、父ちゃんが「他人の目を気にしすぎ」に見えるかもしれませんし、反対に息子の言動に口出ししない私を「非常識」と思うかもしれません。
ただここで私が注目してほしいのは「どちらがいい、悪い」ということではなく、「同じ状況を見ても感じ方が違うと、声のかけ方も違ってくる」という事実です。
では次に2つめのパターン、「転んで泣いてしまった次男くんに、私や父ちゃんがよくしている声かけ」を見てみましょう。
父ちゃん:「お~、大丈夫かぁ?痛かったなぁ。ケガしてないか?よしよし…」
母ちゃん:「ケガはしてないね。歩ける?帰って消毒すれば大丈夫だよ」
…今改めて文字に書き起こしてみると、我ながら中々冷たい感じがしますね。でも私はきっと、無意識にこういう言動をしてしまっていると思います(ノД`)・゜・。
特に子どもたちが小さい頃は、自分にAS傾向があるという自覚すらなく、毎日がほぼワンオペ育児だったため自分の言動を誰かと比較することがありませんでした。しかしあるとき家族4人で出かけた際このような状況に遭遇し、父ちゃんの子どもたちへの接し方が普段の自分とあまりに違ったのでとても驚いた記憶があります。
正直、父ちゃんが次男くんへ声かけする様子を見て真っ先に私が思ったのは「すごい!幼稚園の先生みたい」でした。しかしその後も似たようなシチュエーションで、彼が自然に同じような声かけをしていたのを見て、「え?あれって、演技じゃなかったの?なんか私と全然違う…もしかして私、ちょっと変…?」と自分の言動に違和感を覚えるきっかけとなりました。
思い返せば私は、子供の頃から母に「そんなに相手を突き放すよう言い方しないの!」と何度も注意されてきました。私には自分の発言の何が「相手を突き放している」のかがずっと分からなかったのですが、恐らく「”辛かったんだね”とか”痛かったね”など相手の痛みに寄り添い、共感する言葉がない」という意味だったんだと思います。
「問題解決型」も「共感型」も相手を助けたい気持ちは同じ
しかしここで私が声を大にして言いたいのは、一見冷たく見える(?)私の声かけも、子どもに安心してほしいという思いから発せられたものだということです。
例えば先程例に挙げた、私から次男くんへの声かけ「ケガはしてないね。歩ける?帰って消毒すれば大丈夫だよ」は、「ケガは大したことないから安心してね」という意味で発したつもりの言葉です。
今よくよく考えれば、最初に「痛かったね」という共感のひと言があれば、次男くんの受ける印象も随分違うんだろうと理解はできます。しかし正直に言えばとっさの状況でそういった言葉は出にくく、私にとってはかなり意識しないと難しいような気がします。むしろ目の前でハプニングが起こると「早く問題を解決して安心させてあげたい」気持ちが強く働くため、つい先程挙げたような声かけになってしまいそうです…
もしかしたら時折子どもたちがキョトンとした顔で私を見ているのも、私の言動が理由なのかもしれません。そう思うと、子どもたちになんとも申し訳ない気持ちになります(´;ω;`)
アスピー母ちゃんは共感できない人間なのか?
ところで「ASDは他人に共感できない」という言葉をしばしば耳にしますが、自分の経験から考えると、それは少し違うように感じています。目の前で誰かが辛そうにしていれば助けてあげたいと思いますし、安心させてあげたいと思うのですが、私の場合「自分自身がされると嬉しい対応=困りごとを解決するための具体的な方法or客観的事実を提示してもらう」という方法を無意識に選んでいるような気がするのです。実際私自身も、いたずらに「共感ワード」を並べられるよりも、具体的な解決策を淡々とアドバイスしてもらったほうがずっと嬉しいし、そういう人の方がむしろ信頼できると感じます。皆さんはどう感じますか?
個人的には、特に「AS傾向がある」と指摘された方や、その自覚がある方がどのような感想を抱いていらっしゃるのかに非常に興味があります。もしよかったらご意見や体験談をお聞かせください(*^^*)
結論:タイプの違う夫婦だからこそ、子どもに違う角度からアプローチできる

ここまで「”問題解決型”の母ちゃん」と「”共感型”の父ちゃん」の子どもへの声かけを比べてみましたが、私が今率直に思っていることは「父ちゃんが(私より)共感力が強い人でよかった」ということです。
私と父ちゃんは、性格も食の好みも面白いくらい正反対ですが、ケンカらしいケンカはほとんどすることはありません。一緒に生活していると、お互いに違い過ぎて比べてはゲラゲラ大笑いすることの方が多いです。たまにおっとりマイペースな父ちゃんにイライラすることもありますが、あちらもグータラな私には色々思うところがあるでしょうから、まぁお互い様でしょう…(;^ω^)(ひょっとしたら、父ちゃんの方がだいぶ我慢しているかもしれませんが…)
転んで大泣きする次男くんの痛みに寄り添える父ちゃんと、外で踊る長男くんを気にしない母ちゃん、それにAS特性のあるおっとりした長男くんと、負けず嫌いな次男くん。
私より共感力のある父ちゃんがいるからこそ、AS特性のある私は新鮮な気づきが得られるし、子どもたちもそんな優しい父ちゃんが大好きです。ときにはすれ違うこともあるし意見がぶつかることもありますが、自分と異なるタイプの家族がいるのは、驚きと発見の連続でなんだかんだ楽しいですし、私にとってはこれからも色々と考えさせてくれる飽きない存在であることは変わらないんだろうと感じています。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。ではまた、次回お会いしましょう(^^)/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
