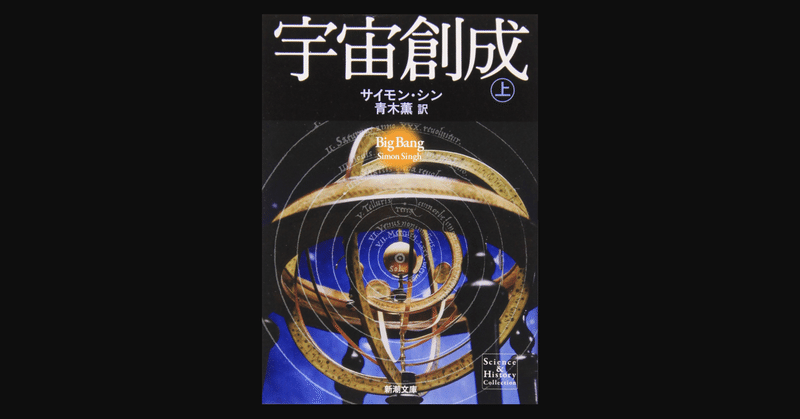
ビックバンモデルは如何にして生まれたか 『宇宙創成』
子どもと宇宙の話をしていても、なかなか宇宙の凄さを伝えきれない。
スケールの凄まじい大きさや、まだまだ人間にはわからない事ばかりである話、不思議すぎて大人でも頭に「?」しか浮かばない宇宙開闢の話など、あれこれと頑張って子どもに向けて説明をしたのだけど、全く盛り上がらなくて寂しかった。
まぁ、説明の仕方がイマイチという点は否めない。「最初は点だったのにボーンって爆発した」とか、「ボーンって生まれてすっごい広くなった」とか、かなり雑な説明になってしまい娘たちはまったく興味をもたなかった。
ビックバンの話、むっちゃおもしろいのに、将来子どもたちが「ああ、それってパパがボーンとかドーンって言ってたアレね?」なんて事になると、各方面に申し訳ない気持ちになってしまうので、もうちょっと具体的に説明出来るようになっておこうと、本書を書棚から取り出し再読してみた。
最初はね、流し読みの予定だったのですよ。だって、今日発売の『三体2』が読みたいから。
だから、最初はざっと流し読みして、気になるところ、面白いところがあればメモをしよう、と本を広げたのに、気がついたら熟読してしまった。だって、すっごい面白いんですもの。
本書は宇宙開闢のときから現在、そして宇宙の未来までについて、これまで様々な科学者が挑み、成果をあげてきた物語を紹介したもの。
話の中心は、いかにしてビックバンモデルが生まれ、支持を得るようになったのかの紹介となる。ビックバンモデル以外にどのような宇宙論が有り、支持されてきたのか、様々な科学者達が挑んできた軌跡が紹介されるのだけど、科学者を主人公にした大河ドラマのようで面白い。
それこそ、ビックバンの話なんて子供の頃から何度も読んできたし、何度も見てきたと思うのですよ。子供向けの科学読本もあるし、書籍もたくさん出ていて、雑誌でもとりあげられる。
なのにあえてサイモン・シンが書いて取り上げる意味。
散々読み聞きしてきたビックバンについて読む意味。
ありましたね、ありますよ。本書にかかれている内容、表題だけみると、ああ、それ知ってるよ、という内容なのに、サイモン・シンのせいで面白い。エキサイティングだし、ドラマチックだし。
やっぱりこの手の本をかかせるとピカイチに上手いなぁ。(何様だ)
それにしても、たかだか何百年前までの世界では、天動説が本気で信じられていたし、それ以前は亀と象が世界を支えているとか言っていたのに、ビックバンモデルという偉業を打ち立てるに至るこの科学の発達っぷり。すんばらしいですよね。
ということで、まるで小説を読んでいる可能用なワクワク感が味わえます。おすすめです。
このnoteからリンクしている文庫は『宇宙創生』だけど、元々は『ビックバン宇宙論』という題で単行本が出ていた本が、改題されて文庫になったもの。サイモン・シンの本、なんで改題されるものが多いのかしら、以前紹介した『代替医療のトリック』も『代替医療解剖』になっているし、フェルマーの定理も暗号解読も改題されてシンプルなタイトルになった。流行りの断捨離? 文庫で並べたときに綺麗だからとかなのかな。
さて、暗黒森林を読もうっと。
「それって有意義だねぇ」と言われるような事につかいます。
