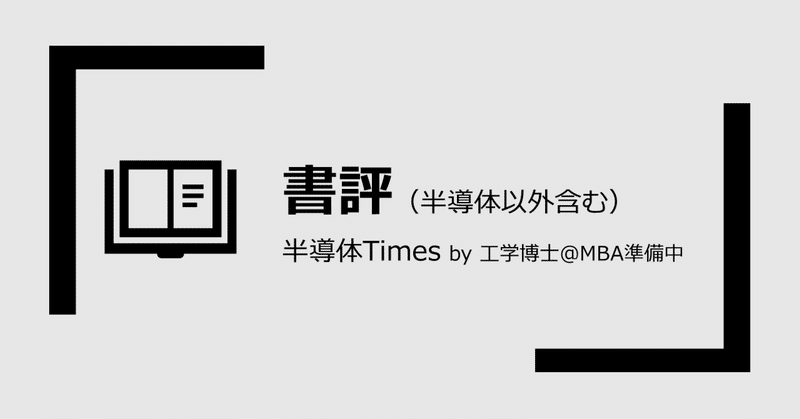
【書評】自分のアタマで考えよう(Vol.5)
はじめに
本書は,月間PV(ページビュー)200万回を
超えるブログ ”Chikirinの日記”
を運営する著者が,
社会人になった最初の頃の自分が
・読んで役立つような,
・分かりやすく,
・読んでいて楽しい
「考えるための方法論をまとめた本」
があればと,本書を執筆したそうです.
・考えるって,つまりなんだろう?
・なにをどう考えればいいんだろう?
と感じている人々にオススメの一冊です.
なお,本書は大変学びの多い内容であったため、数回に分けて書評をお届けしています.良ければこちらも読んでみてください。
就活において情報収集より重要なことは?

就活をする前には膨大な情報を集める(集めた)と思います。
具体的な項目としては、
・給与
・勤務地
・仕事内容
・福利厚生
・株価
・財務状況
などなど,集め始めたらキリがありません.
情報を集める前に
意思決定のプロセスを明確化する
ことは,既にお伝えしたとおりですが,
就活においてはその他に何を意識すべきなのでしょうか?
氏は仕事選びについて以下のような論を述べています.
仕事を選ぶというプロセスは,多くの選択肢を何らかの基準によってフィルタリングし,自分がやりたい仕事と興味のない仕事を選り分け適性のある仕事とない仕事を分離することです.
これを図にすると,こうなりますね.

氏は本書において現在の就活の問題点を,
企業の情報を集めることに必死になりすぎて
意味のあるフィルターを探そうとしないこと
であると述べています.
つまり,ここでも大切なのは情報ではなく
大量の情報をスクリーニングするためのフィルターである.
そう言いたいのだと思います.
確かに現代において情報は,Google先生や書籍に聞けばかなりの部分が手に入ると思います.
でもそれらの情報を分類するためのフィルターを持っていなければどうでしょう?
間違いなく飽和します.
上記の図で言えば,インプットした情報がそのまま下に流れ出してしまうことになります.
私達はその大量の情報を受け取っても,意味のある判断できないでしょう.
氏もこう述べています.
インターネット上での情報開示が進んでいる現代では,企業情報をあつめるのはむずかしくありません.
就活の成否は集めた情報量ではなく,「自分独自の,価値あるフィルターを
見つけられたかどうか?」にかかっているのです.
つまるところ就活とは,
自己対話と他者対話を繰り返して自分独自のフィルターを探す作業
のことなのでしょうね.
あなたのフィルターはなんですか?
結論:就活において情報収集より重要なのは?
自分独自のフィルターを見つけること
今後の行動:自分独自のフィルターを探そう
情報収集ではなく自分独自のフィルター探しを念頭に置きながら,
自己対話と他者対話を繰り返そう.
頭の回転が速い人とは?

頭の回転が早い人っていますよね?
では,頭の回転が早い人ってどんな人のことでしょうか?例えば
何かを見たり聞いたりした時に,すぐに気の利いた意見が言える人
なんか,しっくり来るのではないでしょうか?
えっ?この短時間でそこまで思いつくなんて,
この人は頭の回転が速い人だ!
と思ったりすると思います.
しかし,氏はそれを明確に否定しています.
氏いわく頭の回転が速い人は,
・頭の中に思考の棚を持っており,手に入れた情報をその思考の棚に整理して格納している
・(仮の)結論をあらかじめ考えていている
と述べています.
これだけだと,なんの事?って感じだと思いますので.一個ずつ段階を追って説明していきます.
まず思考の棚とは何か?についてです.
本書の例を出して説明します.
9・11テロの際のNHK,BBC,CNNの報道内容の差についてです.
事故が発生したのは,ご存知のように米国NYです.
その時,著者によると各テレビ局の報道の内容は
以下のようなものだったそうです.
・NHK(日本)・・・自国民の安否情報
・BBC(英国)・・・背景解説と討論
・CNN(米国)・・・現場のパニック状況
テレビ局によって大きな違いがありますね.
確かにNHKは大きな事件が起こると,
”日本人の安否”を真っ先に報じているように思います.
でも待って下さい.もしかしたら,
この報道が一貫性のあるものか考える必要があります.
なぜなら,
今回はNYで事件が起こったから、この様な報道内容になったのでは?
という視点が必要だからです.
つまりロンドンで同様の事件が起こった場合は,
9・11のときは冷静沈着だったBBCも
”パニック状態” or ”自国民の安否最優先”
になるのでは?という視点です.
もちろんこの時点では,真偽は定かではありません.
しかし頭の中(思考の棚)に今回の情報を整理し格納しておくことで,いつか似たような状況が発生した時に予測を立てられる.
その意味で思考の棚の存在が非常に重要である
と氏は述べています.
なお,先程の情報を思考の棚に整理するとこうなります.

さて,これで
思考の棚 + 整理された情報の重要性
について理解して頂けたかと思います.
さて,それでは本題です.
そう.頭の回転が速い人とは?についてです.
氏は頭の回転が早い人がそのように見える理由を
以下のように述べています.
待っていた情報が実際に手に入った時,彼らはそれを頭の中の思考の棚にまるで ”ジグソーパズルの最後のピース” をはめ込むようにポンと放り込んだ上で,「その情報が存在したなら,こういうことが言えるよね」と,
すでに考えてあった結論を「思考の棚」から取り出しているのです.
つまり,これは彼らの「頭の回転の速さ」を示しているのではありません.
思考自体が事前に完了していた
ことを示している.
そういう事なのです.
結論:頭の回転が速い人とは?
思考の棚の中に情報を整理して格納しており,事前に結論を考えている人
今後の行動:整理して格納しよう
PCの中のファイル整理のように,インプットした情報を適切な場所に格納しよう
「考える」って結局どうするの?

さてここまで「考えること」について徹底的に考えてきました.
本書の巻頭に氏の考える,「考える」って結局どうするの?
の回答が列挙されていましたので,
紹介します.
・いったん「知識」を分離すること!
・「意思決定のプロセス」を決めること!
・「なぜ?」「だからなんなの?」を問うこと!
・あらゆる可能性を探ること!
・縦と横に並べて比較してみること!
・判断基準の取捨選択をすること!
・レベルをごっちゃにしないこと!
・自分独自の「フィルター」を見つけること!
・データはトコトン追いかけること!
・視覚化で思考を深化させること!
・知識は「思考の棚」に整理すること!
これらの思考フレームワークを知っているだけで
これまで曖昧だった「考える方法」が明確になることでしょう.

最後に氏自身の反省も込めた,私達への提案を紹介します.
氏はこれまでに
”解法を知ろう,解法を勉強しよう,
解法を覚えよう”
という勉強をしてきた人へあるメッセージを訴えています.
具体的には,問題集を開いて
わからない問題にぶつかった時には
すぐに回答を見るという勉強法ですね.
氏の言葉を引用します.
こんな勉強の仕方では,テストの点は取れても,「考える力」は全く身につかないのだと気がついたのは,(恥ずかしながら)社会人になって3年以上たってからです.
(中略)でも実際には,こんな方法で勉強していたら,初めて見る問題には
手も足も出ません.
確かにこの方法でテストの点は(効率よく)取ることが出来ます.
でも現実社会には,解法を誰もわからない問題が溢れています.
氏はこう述べています.
(前略)働きはじめたあと,現実の社会には,誰かがあらかじめ用意してくれた解法が存在しない課題がたくさんあると気が付きました.
私はそういった課題に取り組む必要が出てきて初めて,「解法を知ること」と「解法を考えること」は異なること」だと理解したのです
心当たりのある方は思考する事を楽しんでみませんか?
きっと稚拙なことや間違いも多くなるでしょう.
でも今は良いのです.
将来的に出来ればそれで良いのです.
氏もこう述べています.
どの分野でも同じですが,自分の頭で考えれば考えるほど稚拙になり,間違いも多くなります.偉大な先人や専門家の智恵に素直に耳を傾け,知識としてそれらを学んだほうが「わざわざ自分の頭で考える」より圧倒的に効率がよいでしょう.
荒削りだけどユニーク,突拍子もないけどおもしろい.
だからこそ ”Chikirinの日記” が200万PVを突破するのでしょう.
最後に
いかがでしたでしょうか?
今回は,ちきりん氏の著書「自分のアタマで
考えよう」の書評(Vol.5)を執筆しました.
○もしこの記事が参考になったという人は
”スキ” よろしくお願いします.
○今後も皆さんの人生に有益な記事を
連載していきますので見逃したくない方は
忘れずにフォローして下さいね!
今日も最後まで読んでいただき,
ありがとうございました.
本書へのAmazonリンクはコチラ↓
Kindle版はこちらです。
その他のおすすめ記事はこちら↓
よろしければサポートもよろしくお願いいたします.頂いたサポートは主に今後の書評執筆用のために使わせていただきます!
