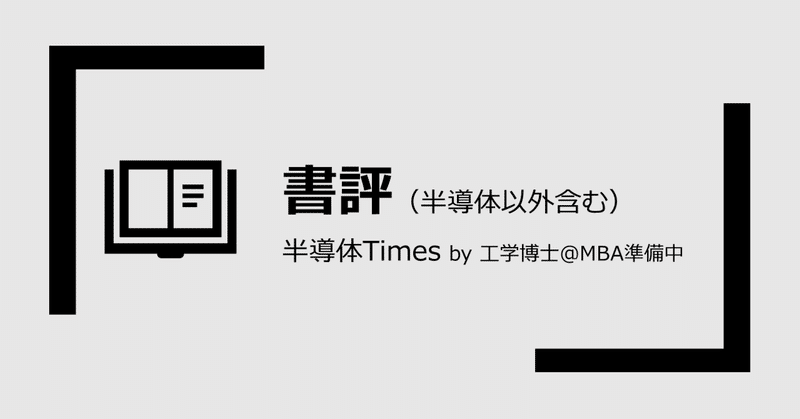
【書評】自分のアタマで考えよう(Vol.3)
はじめに
本書は,月間PV(ページビュー)200万回を超えるブログ
”Chikirinの日記”
を運営する著者が,社会人になった最初の頃の自分が
読んで役立つような,
分かりやすく,
読んでいて楽しい
「考えるための方法論をまとめた本」
があればと,本書を執筆したそうです.
・考えるって,つまりなんだろう?
・なにをどう考えればいいんだろう?
と感じている人々にオススメの一冊です.
なお,本書は大変学びの多い内容であったため、数回に分けて書評をお届けしています.良ければVol1と2も読んでみてください。
数字を見たら考える2つの問いとは?
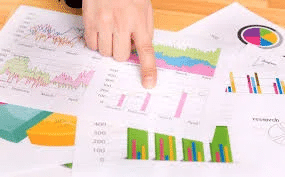
私達は,日々膨大な情報に触れて生きています.
一節によれば,現代人が1日に受け取る情報量は
・江戸時代の一年分
・平安時代の一生分
であるそうです.
おそらくこれからも増加の一途を辿るでしょう.
そんな膨大な情報を浴び続ける我々現代人は,
考えることを放棄してはいけません.
なぜなら膨大な情報の渦に巻き込まれて,
何が正しいのか分からなくなってしまう
可能性が高いからです.
では情報(ここでは特に数字)を見た時に
我々は何を考えるべきなのでしょうか?
氏はこう述べています.
情報を見た時にまず考えるべきことは,
「なぜ?」と「だからなんなの?」の2つです.
「なぜ?」とは数字の背景を探る問いです.
数字はなにかの減少や活動の結果なので,
すべての数字には理由があります.
もうひとつの「だからなんなの?」は「過去の
結果がこの数字に現れているのだとしたら,
次は何が起こるのか?それにたいして
自分はどうすべきなのか?」と,
データの先を考える問いです.
抽象化した概念で,丁寧にデータの見方を教えてくれていますね。
研究者でもビジネスマンでも,算出したデータに対して適切な解釈を付け加えること(=考察する)は必須の能力です.
少し話は逸れますが「考察する」とは
わかりにくい言葉です.
日本語の中には,この様なわかりにくい言葉
(あるいは抽象的な言葉)が溢れています.
・検討する
・調査する
・頑張る
・対処する
・意識する
.
.
.
これらは日常生活で使うのは可ですが,
ビジネスやサイエンスの場ではNGです.
「考察が甘い」という指摘はよくありますが、
それがどう足りていないのか?
抽象化して教えてくれる人は多くないと思います。
もしかすると,染み付いているからこそ
言葉にする必要性さえ感じていなかった
のかもしれません.
でも経験が浅い人には,
当たり前を伝えることが重要な意味を持つ
ことがしばしばあります.
さて,話を戻してデータを見た時には
反射神経的に2つの問いを思い出してみましょう
結論:数字を見たら考える2つの問いとは?
「なぜ?」でデータの背景を探り,
「だからなんなの?」でデータの未来を予測する
今後の行動:自他への質問には
2つの問いを念頭に置こう
自身,他者に対する質問のいずれにおいても
2つの質問に答えられるか?を念頭に置こう.
調べれば分かることを「考える」意義とは?

本書では「なぜ?」「だからなんなの?」
を考える具体例として,
「過去の出生数と合計特殊出生率のデータ」
を用いて将来の出生数を予想するという
ワークが行われています.
こちらの内容も非常に示唆に富んでおり,
ボリューミーなので興味ある方は
一読をオススメします.
ちなみに氏は,
移民の受け入れは不可避な選択
であると結論づけています(内容は割愛).
さて,こんなことを言うと拍子抜けされるかも
しれませんが,これらの予測は既に多くの専門家
によって成されています
つまり,こんな事を思う方も
いらっしゃるのでは無いでしょうか?
わざわざそんな面倒なことをしなくても,
最初から公的機関が予測している
データを見つければそれで良いじゃん!
わざわざ自分で思考するよりも専門家が算出した正しいデータを
見つけられればそれで良い、ということですね。
この考え方は ”情報収集能力を高める” という
視点で見れば間違っていません.
むしろこれからの世界を生き抜く上では
必須の能力と言えるでしょう.
しかし,その得た情報を考察する力.
前述の「なぜ?」と「だからなんなの?」
の問いに答える力は全く養われません.
もし,情報収集能力を高めるだけの教育が
行われたらどうなるか?それは,
インプットした情報をそのまま出力するだけの
動くスピーカーとしての役割しか
果たせない人間が量産される.
ということに他なりません.
重要なのは調べた過去の情報(=知識)から
未来を推測する力を養うことです.
ここで示したような,国の将来人口は
国家計画の基本となるものですので,
当然,公的機関が予測を発表しています.
しかし,皆さんの身の回りの情報はどうでしょうか?
・これまでの支出と消費のデータから,
来年に必要な収入を予測する
・これまでの仕事量とそれに要する時間から
今日の退社時間を予測する
・これまでの彼女の趣味と時期から
喜びそうなプレゼントを予測する
情報収集能力が向上すれば、あなた用に完全にパーソナライズ
(=個人化)された予測は手に入るでしょうか?
否.そんなことは無いはずですよね。
そして探すことしか出来なければ,膨大な時間を浪費することになります。
つまり,考えることが出来るようになれば,
短い時間で将来を予測できるようになる
ということを意味します.
氏の言葉を引用します.
このように,「知識を得る」ことも大切ですが,
同時に「自分の頭で考えて,予測してみること」
もとても意味のあることなのです.
結論:調べれば分かることを「考える」意義とは?
いつでも完全に自身用にパーソナライズされた予測が手に入る保証は無い.そんな時に将来を短い時間で予測するため.
今後の行動:当たり前を考えよう
誰かが考えた当たり前について考えて,自分の考えと比較をしてみよう.
考えモレをなくすには?

現在の日本では,生活保護の受給者数は増加の一途を辿っています.
なんと100人に1人以上が生活保護で暮らしており支給費の総額は3兆円にも上るそう(2010年)
日本の消費税による収入は年間約10兆円(2009年)であることを考えると,
33%が生活保護の受給者を救済するために
使用されていることになります.
この現実を改善するにはどうすればよいでしょう?
例えば,こんな事が考えられるかもしれません.
・自活させる
・不正受給を減らす
・現物支給にする
・生活保護制度を撤廃する
など,他にもいくつかあるかもしれませんが
このように思いつきで案を列挙するだけでは「考えモレ」が出る可能性があります.
この様な場面で有効な方法として,本書で紹介されているのが
分解図を使って「あり得る全ての可能性」を網羅的に洗い出す
という方法です.
具体的には以下の様な方法です.
まず,生活保護費の総額は
以下の数式によって決定されます.
生活保護費の総額=
生活保護を受ける人数 × 一人あたりの支給額
つまり,総額を抑えるためには
・受給者を減らす
・一人あたりの支給額を減らす
・両方減らす
この3つしか存在しないことが分かります.
次に,受給者数を減らすにはどうすればよいか考えます.例えば,
・新規受給する人を減らす
・現在受給している人を減らす
などが考えられますね.
つまり図にすると,こうなります.

このように,分解図を使って「あり得る全ての可能性」を網羅的に洗い出す
ことで考え方のモレを防ぐことが出来るのです.
例えば他にも,Aという事業領域に進出すべきかを検討する際に,
我々の技術力があれば可能だ!
と思っていたけれど,
新規参入企業の可能性を
検討していなかった...
というような事態を避けることが出来るでしょう
結論:考えモレをなくすには?
分解図を使って「あらゆる全ての可能性」を網羅的に洗い出す
今後の行動:まず図式化して把握しよう
問いに対する答えを探す際には,まずは図式化して,全容を把握しよう.
最後に
いかがでしたでしょうか?
今回は,ちきりん氏の著書「自分のアタマで考えよう」
の書評(Vol.3)を執筆しました.
○もしこの記事が参考になったという人は
”スキ” よろしくお願いします.
○今後も皆さんの人生に有益な記事を
連載していきますので見逃したくない方は
忘れずにフォローして下さいね!
今日も最後まで読んでいただき,ありがとうございました.
本書へのAmazonリンクはコチラ↓
Kindle版はこちらです。
その他のおすすめ記事はこちら↓
よろしければサポートもよろしくお願いいたします.頂いたサポートは主に今後の書評執筆用のために使わせていただきます!
