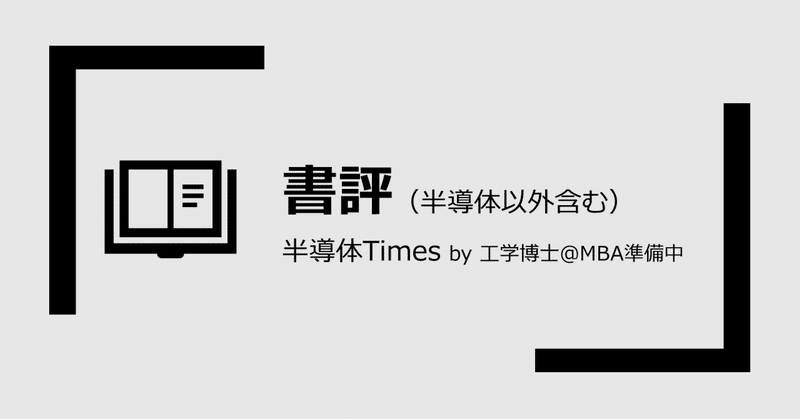
【書評】自分のアタマで考えよう(Vol.1)
はじめに
「あなたは日本のプロ野球の将来性についてどう思いますか?」
参考として,以下の様なデータがあるとします.
ちなみに本書でも同様の問いかけがなされています.
皆さんはどう思いますか?
まず,データを見る限り以下のようなことが「考えられる」かもしれません.
どうでしょう?どれもそれらしく聞こえてきますね.
ただ,一歩立ち止まって考えてほしいのです.
それは本当に考えたことでしょうか?
つまり,データを見て思考した結果でしょうか?
仮にこのデータを見ずしてこれらの意見を述べられたとします.
それはデータを見た上での思考の結果ではありません.
それは,もともと持っていた知識なのです.
実はここに本書の大きなトピックである,知識と思考の違いがあります.
つまり考えた(=思考した)結果の意見だと思っていても,
実は以前から有していた知識を吐き出しているに過ぎないかもしれないということです.
そして,その知識は自身が昔に思考したものでしょうか?
そういうものもあるでしょう.自身が考えて経験して得た知識もあるはずです.ただ,全てでは無いはずです.今回の例はどうでしょうか?
例えば以前,TVで「今後の野球の将来性は暗い」という言説を耳にして,それをそのまま知識としてインプットした.
そして今回のデータを目にして,その知識をただアウトプットしただけ.
そんな可能性はありませんか?
だとしたらそれは,考えているわけではなく,一時的に脳内に保存していたデータを引っ張り出してきたに過ぎない.
そういうことです.
では,仮に前提となる知識が全くない人がこのデータを見たとするとどうでしょう?
以前よりも(お金と時間を持っている)高齢者が増加しているという事実を読み取り,
日本のプロ野球界は明るい!
そう結論づけるかもしれませんね.(氏の知り合いはそう答えたそうです)
つまり口で言うほど,考えるというのは簡単なことでは無いです.
氏は,社会人になった最初の頃の自分が読んで役立つような,分かりやすく,読んでいて楽しい「考えるための方法論をまとめた本」
が欲しいと本書を執筆したそうです.
・考えるって,つまりなんだろう?
・なにをどう考えればいいんだろう?
と感じている人々にオススメの一冊です.ここまでで、もう読んでみたい!と思った方のために、Amazonへのリンクを張っておきますね。
なお,本書の書評は長編であるため数回に分けてお届けします.
自分のアタマで考えられる人とは?
さて,先程の例から知識と思考をはっきりと区別することが重要であると認識して頂けたかと思います.
それでは,ちゃんと考えられる人(=思考力がある)人とは,どんな人なのでしょうか?
著者はこう述べています.
つまり,毎回ゼロベースで物事を捉えられる人
(=知識と思考と分離できる人)
ということではないでしょうか.新たな事象に直面した時,知識(他人が過去に思考した結果)を引っ張り出してただ ”引用” していないか?
今後は自身に問うてみる必要がありそうです.
もちろん,自分が経験した上で得た知識もあるでしょう.
これは,一度は自身が思考した結果であるという意味で,他者の知識よりはマシです.
でも,だからこそ影響力は絶大です.特に自身の成功体験から来る知識から
逃れるのはどんな人でも困難でしょう.
氏もこう述べています.
つまり,自身が思考した結果,得た知識であれ他者が思考していた結果,得た知識であれ
それらを分離して毎度ゼロベースに戻すこと
が重要であると言えるかもしれません.
皆さんも次回からは,
毎回自分で思考しているか?意識してみて下さい.
結論:自分のアタマで考えられる人とは?
他者由来か自身由来かによらず,知識と思考を分離して毎回ゼロベースで考えられる人.
今後の行動:慣習の存在意義を考える
どんな組織であれ ”慣習” は存在しているものです.まずはその存在の有用性について思考してみましょう.
情報を集める前にすべき事は?
・新規事業に乗り出すべきか否か?
・ご飯にするかパンにするか?
・A社に就職するかB社にするか?
人生は間違いなく ”選択” の連続です.
前述の,ご飯かパンかを選択するのにそんなに情報を集めることはないでしょうが,
我社の命運が掛かっている新規事業に参入すべきか?否か?
を決定する場面では,(膨大な)情報が必要になること自体は容易に想像出来ます.
でも待って下さい.まだ情報を集めるのは早いです.
その理由はこうです.
どんな情報が集まれば意思決定に至るか?を決定していないからです.
ちょっと分かりづらいかもしれません.先程の例で言えば,こうなります.
重要なのはここです.
もし,これを決定せずに情報を集め始めれば間違いなく膨大な時間を無駄にします.
理由は,どんな情報も大切に感じてしまうから.特に賢い人(=新たな知識を得る欲求が強い人)ほど陥りがちなワナです.
このことを氏は,非常にユニークな表現で伝えてくれています.
特に研究者は論文読解というワナにハマりがちです.
気づいたらMendeleyやEvernoteの容量が一杯になっている.
そんな方は,是非一度本書を読んでみることをオススメします.
結論:情報を集める前にすべき事とは?
「どんな情報を集めれば意思決定に至るか」という意思決定のプロセスを決定する.
今後の行動:すぐに論文読解に入らない
手に入れたい情報を明確化して,その軸に沿う情報を探す.すぐに論文読解に入らない.
最後に
いかがでしたでしょうか?
今回は,ちきりん氏の著書「自分のアタマで考えよう」の書評(第一部)を執筆しました.
○もしこの記事が参考になったという人は
”スキ” よろしくお願いします.
○今後も皆さんの人生に有益な記事を
連載していきますので是非フォローして下さい!
今日も最後まで読んでいただき,ありがとうございました.
本書へのAmazonリンクはコチラ↓
Kindle版はこちらです。
その他のおすすめ記事はこちら↓
よろしければサポートもよろしくお願いいたします.頂いたサポートは主に今後の書評執筆用のために使わせていただきます!
