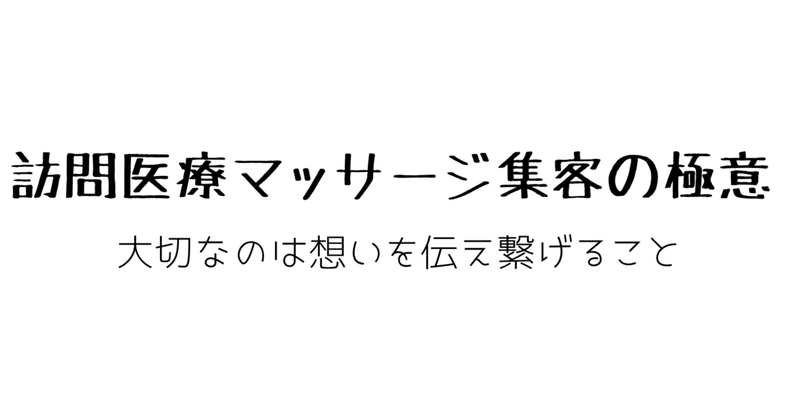
訪問医療マッサージ集客の極意ー医療機関の種類と役割はご存じか?
医療機関の種類と性格を理解する
ここからは、中々知ることのできない病院の種類や役割をざっくりと学んでもらうステップとなります。私たち患者側からすれば、病院は自分の住む地域にあって当然の施設です。病院の抱える課題点など考えたこともないでしょう。病院やクリニックは安定経営とされてはきましたが、地域人口の増減やライバル医療機関の有無が収益に大きく影響しています。人口が減少する中、病院も患者確保に必死ということです。
昨今のコロナ禍で、過去4年分の赤字が1年で到来したという病院もあるほどです。病院も選ばれる時代であり、選ばれなければ倒産する時代なのです。訪問医療マッサージ事業を展開する側として、病院やクリニックの”性格”や”抱える課題”を把握することで近い将来、地域医療・地域介護を支援する仲間として強い連携ができるヒントを得られるのではないかと考えられます。「介護のことは知っているけれど、病院運営については全くしらない」では、地域連携室のソーシャルワーカーと連携できるわけがありません。その点ある程度の知識を身につける必要があります。
皆さんは病院には四つ種類があることをご存じでしょうか。四つに分けることで地域人口や医療資源・介護資源のバランスを図りながら同じ機能を持った病院が重ならないように地域医療を保っているのです。理想としては、人口や地域のバランスを図りながら最適解を見つけることですが、中々計画通りにはいかないようです。その地域に同規模、そして同じような設備を整えた病院をつくっても、働く人は異なるので提供する医療サービスのレベルにバラつきが出てしまいます。そうなると自由に病院を選べる権利のある患者側が、よりレベルの高いそして満足度の高い医療機関を選ぶのは当然のことです。
患者さんは、近くに条件を満たす病院があっても、通院にかかる時間が1時間程度なら、よりの評判のよい病院に流れていってしまいます。実際に、私が北海道のある町立病院のコンサルティングを依頼され、病院の患者動向を調査したら、車で2時間という距離でも町立病院に行くよりは都市部の大型病院に行くという結果が出ていました。
また病院は大きな手術、難しい手術をすれば、それだけ医療収入が確保できる仕組みになっています。風邪は町立病院、手術は都市部の病院と地域住民の中で決められている時点で、病院経営に課題があることがわかります。
病院の種類には①高度急性期病院 ②急性期病院 ③回復期リハビリテーション病院・病棟 ④慢性期病院の4種類があります。その中でも訪問医療マッサージが将来的に連携できる可能性がある病院は、急性期病院と回復期リハビリテーション病院です。それぞれについて簡単に説明します。
①高度急性期病院
「高度急性期病院」とは、「より専門性が高く高度な医療技術が必要とされる患者」が入院する病院です。文字通り高い医療技術を駆使し、患者の病状の早期安定を図るという位置付けになっており、病床数でいうならば2018年(平成30年)度の統計で全国において約16万床です。入院ベッドの数が約16万あるということになります。主に主要都市部に多く設置されています。看護師の人員配置でいうならば7人の患者に対して1人の看護師または准看護師が配置されている手厚い体制です。手厚くなければ重症患者の早期安定を図ることができない、つまり医療の質が担保できなくなるということを意味していますが、急性期病院や回復期リハビリテーション病院の10対1との違いを聞かれると、実はそこまで本当に違いがあるのかは病院の病棟の運営により状況が異なるのです。大きな手術をするような大学病院は、おおよそ高度急性期として考えておけば問題ありません。
②急性期病院
急性期病院も高度急性期病院と同じように、患者さんの早期安定が目的とされていますが、両者の違いは一般的にはわかりにくいものです。診療報酬点数で表すならば3,000点以上に相当する医療を提供する患者比率が高いのが高度急性期病院であり、それよりも少し落ち着いた600点以上30,00点未満の患者が急性期病院です。看護師配置は前述の通り7対1の手厚い人員もしくは10対1の配置となります。病床数は高度急性期が約16万に対して約50万床となっています。私たちが通常、検査入院や軽中度の病気で入院するような病院は、おおよそこの急性期病院です。
③回復期リハビリテーション病院・病棟
「回復期リハビリテーション病院・病棟」とは、高度急性期病院や急性期病院で早期の治療を行い、病状は安定したけれど活動の障害がある患者さんが在宅復帰できるように、集中してリハビリテーションを行うため転院や転棟する病院や病棟です。
身体機能の回復においては、高齢者とそれ以外では回復力も異なり、この回復期リハビリテーション病院を期限内に退院しても、これまでと同じように生活ができるとは限りません。入院期間は、急性期病院とは異なり疾病によって60日から180日以内と決められていますので、この期間中にリハビリテーションを実施するわけです。
回復期リハビリテーション病院には、機能訓練的意味合いを持つ訪問医療マッサージの有効性を理解している医療ソーシャルワーカーが配置されています。そのため、相手の知識量にもよりますが、訪問医療マッサージと連携が取れる可能性が高くなっています。もし皆さんの地域に回復期リハビリテーション病院がある場合は、積極的に営業することをお勧めします。一つの病院と信頼関係が構築できれば、同意書が取得できないというリスクも最大限減らすことができ、新規の患者さんの紹介を受けることができます。
訪問医療マッサージが病院と連携する際に立ちはだかる壁としては、訪問医療マッサージについて知見がない傾向が強いことです。同じ医療資源にもかかわらず、在宅医療・介護までマネジメントする医療ソーシャルワーカーが訪問医療マッサージについて知らないのです。これは、特に急性期病院以上に多い傾向です。
④慢性期病院
「慢性期病院」は、急性期病院以上で早期安定を目的とした治療を行った患者が、回復期リハビリテーション病院でも入院期間内に在宅復帰の目途が立たなかった場合の転院先として、最終的に在宅に戻るためのリハビリテーションを継続し、治療をしながら入院する病院です。自立支援を目的としていますが、実際は元の生活に戻れる患者さんは少なく、リハビリテーションも回復期リハビリテーション病院ほど集中的に行えるわけではありません。というよりもリ、ハビリテーションを行えるような身体状況にはないということです。慢性期病院には、医療処置が必要な医療療養と介護保険が適用になる介護療養の二つの種類があります。
介護療養のほうの慢性期病院である「介護療養型医療施設」は、看護師不足や医療療養との明確な違いがわかりにくくなったことが原因で廃止が決まり、2024年3月末までが移行期間とされています。その代わり、特別養護老人ホームや有料老人ホームと同じように「生活の場」を中心とした「介護医療院」が2018年(平成30年)より新設されました。いち早く対応した病院は、国からの助成金を受けながら体制を整え、介護医療院の利用者を増やすように急性期病院との連携を開始しています。しかし、現実には在宅に戻れる患者さんが少ないと思われるため連携は難しいかもしれません。
⑤介護医療院
「介護医療院」は、2018年(平成30年)につくられた介護療養の代わりとなる施設です。介護医療院は、病院の中に病棟の一つとして併設したり、敷地内に別棟として建てたりすることが可能となっていますが、コンセプトが「生活の場」であるという点は介護付有料老人ホームと同じです。医療的ケアが必要、かつ長期的な療養が必要であるという医師の診察と判断に基づき入院が可能になります。「要介護1」以上の区分が必要であること、ある程度の個別スペースが確保されていることなどが特徴です。
医療という意味合いよりも、介護というニュアンスが強くなっています。その証拠に、施設内にはケアマネジャー配置の義務付けやレクリエーションルームの設置など、生活の場よりの構造になっています。ただ個人的な意見としては、介護と医療のよいところを取ろうとして中途半端な体制になってしまったという印象があります。トレードオフではないですが、上質と手軽を両立させようとすると結局は中途半端になってしまうということです。医師、看護師、薬剤師、放射線技師がおり、医療的ケアは医療保険で受けられ、介護サービスは介護保険が適用となりますが、「要介護4」以上ではないと、人件費とのバランスが取れないという現場の声を聞いたこともあります。そう考えると、「生活の場」というよりも、「療養の場」に近いものになってしまうのではないでしょうか。
⑥地域包括ケア病棟・病床
「地域包括ケア病棟・病床」とは、患者さんの在宅復帰を目的として設立された制度です。回復期リハビリテーション病院・病棟との違いは主に三つあります。
一つ目は入院期間です。回復期リハビリテーション病院では、疾病ごとに入院期間の制限があって最長180日というのは前述で説明した通りですが、地域包括ケア病棟・病床においては、60日が限度となっています。
二つ目は、疾病に制限がないということ。回復期リハビリテーション病院では対象となる疾病が決まっていますが、地域包括ケア病棟・病床には基本的に医師が必要と認めれば利用できるのです。地域包括ケア「病棟・病床」という名称の通り、前述で説明した急性期病院・回復期リハビリテーション病院の一部を病棟ごとや病床ごとに転換できるので、入院ベッドが埋まらない病院の経営戦略として有効活用されることもあります。日本では増えすぎた急性期の病床を減らす在宅復帰、つまり「在宅で生活することに重点をおいた施策」で医療費を削減する方向へ動いてますので、この地域包括ケア病棟・病床があからさまに増えています。
三つ目は自宅で療養している患者さんでも医師の診断があれば入院できることです。地域包括ケア病棟・病床には算定されるいくつかの段階があるため、より高い医療収入を得ようとすると、自宅からの入院患者割合がある程度なければいけないなどの基準が明確になってきます。普段、病院経営に関わらない方にとっては、中々難しい制度だと思います。地域包括ケア病棟・病床の有効活用は、病院経営にとって重要な施策ではありますが、経営努力を怠った病院のベッドの穴埋め施策として用いられるのは、本来の目的とは違うのではと個人的には考えています。
実は、これまで説明した「病院の種類」を表す名称の一部、「高度急性期」「急性期」「回復期」などの言葉は、その病院が「どんな性質の病院か」というだけでなく、その病院の一部に「どんな性質の病棟や病床があるか」を表してもいます。〇〇大学病院の中に、高度急性期病棟や急性期病棟があり、××総合病院の中には急性期病棟があり回復期リハビリテーション病棟、そして地域包括ケア病棟または病床があるのです。
どうしてこのようになっているのか、ホテルを例にして説明してみます。全国でチェーン展開している会社の5階建てのホテルがあるとします。100名が宿泊できます。1階はフロントや温泉、2階以上が客室フロアで階ごとに客層を分けています。都内にあるこのホテルでは、5階は富裕層向け、4階はファミリー向け、3階はビジネスマン向け、2階はシニア向けとし、各階25名ずつ宿泊できる構成になっています。さて、観光地として有名な地域でも、同じような構成でよいでしょうか。観光地にビジネスマン向けのフロアは必用でしょうか。
このように、その地域の年齢人口別、人口の種類に応じてホテルがその形態を変えるのと同じで、病院も地域の事情に応じて経営形態を変えているのです。もっというならば、「在宅へと舵を切った」国の指針が診療報酬に反映しているため、変えるしかないといったところでしょうか。訪問医療マッサージとして、そこまで深く知る必要はないのかもしれませんが、医療と介護の連携を行う上でコミュニケーションは必要不可欠です。そのためには、連携する相手の背景を知ることが重要となります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
