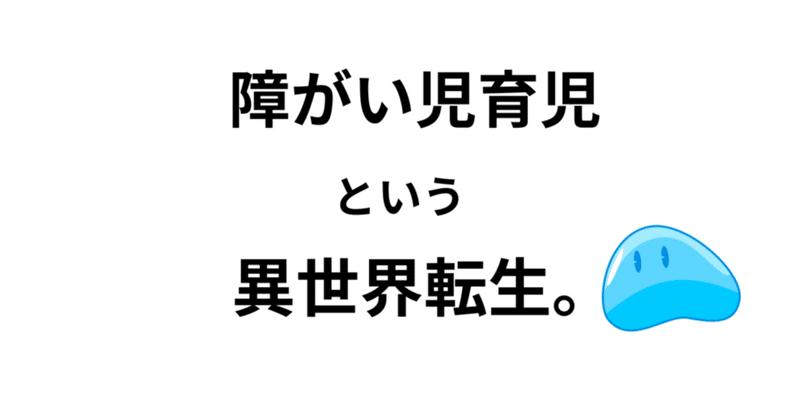
障がい児育児という異世界転生。
ある日、仕事から帰る途中にトラックと衝突して────。
障がい児育児はまさに歩いてたらトラックにぶつかってヨーロッパ風の世界に飛ばされてしまったり、道に穴が空いていて、穴から別の世界に飛ばされたりするアレとよく似ている。
転生後の「まさか」を経験し、普通に過ごしている中でご飯が美味しくなかったり、電車や文明機器がなかったりして「違う世界に来てしまったのだ」ということを理解していく、そんなかんじだ。
子どもを育児していく中で「あれ?このモノってどこで買うの?この世界の人は普通に買ってるがネットで買えないの?」「福祉機器展って何それ?企業向けじゃないの?普通にいけるやつ?」「え、手続きスタンプラリーすぎるけど、おつかいクエストかな?」という場面に遭遇し、料理系の異世界転生のように「美味しいパンが食べたいよ〜〜!(もっと便利にして〜)」と泣き出し、現世の知識を使って壁を乗り越えながらなんとかしていく。
それが私たちの置かれた現状とファミケアの歩んでいる最中の道なのである。
現世の異世界、障がい児家族領域
障がい児育児という領域でスタートアップをする私たちファミケアチームは面白いポジションで、現世の住人(障がい児を育てておらず、周りの環境にもいない人)とも異世界の住人(障がい児育児をしていたり周りにいる人)とも仕事の話する。
現世の住人に事業の説明をすると「あれ、そんなの普通に今までなかったの?そんな環境だったんだ!」「今日はじめて知った」という会話になり
異世界の住人からは「画期的だ!」「こんなの待ってた!」「実現できるの?」と言われる。
実際は同じ2024年を生きている人に話しているので、ここまで価値観が違うのってすごいなと思っている。
実際のところ、異世界住人の生活(筆者も含めて)は美味しいパンなかったり、調理器具なかったりと現世レベルの生活インフラが整ってない状況だ。
そして、そこに住んでいるが故に育児経験が長くなればなるほど、異世界の違和感がなくなっていく。子育て前は保育園というところは週5日、働ける最低限預けられる場所というイメージを持っていたはずなのに「まあ保育園は入れない人もいるから、短時間だけでもいい方だよね」(相変わらず親の就労はできない状況)という場所に変わってしまうのは、ざらにあることだ。
2024年のレベル感では
現世の人:「役所の申請オンライン化して〜」
異世界人:「窓口じゃなくて、せめて郵送対応も受け入れて〜」
という様子が現在地なんじゃないかなぁと日々全国の様々な障がい児育児中の家族、障がい児じゃない子どもの育児中の家族を見て思う。
支援不足ではなく遅れているという事実
こういう話をすると行き着きやすい着地点が「支援が足りていない」ではないかと思う。支援でイメージされるボランティア活動やSDGsを促進しましょうというのは「障がい」に対して誰もがイメージしやすい活動の1つだと思う。
ただし、よく思い出してほしい。私たちは「異世界転生」していて「発展していない世界」に来ているのである。やるべきことは現世の知識を使って、異世界を発展させるのが王道なのだ。
(ある技術で発展できるにも関わらず)遅れているだけ、という事実は障がい児家族の環境を捉え、良くしていく上で大事なポイントだと思う。伸び幅がある、ただし何もしなければもちろん遅れたまま、衰退すらし得る状況もある。(補足をしておくと、疾患や障がいは定型発達と比較して大変なことも多く、いまを日々支えてくれる支援自体は必要で大切なことだ。日々支援者さん方には頭が上がらない)
ファミケアが取り組むIT領域においても現状、メディアやコミュニティアプリを運営しているが、このモデルがスタートアップに登場して流行したのは2010年前半であり、今は世の中の一般的なビジネスとして当たり前のようにみんなが活用して経済も回っている。つまり、ファミケアが提供しているものが「新しい」と感じるこの領域ではITサービスでも10〜15年くらい遅れている。(この階段を急激に駆け上って2024年をさらに飛び越えるために、めちゃくちゃ頑張っている)
この遅れの原因は技術ではなく、当事者の数やインサイトが全国単位で正確に定量化・言語化しきれていないことから、障がい児を取り巻く各分野で事業展開がしにくいことにあるのではないかと思っている。あとは、社会に出てこない(すごく率直にいうと24時間のうちの選択肢が家になりがちで現状説明もしない)が故の実態数よりも障がい児が”少ない”と捉えられがちな課題もある。
ということで、障がい児の社会課題を解決するために「サービスを生み出し、ファミケアが領域No1になることで生活インフラを作ること」を頑張っている。
ソーシャルグッドな領域をしていると「株式会社なんですね」と言われるほどに障がい児家族にモノやサービスを売るイメージが全然つかないのが一般的なのを感じる。そうなった結果、便利なモノやサービスが届かなくなっているのが私たちだ。(完全に余談だが、私は息子を通して障がい児領域に携わってはじめて、”企業にユーザーとして扱ってもらえるありがたさ”があることを感じた。なんでもレコメンドして爆速で改良してもらえる現代はすごい)
だから、私たちは障がい児家族のユーザーさんに世の中のモノやサービスを届けてどんどん利用したり、買ってもらうことで生活を便利に改善してもらい、企業の方には売上を立てて、価格の適正化やより良い製品の開発・サービスの開発をしてもらう。そしてデータ化、可視化をすることでこのドメインの経済の流通を活発にしていく。(「ちょっと広告が最近多くて邪魔だな」なんて感じてきてもらえたら正解なのかもしれない)
NPO法人や行政の方、地域密着で事業を展開されている方もこのレガシーを埋めるべく頑張ってくれてるので、我々はITと大きな経済の分野での発展を担うべく頑張ってまいります。
ということで、最近特にいろんなバックグラウンドの方と「障がい児家族」に関してお話しする機会が増えていて、置かれている状況の特殊性を強く感じていたために、言語化してみました。こんな世界もあるんだな、と思ってもらえたら嬉しいです。
面白そう!新しい発見!など何か感じてくださった皆様、企業の方でも個人の方でも、お持ちの資源やナレッジを活用できる可能性があります。事業者やプレイヤーが圧倒的に足りていません。インサイトやデリバリーは得意分野なので、子ども向けでも親向けでも、何かやってみたい、というレベルでもぜひ連絡いただけたら嬉しいです。
IT企業出身の当事者ご家族の方も、ぜひ一緒にお取り組みできたら嬉しいです。面白いことにメガメンチャー出身の当事者家族が集まっていますので、想いに共感いただける方がいたらテクノロジーで社会課題を解決しましょう!
ファミケアポータルサイト:https://famicare.jp/
ファミケアInstagram:https://www.instagram.com/fami_care/
XのDM解放してます⇨@sekinyams2
サポートはお気持ちだと思って受け取ります🙌小娘よ、頑張れと思っていただける方がいらっしゃったら応援してください、大好きなおやつを買います(*ˊᵕˋ*)੭ ੈ
