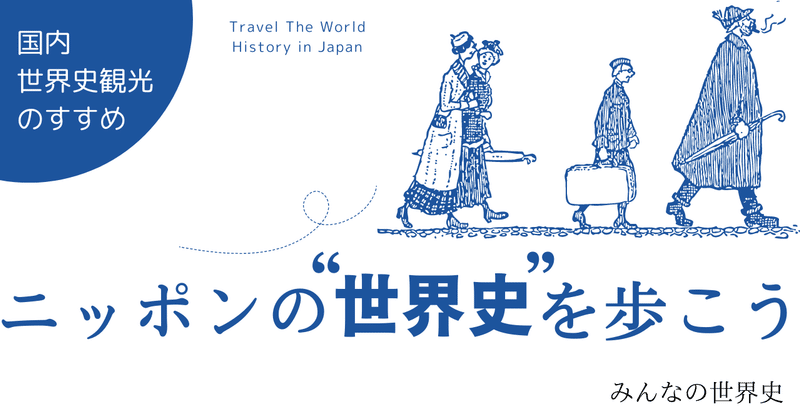
【国内 "世界史" 観光500選】 記録的円安なんて吹き飛ばし、ニッポンの「世界史」を歩こう!
コロナ禍も明け、海外に出かけようとせっかく思い立ったところにふりかかる記録的円安…。これから夏にかけてどのように推移するかは不透明ではありますが、二の足を踏んでいる方も多いのではないでしょうか。
では、日本国内で海外を味わうことはできないのでしょうか?
いえ、そんなことはありません!
「世界史」をキーワードに掲げて視点を変えてみれば、日本全国津々浦々、さまざまなところに海外の人や出来事とのつながりは潜んでいます
いや、「世界史」と「海外」は別物じゃないか。
——その通りです。
しかも、「まるで海外にいるような気分を味わえる」……というわけではありません。向こうから飛び込んでくる新鮮で華々しい光景もない。
見た目はいかにも地味なスポットがほとんどです。
だからこそ必要のなのは、「情報」と「想像力」。
「世界史」をキーワードにその土地を眺めてみれば、あなたと過去の世界、地域と海外の意外なつながりが、時空を超えて浮かび上がってくるかも——。
***
以下にリストアップしたのは、私が独断と偏見で選んだ国内 "世界史" 観光スポット約500選。
世界史的な出来事や人物と、なんらかの形で関わりのある施設や場所を選びました。
悩ましいのは世界史と日本史の切り分けです。何を日本史とし、何を世界史のトピックとして選ぶかということ自体、すでにナショナルな視線が入り込んでいます。ここではばっさりと、現在の日本の領域の外部と何らかの形での関わりに注目することとしています。
採録に際しては、以下のようなキーワードを念頭に、史跡、景勝地、建造物、博物館・文書館・ 資料館・記念館といった施設、コレクション、銅像や記念碑などのモニュメント等を集めました。
具体的には、前近代においては大陸との交流(国や朝鮮半島との交流:遣唐使や渤海使、交易や倭寇などの海賊、蒙古襲来、仏僧の交流など)、近世以降はいわゆる南蛮貿易や朱印船貿易、宣教師の伝道活動、オランダ東インド会社などを通じた蘭学・洋学の吸収、「四つの口」を通した外交・通商関係、幕末にかけての漂流民や外国船の来航、開国以降の外交と通商、居留地における交流、お雇い外国人、幕末以来の留学生や遣欧使節団、外国文化の伝播、近代化産業遺産、海外への移民(中南米や南洋、満洲など)、日清・日露戦争、第一次世界大戦における捕虜、外国における文化人などの訪日・親善活動、スポーツや文化を通した草の根の市民間の親善活動、世界史的事件にゆかりのある地といった項目です。
たとえば「噴煙が地球の平均気温を低下させ、フランス革命の遠因となった」という理由から浅間山を、「"海上の道"とのつながりが推測される」という理由から縄文時代の遺跡をカウントすることも可能ではあるわけですが、このリストではなるべく直接的な関係のある史跡を選んでいます。
ここではなかでも一般になるべく扱われることが多くないものを中心に集めました。たとえば、総合的な博物館や美術館、戦前の軍事遺構(竹内正浩氏の著作など)やダークツーリズム関連、エスニック料理店(「外国料理で世界一周」系の書籍、サイトなど)、擬洋風建築(「洋館探訪」)、墓所(日本のお墓)などについては、すでに優れたガイドとなる書籍やウェブサイトがありますので、ここで網羅するのはやめておきました。とりわけ近代以降の戦争は、対外戦争である以上かならず海外とつながりがあるわけで、なんでもありになってしまうのである程度抑え目に収録してあります。
都道府県によっては、あまり採録できていないところもあります。おおまかにいって前近代は大陸とのアクセスの容易な東シナ海や日本海に近いところ、近代以降は開港場や太平洋岸沿岸や大都市圏が多くなる傾向があります。四国と、中国地方の日本海側、東北地方はもう少し掘り起こしたいところです。
あまり現代に近い出来事に関する場所をピックアップしてしまうと「社会科見学」的になってしまうため、これも除きました。
世界史の教科書に載っているような画家や彫刻家の作品のうち日本でも見られるもの(ただし常設展示とは限りません)は、いくつか含めています。
志摩スペイン村(三重県)やポーセリンパーク(佐賀県)など、人工的につくられたスポットも含めました。
世界文化遺産のうち「近代化遺産」に指定されているものや経済産業省の指定する「近代化産業遺産」は、ヨーロッパにはじまる産業革命で生まれた技術が、はじめて本格的に非西洋へ伝播・移転したことを示すものですが、ちょっと多めになってしまったかもしれません。
なお、宗教施設や教育機関も含まれています。必要に応じて必ず先方の都合や最新情報をうかがい、マナーを遵守するようにしてください(当サイトは責任を負いません)。
***
もちろん私自身もまだ行ったことのないところばかり。
最終目的地としてこれらを目指すということはないでしょうが、知らなければ素通りしてしまうところも、由緒を知っているだけで見え方はだいぶ変わってくるはずです。
お目当ての土地に行かれて、めぼしいところはひと通り回った後で手持ち無沙汰なスキマ時間ができた際には、これを参考にぜひ"寄り道"してみてはいかがでしょうか。
国内にも "世界" はあります。
※ 必要に応じて随時追記します。
***
北海道:高田屋嘉兵衛をはじめロシア関連が豊富
天使の聖母トラピスチヌ修道院 シトー派修道会
歴史と自然の資料館 ラクスマンなどの展示
北海道立北方民族博物館 アイヌ
幌内炭鉱 近代化産業遺産三笠ジオパーク
〒068-2100 北海道三笠市幌内本沢町068 2100
カール・レイモン レイモンハウス 元町店 ハム、ソーセージを日本に紹介。
〒040-0054 北海道函館市元町30−3 函館カールレイモン
徳山大神宮 ロシア海軍ディアナ号艦長ワシーリ・ミハイロヴィチ・ゴロヴニン少佐が幽閉された記念碑がある。
〒049-1513 北海道松前郡松前町神明66
旧日本郵船小樽支店 日露戦争
〒047-0031 北海道小樽市色内3丁目7−8
高田屋嘉兵衛銅像 高田屋嘉兵衛の銅像は北海道に複数ある。
〒040-0043 北海道函館市宝来町
高田屋嘉兵衛銅像 根室のほうはこちら。
〒087-0055 北海道根室市琴平町1丁目
箱館高田屋嘉兵衛資料館 高田屋嘉兵衛
北海道函館市末広町13−22
開陽丸記念館(クルップ砲)オランダで建造され徳川幕府の旗艦となった 軍艦海開陽丸。クルップ砲が展示されている。
「ギリシア正教会」として世界史教科書に登場するキリスト教の宗派は、日本では「日本正教会(ハリストス正教会)」と呼ばれます。
教会は日本各地に点在しています(以下のウェブサイトを参照)。
日本にロシアから正教会が伝えられたのは、19世紀の後半のことです。 文久元年(1861年)、日本への伝道を決意した聖ニコライが函館にやってきました。(…)ニコライは明治5年頃、東京に伝道の本拠地を移し、正教会の伝道を熱心に行いました。教勢はめざましく発展し日本全国に正教会の種がまかれていきました。明治18年には信徒数はすでに一万二千人を越えていました。
1891(明治24)年、東京の神田駿河台にビザンチン建築様式の「復活大聖堂」が建立され、ニコライの名に因んで「ニコライ堂」と呼ばれるようになりました。当時としては驚くべき大きさで荘厳なその姿は多くの人々の関心を引き寄せました。
(…)日本正教会は明治の後半から大正、昭和にかけて苦難の時代を迎えます。 まず日露戦争(1904-05)によって日本とロシアの関係が悪化し、正教会が白眼視されたことがあげられます。そして偉大なる師ニコライが永眠します(1912)。
函館ハリストス正教会正教会
函館市元町3−13
地元では「ガンガン寺」の愛称で親しまれている。
苫小牧市 科学センター
〒053-0018 北海道苫小牧市旭町3丁目1−12
宇宙ステーション「ミール」が展示されている。
氷雪の門 樺太島民慰霊碑 第二次世界大戦
〒097-0000 北海道稚内市稚内村ヤムワッカナイ
銭屋五兵衛貿易の地 ロシア貿易
〒097-1111 北海道礼文郡礼文町船泊村2−2
大鵬相撲記念館
〒088-3465 北海道川上郡弟子屈町川湯温泉2丁目1−20
http://www.masyuko.or.jp/sumo/
大鵬は父がウクライナ系ロシア人。
北鎮記念館
〒070-0902 北海道旭川市春光町 国有無番地
ステッセルのピアノが展示されている。
公式サイト:https://www.mod.go.jp/gsdf/nae/2d/hokutin2/top.html
中川五郎治顕彰の碑
中川五郎治(1768−1848)。千島択捉(えとろふ)島の会所番人で、文化4年ロシア船に捕らえられ9年帰国。シベリア滞在中に牛痘接種法を学び、日本にもちかえった。
〒049-1511 北海道松前郡松前町松城
五島軒 ロシア料理
〒040-0053 北海道函館市末広町4−5
樺太引揚三船殉難 平和の碑 引揚げ
〒077-0048 北海道留萌市大町2丁目
近くにこちらの碑もある。
ラクスマンのモニュメント(ときわ台公園)ラクスマン
〒087-0042 北海道根室市清隆町3丁目3
インディギルカ号遭難者慰霊碑
旧ソビエト連邦の貨客船で、1939年12月12日の未明に北海道猿払村浜鬼志別沖合で座礁・沈没した船。この犠牲者を弔う碑だ。
〒098-6222 北海道宗谷郡猿払村浜鬼志別214−7
スタルヒン球場
スタルヒン(1916−1957)は、昭和時代のプロ野球選手。ロシア革命に追われ来日し、中学3年で全日本チームの投手となり、昭和11年に巨人軍に入団した。戦後は他球団で活躍し、昭和30年に引退(通算303勝(完封83))。だが昭和32年に若くして交通事故死した。
彼をはじめとし、ロシア革命の際に日本に亡命した白系ロシア人(多くがタタール人→東京都の東京ジャーミイ、兵庫県の神戸モスクを参照)に関する史跡は、日本各地に残されている。
〒070-0901 北海道旭川市花咲町3丁目 花咲スポーツ公園内
敷地内にスタルヒン像がある。
ホーレス・ケプロン之像 北海道開拓旧ロシア領事館(函館市 青年センター)
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西10丁目
尼港殉難者追悼碑 尼港事件
〒047-0041 北海道小樽市末広町37−27
ほかにも複数存在する。
レルヒ中佐顕彰像 スキー
〒071-1562 北海道上川郡東神楽町町東2線13号
こちらにもある。
〒044-0025 北海道虻田郡倶知安町 南11条東1丁目34番地2外
北海道スキー発祥之地碑 スキー
〒070-0000 北海道旭川市近文6線
キノルド資料館 教育
〒001-0016 北海道札幌市北区北16条西2丁目1 ギノルド資料館
豊平館 西洋館
〒064-0931 北海道札幌市中央区中島公園1−20 1F
ビート資料館
てん菜や糖業に関する歴史と技術を、映像やパネルを用いて紹介する資料館。旧帯広製糖所を縮尺70分の1に再現した模型も展示している。
〒080-0831 北海道帯広市稲田南8線西14
サッポロビール博物館
元工場の建物を利用した入場無料のビール博物館。館内では歴史資料を展示。見学ツアーがあり、有料で試飲もできる。近代化産業遺産(北海道における近代農業、食品加工業などの発展の歩みを物語る近代化産業遺産群)
〒065-8633 北海道札幌市東区北7条東9丁目1−1
エドウィン・ダン記念館
〒005-0015 北海道札幌市南区真駒内泉町1丁目6
近代化産業遺産(北海道における近代農業、食品加工業などの発展の歩みを物語る近代化産業遺産群)
青森県:「キリストの墓」で村おこし
八甲田山雪中行軍遭難資料館 日露戦争
〒030-0943 青森県青森市幸畑阿部野163−4
多賀丸漂流記念碑(しおさい公園) 漂流民、ロシア、トラペズニコフ
〒039-4711 青森県下北郡佐井村佐井大佐井112
秋田雨雀記念館 ソ連
高良神社
ラクスマンの開国を描いた絵馬があります。
〒039-1702 青森県三戸郡五戸町倉石中市田茂平66
新郷村キリストの墓
〒039-1801 青森県三戸郡新郷村戸来野月33−1
岩手県:キリシタン史跡から鉱山まで
大籠キリシタン殉教公園
〒029-3522 岩手県一関市藤沢町大籠右名沢28−7
後藤新平記念館
後藤新平(1857-1929)は、日清戦争の際、陸軍の検疫事務を担当し、その才能がみとめられ、1898年に台湾総督府民政局長となり、治安維持と植民地統治に辣腕をふるう。さらに1906年には満鉄(→東京都)初代総裁に就き経営を刷新。その後、1908年から閣僚となり、1920年には東京市長に。関東大震災後の東京復興計画の立案にあたった。
記念館は時期別の展示となっており、台湾民政長官・満鉄総裁期の展示もそれぞれ見ることができる。
〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町4丁目1
オランダ島
オランダ人の漂着
〒028-1371 岩手県下閉伊郡山田町船越
久慈琥珀(株) 博物館リトアニア館
〒028-0071 岩手県久慈市小久慈町第19地割42−3
橋野鉄鉱山
近代化産業遺産、明治日本の産業革命遺産
〒026-0411 岩手県釜石市橋野町第2地割15
宮城県:メキシコとの交流を築いた支倉常長
支倉常長像
大航海時代
魯迅の碑(仙台市博物館)
近くに林子平の碑もある。
李登輝俳句碑
宮城県松島町松島 瑞嚴寺與圓通院中間
李登輝お手植えの樹は塩釜神社にある。
佐藤三千夫記念碑
シベリア出兵に反対した人物。
〒987-0702 宮城県登米市登米町寺池道場80
桂林山 禅昌寺
1804年ロシア使節レザーノフに連れられて日本に帰還した米沢屋平之丞所有廻船若宮丸の「若宮丸供養碑」がある。
〒986-0873 宮城県石巻市山下町1丁目4−8
ベーリング像
ベーリング(1681―1741)はデンマーク生まれのロシアの探検家で、カムチャツカ半島やベーリング海峡を発見した。彼自身はこの網地島を訪れていない。訪れたのはベーリングの部下で、デンマーク出身のシュパンベルグの分遣隊の指揮官だった。1739年に網地島の沖に錨泊し、住民と銀貨と野菜や魚、タバコなどを交換すると立ち去った。
この像の序幕に際しては、ロシアではなくデンマーク大使が出席している。
〒986-2526 宮城県石巻市網地浜網地 網地港
秋田県:長崎から輸出された阿仁の銅
鹿角市 先人顕彰館
これはちょっとマニアックだが、東洋史学の世界的権威である内藤湖南の家学と学統資料。幼少年時代の教材と自作の漢詩、隋唐の書法を極めた遺墨と晩棲恭仁山荘の模型。
〒018-5334 秋田県鹿角市十和田毛馬内柏崎3−2
尾去沢鉱山
「おさりざわこうざん」と読む。銅が最初に発見されたのは1666年(寛文6)と伝えられる。近代化産業遺産(有数の金属供給源として近代化に貢献した東北地方の鉱業の歩みを物語る近代化産業遺産群)
〒018-5202 秋田県鹿角市尾去沢獅子沢13−5
鹿角市鉱山歴史館がある。
夕陽の見える日露友好公園
1932年に遭難・漂着し死亡したニコライ・バクレンコ少年の霊を慰める碑。
〒015-0035 秋田県由利本荘市親川深沢
スタルヒンの墓
北海道のところに記載したスタルヒンの墓所。若くして亡くなった。
〒013-0205 秋田県横手市雄物川町今宿今宿85
北鹿ハリストス正教会・生神女福音聖堂 正教会
阿仁銅山 長崎輸出銅
〒018-4613 秋田県北秋田市阿仁銀山下新町41−23
阿仁鉱山は1309年に金山として開発されたと言われており、その後、銀、銅を産出するようになりました。
1716年(享保元年)には産銅日本一となり、別子銅山、尾去沢鉱山と共に日本三大銅山のひとつに数えられ、
阿仁鉱山の名は全国的にもよく知られるようになりました。阿仁鉱山といいましてもひとつの鉱山ではなく、小沢、真木沢、三枚、一の又、二の又、萱草の6銅山(六ヶ山)と向山金銀山、太良鉱山、加護山製錬所から成っています。江戸時代においては秋田藩の直営として、阿仁の銅は貨幣原料や長崎の出島から海外への輸出品として重要視され、多いときには幕府御用銅のおよそ5割が阿仁鉱山から産出されました。
山形県:イザベラ・バードを偲ぶ史跡も
カトリック鶴岡教会
白亜の美しい外観。
〒997-0035 山形県鶴岡市馬場町7−19
ドガ「踊り子たち、ピンクと緑」:山形美術館
〒990-0046 山形県山形市大手町1−63
フェンガー記念館(山形県立新庄神室産業高等学校)
デンマーク式農業を紹介したフェンガーの記念館。
〒996-0051 山形県新庄市松本370
※事前に連絡し、時間・人数などを調整する必要あり。
氏は、農林省が、北海道にならい積雪寒冷地に適した酪農併用の経営(酪農経営)を普及させることをねらい、山形県指導のために夫人(フリーダー・フェンガー)とともにデンマークから招聘した農業技術者である。昭和26年から29年9月まで、当時の新庄原種農場(農業試験場最北支場)に隣接した新庄農業高校の地にモデル農場として、デンマーク農法指導農場をつくり、畜舎、住宅を建て、指導にあたった(全圃場面積4.3ha)。その住宅が、本校新庄神室産業にあるフェンガー記念館である。なお、氏の多大な功績に因んで賞も創設されている。氏は、1894年(明治27年)生まれ、コパンハーゲン国立農業獣医大学卒業後、農業経営や教師をし、従軍も経験している。大正1313年から昭和3年まで招かれて北海道琴似での指導実績がある。
最上徳内記念館
蝦夷地調査隊
〒995-0035 山形県村山市中央1丁目2−12
最上徳内(1755-1836)は、江戸時代後期に活躍した村山市楯岡出身の北方探検家です。江戸幕府の蝦夷地検分隊の一員として蝦夷地に赴いたことをきっかけに、その後8回に渡り蝦夷地での調査を行いました。その範囲は、エトロフ島などの北方諸島やカラフトなど広範囲に及び、その業績は探検家として高い評価を得ています。
最上徳内記念館では、この偉大な業績を後世に伝えていくため、徳内が使用した測量器や描いた北方の地図、エトロフ島に建立した標柱(複製)などの資料を展示しています。
イザベラ・バード記念碑(金山)
イザベラ・バード
〒999-5402 山形県最上郡金山町金山
なお、ハイジアパーク南陽(南陽市)にイザベラ・バードに関する展示があったが、ハイジアパーク南陽は現在改修閉業中。
福島県:白虎隊最後の地にローマの碑?
ローマ市寄贈の碑 ムッソリーニ
〒965-0003 福島県会津若松市一箕町大字八幡大和山乙
松江豊寿紹介板
松江豊寿(1872−1956)は大正3年に徳島俘虜(ふりょ)収容所長となり同6年板東俘虜収容所長。人道主義の精神で第一次大戦でのドイツ人捕虜を待遇したことで知られる(→徳島県も参照)。
〒965-0042 福島県会津若松市大町1丁目10
ファン・ドールンの銅像
1878(明治11)年大久保内務卿が猪苗代湖疏水開鑿および原野開墾の件を、太政官に建議し、内務省御雇長工師としてファン・ドールンが来郡(11月1日~6日)。建設に対して指導をした。2001年には駐日オランダ国王特命全権公使ヤン・ヘイツマ氏が来郡している。
〒965-0201 福島県会津若松市湊町大字赤井戸ノ口30
茨城県:朱舜水から模擬原爆まで多彩な史跡
水戸市 内原郷土史義勇軍資料館 満蒙開拓青少年義勇軍
〒319-0315 茨城県水戸市内原町1497−16 内原郷土史義勇軍資料館
朱舜水像(舜水祠堂跡) 朱舜水
なお、朱舜水は水戸光圀に中国の麺を紹介し、これを「ラーメン発祥」とすることがある。
〒310-0061 茨城県水戸市北見町8−8
朱舜水の墓 朱舜水
〒313-0003 茨城県常陸太田市瑞龍町 德川家墓所
白凛居
日本最初のイコン画家・山下りんの作品・遺品・資料などが収蔵・展示されている施設。山下りん(1857−1939)はハリストス正教に入信し、明治13年イコン(聖像画)をまなぶためロシアに留学。日本初のイコン画家として、東京神田のニコライ堂ほか各地の正教会教会堂に多数の作品をのこしている。山下の代表作は「十二大祭図」。

〒309-1611 茨城県笠間市笠間1510
イコンというのは、こういう絵画。

予科練記念館
この飛行場にツェペリン伯号、リンドバーグが飛来している。
〒300-0302 茨城県稲敷郡阿見町廻戸5−1
尼港殉難者記念碑 尼港事件
〒310-0055 茨城県水戸市袴塚3丁目4−20
牛久シャトー
近代化産業遺産
〒300-1234 茨城県牛久市中央3丁目20−1
那珂湊反射炉跡 近代化産業遺産
「反射炉」は金属の製錬や溶融をおこなうための施設で、日本では外国船の来航に備える大砲を鋳造するため、江戸末期に幕府や各藩が「パドル炉」とよばれる反射炉を製鋼用に建設した。江川英龍 (ひでたつ) (太郎左衛門)が伊豆韮山 (にらやま) に1858年に建設した反射炉がもっとも有名だが、全国各地に現存する(→鹿児島県、山口県、静岡県などを参照)。
〒311-1223 茨城県ひたちなか市栄町1丁目10
古河藩家老・鷹見泉石記念館
日本初の世界部分地図を作成した鷹見泉石(1785-1858)は下総古河 (しもうさこが) 藩士。オランダ人と交流し『新訳和蘭 (オランダ) 国全図』を作成した。
〒306-0033 茨城県古河市中央町3丁目11−2
藤田東湖像
藤田東湖(1806-55)は、江戸後期・水戸学の代表的人物。この地に「眼下東に窮まる亜墨州」と詠んだ句碑がある。
〒311-1301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町
日立製作所山手工場
パンプキン爆弾(模擬原爆)
〒317-0056 茨城県日立市白銀町1丁目1−1
フレーベルの恩物(土浦市立博物館)
〒300-0043 茨城県土浦市中央1丁目15−18
日朝親善記念碑
「一九五九年(昭和二十四年)一二月 在日朝鮮人を乗せた帰国第一船が、新潟港から朝鮮民主主義人民共和国に向けて出港」とある。
〒310-0851 茨城県水戸市千波町, 36.3715476309956, 140.4629060536164
間宮林蔵記念館 蝦夷地探検
〒300-2335 茨城県つくばみらい市上平柳64
この記念館は、18世紀後半にこの地に生まれ育ち、江戸に出て、北方で活躍した大探検家・測量家である「間宮林蔵」を紹介するために(旧)伊奈町が顕彰事業の一つとして建設したものです。 館内の展示は、間宮林蔵に関係するもの及び彼の生きた時代背景などで構成され、時代に沿った紹介をしています。全国各地から収集した数少ない資料のほか、現子孫宅に伝わる遺品、林蔵にまつわる史跡などをおりまぜながらテーマごとに、展示しています。
わすれじ平和の碑
風船爆弾の放流地跡。
〒319-1701 茨城県北茨城市平潟町, 36.84238350923215, 140.79704299724898
栃木県:三浦按針ゆかりのエラスムス像
寛方・タゴール平和記念公園(さくら市氏家)
タゴール
〒329-1311 栃木県さくら市氏家, 36.68095949165364, 139.9675039806141
青木周蔵別邸
繊維工業
〒325-0103 栃木県那須塩原市青木27
旧木村輸出織物工場
近代化
〒376-0004 群馬県桐生市小梅町1−14
エラスムス像の資料館
ウィリアム・アダムズの乗っていたリーフデ号(→大分県)の船尾にとりつけられていたエラスムス像が、縁あって佐野市の寺院にながれつき、のち昭和年間になって「エラスムス」であることが判明したという、いわくつきの品。
〒327-0042 栃木県佐野市上羽田町
この像は慶長5年(1600)太平洋上で暴風雨にあい、大分県に漂着したオランダ船リーフデ号の船尾に取りつけられていたものです。リーフデ号は「エラスムス号」を改名したもので、この船には徳川家康の外交顧問になったウイリアム・アダムス(三浦按針(みうらあんじん))も乗船していました。
この像が竜江院に伝来した理由は、当時幕府の御持(おもち)筒頭(つつかしら)をしていた旗本牧野成里(しげさと)の手に渡り、彼の知行地羽田村の菩提寺竜江院に牧野家ゆかりの品々と共に寄進されたためといわれています。それ以来、この像は中国の造船の創造者とされる貨狄(かてき)像として、寺の山門南側堂宇に安置されていました。この像の姿から寺近辺に「小豆とぎ婆々」の民話が生まれ、今日に至っています。
昭和5年、丸山瓦全の調査により、この貨狄像はオランダの啓蒙思想家エラスムス(応仁元年~天文5年)の像であることがわかりました。そして、オランダからの譲渡の希望を断り、昭和5年、国宝に指定されました(法改正により、昭和25年に重要文化財指定)。右手に垂れ下がっている巻物に「ER(AS)MVSR(OT)TE(RDA)M1598」の文字が認められます。オランダ最古の木彫になります。
なお、佐野市郷土博物館にて、当文化財の複製品が常設展示されています。
足尾銅山
言わずと知れた銅山。近代化産業遺産(銅輸出などによる近代化への貢献と公害対策への取組みに見る足尾銅山の歩みを物語る近代化産業遺産群)に指定されている。
〒321-1514 栃木県日光市足尾町通洞9−2
旧下野煉化製造会社(シモレン)
〒329-0115 栃木県下都賀郡野木町野木3324−1
近代化産業遺産(建造物の近代化に貢献した赤煉瓦生産などの歩みを物語る近代化産業遺産群)
旧下野煉化製造会社煉瓦窯(通称、野木町煉瓦窯)はホフマン式の煉瓦窯で、明治23年(1890)から昭和46年(1971)までの間に多くの赤煉瓦を生産し、日本の近代化に貢献しました。
この煉瓦窯には16の窯があり、1つの窯で1回に約14,000本、全ての窯を連続して使用した場合には約22万本赤煉瓦を生産することが可能でした。また、この煉瓦窯は創業時から約130年経過した現在においても、ほぼ原型のままで存在しており、建造物として価値が高いものです。昭和54年(1979)に国の重要文化財に指定され、さらに平成19年(2007)には、「近代化産業遺産群」の一つに選定されました。
慈覚大師円仁誕生の地 円仁
〒329-4308 栃木県栃木市岩舟町下津原1198
群馬県:近代化を支えた絹織物産業
ベルツ碑 お雇い外国人
〒240-0112 神奈川県三浦郡葉山町堀内1025
ルノワール「読書するふたり」群馬県立近代美術館 ルノワール
桐生織物記念館
優れた生産体制等により支えられる両毛地域の絹織物業の歩みを物語る近代化産業遺産群にしていされている。
〒376-0044 群馬県桐生市永楽町6−6
1300年余の伝統を誇る桐生織物産地。長い歴史の中、近代には昭和恐慌からもいち早く立ち直り、1935年(昭和10年)前後に隆盛期を迎えました。桐生織物記念館は当時の桐生織物同業組合(現桐生織物協同組合)の事務所として、34年(同9年)10月に建てられました。
埼玉県:各地にのこされた渡来人の足跡
タゴール胸像 タゴール
〒355-0062 埼玉県東松山市西本宿,36.00295548041259, 139.38955873825446
将軍山古墳(埼玉古墳群)
騎馬の習慣を示す馬冑が出土。
〒361-0025 埼玉県行田市埼玉4834
将軍山古墳の横穴式石室から出土した副葬品。馬の頭部を守る鉄製の冑。馬冑は朝鮮半島南部、伽耶地域に出土例が多く、高句麗古墳壁画にも多く描かれている。日本国内では、将軍山古墳のほか和歌山県和歌山市大谷古墳と福岡県古賀市船原古墳の3例しか出土していない。
日本聖公会川越キリスト教会礼拝堂
中世ゴシック折衷様式。聖公会とは「英国国教会」の日本での呼称です。
〒350-0056 埼玉県川越市松江町2丁目4−13 川越教会
聖公会は、イギリス国教会を母体とするプロテスタントの教会です。キリスト教の伝統、人間の理性、そして『聖書』を大切にする教会です。川越の宣教は、1878年(明治11年)にさかのぼります。
大谷瓦窯跡
朝鮮半島の技術が見られる。
〒355-0008 埼玉県東松山市, 36.071259783854785, 139.40250985360225
旧日本煉瓦製造
近代化産業遺産(建造物の近代化に貢献した赤煉瓦生産などの歩みを物語る近代化産業遺産群)
〒366-0029 埼玉県深谷市上敷免28
ホフマン輪窯は、深谷市の旧煉瓦製造施設ホフマン輪窯6号窯の他には、栃木県下都賀郡野木町、京都府舞鶴市、滋賀県近江八幡市にそれぞれ1基が現存するのみで、全国では4基しか残されていない貴重なものです。
山吉ビル(山吉デパート)
埼玉県初のデパート。イオニア式柱頭がファサードにみられる。
〒350-0065 埼玉県川越市仲町6
高麗神社
李方子(イ・バンジャ)妃のお手植えの植樹
〒350-1243 埼玉県日高市新堀833
吉見百穴
考古学、戦争遺跡
〒355-0155 埼玉県比企郡吉見町北吉見327
所沢航空発祥記念館 アンリ・ファルマン機
近代化産業遺産(欧米諸国を驚愕させるまでに急成長を遂げた航空機産業の歩みを物語る近代化産業遺産群)
〒359-0042 埼玉県所沢市並木1丁目13 所沢航空記念公園内
旧石川組製糸西洋館
〒358-0008 埼玉県入間市河原町13−13
丸木美術館
「原爆の図」「アウシュビッツの図」など
〒355-0076 埼玉県東松山市下唐子1401
千葉県:ロシア人初上陸の地!
レンブラント「広つば帽を被った男」DIC川村記念美術館
〒285-8505 千葉県佐倉市坂戸 631
ロペス・メキシコ大統領来訪記念碑
〒299-5105 千葉県夷隅郡御宿町岩和田720
ロシア人日本初上陸の地
実はロシア人が初めて日本に上陸したのは千葉県!(1739年(元文4))。
〒299-5503 千葉県鴨川市天津9
利根運河
工事の中心となったオランダ人技師ムルデルの顕彰碑。
〒270-0101 千葉県流山市西深井840−2
ふなばしアンデルセン公園
千葉大学園芸学部フランス式庭園
「松戸の中のパリ」とも紹介されるフランス式庭園のほかに、イギリス式・イタリア式庭園も並ぶ。
〒271-0092 千葉県松戸市松戸648
東京都:近代以降に幅広いラインナップを誇る
まずは記念碑を通じた「世界一周」ができる日比谷公園から。置き場に困る(?)ようなモニュメントがゴロゴロ。日比谷公園は日本初の西洋式庭園でもある。
ルーパロマーナ:ローマの牝狼(日比谷公園)
ムッソリーニ時代に寄贈されたいわくつきの石像でもある(→福島県も参照)。
〒100-0012 東京都千代田区日比谷公園1−1

古代スカンジナビア碑銘譯(日比谷公園)
ルーン文字が刻まれた記念碑。航空便就航記念で寄贈されたもの。
ヤップ島石貨(日比谷公園)
第一次世界大戦後のヴェルサイユ条約によって日本が委任統治したヤップ島から送られたもの。
ホセ・リサール博士銅像(日比谷公園)
〒100-0012 東京都千代田区日比谷公園1
コッホ・北里神社
コッホと北里を祀る。 北里大学構内にある。
〒108-0072 東京都港区白金5丁目8−1
マハトマ・ガンディー像
ガンディー
〒167-0051 東京都杉並区荻窪3丁目40
東京ジャーミイ
〒151-0065 東京都渋谷区大山町1−19
東京ジャーミイの歴史は戦前にまで遡ります。ロシア革命を逃 れ、日本へ避難して来たカザン州のトルコ人たちの礼拝所を求め る動きが、日本政府の協力によって結実したのが1938年(昭和 13年)に竣工する東京回教礼拝堂です。(…)
1917年( 大 正6年 )、 ロシアで社会主義革命 が起き、同国内に居住 していた多くのイスラーム教徒たちは迫害を 受け、生命の危機を逃 れるために海外へと避難せざるを得なくなり ました。その中のカザン州のトルコ人たちは 中央アジアを経由して 満州へと移動、さらに韓国や日本へと安住の地を 求めて移住して来たのです。東京や神戸に定住したトルコ人たちは気候の温 暖な日本の生活にすぐなじむことができました。
1922年(大正11年)の関東大震災の発生直後、アメリカ政府が東京在住の外国人を救助するため横浜港に特別船を用意したにもかかわらず、トルコ人たちはその申し出を断り日本を離れることはあ りませんでした。同年、彼らはアブドゥルハイ・ク ルバン・アリを代表にマハッレ・イスラミイエ協会を設立し、のちに来日するアブドゥルラシード・イブラヒームらと共に日本政府との友好を深めて いったのです。
東京で新たな生活を始めたトルコ人たちの悩み は子供たちの教育にありました。1928年(昭和3年)、 彼らは日本政府から学校設立の許可を得た後、メク テビ・イスラミイエと命名した学校を開設しました。 さらに日本政府の協力により東京の渋谷区に土地 を購入し、1935年(昭和10年)、その地に学校を移転、 1938年(昭和13年)には隣接した場所に彼らの悲願であった礼拝堂(東京回教礼拝堂)を建設するこ とができたのです。

紙の博物館
近代化産業遺産(洋紙の国内自給を目指し北海道へと展開した製紙業の歩みを物語る近代化産業遺産群)
〒114-0002 東京都北区王子1丁目1−3
ヘボン博士胸像 ヘボン
〒108-0071 東京都港区白金台1丁目2
Vasupujya swami jain temple(Indian Temple)
ジャイナ教の寺院(→兵庫県も参照)。ジャイナ教とは仏教と同時代(紀元前5世紀頃)に東部インドのマガダ国でヴァルダマーナが開いた宗教。
〒110-0015 東京都台東区東上野1丁目10−6 4th Floor
シク教の寺院
文京区茗荷谷にある。ランガルの提供もしている。

池袋オリエント博物館
〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目1−4 文化会館ビル 7F サンシャインシティ

杉並区郷土博物館
反核運動
〒168-0061 東京都杉並区大宮1丁目20−8
オーロラの碑
反核運動
〒167-0051 東京都杉並区荻窪3丁目47
小石川後楽園
朱舜水が設計したという中国風庭園や円月橋(アーチ橋)がある(→朱舜水は茨城県を参照)。
尚泰の邸宅(千代田区立九段中等教育学校)
東京に流された琉球王国最後の王・尚泰の邸宅のあった場所。
〒102-0073 東京都千代田区九段北2丁目2−1
夢の島
第五福竜丸事件
〒136-0081 東京都江東区夢の島2丁目1−1
久保山愛吉記念碑
第五福竜丸事件
〒136-0081 東京都江東区夢の島2丁目1
第五福竜丸のエンジン
第五福竜丸事件
〒136-0081 東京都江東区夢の島2丁目1
川路聖謨墓所
下田条約、プチャーチン
〒110-0008 東京都台東区池之端2丁目1−21
勝専寺
金玉均による鐘楼建築記念碑の撰文。
〒120-0034 東京都足立区千住2丁目11
金玉均の墓所は青山霊園に。
都立蘆花恒春園
徳富蘆花、トルストイ
〒157-0063 東京都世田谷区粕谷1丁目20−1
回向院海難供養碑
大黒屋光太夫
巣鴨プリズン跡
〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目1−6

榎本武揚像
樺太・千島交換条約
〒131-0034 東京都墨田区堤通2丁目6−11
アジアゾウのはな子
タイ(太平洋戦争中の戦時猛獣処分の過程で、上野恩賜動物園で餓死したインドゾウ「花子」の名にちなんだもの)
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目15
昭和女子大学 トルストイ像
トルストイ
〒154-0004 東京都世田谷区太子堂1丁目7
鳩山会館
日ソ共同宣言
〒112-0013 東京都文京区音羽1丁目7−1
ニコライ堂
正教会
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4丁目1−3


以下の4つは今は跡形もない戦前の史跡。
旧駐日満洲国代表公署(元麻布3丁目4−33)
大使館
〒106-0046 東京都港区元麻布3丁目4−33
旧南満州鉄道東京支社(麻布台パークハウス付近)
〒106-0041 東京都港区麻布台2丁目1−2
南満州鉄道東京支社(㈱商船三井 本社)
〒105-8688 東京都港区虎ノ門2丁目1−1 商船三井ビル
旧駐日ドイツ大使館(国立国会図書館)
モーツァルト像(かつしかシンフォニーヒルズ)
〒124-0012 東京都葛飾区立石6丁目33−1
ジョサイア・コンドル像
モース像
大森にもかわいい記念碑がある。

ヨハン・シュトラウス(2世)像(京成青砥駅)
哲学の庭
〒165-0024 東京都中野区松が丘1丁目33−34−28
「アブラハム、エクナトン、キリスト、釈迦、老子(世界の大きな宗教・思想の祖となった人物)」「ガンジー、聖フランシス、達磨大師(到達した哲学・思想の境地を社会に広め実践した人々)」「聖徳太子、ハムラビ、ユスティニアヌス(現在も伝わる著名な法を整備した人物)」
マネ「自画像」アーティゾン美術館
〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目7−2
東京医科歯科大学 壁面レリーフ
左からヒポクラテスの誓い、アテネの楽堂の一部、ウィリアム・モートンの麻酔実験。
〒113-8510 東京都文京区湯島1丁目5−45

迎賓館赤坂離宮
〒107-0051 東京都港区元赤坂2丁目1−1
館長です
— 迎賓館赤坂離宮 Akasaka Palace (@cao_Geihinkan) April 20, 2024
中学高校の世界史の授業で新学期早々に古代建築の様式(ドーリア(ドリス)式/イオニア式/コリント式)を学んだ記憶のある方も多いのでは?
花鳥の間では3つの様式を同時に視角に収めることが可能です
なんという贅沢空間。歴史・建築ファンの聖地になってしまうかも(^^)#迎賓館長 pic.twitter.com/Grff5IjN0D
ニュートンのリンゴ(小石川植物園)
〒112-0001 東京都文京区白山3丁目7
ハバッド ジャパン
ユダヤ教
〒143-0023 東京都大田区山王1丁目25−18 3F
浅草モスク
イスラム教
〒111-0025 東京都台東区東浅草1丁目9−12
日本定住(ベトナム)難民の有志による記念植樹・記念碑(八潮公園)
ベトナム難民
高麗博物館
朝鮮
〒169-0072 東京都新宿区大久保1丁目12−1 株式会社韓国広場 本社ビル 7階
古代エジプト美術館
古代エジプト
〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目12−18 メゾン渋谷801
家具の博物館
〒196-0022 東京都昭島市中神町1148 フランスベッド内
中村彝アトリエ記念館
中村屋のボース
〒161-0033 東京都新宿区下落合3丁目5−7
孫文先生座石
孫文
〒112-0001 東京都文京区白山5丁目35−1
自由の女神像
自由の女神
〒135-0091 東京都港区台場1丁目4−2
ゴッホ「ひまわり」SOMPO美術館
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1丁目26−1
東京ゲーテ記念館
ゲーテ
〒114-0024 東京都北区西ケ原2丁目30−1
たばこと塩の博物館
〒130-0003 東京都墨田区横川1丁目16−3
切手の博物館
〒171-0031 東京都豊島区目白1丁目4−23
陸軍板橋火薬製造所跡
日本軍
〒173-0003 東京都板橋区加賀1丁目7
金大中事件(旧ホテルグランドパレス、飯田橋1丁目1−1)
世界のカバン博物館(新川柳作記念館)
〒111-0043 東京都台東区駒形1丁目8−10
文化学園服飾博物館
〒151-0053 東京都渋谷区代々木3丁目22
東洋文庫ミュージアム
〒113-0021 東京都文京区本駒込2丁目28−21
中近東文化センター
オリエント
〒181-0015 東京都三鷹市大沢3丁目10−31
パール博士顕彰碑パール判事
リトルエチオピア レストラン バー
東京の外国人のコミュニティとしては、葛西のリトル・インディア、高田馬場のリトル・ヤンゴン、新大久保のムスリム横丁などが知られるが、エチオピア人のコミュニティもある。
〒124-0014 東京都葛飾区東四つ木3丁目23−6
なぜエチオピア料理店があるのか、背景はこちらを参照。
印刷博物館
〒112-0005 東京都文京区水道1丁目3−3 トッパン小石川ビル
お茶の水女子大学歴史資料館
幼児教育に関する歴史ならこちら。
〒112-0012 東京都文京区大塚2丁目1−1 国際交流留学生プラザ 1階
経済学者に関する屋外展示(日大経済学部前)
写真はアダム・スミスのモニュメント(初版本の貴重書コレクションがあるため、https://www.law.nihon-u.ac.jp/library/pdf/NUCLL.pdf)。
35.70022274051637, 139.75608924813758

絹糸紡績資料館
〒192-0375 東京都八王子市鑓水989−2 八王子市絹の道資料館
神奈川県:目玉はやはり開港関連史跡
次のようなガイドがある。
ペリー上陸記念碑
〒239-0831 神奈川県横須賀市久里浜7丁目15
横浜山手西洋館
横浜山手の定番。
〒231-0861 神奈川県横浜市中区山手町234−1
http://www.hama-midorinokyokai.or.jp/yamate-seiyoukan/
横浜外人墓地
〒231-0862 神奈川県横浜市中区山手町96

横浜市イギリス館
旧・英国総領事公邸
〒231-0862 神奈川県横浜市中区山手町115−3
安針塚
ウィリアム・アダムズについては静岡県を参照(ほかに大分県、長崎県)。
建長寺
日本人にとって「海外」感はもはやないほど、仏寺は日本に溶け込んでいるわけだが、この臨済宗建長寺派の本山である建長寺(開創は建長5年(1253))の開基は北条時頼、開山は蘭渓道隆(らんけいどうりゅう)という宋の涪江(四川省)生まれの中国人である。
マッカーサー像(厚木基地)
マッカーサー井戸
〒245-0012 神奈川県横浜市泉区中田北2丁目6
孫文先生上陸之地碑
孫文
〒236-0051 神奈川県横浜市金沢区富岡東4丁目1−5
浦賀港引揚記念の碑
引き揚げ
生麦事件碑
文久2年(1862)薩摩(さつま)藩・島津久光の一行が江戸から帰還する途上、騎馬のまま行列を横切った英国人4人を殺傷した事件。生麦村の地名から。
首都高 神奈川7号 横浜北線(K7)の直下にあり、こんなところに!となるはず。
元使塚
蒙古襲来
〒251-0032 神奈川県藤沢市片瀬3丁目14−3
箱根マイセンアンティーク美術館
〒250-0408 神奈川県足柄下郡箱根町強羅1320−653
ホテルニューグランド
老舗の洋風ホテル。ヘボン、イザベラ・バード『日本奥地紀行』(→山形県)、開業当時から、皇族、イギリス王族などの賓客や、チャップリン、ベーブ・ルースなどに加え、マッカーサーも二度滞在(一度目は新婚旅行の帰り、二度目は敗戦後)。近代化産業遺産(外貨獲得と近代日本の国際化に貢献した観光産業草創期の歩みを物語る近代化産業遺産群)に登録。
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町 10番地

富士屋ホテル
近代化産業遺産(外貨獲得と近代日本の国際化に貢献した観光産業草創期の歩みを物語る近代化産業遺産群)に登録。
〒250-0404 神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下359
蒋公頌徳碑(伊勢山皇大神宮)
蒋介石
〒220-0031 神奈川県横浜市西区宮崎町64
モース記念碑 日本近代動物学発祥の地
モース
〒251-0036 神奈川県藤沢市江の島1丁目1−2
横浜ユーラシア文化館
オリエント、東洋史
〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通12
日本バレエ発祥之地
バレエ、ロシア、エリアナ・パヴロワ
〒248-0026 神奈川県鎌倉市七里ガ浜1丁目3−26
リカルテ将軍記念碑
フィリピン革命
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町12−1
日本郵船歴史博物館(※2026年まで臨時休業)
近代化産業遺産(『貿易立国の原点』横浜港発展の歩みを物語る近代化産業遺産群)
〒231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通3丁目9
横浜開港資料館
近代化産業遺産(『貿易立国の原点』横浜港発展の歩みを物語る近代化産業遺産群)
〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通3
シルク博物館
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町1 シルクセンタ 2階
JICA横浜 海外移住資料館
〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港2丁目3−1 2階
馬の博物館
近代化産業遺産(旧居留地を源として各地に普及した近代娯楽産業発展の歩みを物語る近代化産業遺産群)
〒231-0853 神奈川県横浜市中区根岸台1−3
新潟県:スキーと登山を伝えた外国人
日本スキー発祥記念館
スキー
〒943-0893 新潟県上越市大貫1丁目18
ウォルター・ウェストン像(道の駅 親不知ピアパーク)
近代登山の紹介者
〒949-0308 新潟県糸魚川市外波903−1
「レルヒ少佐像」
〒943-0893 新潟県上越市大貫2丁目17−5
北海道には「レルヒ中佐像」があるが、これはwikipedia日本語版(項目名:テオドール・エードラー・フォン・レルヒ)によると「訪日時は少佐で、少佐の時にスキーを日本に伝えたため、日本国内では一般的には「レルヒ少佐」と呼ばれる。後に中佐に昇格したあと日本各地を回ったため、北海道などでは「レルヒ中佐」と呼ばれる」。
佐渡金山
銀輸出、近代化産業遺産(近代技術による増産を達成し我が国近代化に貢献した佐渡、鯛生両鉱山の歩みを物語る近代化産業遺産群)
〒952-1501 新潟県佐渡市下相川1305
富山県:チューリップ発祥の地
世界史観光スポットの少ない富山県であるが、いくつか挙げることができる。
常願寺川・白岩砂防ダム
全国各地の土木建築にゆかりのあるデ・レーケは、当時暴れ川として猛威をふるっていた常願寺川をみて「常願寺川は滝である」と上申したとされる。
1891年にデ・レーケは大工事を計画し93年に完成した。
特に石碑や銅像などがのこされていないのは、デ・レーケの技師としての”裏方”意識によるものとされる。
デ・レーケはこちらも指導している。
〒930-1458 富山県中新川郡立山町有峰
砺波チューリップ公園
チューリップ栽培は、大正7年(1918年)に東砺波郡庄下村(現・砺波市)で米農家だった水野豊造(みずのぶんぞう)が裏作として植え付けたのが始まり。発祥には外国との直接的な結びつきはないが、これをきっかけにオランダとの交流が盛んになっている。
〒939-1382 富山県砺波市花園町1−32
なお、日本とトルコの国交樹立100周年を記念し、トルコ西部の町ヤロバと姉妹都市になっている砺波市で4月19日から撮影が始まったとのこと。
「作品のタイトルは、トルコ語で「それから」という意味の「Ondansonra」で、砺波市内のスーパーマーケットで働く主婦たちがチューリップを通してトルコの魅力に気付いていく物語です。」
チューリップとトルコの組み合わせというと、「チューリップ・バブル」を想起してしまいますが、なにか関係はあるんでしょうか。
米騒動発祥の地
シベリア出兵を見越した米の買い占め不安に対し、1918年7月に富山県で勃発し、富山湾沿岸一帯に拡大。8月には新聞で全国的に報道されて急速に波及した大規模な騒乱はここにはじまる。
〒937-0866 富山県魚津市本町1丁目2−26
石川県:渤海使の往来が盛んだった能登半島
福浦港
渤海使
〒925-0315 石川県羽咋郡志賀町
八田與一像(金沢ふるさと偉人館)
八田與一
〒920-0993 石川県金沢市下本多町6番丁18−4
金沢ふるさと偉人館は、平成5(1993)年に高峰譲吉・三宅雪嶺・木村栄・藤岡作太郎・鈴木大拙の5人の偉人を展示し、開館しました。
その後、金沢ゆかりの「近代日本を支えた偉人たち」として、さまざまな分野で国際的国家的業績をあげた人びとを加え、現在では多くの偉人を常設展示でご紹介しています。
(…)
平成16年5月29日八田與一を加える
八田與一 生家と生誕地碑
八田與一
〒920-0106 石川県金沢市今町チ6
尹奉吉暗葬地
尹奉吉
〒921-8104 石川県金沢市野田町921 8104
長崎キリスト教殉教者碑
潜伏キリシタン
〒920-0833 石川県金沢市 卯辰山 自然公園
野田山墓地
日露戦争時の明治38年に捕虜として金沢に連行されたロシア人兵士のうち、病気等で亡くなった10人の御霊を祀るロシア人兵士の墓。
〒921-8174 石川県金沢市山科町ワ
福井県:敦賀が結んだ日本とヨーロッパ
気比の松原(松原客館?)
渤海使
〒914-0801 福井県敦賀市松島町33
福井市グリフィス記念館
お雇い外国人
〒910-0006 福井県福井市中央3丁目5−4
杉原千畝夫人・幸子氏来敦記念の植樹
杉原千畝は1940年(昭和15)にバルト海に面したリトアニアの日本領事館領事代理に就任後、日本通過の査証(ビザ)を得ようとしユダヤ系ポーランド人に、外務省の方針にあらがい”命のビザ”を発給した人物(1991年名誉回復)。
〒914-0079 福井県敦賀市港町1
次の3つは、日本遺産「海を越えた鉄道~世界へつながる 鉄路のキセキ~」に登録されているもの。
旧敦賀港駅舎
日本遺産(海を越えた鉄道~世界へつながる 鉄路のキセキ~)
〒914-0079 福井県敦賀市港町1−25
敦賀市立博物館
日本遺産(海を越えた鉄道~世界へつながる 鉄路のキセキ~)
〒914-0062 福井県敦賀市相生町7−8
敦賀赤レンガ倉庫(旧紐育スタンダード石油会社倉庫)
〒914-0072 福井県敦賀市金ケ崎町4−1
藤野厳九郎記念館
日本留学中に魯迅の慕った藤野先生に関する記念館。
中国人も訪れる藤野厳九郎記念館
福井県あわら市温泉1丁目203番地。あわら湯のまち駅(えちぜん鉄道)から徒歩1分ほどの湯のまち広場の一角に「藤野厳九郎記念館」がある。
記念館には藤野家の診療所を兼ねた木造2階建て旧居=登録有形文化財(建築物)=が移築されている。記念館の前庭には藤野厳九郎が座り、若き日の魯迅が寄り添うように横に立つブロンズ像が設置されている。館内の資料室にも二人の胸像が並ぶ。
〒910-4104 福井県あわら市温泉1丁目203
山梨県:ミレーとアフリカ
世界史観光スポットの少ない山梨県であるが、なんとかいくつか挙げることができる。
ミレー「種をまく人」山梨県立博物館
ミレー
〒400-0065 山梨県甲府市貢川1丁目4−27
アフリカンアートミュージアム
「アフリカのマスク、立像、楽器、テキスタイル、道具、武具など1900点。
アジア、オセアニア、インドネシア、フィリピン、ヒマラヤ、台湾や日本などの美術品700点」を所蔵。
〒408-0036 山梨県北杜市長坂町中丸1712−7
長野県:ナウマンゾウから満洲開拓まで
野尻湖ナウマンゾウ博物館
〒389-1303 長野県上水内郡信濃町野尻287−5
碓氷峠鉄道施設群
近代化産業遺産(『上州から信州そして全国へ』近代製糸業発展の歩みを物語る富岡製糸場などの近代化産業遺産群)
〒379-0307 群馬県安中市松井田町坂本 アプトの道
萬平ホテル(※2024年5月現在改修のため休館中)
近代化産業遺産(外貨獲得と近代日本の国際化に貢献した観光産業草創期の歩みを物語る近代化産業遺産群)
〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢925
軽井沢には、トルコ系タタール人(白系ロシア人)が100名ほど疎開した。スタルヒン(→北海道)のところでふれたように、彼らは革命を逃れてきた亡命者。万平ホテルにも身を寄せた。
ウエストン碑
近代登山の紹介者(1861-1940)。明治21年(1888)にイギリス国教会牧師として来日し、布教のかたわら中部山岳地帯を踏査し、『日本アルプスの登山と探検』を出版。結果的に「日本アルプス」の名を広めた人、となった。上高地では毎年ウェストン祭が開催されている。
〒390-1516 長野県松本市安曇上高地4469
満蒙開拓平和記念館
満蒙開拓に関する私設の博物館。
〒395-0303 長野県下伊那郡阿智村駒場711−10
タゴール記念碑
1911年にアジアで初めてノーベル文学賞を受賞したタゴールは、翌年夏、日本女子大の招きで軽井沢の三井邸に滞在。これを記念したもの。
〒389-0101 長野県北佐久郡軽井沢町峠町
市立岡谷蚕糸博物館
近代化産業遺産(『上州から信州そして全国へ』近代製糸業発展の歩みを物語る富岡製糸場などの近代化産業遺産群)
〒394-0021 長野県岡谷市郷田1丁目4−8
岐阜県:杉原千畝の生家に「人道の丘公園」
輪中館・輪中生活館
日本各地に存在するデ・レーケ関連史跡。アムステルダムの運河会社の上級技師だったレ・デーケはファン・ドールンに認められ、1873年に他の3人の技師とともに来日。木曾川の改修計画にあたった。
〒503-0962 岐阜県大垣市入方2丁目1723
杉原千畝記念館
〒505-0301 岐阜県加茂郡八百津町八百津1071
http://www.sugihara-museum.jp/
近くに人道の丘公園があり、ナイチンゲール像やシュヴァイツァー像が設置されている。
ナイチンゲール像
シュヴァイツァー像
エーザイ内藤記念くすり博物館
近代化産業遺産(情報伝達の質・量を飛躍的に拡大させ社会変革をもたらした電気通信技術の歩みを物語る近代化産業遺産群)に指定。
〒501-6024 岐阜県各務原市川島竹早町1
収蔵品デジタルアーカイブはこちら。
中部大学民族資料博物館
展示室は、シルクロード室(第1室)、地域研究エリア(第2室)の二部構成。第2室は、オセアニア、アフリカ、ヨーロッパ、アジア、アメリカの大きく5つの地域で区分し、約4,000点の収蔵資料のうち750点あまりを展示紹介している。
〒487-0027 愛知県春日井市松本町1200
静岡県:人々の交流をつなぐ幅広いラインナップ
伊豆に関しては次のようなガイドがある。
下田には開国関連の史跡が多い。
ペリー艦隊来航記念碑(ペリー上陸記念公園)
ペリー来航
〒415-0023 静岡県下田市三丁目6−6
長楽寺
日露和親条約
〒415-0023 静岡県下田市三丁目13−19
了仙寺
ペリー来航

豆州下田郷土資料館
〒415-0024 静岡県下田市四丁目4丁目8−13
ブラジル移民の父・平野運平像(掛川市生涯学習センター)
〒436-0068 静岡県掛川市御所原17−1
浅羽佐喜太郎記念碑
ファン・ボイ・チャウ
〒437-1105 静岡県袋井市梅山132
栄西禅師像
日本にお茶を持ち込んだのだから、めっちゃ偉い人。像は複数ある。
袋井の栄西像
島田駅前の栄西像
ふじのくに茶の都ミュージアム
お茶ワンテーマの博物館。世界のお茶の展示がある。
〒428-0034 静岡県島田市金谷富士見町3053−2
清見寺
朝鮮通信使が逗留した場所。
琉球使節の扁額もある(下図)。

戦前は興津は人気の観光地だった。大正天皇が皇太子時代に寺に滞在し、近くで海水浴もしている。
〒424-0206 静岡県静岡市清水区興津清見寺町418−1
ウィリアム・アダムズ像
ウィリアム・アダムズ
静岡県伊東市渚町6
富士市と戸田(沼津市)にはロシアのプチャーチンのディアナ号関連が多い。
友好の像 プチャーチン提督と日本の漁夫
プチャーチン
〒417-0061 静岡県富士市伝法
ディアナ号の錨(三四軒屋緑道)
〒416-0946 静岡県富士市五貫島 三四軒屋緑道公園内
土肥にもある。
浄土宗専修山大行寺
安政年間にロシアとの和親条約改定の舞台となった寺院。ヘダ号を建造したエンジニアの墓所もここにある。川路聖謨の墓所は東京都を参照。
〒410-3402 静岡県沼津市戸田926 大行寺
安政年間、来日中のロシア使節プチャーチン提督は、安政東海大地震の被害により、座乗鑑ディアナ号を失い、代鑑建造地の戸田に滞在していた。幕府は先に締結した和親条約(第6条、領事駐留)改訂のため、勘定奉行川路左衛門尉聖謨(→東京都を参照)を全権として戸田へ出向かせた。川路は大行寺を応接所に当て改訂交渉を行った。(川路の下田日記)その後、大行寺は2回の大火で類焼し、当時の記録は建物とともに失われ現存していない。現在の建物は、旧水野領の名主・斎藤本家(入浜)を移築したもので、宝泉寺本堂につぐ旧戸田村内古建築と推定される。建坪63坪余、書院造りの面影が窺える。なお、この寺にはヘダ号建造時の船大工で、後に造船技術者として活躍した上田寅吉の墓がある。
沼津市戸田造船郷土資料博物館
近代化産業遺産(ディアナ号・ディアナ号)
〒410-3402 静岡県沼津市戸田2710−1
静岡には茶商関連の史跡が残されている。
旧 マッケンジー邸
旧茶商住宅
〒422-8034 静岡県静岡市駿河区高松2852 旧マッケンジー邸
旧エンバーソン住宅
〒422-8005 静岡県静岡市駿河区池田2864−52
ふじのくに茶の都ミュージアム
〒428-0034 静岡県島田市金谷富士見町3053−2

韮山反射炉
近代化産業遺産、明治日本の産業革命遺産
山田長政像
山田長政
〒420-0868 静岡県静岡市葵区宮ヶ崎町
あべの古書店によると、静岡市大浜にもコンクリート製の像があったが、「南進政策の象徴(として利用された)山田長政の像は、アメリカの不興を買うとの理由で取り壊された」という(http://www.sengendori.com/nagamasa/nagamasaohama.html)。
モネ「睡蓮」MOA美術館
モネ「睡蓮」
〒413-8511 静岡県熱海市桃山町26−2
清水港テルファー
近代化産業遺産
〒424-0824 静岡県静岡市清水区入船町13−15
旧赤松家記念館
榎本武揚(→東京都の榎本武揚像)とともにプロイセン・デンマーク戦争を視察し、クルップ(→北海道を参照)を視察した赤松則良(1841-1920)の記念館。
〒438-0086 静岡県磐田市見付3884−10
近代日本の造船技術の先駆者で、明治期に磐田原台地に茶園を開拓した海軍中将男爵赤松則良の邸宅跡です。
静岡大学高柳記念未来技術創造館
近代化産業遺産(情報伝達の質・量を飛躍的に拡大させ社会変革をもたらした電気通信技術の歩みを物語る近代化産業遺産群)、テレビ
〒432-8011 静岡県浜松市中区城北3丁目5−1
浜松市楽器博物館
世界の楽器が多数展示されている。
ショパンの丘公園(アクトシティ浜松)
〒430-0928 静岡県浜松市中区板屋町111−1 アクトシティ浜松 屋上
ワルシャワのワジェンキ公園のモニュメントを模している。
丹那トンネル殉難慰霊碑
平井の養徳寺(ようとくじ)境内にも、丹那トンネル工事の殉難者の慰霊碑が建てられている。
〒413-0017 静岡県熱海市梅園町25−34
愛知県:漂流民「音吉」や、島崎藤村「椰子の実」
ハワイ移民集会所(明治村)
明治村には、聖ザビエル天主堂や神戸山手西洋人住居など、さまざまな西洋建築・擬西洋建築があるが、こちらをピックアップしておく。
〒484-0000 愛知県犬山市内山
トヨタ産業技術記念館
近代化産業遺産(商業貿易港として発展し続ける神戸港の歩みを物語る近代。蒸気機関などの第一次産業革命時代の技術を見ることができる。
〒451-0051 愛知県名古屋市西区則武新町4丁目1−35

実演はなく映像と説明のみなら、豊田佐吉記念館(静岡県)にも展示がある。
船頭平閘門
デ・ケーレ
〒496-0946 愛知県愛西市立田町十六石山
名古屋モスク
イスラム教
〒453-0041 愛知県名古屋市中村区本陣通2丁目26−7
椰子の実の記念碑
南洋
〒441-3623 愛知県田原市日出町浜
岩吉久吉乙吉頌徳記念碑
漂流民
〒470-3236 愛知県知多郡美浜町小野浦

1832年宝順丸という千石船に乗り江戸へ向かう途中嵐に遭い、太平洋を1年2か月も漂流した後アメリカ西海岸へ漂着。
その後イギリス経由でマカオに送られ、そこでドイツ人宣教師ギュツラフの聖書の和訳に協力、翌年モリソン号に乗り日本へ。しかし浦賀、鹿児島で砲撃を受け帰国を断念。
中国にて、多くの日本人漂流民の援助を行い、送還の手助けをする。
また、イギリス海軍の通訳として日英交渉に力をつくした。美浜町が生んだ日本最初の国際人。
唐人お吉の先祖の墓
開国
〒415-0021 静岡県下田市一丁目18−26
渡辺崋山の蟄居の家
開国
〒441-3421 愛知県田原市田原町中小路17
田原市博物館は渡辺崋山の展示が多い。
南山大学 人類学博物館
人類学
〒466-0824 愛知県名古屋市昭和区山里町18 R棟地下1階 R棟
三重県:大黒屋光太夫や伊勢志摩スペイン村
大黒屋光太夫
三重県といえば、まず大黒屋光太夫だ。
大黒屋光太夫記念館
〒510-0224 三重県鈴鹿市若松中1丁目1−8
大黒屋光太夫顕彰碑
〒510-0224 三重県鈴鹿市若松中2丁目3−8
大黒屋光太夫モニュメント
大黒屋光太夫供養碑
ルーブル彫刻美術館
本家・ルーブル美術館公認のレプリカ彫刻の美術館。
志摩スペイン村
スペイン村には、スペインの実在の建造物やモニュメントを模したものが多数つくられている。
コロンブス広場とコロンブス像
ハビエル城博物館
フランシスコ・ザビエル
フェリペ3世騎馬像

ドン・キホーテとサンチョパンサ像

シベレス噴水の後ろのスチームコースター「アイアンブル」の建物に、フェリペ2世、フェリペ5世、フェルナンド6世。


グラナダスの門
アルハンブラ宮殿
滋賀県:世界とつながる近江商人
先人を偲ぶ館
〒529-1161 滋賀県犬上郡 豊郷町大字四十九院815
苦労して身を起こし、明治期には「木綿王」と呼ばれた薩摩治兵衛。
大字四十九院出身の豪商薩摩治兵衛を中心に、豊郷に生まれ全国で活躍した偉大な先人達8名の業績や生い立ち、成功への道程を紹介しています。建物は二代目薩摩治兵衛が寄付した「フランス・パリの日本館」をモチーフにしたもので、内部は先人にまつわる遺品や関係資料を展示しています。
その孫治郎八は、大正9(1920)年に渡英。のちにパリに移り、父である二代目薩摩治兵衛から潤沢な仕送りを受けながら、戦前のパリ社交界で華々しく文化人と交流した。その豪華さから、爵位があったわけではなく、渾名として「バロン薩摩」と呼ばれたという。昭和4(1929)年には、薩摩家の資金でパリ国際大学都市に日本館を建立しフランス政府から叙勲を受けるなど、日仏の文化交流においても活躍し名を残した。第二次世界大戦中も含む約30年間のほとんどをフランスで過ごした治郎八は、昭和26(1951)年に帰国。その後は、本場ヨーロッパで培った豊富な知識を活かした執筆活動などをしていた。
日牟禮(ひむれ)八幡宮
東南アジアに雄飛した近江商人・西村太郎右衛門の奉納した絵馬がある。太郎右衛門はベトナムに出航し、ビジネスを開拓しようとした人物。
露国皇太子遭難之地(大津事件)
大津事件は、明治24年(1891)、訪日したロシア皇太子ニコライ(のちのニコライ2世)が、大津市で警備中の巡査津田三蔵に切りつけられた事件。大逆罪の適用による死刑判決を強要する政府にあらがった大審院長児島惟謙(こじまいけん)の生誕地は愛媛県にある。
〒520-0044 滋賀県大津市京町2丁目2−11
MIHO MUSEUM
シルクロード
〒529-1814 滋賀県甲賀市信楽町田代桃谷300
旧中川煉瓦製造所
近代化産業遺産(建造物の近代化に貢献した赤煉瓦生産などの歩みを物語る近代化産業遺産群)
〒523-0888 滋賀県近江八幡市孫平治町1丁目1−1
野田沼捕虜収容所跡地
〒520-2421 滋賀県野洲市野田4137
京都府:京都には豪商の跡、舞鶴には引揚の跡
エジソン記念碑
〒614-8005 京都府八幡市八幡, 34.878049703926024, 135.6994315670387
以下は東南アジア方面にもビジネスを展開させた近世の豪商に関連する史跡2つ。
茶屋四郎次郎・同新四郎屋敷跡
豪商
〒604-8214 京都府京都市中京区, 35.00620714595346, 135.75667630937235
角倉了以翁顕彰碑
京都に複数石碑・銅像がある。
〒604-8023 京都府京都市中京区備前島町310−2 蛸薬師通, 河原町東入
舞鶴市立赤れんが博物館
戦後の大陸からの引揚げの歴史に関する展示や舞鶴鎮守府に関する資料など。
〒625-0036 京都府舞鶴市浜2011番地
ハバットハウス京都
ユダヤ教のシナゴーグ(超正統派、ハバッド・ルバビッチ派)。
〒606-8335 京都府京都市左京区岡崎天王町30- 3
聖母マリア・聖マルコ・コプト正教会
日本初のコプト正教会の教会。
〒619-0222 京都府木津川市相楽清水2−1
岸壁の母 作詞藤田まさと碑
抑留
〒625-0133 京都府舞鶴市平
霊雲院
日露戦争
〒605-0981 京都府京都市東山区本町15丁目801
国立京都国際会館
京都議定書締結の地。
〒606-0001 京都府京都市左京区岩倉大鷺町422
パール博士顕彰碑(京都霊山護国神社)
パール判事
〒605-0825 京都府京都市東山区清閑寺霊山町1
駒蹄影園跡碑
茶
〒611-0011 京都府宇治市五ケ庄西浦
栄西禅師茶碑
茶
〒605-0811 京都府京都市東山区小松町
グンゼ記念館
近代化産業遺産(『上州から信州そして全国へ』近代製糸業発展の歩みを物語る富岡製糸場などの近代化産業遺産群)
〒623-0011 京都府綾部市青野町膳所1
舞鶴引揚記念館
引揚げ
〒625-0133 京都府舞鶴市平1584 内 引揚記念公園
旧神崎煉瓦
近代化産業遺産(建造物の近代化に貢献した赤煉瓦生産などの歩みを物語る近代化産業遺産群)
〒624-0961 京都府舞鶴市西神崎, 35.51453986325245, 135.29274736706793
大阪府:アジア間貿易を支えた東洋のマンチェスター
大阪紡績會社跡
〒551-0002 大阪府大阪市大正区三軒家東2丁目12 12番地 先
綿業会館
近代化産業遺産(『商都から近代経済都市へ』産業近代化と先進的都市計画による大阪発展の歩みを物語る近代化産業遺産群)に指定。リットン調査団も滞在した。
堺事件顕彰碑
土佐藩兵が、突然上陸してきたフランス海軍の水兵を銃撃した事件を検証する碑。
〒590-0971 大阪府堺市堺区栄橋町2丁3−30
「遣唐使進発の地」碑
遣唐使
住吉大社, 34.612827831662344, 135.49150642469917
兵庫県:国際色豊かな開港地
シク教寺院 グル・ナーナク・ダルバール
シク教
〒651-0054 兵庫県神戸市中央区野崎通2丁目1−15
孫文記念館(移情閣)
孫文を顕彰する記念館。なお有名な「大アジア主義講演」は現在の神戸高校でおこなわれた。
〒655-0047 兵庫県神戸市垂水区東舞子町4−2051
聖フランシスコ・ザビエル像(神戸市立博物館)
ザビエルの「あの絵」が展示されている。
〒650-0034 兵庫県神戸市中央区京町24
神戸モスク
イスラム教
〒650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通2丁目25−14
生野銀山 鉱山資料館
銀・銅の輸出で栄えた。
〒679-3324 兵庫県朝来市生野町小野33−5
北野異人館街
〒650-0003 兵庫県神戸市中央区北野町
日露友好の像 高田屋嘉兵衛翁とゴロヴニン提督
高田屋嘉兵衛、ゴローウニン
〒656-1301 兵庫県洲本市五色町都志1087 ウェルネスパーク五色・高田屋嘉兵衛公園
高田屋顕彰館・歴史文化資料館 菜の花ホール
〒656-1301 兵庫県洲本市五色町都志1087
神戸市立海外移住と文化の交流センター
〒650-0003 兵庫県神戸市中央区山本通3丁目19−8
メリケン波止場
近代化産業遺産(商業貿易港として発展し続ける神戸港の歩みを物語る近代化産業遺産群)
〒650-0042 兵庫県神戸市中央区波止場町2
本邦民間新聞創始者ジョセフ・ヒコ氏旧居跡
ジョゼフ・ヒコ
〒650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通6丁目2
ユーハイム本店
似島独逸俘虜収容所に収容されていたカール・ユーハイムが日本ではじめて製造した。広島県の原爆ドーム、似島独逸俘虜収容所を参照。
似島独逸俘虜収容所の跡地
〒734-0017 広島県広島市南区似島町182
奈良県:シルクロードの終着点
復原遣唐使船
遣唐使
〒630-8012 奈良県奈良市二条大路南4丁目6−1
阿倍仲麻呂の歌碑
阿倍仲麻呂
〒639-1101 奈良県大和郡山市下三橋町
法隆寺金堂壁画
アジャンター石窟寺院との関連
〒636-0115 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺山内
正倉院
シルクロード
〒630-8211 奈良県奈良市雑司町129
和歌山県:エルトゥールル号ゆかりのトルコ史跡
次のようなガイドがある。
和歌山県は、潮岬周辺に明治時代のエルトゥールル号遭難事件に関する史跡が集中している。
8年前に行ったときには、トルコ記念館前にトルコアイスの屋台が出ていた(今もやっているのかな?)。
トルコ記念館
オスマン帝国の木造艦エルトゥールル号を追悼するためのトルコ軍艦遭難慰霊碑と記念館。難破船から回収した遺品などが展示されている。
〒649-3631 和歌山県東牟婁郡串本町樫野1025−26
トルコ軍艦(エルトゥールル号)遭難慰霊碑
〒649-3631 和歌山県東牟婁郡串本町樫野, 33.47052846695113, 135.86028359581246
ムスタファ・ケマル・アタテュルク騎馬像
ケマル・アタテュルクは現在のトルコ共和国の父ということで、本名のムスタファ・ケマルに対し「トルコの父(=アタ・テュルク)」という名が与えられた人物。かつては新潟県柏崎市に柏崎トルコ文化村なる施設があり(1996年開園)、ここにもトルコ本国から贈られた像があったが、2001年に閉園。柏崎のアタテュルク像の行方について委細は不明であるが、一国の建国の父の像ということでトルコ大使館側からも、ゆかりのある串本町での再建立についてアプローチがあったようだ。
〒649-3631 和歌山県東牟婁郡串本町樫野1027−7
アンベードカル博士記念碑(高野山大学)
アンベードカル(1891-1956)は独立後のインドで初代法務大臣をつとめたインドの社会改革運動家・政治家で、不可触民の集団の一つである「マハール」の出身。新仏教運動の祖となった人物。
第五福竜丸 建造の地
第五福竜丸は東京都を参照。
〒649-4122 和歌山県東牟婁郡串本町西向1480−82
ポルトヨーロッパ
中世ヨーロッパの街並みをモデルにしたパーク。
鳥取県:世界史観光スポットも"砂漠"地帯
世界史観光スポットの乏しい県ではあるが、いくつか頑張って挙げてみよう。
砂の博物館
砂をつかった彫刻などを展示。海外の実在の建築物や彫刻をモチーフにしたものも。
〒689-0105 鳥取県鳥取市福部町湯山2083−17
日韓友好交流公園風の丘
「韓国船を2度に渡って救助した史実をふまえ、鳥取県と韓国との交流の歴史を記念して造られた」。記念碑のほか韓国様式の建築物や石塔、石造りのモニュメントもある。
〒689-2502 鳥取県東伯郡琴浦町別所167−1
島根県:世界の半分の銀を産出した石見銀山
石見銀山
銀輸出、近代化産業遺産(近代技術による増産を達成し我が国近代化に貢献した佐渡、鯛生両鉱山の歩みを物語る近代化産業遺産群)
〒694-0305 島根県大田市大森町
イルティッシュ号 慰霊碑
日露戦争の日本海海戦で被弾し、1905年5月28日に島根県江津市和木町沖で沈没したロシアのバルチック艦隊の特務運送船。この乗組員を沿岸住民が救助している。
〒695-0017 島根県江津市和木町570−1
名馬寿号の碑
日露戦争時に乃木大将に感服したステッセル敵将から贈られたとされる名馬の墓所。
〒684-0413 島根県隠岐郡海士町崎1735
岡山県:エル・グレコ「受胎告知」の大原美術館
エル・グレコ「受胎告知」大原美術館
エル・グレコ
〒710-0046 岡山県倉敷市中央1丁目1−11
近くに「珈琲エルグレコ」さんもあります。
箕作阮甫旧宅
幕末の蘭学者。1822年(文政5)津山藩医となるも翌年には藩主に随行して江戸で蘭学・儒学を学。39年(天保10)には幕府天文方蛮書和解御用となり、ロシアのプチャーチンやアメリカの外交使節と応接。1856年(安政3)蕃書調所設立に関わる。
〒708-0833 岡山県津山市西新町6
広島県:ハワイ移民の送り出し地 周防大島
原爆ドーム
言わずもがなの「負の遺産」である。

なお、原爆ドームと成り果てたかつての広島県物産陳列館は、1919年に開かれた「似島独逸俘虜技術工芸品展覧会」には、似島独逸俘虜収容所のドイツ人カール・ユーハイム(→兵庫県)が日本ではじめてバウムクーヘンを焼きあげたゆかりの地でもある。
似島は当社創業者カール・ユーハイムが第一次世界大戦で捕虜として日本に連行され収容されていた似島独逸俘虜収容所があり、1919年に広島県物産陳列館(現・原爆ドーム)にて開催された「似島独逸俘虜技術工芸品展覧会」に出品するため日本ではじめてバウムクーヘンを焼きあげたゆかりの地でもある(…)。
ハワイ移民資料館 仁保島村
スポットライトの当てられにくいこちらに注目しておきたい。ハワイとの交流を通して「瀬戸内のハワイ」というキャッチフレーズも生まれている。
〒734-0026 広島県広島市南区仁保3丁目17−6
明治の「官約移民」時代(1885年〜1894年)には、周防大島全体で3913人をハワイへ送り出しました。島に根付いていた出稼ぎの文化、自然災害、そして当時の社会情勢などもあいまって多くの人々が周防大島からハワイへ渡りました。
呉市海事歴史科学館
欧米諸国に比肩する近代造船業成長の歩みを物語る近代化産業遺産群。
〒737-0029 広島県呉市宝町5−20
山口県:日清講和条約締結の地
下関春帆楼
日清戦争の講和条約がおこなわれた舞台。
〒750-0003 山口県下関市阿弥陀寺町4−2
この旅館に日清講和記念館が併設されており、会議場の風景が再現されていて興味深い。
日清講和記念館
〒750-0003 山口県下関市阿弥陀寺町4−3
この記念館は、明治28年(1895)春、この地で開かれた日清講和会議と、下関条約と呼ばれる講和条約の歴史的意義を後世に伝えるため、昭和12年(1937)6月、講和会議の舞台となった春帆楼の隣接地に開館しました。
浜離宮から下賜されたといわれる椅子をはじめ、講和会議で使用された調度品、両国全権の伊藤博文や李鴻章の遺墨などを展示しています。また、館内中央には講和会議の部屋を再現し、当時の様子を紹介しています。
伊藤博文公の座ったイス@下関条約 pic.twitter.com/UFRmav7bij
— みんなの世界史 (@minnanosekaishi) May 1, 2024
恵美須ヶ鼻造船所跡
近代化産業遺産、明治日本の産業革命遺産(前期にロシア式、後期にオランダ式の技術を用いて大型の洋式軍艦を製造した造船所跡)
〒758-0011 山口県萩市椿東5159−14
http://bunkazai.pref.yamaguchi.lg.jp/bunkazai/detail.asp?mid=110124&pid=bl
日本ハワイ移民資料館
ハワイ移民
〒742-2103 山口県大島郡周防大島町西屋代2144
萩反射炉
近代化産業遺産、明治日本の産業革命遺産
〒758-0011 山口県萩市椿東4897−7
徳島県:世界の名画やドイツとのつながり
大塚国際美術館
西洋絵画
〒772-0053 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦福池65−1
徳島といえば、第一次世界大戦後にドイツ兵を収容した捕虜収容所がある。直接の戦場にならなかったものの、未曾有の世界大戦との接点ということで、世界史観光の目玉である。四国八十八ヶ所の一番札所、霊山寺(りょうぜんじ)の近くにある。日本ではじめてベートーヴェンの《第九》が演奏された地でもある。
鳴門市ドイツ館
第一次世界大戦
〒779-0225 徳島県鳴門市大麻町桧東山田55−2
板東俘虜収容所跡・ドイツ兵慰霊碑
〒779-0225 徳島県鳴門市大麻町桧丸山・〒779-0225 徳島県鳴門市大麻町桧丸山26−26
松江豊寿大佐の住居跡
第一次世界大戦
〒770-0835 徳島県徳島市藍場町2丁目
ドイツ橋
第一次世界大戦
〒779-0025 徳島県鳴門市大麻町板東広塚
デ・レイケ公園
治水
〒779-3610 徳島県美馬市脇町大字脇町1391−2
磐境神明神社
古代ユダヤ
〒777-0006 徳島県美馬市穴吹町口山宮内138
香川県:数は多くないが日露戦争捕虜収容所など
世界史観光スポットの少ない香川県であるが、いくつか挙げることができる。
日露戦争捕虜収容記念松の石碑
〒714-0066 岡山県笠岡市用之江2047
プッチーニの小路
〒760-0028 香川県高松市鍛冶屋町6−1 フェスタ1
アンリ・デュナン像(高松赤十字病院)
1859年、オーストリアはイタリアの独立戦争に介入。このときの戦場における惨状に衝撃を受け、スイスの実業家アンリ=デュナンはのちに、敵味方関係なく負傷兵を手当するために国際赤十字を設立する。
〒760-0017 香川県高松市番町4丁目1−3
※医療機関の施設内につき注意。デュナン像は全国各地の赤十字病院にある。
香川マスジド
1547-1, 江尻町 坂出市 香川県 762-0011
愛媛県:長崎から輸出された別子銅
別子銅山記念館
1690年(元禄3)に発見。大部分が長崎輸出銅にあてられた。
〒792-0844 愛媛県新居浜市角野新田町3丁目13
樺崎砲台跡
宇和島藩が築造した砲台の跡。宇和島湾の防備として、安政2年(1855年)3月から12月にかけて10ヶ月かけて築造された。
〒798-0003 愛媛県宇和島市住吉町2丁目4−34
ロシア兵墓地
日露戦争の際のロシア兵の墓所。松山大学キャンパス近くにある。
〒790-0824 愛媛県松山市御幸1丁目531−2
捕虜の中で、負傷し懸命の看護の甲斐なく異国の地で生涯を終えたワシリー・ボイスマン大佐ほか捕虜97名を埋葬しているのがロシア兵墓地です。墓碑は祖国を望むように北向きに建てられています。なお、埋葬者の出身地は、当時の広大なロシア帝国の各地におよんでおり、ロシアやポーランドに限らず、現在のウクライナ、ベラルーシ、バルト諸国、中央アジア諸国が含まれています。
児島惟謙の生誕地
大津事件(→滋賀県)に関連し、大審院の児島の生誕地。
〒798-0050 愛媛県宇和島市堀端町1
萬翠荘
〒790-0001 愛媛県松山市一番町3丁目3−7
萬翠荘は、大正11年(1922年)旧松山藩主の子孫にあたる久松 定謨(ひさまつ さだこと)伯爵が、別邸として建設したものです。
陸軍駐在武官としてフランス生活が長かった定謨伯爵好みの、純フランス風の建物は、当時最高の社交の場として各界名士が集まり、皇族方がご来県の際は、必ず立ち寄られたところであります。また、裕仁親王(後の昭和天皇)の松山訪問に合わせ、完成を急がせたとも伝えられております。
萬翠荘は戦禍を免れ、建築当時の様子をそのまま残す貴重な建築物として、昭和60年(1985年)に愛媛県指定有形文化財となりました。
近くに坂の上の雲ミュージアムがある。秋山兄弟の生誕地も近くにある。よく知られているように兄好古はフランスに留学した「日本騎兵の父」で、のち北豫中学校(現・松山北高校)校長。弟真之は、駐在武官としてアメリカに着任中、米西戦争を観戦しサンチャゴ湾封鎖作戦を旅順港に応用した海軍参謀。
三瀬諸淵の生家
電信の起源とされる実験をおこなった学者。実験をおこなった八幡神社前に「日本における電信の黎明」記念碑がある。
高知県 リアル「モネの睡蓮」とジョン万次郎
ジョン万次郎資料館 ジョン万次郎
〒787-0337 高知県土佐清水市養老303
中浜万次郎筆アルファベット(高知県立歴史民俗資料館)ジョン万次郎
〒783-0044 高知県南国市岡豊町八幡1099−1
西浜公園(土佐藩砲台跡)幕末
〒785-0008 高知県須崎市中町2丁目2
小野梓記念公園 近代化
〒788-0001 高知県宿毛市中央5丁目2−2619
北川村「モネの庭」マルモッタン
モネで有名になったジヴェルニーの庭をモデルに作られた庭園。
〒781-6441 高知県安芸郡北川村野友甲1100番地
駐日欧州連合代表部のにも、日本にいながらヨーロッパが楽しめる場所の筆頭として紹介されている。
満洲開拓殉難碑 満洲開拓
〒786-0515 高知県高岡郡四万十町久保川518−11
福岡県:大陸との通交の最前線
福岡市博物館 金印
〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜3丁目1−1
鴻臚館 大陸との交流
〒810-0043 福岡県福岡市中央区城内1

筥崎宮楼門 蒙古襲来
〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎1丁目22−1
朝鮮通信使関連の史跡は、朝鮮通信使の逗留した相島にある。
朝鮮通信使客館跡 朝鮮通信使
〒811-0118 福岡県糟屋郡新宮町相島1326
朝鮮通信使の石碑 朝鮮通信使
朝鮮通信使上陸淹留之地の碑 朝鮮通信使
水城
〒818-0138 福岡県大野城市下大利3丁目7−25


官営八幡製鐵所
近代化産業遺産(鉄鋼の国産化に向けた近代製鉄業発展の歩みを物語る近代化産業遺産群)、明治日本の産業革命遺産
〒805-0057 福岡県北九州市八幡東区尾倉
遠賀川水源地ポンプ室 近代化産業遺産、明治日本の産業革命遺産
〒809-0033 福岡県中間市土手ノ内1丁目3−1
ドイツ人俘虜収容所跡
第一次世界大戦時のドイツ人俘虜収容所。
佐賀県:朝鮮の陶工が伝えた有田焼
李参平の墓 朝鮮出兵
〒844-0007 佐賀県西松浦郡有田町白川2丁目6−5
有田ポーセリンパーク
いかにもバブル期のすごい建築。ドレスデンのツヴィンガー宮殿が再現されている。バロック式の庭園も見られる。
ヨーロッパの王候貴族を魅了し、世界の陶磁器に影響を与えた有田焼。世界に名だたるマイセン磁器も有田焼の、特に柿右衛門様式に大いに触発されたことが知られている。東洋磁器に憧れてマイセンで磁器製造を始めたのが、領主だった18世紀のザクセン選帝侯・アウグスト強王だ。彼がドレスデンに建設したツヴィンガー宮殿には、膨大な数の東洋磁器や東洋に関する文献が集められたと言われていた。1970年になって、ツヴィンガー宮殿などから古伊万里をはじめとする有田焼が発見され、その後、有田町でこれらの磁器の「古伊万里里帰り展」が開催された。それを機に、有田町とマイセン市が姉妹都市協定を締結。マイセン市から、2つの都市を結びつけるきっかけとなったツヴィンガー宮殿の設計図が贈られ、これを参考に有田ポーセリンパークのツヴィンガー宮殿が建てられた。
高麗人の墓
藩窯以前に渡来した陶工の墓で、山の高台に遥かな望郷にかられ北方に面して建立されています。
この墓のすぐ下には権現谷窯跡があり、発掘調査の結果、古唐津も出土しています。藩窯以前に朝鮮から陶工がきて焼物をつくっていた証です。
三重津海軍所跡 近代化産業遺産、明治日本の産業革命遺産
〒840-2202 佐賀県佐賀市川副町大字早津江津
築地反射炉
近代化産業遺産
〒840-0853 佐賀県佐賀市長瀬町9−15
香蘭社
近代化産業遺産(多様な製品開発と生産能力の向上による九州北部の窯業近代化と発展の歩みを物語る近代化産業遺産群)
〒844-0005 佐賀県西松浦郡有田町幸平1丁目3−8
多布施反射炉 近代化産業遺産
〒840-0844 佐賀県佐賀市伊勢町15−1
嘉永6(1853)年、浦賀への黒船来航に危機感を持った幕府は、急遽江戸湾の砲台に配置するために鉄製大砲鋳造を佐賀藩に依頼しました。この依頼に応えるべく新たに建造されたのが、多布施反射炉です。ここで鋳造された大砲は幕府が品川に築いた砲台に備えられ、その遺構は今も「お台場」に残っています。(…)築地・多布施の反射炉で培われた近代兵器に対する知識は、最終的に旧幕府体制を討ち滅ぼす事になります。特に強力な威力を持つアームストロング砲は「佐賀の大砲」として恐れられました。
旧海軍佐世保鎮守府凱旋記念館 海軍
〒857-0056 長崎県佐世保市平瀬町2

長崎県:出島だけじゃなく、倭寇と鄭成功にも注目
長崎といえば四つの口のうちの一つ。
稲佐悟真寺国際墓地
ヘンドリック・デュルコープ(出島オランダ商館長)、グスタフ・ウィルケンス(貿易商人)の墓所。
〒852-8008 長崎県長崎市曙町6−14
ほかにも、以下のような世界史観光スポットがある。
活版伝習所跡・唐通事会所跡石碑
「通事」は中国人との通訳・翻訳にあたる役職で、長崎に代々定住がゆるされた住宅唐人の子孫が着任した。下に墓所を挙げた穎川(えがわ)家や林家などが知られる。
〒850-0032 長崎県長崎市万才町1
近代活版印刷発祥之地 新町活版所跡石碑
「日本のグーテンベルク」といわれる本木昌造が、上海から技師ウィリアム・ガンブルを雇い入れて銅活字の鋳造に成功し、1870年から印刷をはじめた。本木家は代々オランダ通詞の家柄にあたり、1854(安政元)年にはプチャーチン(→静岡県を参照)の通訳としても活躍しているほか、維新後には日本最初の鉄橋(くろがね橋)も架橋している。まさに万能人だった。
〒850-0032 長崎県長崎市興善町6
サント・ドミンゴ教会跡資料館
日本での布教ははじめ、教皇グレゴリウス13世によりイエズス会に限定されていたが、1600年以降はフランシスコ会とドミニコ会などの托鉢修道士も来日可能となった。
これはドミニコ会のモラレス神父が1609年に建立したもの。
〒850-0028 長崎県長崎市勝山町30−1
イエズス会本部跡
なお、イエズス会の本部は、現在の長崎県庁正門の右手の石碑のあたりにあった。コレジヨ(教育機関)や教会もあったが1614年に破壊された。跡地にできた糸割符会所も1663年の大火で消失し、結局長崎奉行所になった。
なお同地には幕末に海軍伝習所が置かれ、海軍建設に備える場所となった。
日本二十六聖人殉教記念碑
〒850-0051 長崎県長崎市西坂町4
万寿山聖福寺(しょうふくじ)
境内にじゃがたらお春の碑がある。じゃがたらお春(c.1625-1697)とは、江戸時代初期に長崎に住み、後にバタヴィア(ジャカルタ。当時「じゃがたら」と呼ばれた)へと追放されたイタリア人と日本人の混血女性のこと。長崎各地にお春にちなむ記念碑や像がある。
〒850-0053 長崎県長崎市玉園町3−77
煙草栽培地の石碑(春徳寺)
日本ではじめて輸入された煙草を栽培したところ。タバコの原産地は新大陸である。
〒850-0016 長崎県長崎市夫婦川町11−1
なおここにイエズス会修道士のアルメイダ(→大分県)の碑がある。彼の弟子のガスパル・ヴィレラが建てたのがトードス・サントス教会(現存せず)で、教会にはコレジヨやセミナリヨもあった。
唐人屋敷跡
長崎にあった人工島は出島だけではなく、もうひとつ中国との貿易の荷物保管用の新地蔵所(しんちくらしょ)もあった。
ここは開国後に居留地になり、現在は中華街となっている。
この近くにあるのが唐人屋敷だ。中国人の自由な移動や抜け荷を制限するために1689(元禄2)年に完成した。横浜や神戸にもみられるように、航海安全の女神である媽祖(まそ)をまつった天后堂や、福建会館がある。
日本からはよく知られているように銅(→愛媛県、秋田県を参照)や俵物を輸出した。
〒850-0905 長崎県長崎市籠町6
東山手の洋館群
***
さて、ここからはいったん平戸について見ていこう。出島に移される前、商館は平戸にあった。
オランダ商館
南蛮貿易
〒859-5102 長崎県平戸市大久保町2477
その平戸は|鄭成功《ていせいこう》ゆかりの地でもある。
鄭成功の生まれは日本の肥前国松浦郡の平戸(ひらど)だ。
その父は鄭芝龍(ていしりゅう)、明の末期に中国南部から日本にかけて、東シナ海をまたにかけ活躍した、福建省出身の貿易商である。だがこの男、たんなる商人ではない。鄭芝龍の許可がなければ、東シナ海を安全に航海することもむずかしかったのだ。
平戸藩主松浦隆信は鄭芝龍の力をたのみ、藩内への居住を許すことに。ここで日本人の田川マツとの間に生まれたのが鄭成功だ。
鄭成功記念館
〒859-5132 長崎県平戸市川内町1114−2
王直屋敷·天門寺跡
〒859-5112 長崎県平戸市鏡川町277
平戸は三浦按針(ウィリアム・アダムズ)ともゆかりがある(→静岡県、大分県を参照)。
按針の館
ウィリアム・アダムズ
〒859-5113 長崎県平戸市木引田町431
三浦按針終焉の地碑
ウィリアム・アダムズ
〒859-5113 長崎県平戸市木引田町455
イギリス商館遺跡碑
〒859-5152 長崎県平戸市鏡川町281−1
近くの五島列島も倭寇の拠点として知られる。
倭寇とは13世紀〜16世紀にかけて、朝鮮および中国大陸沿岸で略奪行為や密貿易を行った海賊集団。一般に15世紀までの前期倭寇は瀬戸内海・北九州を本拠とした日本人が多かったが、16世紀の後期倭寇は中国人を主体とする。
小手ノ浦倭寇城
〒857-4414 長崎県南松浦郡新上五島町飯ノ瀬戸郷524
刀伊の入寇古戦場(長崎県壱岐市勝本町立石南触)
刀伊の入寇とは、平安中期の1019年(寛仁3)3月末から4月にかけて、「刀伊の賊」が大宰府管内に侵入した事件。後に金を建国するツングース系民族である女真とみられている。
対馬から福岡県北部にかけては1019年に刀伊の入寇に見舞われた地域でもある。たとえば壱岐には刀伊の入寇の古戦場がのこされている。
元寇よりも約160年前の1019(寛仁3)年、刀伊族が壱岐を壱岐に攻めてきました(刀伊の入寇)。この時、刀伊族との激戦があったと伝えられる場所が壱岐の西海岸部の片苗湾付近と云われています。刀伊族を壱岐国司の藤原理忠が迎え撃ちましたが、激戦の末、戦死しました。この戦いでは藤原理忠をはじめ、148人が戦死、239人が捕虜として連れ去られたと云われています。この古戦場跡を見下ろす丘の上に理忠の墓と伝えられる積石塚があります。地元では「理忠(りちゅう)さんの墓」と親しみを込めて呼んでいます。
海底線史料館
長崎は近代化・グローバル化に欠かせない役割を果たした海底電信ケーブル発祥の地でもある。近代化産業遺産(情報伝達の質・量を飛躍的に拡大させ社会変革をもたらした電気通信技術の歩みを物語る近代化産業遺産群)
〒850-0075 長崎県長崎市西泊町22
ヴァリニャーノ(口之津港緑地公園)
ヴァリニャーノら宣教師の活動の結果、カトリック教会は北九州を中心に信者を増やし、戦国大名の中にも熱心な信者が現れた(注:大友宗麟(おおともそうりん)、大村純忠(おおむらすみただ)、有馬晴信(ありまはるのぶ))。
〒859-2504 長崎県南島原市口之津町
平成24(2012)年に口之津開港450年を記念してイタリアのキエーティ市から寄贈されたヴァリニャーノ神父の胸像があります。
神父は1579年に南蛮船で口之津港に来航し、有馬のセミナリヨ設置や天正遣欧少年使節の派遣、全国宣教師会議を口之津で開催するなど、当時のキリスト教の布教に大きな功績を残した人です。
有馬セミナリヨ跡
巡察師ヴァリニャーノの布教方針のもと、1580年に日本で初めてつくられたイエズス会の初等教育機関。日野江の城下町(有馬)のほかに安土(滋賀県)にも設立された。
〒859-2412 長崎県南島原市南有馬町乙1395
有馬には1587年初頭まで置かれ、安土と統合された後、領内の八良尾・加津佐・有家、そして長崎へと移った。キリスト教を取り巻く状況の変化により、1601年に再び有馬に設置され、1612年まで継続した。この推定地は、1612年まで設置されていた場所である。
https://oratio.jp/p_burari/ariienoseminariyonoatoniauutsukusiibohi
南蛮船来航の地
この浦を、キリシタン大名大村純忠がイエズス会に寄進し「御助けの聖母の港」と改名した。これがのちに物議をかもすこととなる。
〒851-3509 長崎県西海市西海町横瀬郷
千々石ミゲル夫妻(と思われる)墓石
〒859-0415 長崎県諫早市多良見町山川内57
遣唐使船型展望台
遣唐使
〒853-0601 長崎県五島市三井楽町濱ノ畔
雲仙観光ホテル
近代化産業遺産(外貨獲得と近代日本の国際化に貢献した観光産業草創期の歩みを物語る近代化産業遺産群)
〒854-0621 長崎県雲仙市小浜町雲仙320
荒木宗太郎の墓
豪商
〒850-0821 長崎県長崎市高平町24
小菅修船場跡
近代化産業遺産、明治日本の産業革命遺産
〒850-0934 長崎県長崎市小菅町5
大浦天主堂
〒850-0931 長崎県長崎市南山手町5−3
以下、対馬のロシア関係の世界史観光スポットをいくつか。
日露友好の丘
〒817-1703 長崎県対馬市上対馬町西泊
ロシア軍艦泊留地跡(文久元年 魯寇之跡)
ロシアによる対馬占拠
〒817-0513 長崎県対馬市美津島町昼ケ浦, 34.321496554284565, 129.26709304003066
ステッセル将軍一行上陸の碑
日露戦争
〒852-8004 長崎県長崎市, 32.748908849480564, 129.86345202647036
帝政ロシア長崎領事館跡
ロシア
〒850-0931 長崎県長崎市南山手町11−11, 32.73317180082028, 129.8673518246169
梅ヶ崎ロシア仮館跡 レザノフ
〒850-0842 長崎県長崎市新地町6−6
旧長崎内外クラブ
〒850-0862 長崎県長崎市出島町6−9−22
近代化産業遺産(旧居留地を源として各地に普及した近代娯楽産業発展の歩みを物語る近代化産業遺産群)
旧グラバー住宅
近代化産業遺産、明治日本の産業革命遺産
〒850-0931 長崎県長崎市南山手町8−8
三菱重工業長崎造船所史料館(※工事のため臨時休館中)
近代化産業遺産、明治日本の産業革命遺産
〒850-0063 長崎県長崎市飽の浦町1−1
端島炭坑
近代化産業遺産、明治日本の産業革命遺産
〒851-1315 長崎県長崎市高島町
高島炭坑
近代化産業遺産、明治日本の産業革命遺産
大音寺(81代長崎奉行・松平図書頭康平の墓)
文化五年(1808年)のフェートン号事件で切腹した松平康平の墓所。
〒850-0831 長崎県長崎市鍛冶屋町5−87
ハウステンボス宮殿
Huis Ten Bosch。バブル経済期に構想が浮上し、平成4年(1992)開園。中世オランダの町並みを再現したもので、アトラクション・レストラン・美術館・ホテルなどの施設がある。1997年に年間入場者数380万人を記録も、その後は伸び悩み、2003年に会社更生法の適用を受けた。2010年に旅行会社エイチ・アイ・エス(HIS)の傘下に入り経営を再建。
〒859-3243 長崎県佐世保市ハウステンボス町1−1
シーボルト記念館
シーボルト
〒850-0011 長崎県長崎市鳴滝2丁目7−40
ド·ロ神父記念館
諸説あるパスタ発祥の地のうちの一つでもある。お土産には「ド・ロさまそうめん」を。
昭和56年12月、ド・ロ神父(地元の人々は、今も敬愛の念を込めて「ド・ロさま」と呼んでいます)にゆかりの深い、出津修道院のシスターが当時見聞きしていたかすかな記憶を手がかりに、地元の生活改善グループの人たちがド・ロさまそうめんの復活に取組みました。
最後に松浦市の銘菓・てつはうも紹介しておこう。
これは元寇の舞台となった鷹島にちなむものだ。とくにパスパ文字や、クビライ・ハーン治世下の年号がみえる管軍総把印が重要史料である。
なお現在の鷹島はモンゴルのホジルト村と姉妹関係にあり、ゲルの設置された「モンゴル村」もある。
熊本県:「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の構成県
天草市立天草キリシタン館
〒863-0017 熊本県天草市船之尾町19−52
尼港事変殉難者碑
尼港事件
〒863-2424 熊本県天草市五和町手野1丁目
三角西(旧)港
近代化産業遺産、明治日本の産業革命遺産
〒869-3207 熊本県宇城市三角町三角浦
三角西港を描いた坂口恭平さんのパステルが素敵だ。
今日のパステル画。三角西港の光。 pic.twitter.com/fJDuqUNVSF
— 坂口恭平 (@zhtsss) September 13, 2021
石光真清記念館
『城下の人』『曠野の花』で知られる軍人。
〒860-0821 熊本県熊本市中央区本山4丁目7−63
大分県:リーフデ号漂着の地
リーフデ号の漂着地
静岡県、長崎県でも登場したウィリアム・アダムズの乗った船・リーフデ号の漂着した地点。
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目4
廣瀬武夫に関連する史跡。
広瀬神社
〒878-0013 大分県竹田市竹田2020
廣瀬武夫記念館
〒878-0013 大分県竹田市竹田
育児院と牛乳の記念碑
〒870-0021 大分県大分市大手町1丁目3−2
府内に育児院が建てられた事と、育児院で牛乳が飲用されたことを祈念する彫刻です。
1557年、ポルトガルの青年医師アルメイダが、日本最初の西洋式病院を府内に建てました。
また、当時日本は戦乱が続き、貧窮から赤ん坊を殺す悪習があり、これに胸を痛めたアルメイダは自費で育児院を建て、赤ん坊を収容し、乳母と牝牛を置いて育てました。
これは、近世における福祉事業の先駆けとなりました。
なお、大分のアルメイダ病院は彼の名にちなむ。
アルメイダは長崎を1569(永禄10)年に訪れており、碑文が春徳寺(→長崎県)にある。また、熊本・玉名の銘菓「松の雪」は、彼が製法を指南したとつたえられる。
宮崎県:伊東マンショ像
世界史観光スポットの少ない宮崎県であるが、ひとつだけ挙げることができる。
伊東マンショ像
遣欧少年使節団
〒887-0021 宮崎県日南市中央通1丁目
小村寿太郎生誕地
〒889-2535 宮崎県日南市飫肥5丁目2−20
ポーツマス条約や日英通商航海条約締結(不平等条約の改正)に尽くした外交官・政治家。飫肥城のすぐ近くにある。
鹿児島県:鉄砲伝来と薩摩スチューデント渡欧の地
「鐵砲傳来 葡國人上陸之地」碑(ポルトガル人上陸の地碑)
鉄砲伝来
〒891-3705 鹿児島県熊毛郡南種子町西之7288
種子島開発総合センター「鉄砲館」
〒891-3101 鹿児島県西之表市西之表7585
露国皇太子ニコライ殿下来麑記念碑
ニコライ皇太子
〒892-0853 鹿児島県鹿児島市城山町3−35
薩摩藩英国留学生渡欧の地
〒896-0064 鹿児島県いちき串木野市羽島4930
旧集成館(旧集成館反射炉跡・旧集成館機械工場・旧鹿児島紡績所技師館)
(※2024年9月までリニューアルのため休館)
近代化産業遺産、明治日本の産業革命遺産
〒892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町9698−1
鑑真記念館
〒898-0212 鹿児島県南さつま市坊津町秋目225−2
硫黄鳥島
日宋貿易、日元貿易、硫黄の産地
〒901-3125 沖縄県島尻郡久米島町鳥島
徳之島のカムィヤキ
大陸との交流
〒891-8201 鹿児島県大島郡伊仙町伊仙
沖縄県:「万国津梁」の琉球王国と軍事遺構
久米至聖廟
中継貿易
〒900-0033 沖縄県那覇市久米2丁目30−1
北大東島燐鉱石採掘関連遺産(旧東洋製糖北大東出張所跡)
近代化産業遺産(近代の沖縄経済に貢献した『2つの黒いダイヤ』製糖、石炭両産業の歩みを物語る近代化産業遺産群)
海洋文化館
樺太南部とともに激しい地上戦に見舞われた沖縄には、旧日本軍が構築した砲台跡や塹壕、トーチカ、兵舎跡など、おびただしい軍事遺構(約1000か所)が残されている。たとえばこちらを参照されたい。
参考文献・サイト
・歴史散歩シリーズ(山川出版社)

・稲生淳 2015 『熊野海が紡ぐ近代史』森話社
・岩下哲典・中澤克昭ほか 20123『信州から考える世界史』えにし書房
・藤田賀久監修 2021 『神奈川から考える世界史』えにし書房
・村井章介ほか 2018 『世界史とつながる日本史:紀伊半島からの視座』ミネルヴァ書房
・桜井祥行 2002 『伊豆と世界史:豆州国際化事始め』批評社
・文化遺産オンライン
・小原淳2020「北海道に存するドイツ関連史跡の総合的検討 ── 日独関係史の再検討に向けて 」『WASEDA RILAS JOURNAL』8、
https://www.waseda.jp/flas/rilas/assets/uploads/2020/10/053-064_Jun-OBARA.pdf
・近代化産業遺産
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/creative/kindaikasangyoisan/index.html
・日本遺産ポータルサイト
・発祥の地コレクション
・日本のなかのロシア
・BRUTUS「世界の食文化に触れられる料理店 WEB版マップ」
・日本の銅像探偵団
・駐日欧州連合代表部「日本にいながらヨーロッパを楽しむ! 欧州テーマパークの世界」、2021年
このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊
