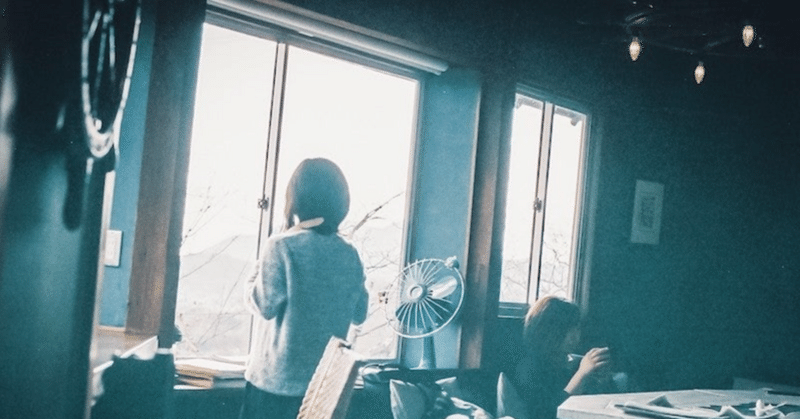
ドームのセンステから飛び降りる。【第11話】
「ねえ、明日さ、何着て行こうかな」
切り替え速いな。
「何でもいいと思う。でも、それこそダサいのはやめたほうがいい。会場ってお洒落なお姉さま方が多いから」
だから、男装するようになったんだよ。私には出る幕もないし、目に映らないだろうって思ったからだよ。
「ワンピースとかは?」
「いいと思うよ」
うーん、と一葉ちゃんは悩み込んだ。
「そうだ、双子コーデはどう?」
私たちが双子? 無理があるような気はする。顔もスタイルもだいぶ違う。私は割と直線的な顔だけれど、一葉ちゃんは猫みたいな顔をしている。パーツに丸みがあって愛嬌がある。なかなか、二人のどちらともに似合う服は見つからないだろう。
「似合うのがあるといいけどな」
ワンピースかな。でも、一葉ちゃんにはふわふわのものが似合いそうだし、私はボリュームが抑えてあるものの方が良さそう。生地も、形も、工夫しないと同じものは着られないだろうな。
「ねえ、これは?」
幼い少女のように一葉ちゃんは訊いてくる。手に持っていたのはクラシカルなワンピースだった。水色のドレスにも見えるような。
「ちょっと私には可愛すぎるんじゃない? 私ってコテコテのガーリーは似合わないと思うし」
「そんなことないよ。澪って笑うと顔がくしゃってなって可愛いし」
そうかな? でも、着てみる価値はありそう。私もこういう服に憧れあったし。
「試着室行こうよ」
手を引かれて、奥の試着室に連れていかれた。私は右の部屋に入って、一葉ちゃんは左の部屋。
「もう着替えられた?」
「うん」
「開けるよ」
一葉ちゃんには絶対に似合う。ジャージでも、制服でも、一葉ちゃんが着ればなんでも可愛く見えるから。
顔を覗かせた一葉ちゃんは、顔を赤らめていた。見れば、チュールがひらひらと一葉ちゃんの動きに合わせて揺れていた。不思議の国のアリスを連想させるようなビジュアルだ。
「んは、澪めっちゃ似合ってるんだけど」
「一葉ちゃんも似合ってる」
間違いなく、これだと確信した。これ以上に、二人にぴったりな服はあるのだろうか。
明日が来なければいいのに、とライブに行く度に思う。前日が一番楽しい。本番は夢現な感じで、現実味がないし、席が遠かったらあんまり気分が上がらない。でも、結局は生歌が聴けるだけで嬉しかったりもする。
「明日は楽しみだね」
うん、と軽く返事をした。
ただ、アイドルとしての彗が好きなだけで、それ以外の何でもなかった。それが安心材料になったのか、不安材料になったのかわからない。でも、リアコであることで雑念はあったと思う。彗は私のもの、みたいな思考が頭の片隅にはあった。だから、それが取り払えただけで大きなことだと思う。
でも、彗は明日どうやって私たちの前に現れるのだろうか。頭を下げるだろうか、それとも普段と変わらずにファンサをしてくれるだろうか。私は後者の方がいい。
あっという間に日が暮れて、朝が来た。ライブ当日。ドキドキワクワクのライブ参戦。午前中はのんびり準備して、三時に会場に集合する。そして、思いっきり写真を撮って楽しんでから、会場に入る。何の憂いもなく、戸惑いもなく挑めるようにする。
スマホのバイブで起きた。
「澪、起きてる?」
「起きた、が正しいね。今、電話に起こされたよ」
電話越しでも落ち着きがないことが伝わってくる。
「居ても立っても居られなくてさ、五時に起きちゃった」
「流石にそれは早いよ。もう少し寝た方がいいよ。体力勝負だから」
「着替えちゃったし、メイクもしたから寝ようにも寝れないよ」
かなり焦っている。初めてのライブって、私もそんなものだったかな。でも、せっかちな一葉ちゃんっぽいかも。
「だーかーらー、私なんて今起きたところだよ? 落ち着いてよ」
「落ち着けって言われてもさ、体がムズムズするっていうか、もう立っていられないんだよね」
「深呼吸して。まだゆっくりしててもいい時間だし」
一葉ちゃんは二回ほど深呼吸をした。
「とりあえず、スクワットして、フリースローするわ」
「その格好で?」
「うん。一番落ち着けるもん」
一葉ちゃんらしいね。本当にバスケが好きなんだね。そう思いながら、電話を切った。
やっと落ち着いたかと思えば、階段を上がってくる音がした。
「澪ちゃん? いるの?」
やばい。お母さんがくる。片付けなきゃ。
扉が開いた。お母さんが顔を覗かせる。
「澪ちゃん、今日どこか行くの?」
「うん。ちょっと友達と出掛けようかなって思って」
なんでこんな微かな物音と、電話の話し声だけで気づくの? と言いたいところ。
「それにしては、少し派手なんじゃない? その服。なんか、露出多いし」
しくじった。服をクローゼットにかけたままだった。
「別に、何着ようが私の自由じゃない?」
すると、お母さんは形相を変えた。
「澪ちゃんのために言ってるの。だいたい、友達なんていなくてもいいって言ったじゃない。いつかは離れ離れになるし、疲れて傷つくだけよ」
ほとんどの人と関わればそうなるけど、一葉ちゃんは違うの。でも、それを言ったところでお母さんは理解しようとしない。自分の生き方を曲げたくないのだ。
「澪ちゃんが傷ついたらさ、お母さんが悲しむことわかるでしょ? 露出が多い服は変な人が近寄ってくるかもしれないし、友達と街を練り歩くのだって危険よ。何より、その友達って誰なの? どういうお家の子なの?」
あー面倒くさい。また尋問が始まる。
「それは今関係ないでしょ?」
「関係あるのよ。澪ちゃんが心配だから」
じゃあ、心配しないで。また言えない。言っても無駄だし、お母さんのヒステリックはどうにもならない。急に叫び出して、暴れて、家をかき乱す。折角、普段お母さんが整えている家なのに。
「とりあえず、私は二時半に出て行くから」
「嫌だ。行かないで」
あーたぶん、私が友達をつくれないのはこの人のせいなのかも。今気づいたわ。
「もう、最悪」
扉を閉めて無理やり追い出した。
今日はこんなこと忘れたいの。煩わしい学校の空気とか、家の雰囲気とか、お母さんとか全部投げ出したい。
辛くてどうしようもない、という状況に初めて陥ったときに出会ったのが彗だった。中学一年のときは、お母さんと担任の板挟みになっていた。部活もあったし、今よりも友達はいたから、かなり忙しい中で、だった。
お母さんは熱心なクレーマーだ。暴走し出したらお父さんでさえも止められない。私の成績が急に落ちたら、電話。部活で少しトラブルがあったら、電話。友達と喧嘩したら、電話。体調を崩して丸一週間休んだら学校に責任転嫁して、電話。心配事は一点集中で学校に攻撃を加えた。担任を困らせていた。
担任が少し精神を病んできたときに、学年主任が私に話しかけてきた。
「申し訳ないんだけど、澪さんの方から何とか言ってもらえないかな?」
ってね。どっちが親なのかわからないような状況だった。収拾がつかなくて、お父さんも一カ月仕事を休んだ。
お母さんはセーターのほつれみたいだ。家族が規則的に、組み合わさって絡まっていたとしても、お母さんを発端にして少しずつ結束力が弱くなる。やがて、形をなさなくなるのではないかと思う。でも、お父さんはまだ懲りていない。それは、自分の最愛の人だからね。でも、私にとってお母さんは所詮お母さん。血が繋がっているだけの飾りに近い。私はお母さんを選んだわけじゃない。今はただ、お母さんが障害になっている。生きる障害に。
まだ言い訳に聞こえるだろうか。それなら、私はこの家を出たい。恐らく叶わない願望だけれど。
そそくさと準備をして、少し早めに家を出た。気分が悪いから。
To be continued…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

