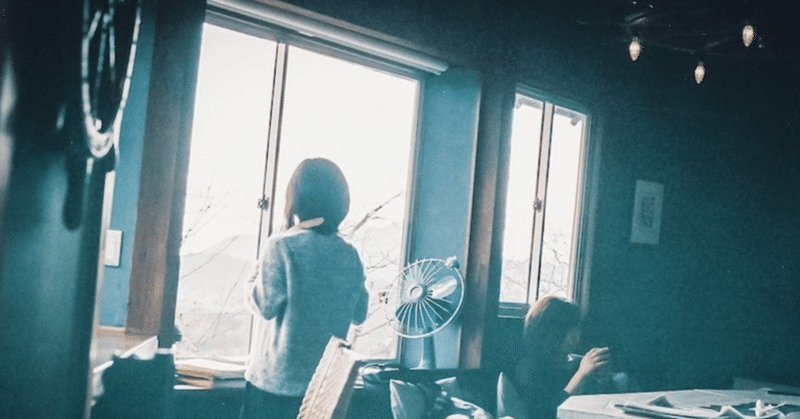
ドームのセンステから飛び降りる。【第4話】
「待って、一葉ちゃん。それじゃ、アイドルしか使えなくない?」
「たしかに。ステージに立てる人しか、使用許可下りないね」
笑いながら、コンビニを出た。百均に向かいながら、スキップした。
重いスカートがひるがえりそうになる。危うく、痣が見えるところだった。バスケをやれば、痣ができてしまう。膝とか、太ももとか、あらゆるところの青痣を隠しながら生活している。
百均では、四つ切画用紙とカッティングシートを買った。澪が店員さんに、
「これって、何円ですか?」
と訊いたときは流石に驚いた。店員さんは困惑の色を浮かべていた。
「最近は、二百円とか五百円の商品も多いからね」
とフォローするのが、精一杯だった。
はず、と手で顔の周りを仰ぐ澪。男装していることは忘れて、地声で質問したからより驚かれただろうに。
チロルチョコも追加してレジを通った。
「そういえば、いつもチョコの包み紙で鶴を折ってるよね」
エコバッグを持ってきていないから、素手で画用紙を持って帰るしかない。澪は後悔したような、ミスを悔やむ顔をした。
「なんで鶴なの?」
「この世界のどこかの、病気とかで苦しんでいる人のために祈ってるの」
「だいぶ抽象的だけど、澪らしいね」
もしかしたら、世界を救うのは愛でもスーパーヒーローでもなくて、こういう小さな優しさなのかもしれない。もしくは、それを愛と呼ぶのかもしれない。つまり、あの折り鶴は地球を救う可能性がある。
外に出ると梅雨の湿っぽい風が吹いていた。
「結局どうするの? 鶴」
「普通に、お見舞いとかに送ろうかな。おばあちゃんとか」
ちょっと面白いかも、と思った。あの小さい、絶妙にカカオの香りが残る折り鶴が病室に飾られるのが。
「よし、うちわつくってこっか」
「乗り気なんだね。ありがと」
澪はさして嬉しそうではないが、足取りは軽かった。
私も行っていいかな、それを言えたらどれだけいいだろうか。一度だけでいいから、澪が愛してやまない彗を見てみたい。
退屈で窮屈で、抑圧された生活を彗が変えてくれたらしい。澪が言っていた。私にもそういう存在がいれば、楽天的にも生きていけるのかもしれない。でも、変わろうとすれば思うほど、自分の今までを否定するみたいで怖い。
ボロアパートのドアを開けた。家賃が驚くくらい安い。この周辺ではありえない値段らしい。不動産業をやっているおじさんが言っていた。
「どうやってつくるの?」
「簡単だよ。印刷した紙を画用紙に張り合わせて、うちわの形に切るだけ。細かいこと言えば、穴を開けてリングに通すって感じかな」
リングは、単語帳の端を留めているような事務用のものでいいらしい。百均で売っていた。
本当に簡単にできて、二人で作業すれば三十分もかからなかった。
「できたね」
「飛び降りてのやつ、一番前にもってきてよ」
「嫌だね」
見せるつもりはないな、と悟った。
「私も行っちゃだめかな」
「え、ライブに行くってこと?」
私は頷いた。
「今日の映画でファンになったの? でも、私は同担拒否だから他の人を推してね」
そういうことじゃない。弁解の余地あり。
「違う、澪がそれほど夢中になる彗を見てみたくなったの。生で」
なるほど、と言いながら澪は椅子に腰かけた。
「いいよ。私、他に友達いないから一緒に入る予定の人いないし」
「私もできることは、手伝うから」
一筋の希望が見えた気がする。私の好きな人、の好きな人を見る。そうやって、世界が繋がっていく。地球を救うのは愛じゃなくて、片想いなのかもしれない。こんなにも心と体が突き動かされるのは、澪のおかげだと思うから。
「何食べたい? デリバリー頼む?」
普段は適当なものしか食べていないから、こういうときどうすればいいのかわからない。そもそも、家に友達を入れたのも初めてだ。でも、抵抗はなかった。ただ、全く後先のことを考えていなかった。
「頼もう。ピザもいいし、ハンバーガーもいいよね」
「結構ジャンクだね」
最近はダイエット食しか食べていないからか、聞いただけで胃がもたれる。
「私は、海鮮丼とかでいいかな」
「じゃあ、私もそうする」
デリバリーが届くのを待っている間、しばらくの沈黙が流れた。
私は、再びあの言葉を思い出した。「生産性」の三拍のリズムが、脳裏に焼き付いてしまった。
インターフォンが鳴った。
「速くない?」
「出てくるわ」
重いドアが軋む。
「ちょっと、やめてってば」
菜々子の声がした。嫌な予感しかしない。
「入らせろよ、なあ」
ドスの利いた、しゃがれた声だ。たぶん、菜々子の恋人。そう察知し、瞬時にドアを閉めた。
「一葉ちゃん、どうした?」
「ううん。なんでもない」
「海鮮丼は?」
まだみたい、と言って心を落ち着かせる。大丈夫、大丈夫。ドアを閉めたら安心だ。一度大きく波打った心臓の音は、しばらく残響している。まだ、体の奥で反響している。汗が噴き出そう。本当に、菜々子ってろくなことしない。
「おーい。一葉ちゃんよお。開けてくれよ」
馴れ馴れしく名前で呼ぶなよ、と思いつつツーロックをかけた。
「ねえ、やめて」
「はあ?」
ドアを叩く音が頭に響く。
澪が怯えている。澪の家はこういうことがないから。
「大丈夫。いずれ、帰る」
「そっか」
ガタガタ震えている澪を横目に、どうにかしなければならないと考えを巡らす。
ドアを叩くテンポが徐々に速くなっていく。そして、バーンと鈍い音を立ててドアが壊れた。
「やめてって言ってるじゃん」
「一葉ちゃん、明日から僕がお義父さんだよ」
「どうにかしてよ、菜々子」
呆れながら言った。でも、菜々子は何もしない。
「どうにもなんないわよ。別れるって言ってるのに、聞かないの」
「お義父さん何人目だよ。もう、もううんざり」
澪が口を開けたまま、静止している。
「一葉ちゃんには手を出さないで」
菜々子の恋人らしき人が殴りかかってくる勢いで、こちらに向かってくる。
「うるさいよ。菜々子もいい加減、目覚ませよ。もう、四十でしょ? 自分の力で地に足つけて働いて、食べていくとか考えないわけ? 私だって、いつまでも子どもじゃないんだよ。別に、あんたに母親らしいことされた記憶ないけどさ。とにかく、この家出て行ってくれない?」
「それが母親に利く口なの?」
「あんたのこと、母親だって思ったこと一回もない」
澪を和室に避難させた。菜々子は半ばヒステリックになって、髪をかき乱している。そして、涙と鼻水で顔をぐちゃぐちゃにしている。
「最近の一葉ちゃん見てると、お父さんのこと思い出すの。葉一さん。あなたと私、似ているところを探そうとしても、全然似てない。でも、葉一さんとあんたはそっくり。だから、この家に居づらいのよ。わかった。出て行くよ」
「そうやって、すぐ言い訳するよね。私に謝ったりとかしないわけ?」
「ごめん。謝って済む問題じゃないじゃん。わかるよ。でも、私はあなたのこと愛して……」
「愛してなんかない」
気付けば、叫び出していた。
「あんたが私のことをどうでもいいと思ってるの、知ってるから」
To be continued…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

