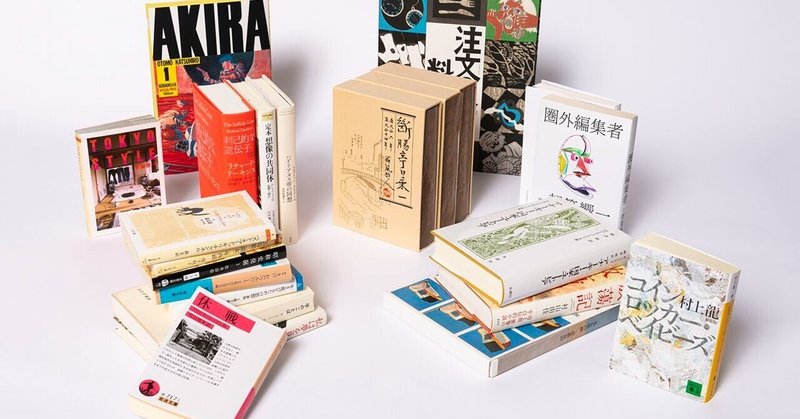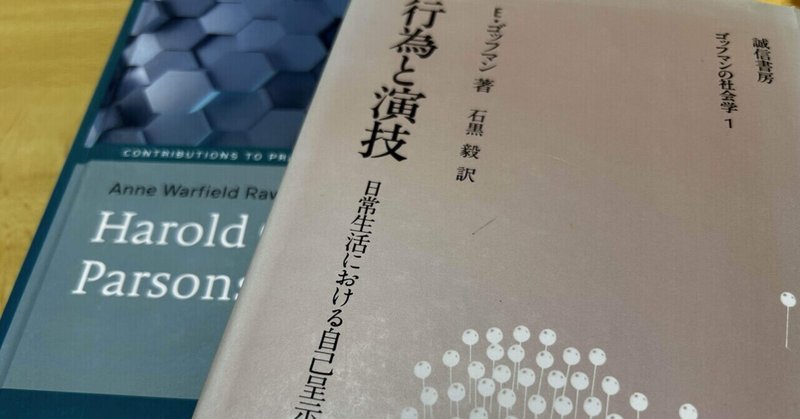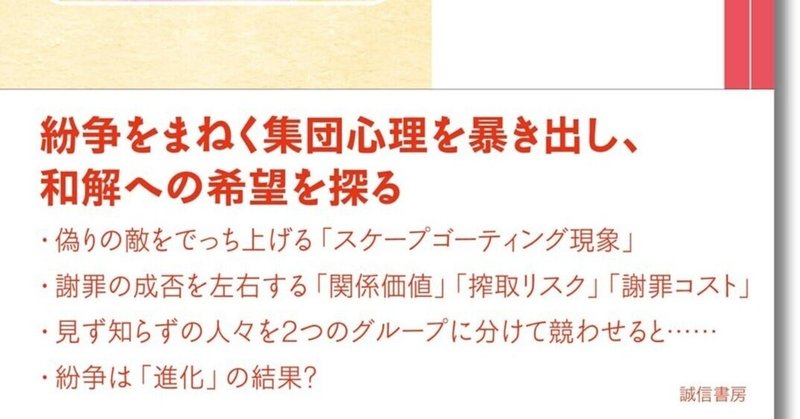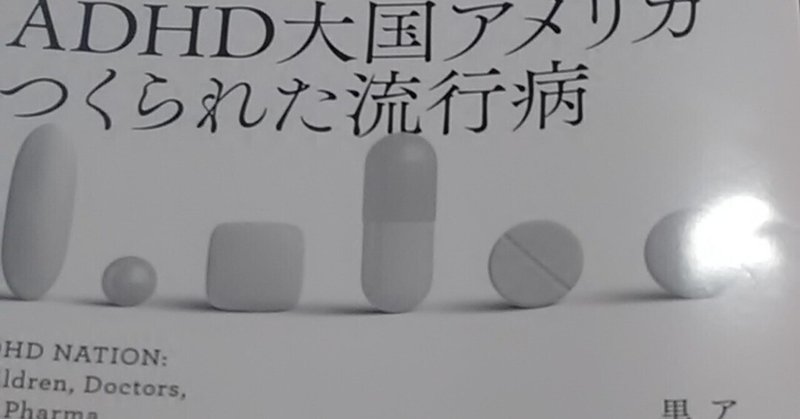記事一覧
#283:河合隼雄著『カウンセリングの実際問題』
『カウンセリングの実際問題』(誠信書房, 1970年)を読んだ。私は本書を20代の頃に一度読んでおり、その本は手元にあるのだが、考えたいことがあってもう一度読んでみようと取り出したら、あらゆるページにびっしりと赤鉛筆で傍線が引いてあったので、改めて新しく本を買い直した。手元に届いた本は、2021年発行の第60刷とあり、本書が今も読み継がれているロングセラーであることをうかがい知ることができる。
自分を救えるのは自分しかいない-片岡一竹著『疾風怒濤 精神分析入門』(誠信書房,2017年)書評
精神分析の面白いところは、人は誰もが狂気的で変態的な生き方をしている、というやや厭世的な前提からはじまることです。
「自分はどこかおかしい」といつも考えてしまうのは、人間の初期設定なのかもしれない。
精神分析には健康や健常者という概念が無いため、「苦しいのは精神が病んでいて不健康な生活をしているからだよ、一緒に治そうね。」とは言いません。
代わりに、苦しいのは「自分が納得できる〈生き方〉」を見つ
影響力の武器[新版]:人を動かす七つの原理 ビジネス書レビュー
はじめに
「影響力の武器[新版]:人を動かす七つの原理」は、ロバート・チャルディーニ博士による社会心理学の理論を基に、人の行動に影響を与えるための原理を明らかにした書籍です。これまでの6つの原理「返報性」「コミットメントと一貫性」「社会的証明」「好意」「権威」「希少性」に加え、新たに「承諾誘導戦略」を加えた7つ目の原理が紹介されています。
概要
本書では、日常生活におけるさまざまな場面で、私
【影響力の武器】自分の意見が素通りする5つのトリガー【なぜ人は動かされてしまうのか?】
みなさんこんにちは!あなたをモチベートと申します。
最初に一つだけみなさんにお願いがあります。今回お伝えする言葉は盛りだくさんになるんですが、その中で「一つだけ」、たった「一つだけ」でいいのでみなさんの今後に役立つような内容を持って帰っていただきたいんです。あなたが重要だと思ったこと、胸に響いた言葉、その一つのエッセンスがあなた自身の人生を良くするカギになってくれるはずです。
ということで、今
『終わりのない質問』を読む
引き続き、ボラスのインストール中だ。なるだけ臨床に接地したボラスを読む。2011年に誠信書房から出版された『終わりのない質問』を紐解く。原書は"The Infinite Question"で、2009年にラウトレッジ社から出ている。本書には、3名の被分析者のセッション記録が逐語的に載せられており、そこに対するボラスの後知恵が付されている。分析家の頭のなかを垣間見ることができるという点でも興味深い
もっとみる医療職・福祉職・心理職におすすめ!性の多様性の本 - 司書の本棚
こんにちは。
respectrum(リスペクトラム)の小川奈津己(おがわなつき)です。
「司書の本棚」では、多様な性に関する本をご紹介していきます。
今回のテーマは医療・福祉・心理に関する本です。
吉田絵理子ほか(2022)『医療者のためのLGBTQ講座』南山堂
葛西真記子(2023)『心理支援者のためのLGBTQ+ハンドブック 気づき・知識・スキルを得るために』誠信書房
佐々木掌子(20
酒と本の日々:ADHDの生みの親、キース・コナーズの伝記として
アラン・シュワルツ『ADHD大国アメリカ つくられた流行病』(誠信書房、2022)
こういう題目の本を、ジャーナリスティックとかセンセーショナルな話題にすぎないとして敬遠する人は多いと思う。精神医療『噂の眞相』班をもって任ずる僕の紹介ならなおさらだろう。
だが、ADHDの過剰診断と精神刺激薬の乱用はすでにアメリカでは社会問題になっており、それでも逆に子どもの診断マーケットが飽和して大人の領域





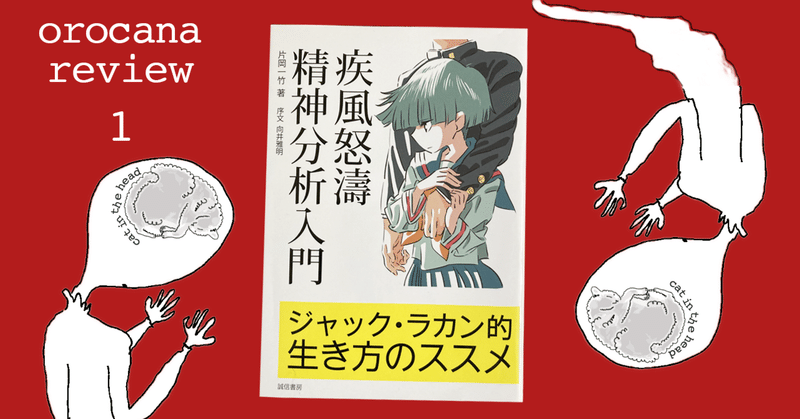

![影響力の武器[新版]:人を動かす七つの原理 ビジネス書レビュー](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/131401833/rectangle_large_type_2_a341e6544ca0cbbd0499f7e72869133b.png?width=800)