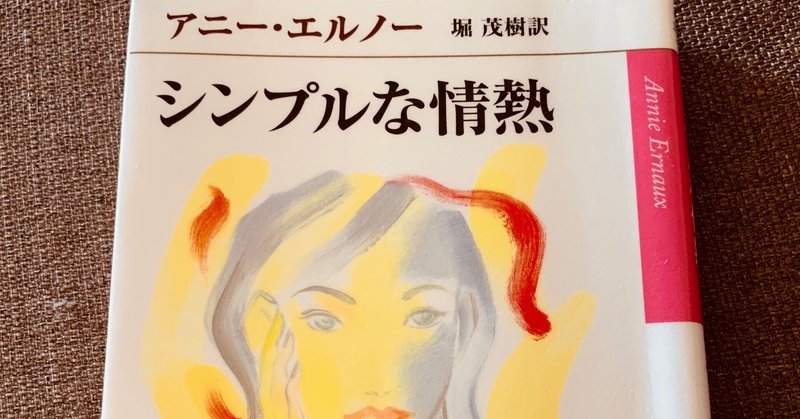
【読書録】『シンプルな情熱』アニー・エルノー
今日ご紹介する本は、フランス人のノーベル文学賞受賞作家アニー・エルノー(Annie Ernaux)氏の小説、『シンプルな情熱』(原題は『Passion simple』)。
私の読んだのは、冒頭の写真のハヤカワepi文庫版。堀茂樹氏の訳によるものだ。
1991年に発表された作者の自伝的作品で、自身と不倫関係にあった既婚の年下男性との関係や、自身の愛情や気持ちの変化について赤裸々に告白し、大反響を呼んだ作品だ。2020年に映画化もされている。
この作品は、禁断の恋に身も心も支配されてしまった女性の心理をとてもよく描いている。賛否両論があったようだが、私にとっては、紛れもない名作だ。
以下、いくつか特に心に残った箇所を引用しておく(以下ネタバレご注意ください)。
昨年の九月以降、私は、ある男性を待つこと ー 彼が電話をかけてくるのを、そして家へ訪ねてくるのを待つこと以外、何ひとつしなくなった。
会話の流れの中で、私の無関心を突き破ってくる話題といえば、彼、彼の役職、彼の故国、彼が行ったことのある土地などに関連する話題だけだった。
私にとって、未来への展望といえば、いつ会うかを決める次の電話だけだった。
私はよく、ひとつの願望と、自分が引き起こすか犠牲になるかする事故、病気など、多少とも痛ましい何かとを天秤にかけてみる。私が自分の願望の強さを計測しようとする ー そしてたぶん運命に挑戦しようともする ー とき、イメージを惹起して、自らの心にその願望の代償を支払う覚悟を問うてみるのは、かなり信頼できるやり方なのだ。
私はまた、彼と何回交わったか、足し算してみたものだ。毎回、新たに何かが私たちの関係につけ加わるように思えたけれど、しかしまた、そのほかならない行為と快楽との積み重ねによって、私たち二人の間が確実に隔てられていくのだとも、私は感じていた。蓄積した相手への欲望を、とことん消費していったのだから。肉体的昂奮の強度が増せば、その分を、時間の持続において失うのだった。
彼が来ていたある日の午後、私は、居間の床に火から下ろしたばかりのコーヒーポットを置き、敷いてあった絨毯を、糸目が見えなくなるほど焦がしてしまった。ところが、まったく気にならなかった。それどころか、その後、その焼け焦げが目に入るたびに、彼と過ごしたその午後を思い出して、私は幸せな気分になった。
RERや地下鉄の車内、各種の待合室など、何もしないでいてもおかしくない場所ならどこでも、私は、腰を下ろすやいなや、Aをめぐる夢想に入った。その状態に没入すると、瞬時にして、頭の奥にしびれるような充足感が生じるのだった。それは肉体的快感に身をゆだねるような感じだった。あたかも脳髄も、繰り返し押し寄せる同じイメージ、同じ記憶の波に反応して、性的な悦びに達することができるかのようであり、他と変わることのない性器の一つであるかのようだった。
私は是が非でも、彼の躰を、髪から足の指にいたるまで思い起こそうとした。そして、彼の緑色の眼や、額の上で揺れる前髪や、両肩の曲線を、細かい部分まで明瞭に思い描くことに成功した。彼の歯を、口の内部を、大腿部の形を、肌触りを感じた。私は思った。このイメージによる再構成とある種の幻覚、記憶と狂気の間は紙一重だと。
あの夜帰ってきた男も、彼がいた一年間、そしてそのあとの執筆期間、私が自分の内にずっと抱き続けていた男性ではない。ほかでもないその男性には、私は絶対に再会することがないだろう。が、それにもかかわらず、あの非現実的で、ほとんど無に等しかったあの夜のことこそが、自分の情熱の意味をまるごと明示してくれる。いわゆる意味がないという意味、二年間にわたって、この上なく激しく、しかもこの上なく不可解な現実であったという意味を。
私は、人がその気になればどんなことを仕出かし得るか、何でもやりかねないのだということを発見した。崇高な、あるいは致命的な欲望、みっともないふるまい、あるいはまた、自分自身がそれに頼ったり訴えたりすることになるまでは他人事として見て、およそばかげていると思っていたある種の信心や行動・・・・・・。彼は、彼自身の知らぬ間に、私を以前より深く世界に結びつけてくれた。
子供の頃の私にとって、贅沢といえば、毛皮のコート、ロング・ドレス、それに海辺の別荘だった。その後、贅沢といえるのは、知識人の生活を営むことだと信じた。今の私には、贅沢とはまた、ひとりの男、またはひとりの女への激しい恋を生きることができる、ということでもあるように思える。
主人公の「私」(作者)は、東欧の外交官をしていた既婚の年下の男と恋愛関係になり、彼が時々通ってくるのを待つ日々を送る。気が付けば、いつも愛する男のことばかりを考えてしまう。それ以外のことに、何ら集中できなくなる。
どうしようもなく、やるせない情熱。狂気と紙一重であり、ストーカーと言われてもおかしくない行動をも取ってしまいそうになる。恋をしたことのある女性ならば(あるいは男性も)、誰でもこういった気持ちに感情移入してしまうのではなかろうか。
そして、男が本国に帰国してしまうと、作者は、やり場のない感情とともに日々を過ごしていった。長い音信不通期間を経て、ある日突然、一度だけ男が帰ってきて、一夜をともにした。そのとき、作者は、男が、自分が想い続けてきた男とは別人のようであると感じた。
相手との距離感が変わることにより、感情に変化が生まれるというのも、多くの人が経験したことがあるのではないだろうか。
「私」が一人称で自分事として語っているのだが、もどかしさや、感情の移り変わる様子は、まるで自分が当事者であるかのように、リアルに迫ってきた。そして、誰かを愛するパッションが人生においてとても貴重で贅沢なことである、というフレーズにも大いに共感した。作者の文章力に、ただただ脱帽だ。
ところで、本書の最後には、女優の斉藤由貴さんの解説が収録されていた。これが、とても秀逸だった。失礼ながら、斉藤さんの文章がお上手であることに驚いた。斉藤さんについては、『スケバン刑事』のイメージしか持っていなかったが、文筆家として作品を発表されていると知った。いつか斉藤さんの作品も読んでみたいと思う。
ご参考になれば幸いです!
本作品を映画化したものはこちら。DVDのほか、Amazon Prime Videoでも観られます。
私の他の読書録の記事へは、以下のリンク集からどうぞ!
サポートをいただきましたら、他のnoterさんへのサポートの原資にしたいと思います。
