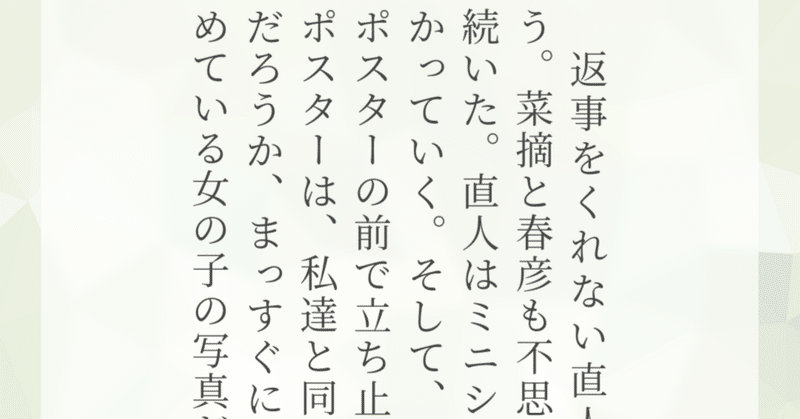
(短編)君の瞳を届けたい
「映画」をテーマに2022年12月に書いた1万字程の短編小説です。映画というより「映画館」かもしれませんが。お暇な時にでもお読みいただけますと幸いです。
そこに映画館があることは知っていた。ああいうのはミニシアターと呼ぶのか。でも、私達貧乏高校生にとって、東丸プラザの四階といえば、格安イタリアン「イタリ屋」のある場所でしかなかった。
エスカレーターで四階へたどり着き、私達四人はいつものようにイタリ屋に向かおうとした。なのに、直人が反対方向へと歩き出した。
「何、どうしたの」
返事をくれない直人の背中を追う。菜摘と春彦も不思議そうに私に続いた。直人はミニシアターへと向かっていく。そして、壁に貼られたポスターの前で立ち止まった。そのポスターは、私達と同じくらいの歳だろうか、まっすぐにこちらを見つめている女の子の写真だった。
「直人?」
横から顔を覗き込む。直人も、写真の子に負けないくらいの真剣な表情をしていた。
「更紗。ごめん。これさ、なんか、すごくない?」
「え?」
やっと私の顔を見て、直人が言う。
「視線感じた。呼ばれた」
「この女の子? 映画のポスターでしょ。誰だろ」
「俺も知らない。でも、惹きつける力がある」
「何の映画?」
春彦が私達の後ろから聞く。ポスターの下のほうに「瞳」という文字がある。あとは細かい字で、出演者やスタッフの名前が並んでいる。
「『瞳』っていう映画なのかな」
「知らないねえ」
菜摘もつぶやいた。
「あの! すみません!」
後ろから知らない声がした。私達は一斉に声の主を見る。
「その映画、興味あります?」
ショートカットの小柄な女性が、満面の笑みで私達を見ていた。服装はカジュアルで、ジーンズを履いている。両肩から大きなバッグを下げ、その片方には丸めたポスターが何本かささっている。
「なんかこの女の子の視線感じて……」
直人が応じる。その言葉を聞いた女性は、身を乗り出して話し始めた。
「でしょう! 表情がすごくいいの! あっ、その子、小川美琴っていうんだけど」
「はあ」
「ごめんなさい。私、この映画の監督なんです」
さらりとなされた発言がすぐには飲み込めず、私達は戸惑った。
「え? 監督? 映画の?」
春彦が尋ねる。
「はい! 真野和歌子っていいます。よかったらチラシを……」
真野監督はそう言うと左肩に下げたバッグを探して、チラシを何枚か引っ張り出した。それはポスターと同じ柄だった。勢いに押されるように、私達はそれぞれチラシを受け取った。
「今週の土曜からここ、シネマステラで公開するんです。主人公は高校生だし、ぜひ同年代の方に観てもらいたいなって」
「あの」
「はい!」
直人が怪訝な顔で尋ねる。
「普通、映画監督がチラシ配ったりします?」
直人の疑問を受けて、真野さんはあははと笑った。
「ですよねえ。普通はしない」
「あ、こっち地元とかですか?」
「いえいえ、全然」
春彦の問いかけを真野さんは右手を振って否定した。
「シネマステラさんが上映決めてくださって。だから、できるかぎりのことをしたいなって、東京から来ました!」
直人の持つエコバッグに、ポスターが三本ささっている。
「まずさわやか書店だろ。で、げんきラーメンはいけるな」
学校から坂を下っていく。私達、青村高校生御用達の、さわやか書店が見えてきた。
「もう一本は?」
「あー、ほら、こないだ行ったカフェ、スマイルコーヒーとか」
二人で、さわやか書店の自動ドアの前に立つ。中へ入るやいなや、直人はレジに進む。
「すみません、ポスター貼ってもらえませんか?」
店員と直人とのやりとりを、私は一歩後ろで見ていた。
「学校の行事じゃないんですよね?」
「そうなんですけど、監督が高校生に観てもらいたいって」
吹奏楽部とか演劇部とか、部活関係のポスターは時々貼ってあるの見かけるけど、こういう商業的な物は難しいのかもしれない。
「お願いします! 土曜から上映なんで俺もまだ観てないんですけど、いい映画だと思います!」
直人が懸命に頭を下げているのを観て、店員さんもかわいそうに思ったのか、とりあえずポスターは受け取ってくれた。
「上映、一週間しかないの」
「はい。その一週間でいいんで!」
じゃあ、一週間だけね、という約束で、さわやか書店の店頭にポスターが貼られることになった。
げんきラーメンはポスターやチラシでいっぱいの店なので、快く受け取って、さっそく貼ってくれた。ただ、こんなにべたべた貼ってあると、埋もれてしまう気がするのだけど。
その後、直人は味噌ラーメンを、私は醤油ラーメンをいただいて、げんきラーメンを出た。太いちぢれ麺に、あっさり醤油味が私は気に入っている。
「あー、味噌最高」
「げんきは醤油だよ」
「味噌の奥深さがわかってないな」
そんないつものやりとりをしながら、私達は次の目的地を目指す。スマイルコーヒーは、系列の大学の学生がよく行く店だ。
「なんでそんな一生懸命なの」
「いや……。一目惚れっていうか」
「え?」
まさか真野監督に?
「最初にポスター見た時にも言ったけどさ、あの視線にやられた」
ああ、ポスターの女の子か。ちょっとほっとした。
「まだ映画観てもないのに。つまんなかったらどうするの」
「そんなことは……ないと思うんだよなあ」
「勘?」
「うん。でも真野監督もいい人そうだしさ」
性格で映画撮るわけじゃないだろうに。その真野監督は、今日は地元のラジオに出るって言ってた。ポスターは持ち歩いていて、シネマステラから近い、街の商店街の店に、貼ってもらえるか頼んでみるそうだ。
「なんか、駅前のゲストハウスに泊まってるんだって」
「え、監督ってもしかしてお金ない?」
「若手の監督はそうなんじゃない」
スマイルコーヒーの、白い壁に赤い屋根が目に入った。並んで待っている人達がいる。彼らの後ろに並ぶ。
「そういうところも含めて、応援したいなって思って」
「ふうん」
まあ、直人がやりたいようにすればいいや。
「明日は現地集合な」
私に向かってそう告げると、直人はスマホをいじり始めた。
「え? 私も観るの?」
「あれ? 興味ない?」
スマホを打つ手を止めて、直人がじっと私を見る。
「なくは……ないけど」
「じゃあ上映、十七時からだから、十五分前に。と、グループにも送っといた」
菜摘と春彦も呼ぶようだ。興味、なくはない。直人がこんなに惹かれているものの正体を、突き止めてやりたい感じ。あと、単純に、シネマステラとやらに入ってみたい。知らない映画ばかりやってるし、それらが何となく難しそうだから、これまで入ろうと思う機会がなかった。
土曜日、十一月二十六日。『瞳』の上映初日。今日は上映後に監督のトークもあるそうだ。ということで混雑するのかと思ったが、そうでもない。シネマステラの前には、私達四人の他には、ぽつりぽつりと人が、四、五人待っているだけだ。
「チケット代、学生は五百円なんだね」
「安いよね。暇な時こっち来てたらよかったかも」
確かに。向かいのイタリ屋で、ドリンクバーとデザートだけで粘って、目的もなしにだらだら喋っているくらいなら、映画でも観てたほうが有意義かもしれない。
「にしてもさあ」
春彦が難しそうな顔をしている。そして声をひそめて言った。
「観客、少なくね……?」
私達の間に微妙な空気が流れた。
「あー、まあ、ね」
「ほら、ギリギリになったらもっと来るかも」
「でもあと十分」
反論しかけた春彦が口を閉じた。
「みんな来てくれたんだ! ありがとう!」
真野監督がやってきたからだ。監督は、初めてみた時のようなカジュアルな格好ではなく、シンプルで上品な緑のワンピースを着ていた。
「はい! むっちゃ楽しみにしてます!」
「よかったら、アフタートークで質問してね。何にも出ないと寂しいから」
「ぜひ!」
監督は手を振って、シネマステラの事務所の入口だろう、に向かっていった。
シネマステラの中は、意外と、と言ったら失礼だが、綺麗だった。特に装飾らしき物がない、グレーを基調としたシンプルな作り。座席は八十席位だろうか。紺色の椅子は、シネコンの大きな椅子に比べたら小さいけど、座り心地は悪くない。直人は一番前で観たいと最前列に陣取った。春彦と菜摘は一番後ろの席に並んで座った。私は真ん中のほうに腰を下ろす。しばらくすると照明が徐々に暗くなり、宣伝が流れ出した。やっぱり、知らない映画ばかり。でも、ちょっと面白そうだと思った作品もあった。宣伝が終わったのだろうか、少しの間画面が黒くなった。『瞳』の上映が始まる。
細めた目を大きく写したシーンから、映像は始まった。目をこする。のそりと体を起こす。白い布団の上に、明るい光が降り注いでいる。「瞳」と呼ぶ声がする。瞳は制服に着替える。家を出てバスに乗る。だが、彼女が降りるべきであろう高校前のバス停では降りない。その次のバス停で降りる。少し歩いて、瞳は広い公園に着いた。
瞳はその公園で、不思議な、というより、どこか不気味な女性、永子に出会う。何者かよくわからない永子だが、瞳は永子の話術に惹かれ、その後も公園で彼女と会うようになる。親交を深めていく二人。しかし、瞳が登校していないことが親に伝わり、一緒にいた永子が批難されてしまう。
落ち着いた雰囲気のする映像。騒がしくなくて、展開は早くはない。でもその速度が、ちょうどいい感じがした。口数の少ない瞳が、早口の永子に触発されてか、自分のことをぽつりぽつりと話しだす。学校に行きたくないこと。居場所がないと感じていること。
私は学校が好きだから、瞳の気持ちを理解できたとは思わない。でも、瞳と同じように悩んでる子、クラスにもいるんじゃないかな。そんなふうに思わせてくれた。
上映が終わり、客席の電気が点く。マイクを持った男性が出てきた。
「この後、監督のトークイベントを行います。準備をするので少々お待ちください」
直人のいる席に近寄った。ぎょっとした。直人が涙を浮かべている。
「大丈夫?」
「うん。あー、すげーよかった」
そう言いながら涙を拭っている。泣くほど感動するなんて……。直人って、明るくて目立つし人好きだし、瞳みたいな子の悩み、わかんないんじゃないかと思ってた。そうでもないのかな……。
そうこうしているうちに、スクリーン前には二脚の椅子、その上にはマイクが準備されていた。先ほどの男性がマイクで話しだす。私は慌てて、座っていた席に戻った。
「それでは、真野和歌子監督のトークイベントを始めます。進行を担当します。シネマステラの等々力です。よろしくお願いいたします。早速お呼びしましょう、真野監督です」
「こんにちは。真野です」
拍手の音がぱらぱらしていて、それは客席が満員ではないことを表していた。椅子につくと、しばらくの間は二人で会話をしていた。なぜこの映画を作ろうと思ったのかとか、撮影ではどんなことが起きたのかとか。
「では、会場の方からも質問を、って、早いね」
等々力さんの声掛けも終わらないうちに、直人の手がびしっと挙げられていた。スタッフからマイクを受け取った直人は、まず、とても感動したことを力説した。そしてこう質問した。
「どうして映画監督になろうと思ったんですか?」
真野監督がマイクを口に近づける。
「映画に、たくさん救われたからですね。私は高校時代に映画研究会に入って、そこで先輩に、いい映画をたくさん教えてもらったんですよ。あと、映画館連れていってもらったりとか。映画を観ている時が本当に幸せだったんです。だから、映画に関わる仕事がしたいなって思って。最初はスタッフから始めたんですけど、やっぱり監督、やってみたくって」
そこで監督はちょっと笑った。
直人が学校の友人知人に、映画鑑賞を勧めるメッセージを送りまくったらしく、私にまで問い合わせがあった。
「東丸の四階。そう、イタリ屋の反対側。学生は五百円だよ。え? うん、思ったより良かったよ。安いし観てきたら」
そして、夜にはこんなメッセージも入った。「『瞳』良かったよ。お勧めありがとね!」観た人から満足の感想を聞けて、他人事ながら、ほっとした。
放課後に、いつものように街をふらふらして、お店で服を見ていた。スマホが震えた。一緒にいた菜摘のも同時に。菜摘がさっとスマホを取り出し、確認した。
「直人からだ。十七時の上映開始までにシネマステラに集合! だってさ」
「あいつは今日も映画観に行ってんのか。どうする?」
「まあ、近いし、行くだけ行こっか」
私達は少し歩いて、東丸プラザに到着した。エスカレーターで四階へ上がる。シネマステラの前に設置されたベンチに、神妙な面持ちの直人と、それを励ましているような春彦がいた。
「直人、どうしたの?」
私の声に、顔を上げる直人。
「『瞳』さ……。昨日は日曜だし、クラスの子でも観に来てくれた人、そこそこいたっぽいんだけど」
うんうん、と話を聞く。直人は大きくため息をついた。
「今日、全然、客入ってないんだって……等々力さんに聞いた……」
ああ。やっぱりそういうことか。
「もう一回観ない?」
「え? もう一回?」
菜摘が声を上げた。春彦が、その反応が当然、というふうに菜摘を見てから、直人を見た。
「チケット代、俺が出すからさ」
「そんな、そこまでしなくても……」
菜摘の声に、私も、多分、春彦も同意見だ。監督が頑張ってるのはわかるけれど……。
「あれ、みんな」
その時、背後から監督の声がした。
「えっ、今日もこっちにいるんですか?」
「そうなの。最終日まで見届けようかと思って」
すごい熱の入れようだ。
「仕事とか大丈夫なんですか、って、あ、そっか、監督が仕事か」
春彦が失言した。監督は、あははと軽やかに笑った。
「お察しの通り、監督業だけで食べられてはないよね」
「すみません」
「いいのいいの。別の仕事もしてるよ。あ、してたよ、か」
さりげなく、どきりとさせる発言があった。私達は固唾を飲んで、監督の次の発言を待った。
「会社、先月で辞めちゃったんだよね」
そうさらりと言うと、監督はまた、笑った。
月曜日は、結局、四人それぞれがチケット代を支払って、二度目の『瞳』を観た。一度観たことがある映画をまた観るなんて、退屈するかと思っていた。けれども、最初に観た時には気付かなかった細かいところに気付いたりした。音楽がよく聴こえてきた。小道具などにも目がいくようになった。最初観た時と、違う印象を持った場面があった。こうだと思ってたけど、実はそうではないのでは、なんて考えたりもした。そんな体験は、始めてだった。
昼食のパンを口に詰め込んで、缶コーヒーで流し込むと、直人はスマホをものすごいスピードで打ち始めた。終わった。と思ったら、机に置いたメモを確認してから、また同じように文字を打ち込んでいる。
「何、打ってんの」
「お誘い。『瞳』を観てくれって、映画関係者に」
メモを見せてもらうと、そこにはいくつものアカウント名が並んでいた。映画評論家、ミニシアター支配人、といったメモ書きがある。
「えっ、シネコンに投げても無理でしょ」
「いや、なんでもやってみないと」
直人は顔をこちらにも向けずに、そう答えた。
「メモ一枚ちょうだい」
「まさか!」
「メッセージ送ったげる」
私はスマホを取り出して、SNSアプリを立ち上げる。こんな地味なこと、効果はあるのかな。そう思うけれど、昨日の監督の重大発言を聞いてしまった身としては、見過ごすことができなかった。と同時に、監督は見通しが甘すぎるのでは、という考えも、昨日から消えてはいなかった。監督業だけでは食べていけないのに、会社辞めちゃったって。肝心の映画も客入りがよろしくないわけで、監督、これからどうするんだろう。
その日の放課後も、直人はシネマステラに向かった。私は家の用事があったので、勘弁してもらった。
明けて水曜日。昨日もお客さんが五人ほどしかいなかったと、直人が落ち込んでいた。仕方がないので今日は私も付いていくことにする。上映までの時間を、コーヒーショップで潰す。
「でもさ、直人が『瞳』にそんなにはまるなんて、不思議なんだけど」
ホットのカフェラテを両手で持って、飲みつつ直人の様子を窺う。
「いい映画だけどさ、直人はもっと、エンタメ大作みたいなのが好みかと思ってた」
「そうかも。だから、『瞳』みたいな映画があること知らなくて、その分感動が増してるのかな」
「なるほど」
直人はホットコーヒーをちょっとずつ飲みながら、私の方をちらちら見ている。
「何よ」
「いや、まあ、更紗になら言ってもいいか」
やけにもったいぶる直人の左腕を、ちょんとつつく。
「秘密の話な」
「うん」
直人は視線を下に落として、ぼそりぼそりと話し始めた。
「俺も、瞳みたいに学校行ってない時あって。中学の頃」
無言で頷いて、直人の言葉の続きを待つ。
「だから、なんか、独りぼっちの瞳の気持ち、わかるような気がして」
そうなんだ。直人って、明るいし、賑やかだし、不登校になるような感じしないのにな。
「意外だと思ってるだろ」
「ばれたか」
直人がちょっと笑った。そのまま、視線を窓の外に向けて、思い出すように言った。
「俺、言いたいこと言っちゃうから、それで悪目立ちしちゃって、クラスから浮いちゃったんだよな」
「あー」
「それで、フリースクール行ってて。そこに、永子さんみたいな変な大人がいてさ」
「うん」
「その人がいたから、今、高校通えてるんだと思う。俺のこと認めてくれて、面白い話いっぱいしてくれた」
そっか。直人、何にも考えてないくらいさっぱりしてるように見えるけど、実は今まで、たくさん悩んできたのかも。
何か言いたいけど、ちょうどいい言葉が見つからない。私は直人の左腕、ジャケットをきゅっと掴んだ。直人の右手が、私の右手に、そっと覆いかぶさった。
四階にエスカレーターがたどり着く前から、そのどんよりとした感じが伝わってきたように思えた。シネマステラの前のベンチに、監督が座っていた。頭を深く落として、今にもため息が吐かれそうだ。
「監督……」
「あっ! 直人くんに更紗ちゃん!」
監督は私達に向かって、慌てて笑顔を作ってみせた。
「あの……無理しないでいいですよ……。俺、等々力さんに毎日尋ねてるんで」
「あー。ばれてるか。まあばれるよね。そう。あんまり人入ってなくて落ち込んでます!」
「あの、でも、観た人はみんな、いい映画だねって」
「ありがとう」
監督の笑顔には、消しきれない悲しみが滲んでいるようだった。
「ここでの入り具合で、他の映画館での上映も決まるかもしれなかったんだけどね」
私達は何も言えないでいる。いい映画。でも、お客さんを呼ぶのは大変なこと。何枚かポスターを貼ってもらったり、口コミしてみたりくらいじゃ、全然広まらない。
「映画はたくさんあっても、スクリーン数には限りがあるからね。シネマステラさんでかけてもらえただけ、奇跡みたいな話なんだよ」
十二月一日。今日は直人の弟の誕生日だそうだ。家族でお祝いをするために、直人は家に帰らなければならない。直人に懇願されて、今日は私が一人で、シネマステラにやってきた。あ、今日もだ。ベンチに監督がいる。なぜか大荷物である。
「どうしたんですか」
「それがねえ。宿の予約、間違えてたみたいで」
木曜まで宿泊、金曜にチェックアウトのところを、木曜チェックアウトにしていたらしい。しかも、その宿は、今日は予約で埋まっているそうだ。
「更紗ちゃん、この辺にネットカフェ知らない?」
「ありますけど……ネットカフェに泊まるんですか?」
「あと一日だし、お金もないしね」
そう言って肩を落とす監督を見ていると、放っておけない気持ちになった。ネットカフェで寝泊まりなんて心配だ。
「よかったら、うちに泊まってください」
「え? そんな、これ以上迷惑かけるわけには」
「兄が上京して、部屋空いてるんで。別に綺麗な部屋じゃないですけど」
「でも、ご家族の方とか」
「次回『瞳』ご覧になる方、入場開始します」
シネマステラのスタッフが入場開始を告げた。
「私、観てきますから、出てくるまで待っててくださいね!」
こう強引にでもしないと、監督は遠慮するだろう。まだ何か言いたそうな監督を後に、私はシアターに入場した。
来客用として使われている兄の部屋で、ベッドシーツを変えていると、お風呂上がりの監督がやってきた。スウェットの上下に着替えている。
「なんか本当、いろいろお世話になってしまって」
「いえ。うちは来客多いし、両親も楽しんでるから気にしないでください。ベッド、シーツ変えたんで。布団も時々干してるから、大丈夫だと思います」
「ありがとう」
監督はベッドに腰を下ろす。
「あの、監督」
「ん?」
「『瞳』で描かれてることって、監督の体験も入ってるんですか?」
「うん、そうだね」
監督が手招きしたので、私はベッドの、監督の横に腰を下ろす。
「私は瞳と逆で、学校に居場所を見つけたんだけど。アフタートークでも話したけど、映画同好会ね。私は家に帰りたくなかったから、ずっと部室にいたなあ。それか映画館に行ってた」
「そうだったんですか」
「だから、誰にでも、どこかに居場所があるよってことは、言いたかったんだよね」
『瞳』では、瞳の居場所は公園であり、永子のいる場所だった。しかし瞳はその場所を奪われてしまう。そして瞳は、衝撃的な結末を知ることになる。新聞に載った、女性の自殺記事。そこに書かれた女性が永子だったのだ。
「でも、永子さんはいなくなってしまって……」
「うん……。実はそれも私の経験から来てる。すごくお世話になった先輩がね」
監督は前を向いて、しばらく目を閉じた。
「でもね、先輩が私にくれたものは、私の中に残っているんだ」
永子の実家の住所を突き止めた瞳は、そこに向かう。家族が永子の部屋へと瞳を迎え入れる。永子の残した日記帳。その中には、彼女が患っていた精神の病に関連したと思われる、苦悩的な表現が並んでいた。しかし、そこに瞳との出会いが書かれた日から、時折、楽しげな描写が差し込まれるようになる。
「人生って多分、基本あんまりうまくいかないんだろうけど。それでも、楽しくて温かい、光みたいな日々は確かにあったんだって、思えるんだよね。先輩の顔、思い出すと」
永子の家族から日記帳を渡される瞳。日記帳を大事に鞄にしまい、永子の家を出る。「これから私は、永子さんと一緒に生きていく」。そう呟いて、一歩を踏み出す。瞳を照らす柔らかい光が広がって、映画は終わる。
「瞳がちょっと強くなれたみたいなラスト、好きです」
「ありがとう。私の言いたいこと、更紗ちゃん達にはきっと伝わってる」
私と監督は顔を見合わせて、笑い合った。
金曜日。『瞳』の上映最終日。今日は四人でシアターに入った。お客さんの数が心なしか多いような気がする。もう何度も観たシーン。でも、もしかすると、もう観ることができないかもしれない映像。しっかり記憶するつもりで観た。
映画が終わり、客席の電気が点く。今日は並んで観ていた直人の表情を伺う。ちょっと涙目になっているような気がした。
今日は監督も観ていた。みんなでぞろぞろとシアターを出て、次の作品の開場を待つお客さん達から離れて、話す。
「みんな本当にありがとう。私、こっちに知り合いもいないし、みんなが何度も来てくれて、すごく力づけられたよ」
「いや、でも、もっと人が呼べたら……」
直人が残念そうにつぶやく。
「いいの。みんなに観てもらえて、『瞳』は幸せな映画だよ」
「そんな出会いの機会をもっと増やしたくてですね」
背後から、知らない男性の声が聞こえた。みんな振り向く。でも誰の知り合いでもないみたいだ。
「すみません、私、こういう者です」
男性は監督に名刺を渡す。
「シアターやまびこ支配人、長岡勇気……さん……。もしかして」
監督が驚いて男性を見つめる。
「はい、隣の県でミニシアターをやってます。SNSで高校生の男の子におすすめされまして、観に来ました」
「あ。送った。シアターやまびこ。送りました! それ俺です!」
「君なんだ。おすすめありがとう。良かったのでうちでも上映したいなと思ってたら、等々力さんが、監督が来てるって言うから」
監督は口を両手で押さえて、目を見開いている。
「監督! 良かったですね!」
「え、えっと、本当……ですか……?」
長岡さんがうなずいた。監督の目から、涙があふれ出した。
「同好会って、何人からいけるんだっけ?」
監督と長岡さんが話し合っている様子を、少し離れた所から見ながら、直人がぼそりと言った。
「副会長やったげようか」
「えっ、本当?」
「私、ただの会員にならなるよ」
「あ、俺も」
「ねえ、監督に名誉顧問になってもらおうよ」
そして、監督がこれまでに観てきたたくさんの光のことを、教えてもらうんだ。
お気持ち有り難く思います。サポートは自費出版やイベント参加などの費用に充てます。
