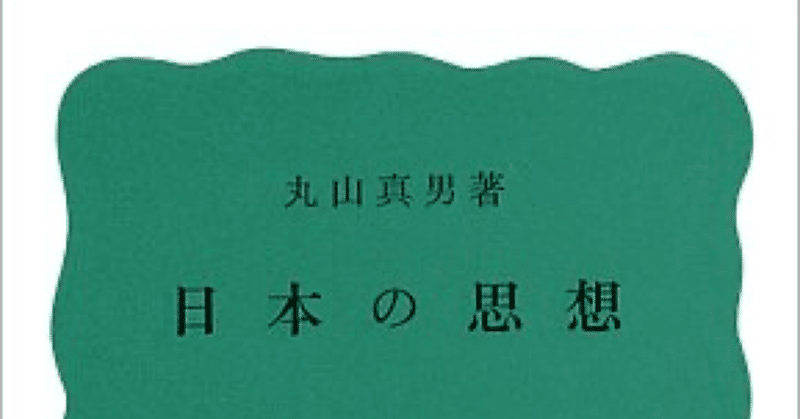
選択的影響と状況的影響(2011)
選択的影響と状況的影響
Saven Satow
Feb. 19, 2011
「影の形に従うが如し」。
『法句経』
日本の思想史を辿ると、驚くべきことに、多くの知識人が「選択的影響」を受けている。複数の思想を比較した上で、ランキングづけしてどれかを選択する。歴史的・社会的背景は認められるものの、主に個人的動機によって思想を選び、その影響を受容している。空海や日蓮、藤原惺窩、本居宣長、和辻哲郎、江藤淳など枚挙に暇ない。こうした過程を経ているため、思想がアイデンティティと意識されている。過剰とも思える思想との一体感を示す反面、しばしば、それ以外を激しく攻撃する。
しかし、世界史を見てみると、この選択的影響と違う場合も少なからず認められる。社会的・時代的状況の動向によって、受けざるを得ない影響の思想が決定される。これを「状況的影響」と呼ぶことにしよう。個人的志向はあるにしても、その受容は社会的・時代的状況が決めている。
孫文のウラジーミル・イリイチ・レーニンからの影響がこの一例である。この中国の革命家はマルクス主義者ではない。しかし、半植民地状態の祖国の状況を考慮するならば、あのロシアの共産主義者が構築した反帝国主義運動の理論をとり入れざるを得ない。自分の好き嫌いなど二の次でよい。祖国を救うためなら、その状況が求める思想の影響を受けることは厭わない。
こうした状況的影響は世界的には決して珍しくはない。スコットランド啓蒙やプラグマティズムなどその誕生・形成が状況から説明し得る。社会的・時代的状況に強いられてある思想が受容されるのではなく、むしろ、なぜ選択的影響を受けた人物が日本では思想家として育っていくのかが不思議である。日本の思想史では、状況的影響の理論家を探すとのは難儀である。
選択の余地があるというのは、状況がそれだけ切羽詰まっていない証拠だとも言える。近代以前の日本は、主に東アジア情勢の変化の中で位置づけられる。けれども、朝鮮半島や沖縄と違い、大陸の動向と密接に連動しているわけではない。また、国内体制は、程度の差はあるものの、分権的である。日本の中世研究の最大課題は公家=寺家=武家の関係がどうであったかである。朝廷が都にあろうが、幕府が開かれようが、中央集権制が弱く、権力が分散しており、それぞれに裁量が許されている。
日本の思想が雑多かと言えば、実際にはそうではない。丸山眞男が『日本の思想』で日本の思想の状態を「雑居」と評したことはよく知られている。しかし、奈良時代から江戸時代に入るまでのほぼ1000年間、仏教が日本の思想を支配している。仏教を考えることなしに、日本の思想史研究はありえない。中でも、最澄の開いた天台宗は、以後の思想史に決定的な影響を及ぼしている。鎌倉仏教の知識人はほとんどがこの総合仏教で修行をしている。天台宗の整備された体系を拡張・補完・変更・統合することが近代以前の日本の思想の総体だと言える。国学の苛烈な仏教糾弾は、逆に、その強固さを物語っている。
江戸時代の絵画の多様性は目を見張るものがある。しかし、それも狩野派という強い規範を基盤にしている。狩野探幽(1602~74)は雪舟など室町時代に水墨画を学び、国内外の大量の古画を研究し、制作に生かしている。鑑定のために持ちこまれた農大名古画を破は綻念に縮写しているが、その記録は今日の美術史研究には欠かせない史料である。探幽は将軍家専属の絵師となり、彼の画風は江戸時代の基本となっている。狩野派は武士と同等のエスタブリッシュメントとして幕府や大名に仕え、また、市井の絵師として活動するものも多く、組織網は全国に及び、絵画界におけるそのヘゲモニーは江戸時代の終わりまで絶対的である。
探幽の死後、狩野派は彼の絵画を徹底的に解剖してマニュアル化し、入門者に模写を通じて絵画のリテラシーを習得させる。狩野派は保守的で革新を厭い、実力より家名、個性的創意よりも先例を重んじる。その傾向は武士の道徳とは合っている。絵画を学ぼうとするものは狩野派の画法を学習し、その拡張・補完・変更・統合から自身の画風を形成する。独創性を追及する絵師は選択的影響を受け、狩野派から離れていく。けれども、江戸時代の絵画の多様さは狩野派という共通基盤が可能にしている。狩野派は創造性を提供したわけではないが、絵画教育の役割を果たしている。
選択的影響が可能である状況は、規範がしっかりしているが、その強制力は少々緩いということになろう。無規範だから選択が許されているわけではない。そのような状況では、さ迷い歩き続けるか、足を踏み出すのを躊躇するかのいずれかしかない。選択はある幅の中の裁量権である。選択的影響を見出したならば、穏健な状況は言うに及ばず、当人の選んだ理由はともかく、そこに規範が働いていると考えるべきである。「雑居を雑種にまで高めるエネルギーは認識としても実践としてもやはり強靱な自己統御力を具した主体なしには生まれない」(丸山眞男『日本の思想』)。今やもっと繊細な見方が必要だ。
〈了〉
参照文献
佐藤康宏、『日本美術史』、放送大学教育振興会、2008年
丸山眞男、『日本の思想』、岩波新書、1961年
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
