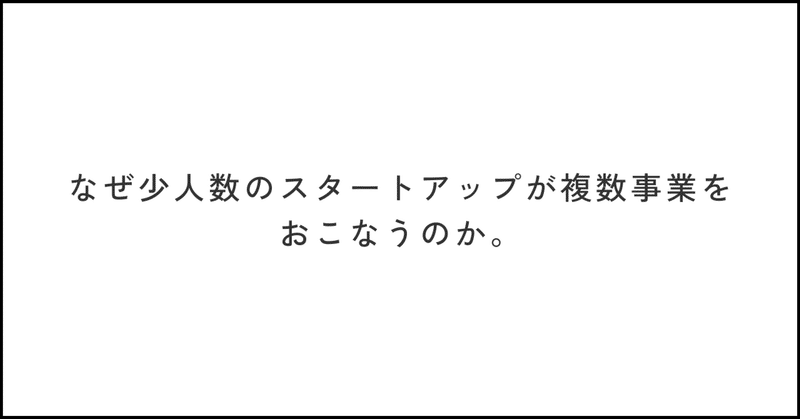
なぜ少人数のスタートアップが複数事業をおこなうのか。
こんにちは、Canvasの小黒です。
本日はCanvasの事業方針である複数事業の立ち上げについて話していきたいと思っています。
複数事業はスタートアップのアンチパターン
Canvasでは現在、チャットマーケティング事業、デジタルマーケティング事業、スポーツビジネス事業の3事業を運営しており、スポーツビジネス事業の中で複数の新規プロジェクトを動かしています。また、海外向けの新規事業も現在プロジェクトが進んでおります。
一般論としてビジネスでは「選択と集中」が重要であるとされています。特にスタートアップではリソースが限られることもあり、リソースの分散を避けるため、単一事業を伸ばそうというのがセオリーとなっています。
スタートアップなのになぜ複数の事業をやるのか
では、なぜ複数事業をやるのかと言う話ですが、
前提として、Canvasは長期的な視点で経営をおこなっており、100年、200年続く会社を作っていきたいと思っています。なので短期的に会社を売却するといったことは考えていません。
かつ、継続的に事業成長しつづけるビジョナリー・カンパニーを目指しています。
(このあたりは完全にビジョナリー・カンパニーの影響を受けています笑)
この前提に立つと、複数事業を展開する必然性が見えてきます。
①どんなプロダクト/事業でも必ず衰退する。(プロダクトライフサイクル)
まず1つ目の理由につながる話ですが、経営学で「プロダクトライフサイクル」という概念があります。
簡単にいうと、プロダクトは導入期〜衰退期の4つのフェーズに分けられ、やがて衰退していく。という理論となっています。
ここで伝えたいのは、「どんなプロダクトや事業でもいつかは必ず衰退する」ということです。もちろん市場規模や人口動態などによって期間は変化しますが、 例えば、Canvasの事業で言えば「企業が消費者に対してマーケティング活動する」と言う行為は100年後もなくならないかもしれませんが、その手法は現在のSNSやLINEを活用したデジタルマーケティングとは大きく変わっていると思います。
そもそもテクノロジートレンドは短期で変わりやすいと言う特性があり、例えばスマートフォンも2010年代から本格的に普及している10〜20年位のトレンドです。そう考えれば今のテクノロジー系の事業が10年後や20年後にも同じ形として残るか非常に疑問で、例えば我々のLINEを使ったチャットマーケティング事業が10年後も同じ形で継続しているとは思っていません。
そのように考えれば、新しいテクノロジーを生かして、どんどん新しいプロダクトを出していく、というのは必然かと思っています。
②スポーツビジネスに必要なのは新しいビジネスモデル
Canvasが注力しているスポーツ領域は既存のビジネスモデルだけでは収益性に限界があります。
例えばスポーツクラブで考えると、主たる収入源の一つである入場料収入やグッズ収入は物理的な制約からアッパーがきてしまいます。
スポーツが社会的にもっとインパクトを提供していくためには、スポーツビジネス自体が産業としてもっと大きくなる必要があり、そのためには既存の枠組みにとらわれない、新しいビジネスモデルの構築が必要だと感じています。
スポーツと様々な業種と掛け合わせた事業開発をおこない、新たな収益源を作り出す。それがクラブやアスリート、施設に還元されることでスポーツ界全体の活性化につながると信じていて、そのためにスポーツ×他業種の新規事業を複数立ち上げていこうとしています。
現状スポーツ領域はいわゆる「儲からない」ビジネスだと認識されていますし、事実としてそういう側面もあると思います。
そう考えると、今のスポーツビジネスに必要なのは何よりもトライ数だと思っています。
そもそも儲からないと思われている領域で新しいことをおこなうためには、とにかく数をこなして、小さくてもいいので一つでも多くの成功事例を生み出していくことだと捉えています。
③会社の掲げる目標に到達できない。
現在「スポーツ×デジタル×グローバル」を事業ドメインとして、
・世界と日本をスポーツ×ビジネスでつなぐ
という思いで会社を経営しています。
日本と世界がコネクトした状態=ヒト・モノ・カネ・情報が常に行き来している状態
と捉えると、
人材が行き来する仕組みも必要だし、海外進出支援も必要だし、マーケティング支援や越境ECも必要だと思っています。
もちろん、物理的な制約もあるので全ての事業をCanvasでやるわけではないのですが、要は自分たちのリソースや市場からの見え方を気にするのではなく、まず最優先に「コトに向き合う=自分たちの目標達成を優先する」という視点で事業をやっていければと思っています。
なぜ初期からやるのか
複数事業をおこなう理由を説明してきましたが、
「別に今やらなくてもいいんじゃないの?」
「1つの事業が伸びきった後に多角化してもいいんじゃないの?」
と言う声もあるかと思います。実際に多くの人から同じことを言われています。
ですが、個人的な意見として、1つの事業が伸びきってから複数事業を展開していくのは非常に困難であると感じています。
別の言い方をすれば、事業がうまくいけばいくほど、別の事業がやりづらくなると思っています。
事業が伸びきってから新規事業を開発しようとすると、例えば既存事業が売上10億になれば新規事業にも10億以上、既存が売上30億になれば30億以上の新規事業の規模感を求めてしまい、どんどんハードルが上がっていきます。
また、既存事業とのシナジーを基本的に求めるので事業の制約が高まり、飛び地での新規事業となるとますます困難を極めます。
ただ、新規事業は概して最初の計画通りには進まず、試行錯誤しながらPMFを狙っていくことが圧倒的に多いです。
そうすると最初に想定していた市場やビジネスチャンスとは別の部分に可能性を見出すことも多く、最初から大きい売上を目標に置くより、まず小さくても良いので、新しいマーケットに参入する方が結果的に大きな事業になると考えています。(もちろん大きな市場規模があるという前提ではありますが。)
例えば、弊社のチャットマーケティング事業も、最初に立ち上げた時は、周りからそんなのニーズがあるのといった声がありました。
また正直自分たちでもそこまで大きな市場規模や売上を見込んでいたわけではありませんが、とにかくトライしてみよう、ということで事業を立ち上げました。
いくつかのピボットを経て、結果としてConversational Commerce領域として市場がどんどん拡大している状況です。
こういった点を複合的に考えると、会社が初期の段階から新規事業を立ち上げ続ける仕組みやカルチャーを醸成していくことが何よりも大事であると考えています。
普通に考えれば既存事業を伸ばしたほうが短期的に合理的です。同じ100万円の売上を創出するのであれば、新規事業よりも既存事業の方が圧倒的に簡単なのです。だから普通に経営していけば、単一事業を伸ばそうという力学が組織として働きます。
だからこそ、カルチャーとして新規事業を立ち上げ続け、それを称賛する仕組みをつくっていくことがなにより大事であると感じています。
偉大な会社は次々と事業を作っている
リクルート、サイバーエージェント、メルカリ、mixi、DeNA、GREE、ビズリーチ、ソフトバンク、楽天、Yahoo。
メガベンチャー、大企業と言われる企業も、立ち上げた時期に差はあれど、複数事業を展開しながら会社を大きく成長させています。
日本を市場として捉えると、人口減少問題もあり、同じ事業を行っていくだけではいつかは衰退していきます。安定的に成長させつづけるためには新規事業を立ち上げ続けることが必須だと感じています。
具体的にどうやるのか
複数事業を立ち上げ、継続的に会社として成長していくためには、
・新規事業を立ち上げるカルチャー
・志を持った事業家人材
が必要だと感じています。
そのため、現在Canvasでは採用に注力しており、
・DXベンチャーの事業責任者
・外資系メディアのコンテンツディレクター
といった人材が入社し、新規事業開発に取り組んでいます。
「スポーツ×デジタル×グローバル」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
