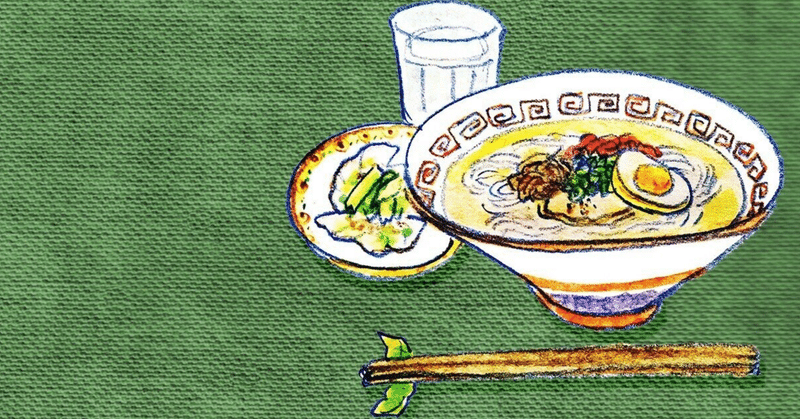
『「ご当地ラーメン」の地域ブランド戦略』(関満博・古川一郎編/新評論)を読んで ~ラーメン県ができるまで~
総務省の家計調査で中華そばにかける外食費用は山形市が全国1位となり、ぼくの故郷・山形はいつの間にかラーメンで町おこしをするほどの「ラーメン県」になりました。山形のラーメンは、関東大震災で被災した横浜中華街の職人たちが湯治に蔵王を訪れ、そこで地元の蕎麦屋にラーメンを教えたのが始まりとする説が濃厚です。しかし、その職人たちは、なぜ栃木でも宮城でも福島でもなく、山形を訪れたのでしょうか? なぜ山形の蕎麦屋がこれほどラーメンを取り入れたのでしょうか? そこを調べていきたいと思っています。

◤気になったポイント◢
・本書で取り上げた10のご当地ラーメン
①旭川ラーメン
②和歌山ラーメン
③熊本ラーメン
④上州藤岡ラーメン
⑤釜石ラーメン
⑥八王子ラーメン
⑦笠岡ラーメン
⑧伊那ローメン
⑨八幡浜ちゃんぽん
⑩沖縄そば
・1988年、旭川は地元の青年会議所がラーメンマップを作成、旭川中央郵便局主催のPT「レディースミーティング」も参加。95年に市民団体「ラーメンバーズ」が立ち上がり、夏祭り「ラー1グランプリ」開催からフードテーマパーク「あさひかわラーメン村」までつながった。
・和歌山ラーメンは井手商店が有名。全国のブームの先駆け的存在。地元製麺組合が地域団体商標を登録。
・群馬の上州藤岡ラーメンは地元の名士的存在の市議会議員が町おこしに、と会を立ち上げ。スタンプラリーを企画。
・釜石ラーメン文化の特徴は、【中華専門店に限らず、一般食堂系でも自家製麺を提供していること】。きっかけは戦後の米軍からの救援物資である小麦粉が配給されたこと。もともと三陸海岸では1970~80年代に国道45号線開通によって観光地化が進み、海の幸を使ったラーメンがドライブインで提供されていた。
・八王子ラーメンは有志による「八麺会」活動。市も2007年に「八王子『食』のブランドづくり」をアクションプランとして掲げた。地元にある東京工科大学との産学連携も。
・岡山の笠岡ラーメンは県の「むらおこし事業等地域活性化事業」として「笠岡らーめん屋台プロジェクト」を採択。ラーメン店主育成事業も付随。商工会議所青年部も活動。
・とみとんのショッピングモールの一角で常設の「沖縄そば博」。より多くの観光客がアクセスできる場所。
◤本書内で紹介されている気になった文献◢
『中小都市の「B級グルメ」戦略』(新評論)→米沢ラーメンへの言及あり
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
