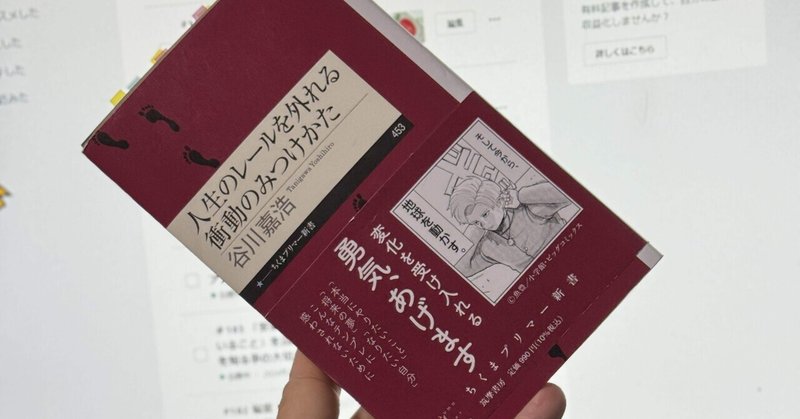
#194 「人生のレールの外れる衝動の見つけ方第4章~最後まで」を読んで衝動の実装を考えた話
こんにちは!けーたです。
今日は「人生のレールの外れる衝動の見つけ方」の第4章から最後まで読みましたので、気づきなどをnoteに投稿いたします!
同じ本での気づきなどを書いた過去投稿はこちら。
ちなみに、本書は250頁ぐらいのボリュームなので時間さえ確保できれば3時間ぐらいで読めそうな感じですが、そのまとまった時間確保ができませんでした、、、最近ドタバタです。
最近、荒木マスターのVoicyでこの本の著者谷川嘉浩さんとの対談をやっていて、本の中身に触れられていました。
これを聞きながらだと、より著者の意図が分かり行間が読めるような気がしたので、是非こちらも聞かれると良いと思いました!リンクをどうぞっ
という事で関係したリンクの嵐でいっぱいになってしまいましたが、ここからは本からの気づきについて触れていきます。
どんな人におススメ?
自分には寝食を忘れて没頭してしまう(打算的な考えが働かずについついやってしまうレベルの行動)ようなものがなく漠然と焦りみたいなものがある人には是非是非おススメです!!
もし、モチベーションやインセンティブとは無縁なモノとして既に「衝動」が日常生活で駆動している方にも、実際どうやって自分の人生に再現性?高く「衝動」を実装するかのヒントもあるのでこちらの方にもおススメです。
頭に刻みこんでおきたい考え方達
キャリアデザインの隠れた前提
なるほど!と気づいたのが、キャリアデザインとは、これまでの過去の延長線のコントロールしたい欲望の中に納まる思考であるということ。
この考えはレールを外れる可能性を是としないという考えかたが含まれているという、隠れた前提に気づけました。
どうせキャリアを描く(検討する)なら、自分自身の予測外のルートも含めてのキャリアデザインなら、また面白さが増えるというのも学びでした。
衝動を捉える為のセルフインタビュー
「衝動」をどう捉えるか?の中で提案された一つのアクションとして、特定化された自己の偏愛について、落ち着いた状態で行われるセルフインタビューにより、その輪郭をはっきりさせることができる可能性が示唆されていました。
これは、すごく面白そうな取り組みですが、もう少しインタビューの手段について語られていると良かったなと思い少し残念なポイント。
きっと、このインタビュー設計をすることで自己理解が深まるだろうという理由で詳細のガイドがないのでは?と思い、無い事には納得していますがw
居合わせる事の本質的な意味とは
これは、自分が考えたことが無かった論点なので大変参考になったのでここに取りあげました。
別の言葉では「ライブであることがそんなに大事なのか?」という問い。
この言葉には、自分達が居合わすことができるわけもない、過去の書物「源氏物語」や「方丈記」その他の歴史的書物から本質的な学びを得られないのか?という所まで発展しており、大変よい問いだなと思いました。
結論としては、ジャックインという言葉で、その当時の考え方に同期させるという表現で自分の中で憑依、追体験すれば学びを得る事ができるとあり、確かに憑依するレベルでという事がポイントだなと気づきました。
過去の大学院のケーススタディーでも冷や汗をかくレベㇽでケースに没入しCEOの立場になって考えないと意味がない!と言われたことを思い出しました。
大事ですね。憑依するレベルでモノゴトを追体験すること。
まとめ
「衝動」って言葉をもちろん聞いたことがありましたが、自分の口から衝動について話をしたことがないというレベルの距離感の言葉でした。
第一章で使われている否定神学のアプローチである、「衝動」とは何でないのか?という考え方が自分は好きになりました。音の響きも好きです。
「○○とはナニデナイノカ?」
そして、偏愛というモノをガイドに自分自身を大切にしてインタビューしていく。その上で、どうしたら衝動を実装できるのか?
自分の内部と外部の接続についての自己認識を上げること。そこが分かったうえで衝動を使って方向感だけ合わせながら自走させる。
そんな流れを本書から学ぶことができました。
自分でも制御できない面のある「衝動」。今の自分にもあるので、丁度よいまとまった時間のとれるGWであるので、じっくりジブン自身に問いかけたいと思います。
この投稿が誰かの選書の参考になれば幸いです。
ではでは
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
