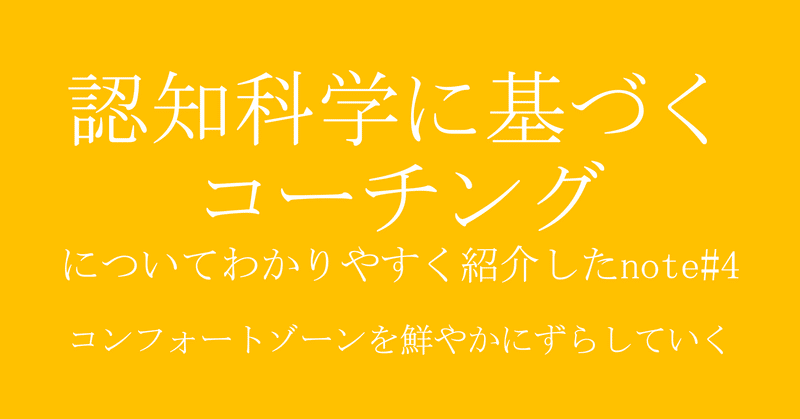
認知科学に基づくコーチング コンフォートゾーン
こんにちは!
サトシです。
今日も株式会社GOAL-Bの山宮健太郎さんが解説する認知科学に基づくコーチングについて私なりにまとめ、紹介していきます。
○コンフォートゾーンを鮮やかにずらしていく○
前回紹介した通り、人間には自身の安心で安全な状態を保つために生活リズムが存在しています。
心地の良い環境=コンフォートゾーンを常に保ち、変化があった場合にはホメオスタシス(現状維持機能)が作用し、現状(コンフォートゾーン)に生活リズムを戻そうとします。
ではどのようにしてコンフォートゾーンをずらし、理想の生活リズムを形成するのでしょうか?
それを可能にするのが
認知科学に基づくコーチング
です。
○モチベーション○
大前提として、モチベーションの基準は人によって異なります。
例えば、、、
①プロサッカー選手になろうと一流のチームに加入して練習する人
②大学のゆるいサークルや遊びでサッカーをしている人
上記の人たちのモチベーションの基準は異なるのはわかりますね。
つまり、マインドのコンフォートゾーンが異なると言うことです。
仮に、
①の人が②の練習を
②の人が①の練習を


することになった時、彼らはどんな行動をするでしょうか?
おそらく、マインドのコンフォートゾーンである、
元の生活リズムを取り戻そうとするでしょう。
その元の生活リズムに戻そうとする力のことを
モチベーションと言います。
○マインドのコンフォートゾーン○
現状に対して、マインドのコンフォートゾーンが
圧倒的に未来にある場合はどうでしょうか。
その未来と現状の乖離が大きければ大きいほど、
マインドのコンフォートゾーンに戻ろう(引き寄せる)とする力が働きます。
その時、未来に対しての乖離であるその空白を
埋めるために、気づかなかった創造性やエネルギーが働き、
無意識に行動するようになるでしょう。
例えば
情報を集める/人と会う/何か新しいことを始める

結果、パフォーマンスを最大化させ、
様々な行動を無意識的に行い、マインドのコンフォートゾーンに
近づき、行動が最大化されます。

コーチは新たなマインドのコンフォートゾーン
を構築するサポート行います。
これが認知科学に基づくコーチングの一部です。
次回は複数のGOAL設定をする理由や
コーチの役割について詳しく説明します。
最後までお読みいただき、誠に感謝致します。 よろしければサポートをお願い致します!今後、プロコーチとしての活動(CTI受講料/コーチング資料購入)に活用し、みなさまにアウトプットさせていただきます!
