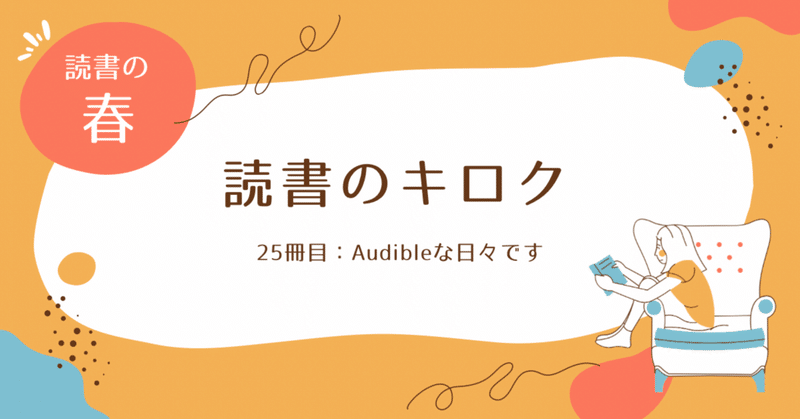
【読書のキロク:番外編9】余裕を持って生きる【Audible】
こんばんは、"もっちゃん"です。
記事に興味を持ってくださり、ありがとうございます。
最近では、Audibleで聴く書籍の方が、紙媒体で読む書籍の量を超えてきているように感じます。
断じて、紙媒体の書籍を軽んじ、読む時間が減っているわけではありません。
ただ、Audibleの利便性がスゴイ、ということでしょうか。
通勤時間はもちろん、ジョギング等の運動中や、散歩などでも聴くことができるというのは大きな利点です。
私は音楽が好きでよく聴いているのですが、その替わりになりつつあります。
大好きな音楽の時間を確保しつつ、Audibleも楽しむという。
そんな生活になってきております。
さて、以下はキロクです。
◯今回聴いた本:メタ思考 「頭のいい人」の思考法を身につける 著者:澤円 大和書房
教員でいれば、"メタ認知"という言葉をよく耳にするかと思います。
何かと言われる"メタ"ですが、私もその言葉だけに反応し、選んでみました。
⓪概要〜メタ思考〜
ルールを疑わない人は思考停止している。正解もルールも変わる時代で、頭のいい人はどこを見て、何を聞き、どう考えているのか?
こうして見ると、何も本書について書いていない気もするので、少し紹介します。
メタ思考とは、
自分自身のこと(また自分を取り巻く周囲の事象)を俯瞰的な視点で捉える見方・考え方のこと
と解釈しました。言葉通りかと思います。
ただ、エイリアスと呼ばれる自分自身の捉え方は本書で初めて聴いたものだったので、新しく感じました。
それぞれの集団で動く自分を、自分の分身ぎ動いている、というように捉える見方だと言っていたように思います。
面白い見方であり、現代的だなぁと感じる視点でした。
◯雑感
最近読んで(聴いて)いる本で、また本書でも言っていたことが、
「面白いと思ったことをやる」
(他はやらなくてもよくね?)
というスタンスです。
非常に合理的であり、納得する部分はとても多いです。
私自身、けっこうそういうところがあります。
逆に、仕事で面白くないとおもっているところは、面白くしようとしてしまう、とか。
学校では特別活動を担当することが多かったのですが、
学校行事なんかはまさにそうですね。
文化祭や運動会など。
まずは運営側が楽しむことを大前提に企画していきました。
(それがどこまで子どもたちの資質・能力の育成に寄与したかはさておき)
こういうことは大事だなぁと思います。
◯おまけ その1:心の余裕
本書でも言っていましたが、メタ思考するには心の余裕が必要だと思います。
逆に、メタ思考をすることで、心の余裕が生まれるのだとも思います。
いっぱいいっぱいになっていると感じるときこそ、自分を俯瞰的に見て、「自分のエイリアスに余裕がなさそう」と感じられるようにしたいです。
◯おまけ その2:ランドルト環
本書の中でランドルト環のくだりが出てきました。
簡単に言えば、
「欠けているところは目につきやすいが、その他は意識されにくい」
ということでしょうか。
非常にわかりやすい例えでした。
(誰かの話の引用だったと思いますが)
教員の子どもを見るスタンスとして、忘れないようにしたいと思います。
欠けてるところの指摘は誰だってできる。
そうでない部分にどう意味を持たせるかを考えていきたいです。
ということを考えた1冊でした!
このnoteを書いている自分をメタ的に捉えてみると、「何書いてるんだかなぁ〜」と思う部分もあります。
ただ、面白いと思っていることだから、やってみているのは良いかもしれませんね。
自己紹介はこちらから。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
