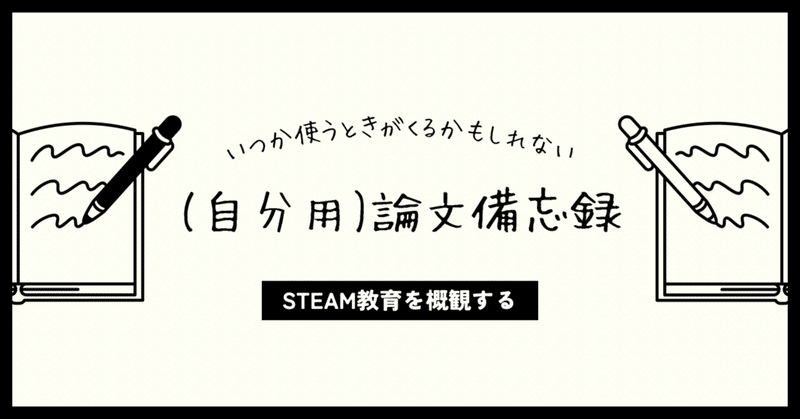
【論文備忘録】STEAM教育を概観したい
こんばんは、"もっちゃん”です。
記事を開いてくださり、ありがとうございます。
“Science”というと、なんかカッコよく感じるのは私だけでしょうか。
「理科」というよりも「科学」と言うと、なんとなくカッコよく感じる気もします。
でも、教科でいうと「理科」ですよね。
「科学」ではなく「理科」となった背景には、確かいろいろなことがあったと思うのですが、本稿の趣旨ではないので省きます。
自分としては、「自然科学」が中心となった現在の「理科」は、物足りなさはあれど、比較的好きに感じております。
今回は【論文備忘録】です。(久しぶり)
なんとなく気ままに読んだ論文について、完全に私見を書き綴っていきます。
もしかしたら後ほど使うかもしれませんので…。
なお、基本的にはネットで検索可能な論文ばかりを取り上げていきますので、ご承知おきください。
今回は、自分もけっこう興味のあるSTEAM教育に関する論文です。
⓪今回取り上げる研究:大谷忠(2021). STEM/STEAM教育をどう考えればよいか―諸外国の動向と日本の現状を通して―. 科学教育研究 45巻 2号. pp.93-102
科学教育研究のこの号の招待論文になります。大谷先生は、東京学芸大学の技術教育の先生のようです。
①要旨
本論文の抄録をそのまま引用させていただきます。
This paper gives an overview of the current situation of STEM human resource development and STEM/STEAM education as being promoted in other countries under the circumstances of the Fourth Industrial Revolution, which is drawing worldwide attention. In addition, this paper tries to sort out how to understand STEM/STEAM education from the above current situation. These perspectives focused on an education enabling everyone to work toward the future in a friendly manner, on cross-disciplinary education, and problem-solving activities to address global issues and issues related to new work styles. They also included characteristics of an education complementating design science and cognitive science. From the perspectives and characteristics of STEM/STEAM education, it was considered that the Japanese school education has been required to shift from the traditional way of education based on individual academic fields, to a new education based on cross-disciplinary education including comprehensive learning.
んー、簡単に言えば、
世界各国で注目され推進されているSTEM/STEAM教育を概観し、整理するとともに、日本におけるその必要性(従来の教育からより学際的に学ぶ教育へ移行していく必要性)について主張している
ということでしょうか。
非常に網羅的にレビューされている研究になります。
詳細が気になる方は、ぜひ目を通していただければと思います。
以下では、論文の気になった点について、完全に私見を述べていきます。
なお、STEM/STEAM教育に関して多少知っている、という方は以下の文章も伝わるかと思いますが、そうでない方は、まずは論文に目を通していただければ幸いです。
②AとSTEMの関わり
まず、気になったところは"AとSTEMの関わり”です。
あらゆる場で議論され、方向性を見失いつつある(?)、STEAM教育の中の"A"です。これは、"Art”の"A”になります。
個人的には、学際的に考える上で必要なものの見方の中に"Art"が含まれることはとても良いことだと思っています。
ただ、これまでの日本の歴史もあってか、なかなか日本は"Art"から縁遠いところにあるようにも感じています。
この論文では、その"A"の位置づけをわかりやすく図で示してくれています。

とても明快で、納得させられる部分が大きいです。
この論文でもありましたが、「デザイン」という考え方が、STEMとSTEAMを繋ぐ上で重要になってきそうな気がします。
「デザイン」となると、"E"のプロセスともとれるし、"A"ともとれる。なんとも難しい感じはしますが、とてもしっくりくるまとめになります。
個人的には、課題解決のプロセスにも"A"の見方は大きく寄与するだろうと考えてはいますが、そこら辺はもう少し研究をあたってみたいと思います。
③学校教育におけるSTEM/STEAM教育
ここからが本題でしょうか。
日本の学校教育ではSTEM/STEAM教育は現在どのようになっているのか。
基本的には“産業界からの必要に迫られ”、高等学校等の「探究の時間」などで実践されているようです。
(なんとなく日本の教育の出遅れ感が否めません)
実践事例等をたくさん紹介した書籍等も出ているので、そちらから参照可能かと思います。
技術分野(プログラミング等)で先行している感じはしますね。
教育現場で感じることとしては、意識的に進めようとしている一方、なんとなく“教科外の特別な活動”的な感じで捉えられてしまっているようにも感じます。
おそらく、本来の目的と少なからず異なってきてしまっている印象です。
ただ、「探究」や「総合」の時間があるなど、制度的にも整ってきている感じは自分としてはしています。
それが有効に扱われているかは別として。
④中学校ではどうするか!?
私は中学校の教員ですので、やはり中学校の現場での取り組みを考えたくなってしまいます。
中学校では、一番は「総合的な学習の時間」でしょう!
自分としては「総合」はカリキュラムの中心に据えられるべき時間だろうと考えています。そこでの学びを充実させることが、何より子どもたちにとって今後必要となってくる力を身につけることにつながるのではないでしょうか。
STEM/STEAM教育との親和性も非常に高いです。
(というか、理念としてはほぼ同じなのではないでしょうか)
ただ…
「総合的な学習の時間」がそんなふうに生かされている感じはしない!
と感じる方も多いのではないでしょうか。
少なくとも私は感じています。うまく活かしきれていないわけです。
教育課程編成、カリキュラムマネジメントに大きく関わってくることですので、
組織全体が動かなければならないことになります。
それぞれの中学校が重い腰を上げ、コツコツと実践を積み重ねていくことが大事になってくるのでしょう。
⑤教科の中でのSTEAM
一番実践が積み重ねられているのは、各教科での実践かと思います。
理科・数学・技術家庭など、各教科の中でSTEAMの視点を盛り込み、実践している方はたくさんいらっしゃいます。
そうしたひとつひとつの積み重ねが、学校全体を動かし、各自治体を動かし、国を作り上げていくのだと思います。(そうだと思いたい)
そう思いながら、自分も実践していこうと思った論文でした。
以上です。長くなってしまって申し訳ありません。
興味のある分野は、なんとなく書きたくなってしまうものです。
(これでも書き足りない)
5月の目標は"創作を意識する”です。
未だ読んでくださる方の気持ちをほぼ考えないまま書いてしまっている自分に反省しています。
次はもう少し、みなさまに向けた文章にしていきたいなぁ。
自己紹介はこちらから。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
