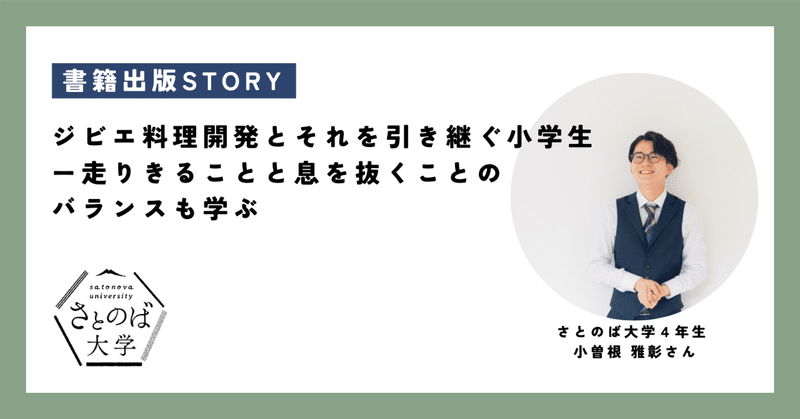
ジビエ料理の開発と、それを引き継ぐ小学生 ー走りきることと息を抜くことのバランスも学ぶ
【書籍出版STORY】学び3.0 -地域で未来共創人材を育てる「さとのば大学」の挑戦-第2章「さとのば大学の学生たち」より、岡山県の西粟倉村で学んだ小曽根さんのストーリーをご紹介!
4年間で全国4つの地域に1年ずつ暮らしながら、自分で立てたテーマに現地の人々と取り組む「プロジェクト学習」と、地域共創の専門家から学ぶ「オンライン学習」を行き来しながら学ぶ、さとのば大学。
その学びの軸となるのが、自分の思いと地域の資源や課題、そこに暮らす人々の思いを掛け合わせ、1年かけて0から作り出す“マイプロジェクト”です。そこには、期待や葛藤、喜びや失敗など、様々な経験が詰まっていました。
一人で未知の地域に飛び込み、試行錯誤した経験を、学生たちはどんな風にうけとめ、何が変わったのか? この4月に出版した「学び3.0 ―地域で未来共創人材を育てる『さとのば大学』の挑戦」から、日本の各地で奮闘する学生たちの姿をピックアップしてご紹介いたします!

※本原稿は、書籍にて一部に地元の方が使わない表現や不足している情報があったため、修正を行ったうえでこちらに掲載しております。
小曽根雅彰さんは、10人きょうだいの4番目。
一度は全日制の高校に入学したものの、いじめを受け、2年生の7月に通信制高校へ転入し、親に負担を掛けないよう、アルバイトをしながら高校時代を過ごしました。進学を考える際も、学費や生活費を含め、自分でやりくりできることが前提だったと言います。検討した結果、Instagramで存在を知った、さとのば大学に入学を決めました。
彼は、料理好きで、「料理の道で生きていきたい」という強い意志を持っていました。そのため、さとのば大学入学前に面談した際、「調理系の専門学校で学んだ方がいいのでは」ということも伝えたのですが、「将来、単に飲食店で働いたり、経営したりするのではなく、食の意義をきちんと社会に伝えていきたい。どうすれば、そういうことができるのかを考えたとき、さとのば大学の方が、深く面白い学びができそうだから」といったことを話していました。
そんな小曽根さんが1年目に選んだ地域は、岡山県の北東部に位置する西粟倉村。山間の町であり、百年の森林構想を掲げている村でした。彼はそこで、鹿などに植林した木の芽が食べられるなど、深刻な獣害がある現実を目の当たりにします。その一方で、地元の人は、あまり鹿肉や猪肉を食べないことも知りました。
そこで、駆除された生きものを森のめぐみとして捉え直し、鹿肉を使ったハンバーガーなど、ジビエ料理のレシピ開発を進めます。また、学校給食の献立づくりに声をかけてもらい地元産のジビエを取り入れたメニューを開発したり、全国各地の家庭にジビエバーガーのレシピと食材を送り、各地のキッチンをオンラインでつなぐことで「孤食」をなくすプロジェクトを行ったりと、次々と実践を重ねていきました。

もともと小曽根さんは、西粟倉村にやってきた当初、「生産者と消費者をつなげたい」という大きなテーマを持っていました。一次産業に関わる人口を増やすことによって、地域が活性化するんじゃないかと考えていたようです。
ただ、一次産業の担い手を集め、育てるためには、イメージから変えていかなくてはいけません。それには食だけではなく、職業理解に関する教育も必要だと考えていました。

そうしたとき、彼はある小学生と出会います。最初に実施したジビエ料理教室に参加した5年生が「料理人になりたい」という夢を語ってくれたのを機に、彼と一緒に、猪肉を使ったライスバーガーやジビエ餃子などの料理教室を企画し、実施していきました。最初は特別講師としてイベントの一部を任せることから始めて、徐々に小学生が主体として企画・運営できるように、伴走、工夫していったのだとか。
その後料理教室は進化して、彼の「料理人になりたい」という夢に近づくためにも、「食堂」を開くことになりました。それが、小曽根さん西粟倉村滞在最後のイベントとなります。無事に「鹿肉の冷やし中華」を有料で地元の人に提供し、自信をつけたその小学生は、小曽根さんが村を離れてからも、「猪汁定食」や「イノシシ肉のすき焼き定食」など、一日限定の「食堂」を何と一人で実施しているそうです。
「この子がいてくれたからこそ、教育に改めて目がいった」と小曽根さんは話します。
そして、彼が持つ食に対する思いと、教育や職業選択に対する思いが合わさり、食育と職育を絡めた「二つのしょく育プロジェクト」を推し進めることができたわけです。彼のこうした活動は、メディアでも紹介され、大きな反響を呼びました。
そんな小曽根さんが2年目に選んだ地域は、岐阜県の郡上市でした。ここでの彼は、少し肩の力を抜いた過ごし方をすることに。学士取得のためにダブルスクールとして学んでいた通信制大学は休学し、地域でのプロジェクトの数も減らしていました。その1年を、期末の発表会では、こんなふうに振り返っています。
「郡上に来てからは、何もしていませんでしたが、思い出に残っていることがたくさんあります。深夜、川に潜って鮎を採るという〝宵い狩り〟では、川に流されながらも8匹ぐらい採り、焚火で塩焼きにして食べました。地元の酒蔵の蔵開きに訪れた際は、昼間からお酒をふるまわれ、地元の人たちと語らいました。早朝の出荷に間に合わせるよう深夜から始まる野菜の収穫のお手伝いでは、辛い仕事だなと思いつつ、こういう農家の人たちがいるからこそ、おいしい野菜が届けられるんだという事実に気づくことができました。川に触れ、畑に触れ、さまざまな文化に触れ、改めてプロジェクトをしなくてもいいんじゃないかって思うくらい生活は充実していました」
これまで彼は、ずっと走り続けてきた状態でした。高校時代から、働きながら学んできたこともそう。自立心が強く、「ちゃんと稼げるようになる」という思いが常にあり、西粟倉でもアルバイトをしながら、ジビエ料理開発や食育・職育などのプロジェクトも数多く動かしてきました。そのなかで、初めて「もう少しゆっくりしたい」ということを言えるようになったわけです。これは、すごいことです。彼は、こう続けます。
「西粟倉でやっていたプロジェクトが発展し、小学生のみでイベントを運営するまでになりました。それは僕にとっての成功体験で、その感覚を持った状態で郡上に移動したのですが、ここで新たなプロジェクトを動かすモチベーションにはなりませんでした。スタッフの方とも話をさせていただき、何とか形となるものをつくろうと思っていたけど、一旦手放すことも大事だなって感じたんです。1年目の西粟倉を走り切り、2年目の郡上では少し息抜きしている状態ですが、そのバランスを自分で調整することで、自分の中のワクワクが保たれることもあると思っています。周りに流されず、やるかやらないかも自分で決めて、それに責任を持ってやっていく。そんな覚悟が生まれつつあります」
こうも話していました。
「西粟倉と郡上とを比べてみて、どちらも魅力的だけど、少し違う雰囲気もあります。それぞれの地域を経験したからこそ言えることがあるし、実際に住んでみないと、わからないことだらけ。さとのば大学のある意味って、そこなんじゃないか」と。
彼は今、母校である通信制高校でのラーニング・アシスタントの活動のほか、キャリアアップ教育など、既存の教育にはない課外授業プログラムの企画・運営をオンラインで実施しているようです。
西粟倉村でも郡上でも、まずはアルバイト先を探すことが先決だった小曽根さん。
「今までは、稼ぐこととプロジェクトは別々のものだと考えていたけれど、プロジェクトの一環としてバイトを捉えるようになってきた」
と話します。それがその先、自分の仕事につながっていくような感覚もあると言います。生きることと、学ぶことが徐々につながってきているようです。
【書籍情報】

●タイトル:『学び3.0―地域で未来共創人材を育てる「さとのば大学」の挑戦―』
●著者:信岡良亮
●発売日:2024年4月10日
●ページ数:239
●定価 :1,650円(税込)
●発行 :リテル
●発売 :フォレスト出版
●ISBN:978-4-86680-852-9
全国の書店、ネット書店等にてご購入いただけます!
・Amazon:https://amzn.asia/d/bPq9MN8
・楽天ブックス:https://books.rakuten.co.jp/rb/17804211/
■暮らしながらプロジェクトを実践する、さとのば大学の学びのフィールドは全国各地
さとのば大学では、4年間1年ずつ多様な地域へ留学し、地域での様々な人との出会いや対話を通して自分自身の関心を探り、マイプロジェクトへと繋げて実践していきます。ぜひあなたらしさが活かせる地域を、見つけに行きませんか。
▼学生の日常や大学最新情報は公式SNSで発信中!
Instagram/Facebook/Twitter/Youtube
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
