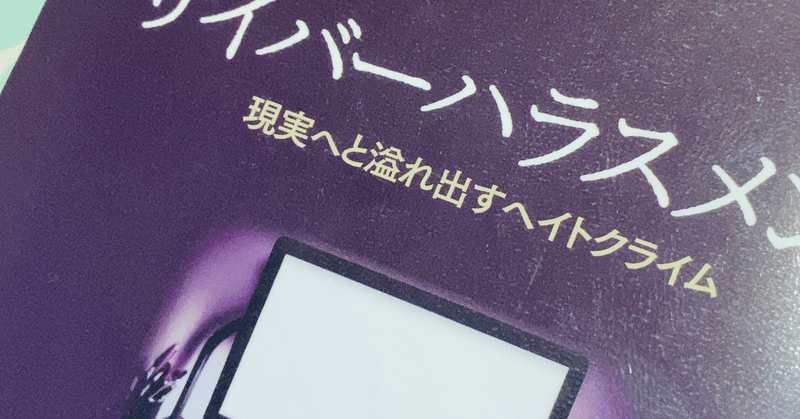
ネット介した中傷問題は米日で大して変わらねぇんだなと知る|『サイバーハラスメント』
『サイバーハラスメント──現実へと溢れ出すヘイトクライム』を読んだ。
この本で学べるのは、サイバーハラスメント──つまり、インターネットを介したハラスメント行為をどのようにして抑制、または排除できるのか……を一緒に考えよ?みたいな内容。いくつか実際にあった事件を例にして、発覚から訴訟までの流れを追うことで、こちらも「う~ん、どうしたらいいんすかねぇ?」を知っていく感じ。学術書に近い内容だが、「だ途上だからお前も一緒に考えるんだ!」と、熱を感じる部分も。
女性への汚い軽口も学べる本(同時に下衆な男も知る)
ネット上のハラスメント行為は、オフィスで直接尻に触るような行為ではない。誹謗中傷をひたすらメール・メッセで送ったり、あらぬ噂を掲示板やウェブサイトで書き込んだり、えちえちなコラージュ画像を拡散したり、住所を特定してプライバシーを暴いたり……などが、サイバーハラスメントとされている。外堀をじわじわ埋めていたら、「手伝いましょうか?」と見知らぬ人がどんどん来て、いつのまにか城壁ができちゃってたのがネットのハラスメント行為。きっかけは1人が発した一言でも、面白がって1億人に同じことを言われれば、誰でもメンタル凹むしょ。
とにかく、これはハラスメント行為なので犯罪である。ハラスメント行為が犯罪と認められたのも、実はつい最近のこと。女性軽視は何も日本だけの問題ではない。
男女問わず”された側”は被害者で、”した側”は犯罪者となる。基本は現行犯逮捕、もしくは証拠を固めての法廷バトルになるが──
サイバーハラスメントが厄介なのは、匿名性が非常に高いネット上の出来事でありつつ、情報の拡散が早く愉快犯がミーム状に拡大してしまうため、実行犯を特定するまの労力がハンパないこと。ISPなどネット接続を担う企業は、アクセスログを保存する期間も法律で定められている。
まあ全て保存していると、記録媒体がいくつあっても足りない。だから半年間の全ユーザーログ保存と決めていることが多い。短ければ数ヶ月分とか。
それはすなわち、ネット犯罪の元を辿るリミットは「半年前まで」ということになる。だからネトハラ受けて半年引きこもり、メンタルがようやく戻って「さあ訴訟するぞ訴訟するぞ!」と意気込んでみたものの、ISPにログが残っておらずアクセスログからの追跡が不能となり、真に泣き寝入りしてしまうこともある。この辺は現実の痴漢行為と似たようなものかな。
この本で面白いと感じた記述がある。
『匿名性をなくせばネット犯罪を抑制することは可能かもしれない。でも匿名性が高ければこそ、政治や企業の闇を暴くための動力になるかもしれない。法整備をすすめることは、そのバランスを維持するために必要なこと。決して匿名性を無くそうとは考えていない──』的なニュアンスの文。
今のネットは実名ウェルカムどころか、往く先々でセルフィーしないと死ぬレベルで自撮りアップも当たり前になった。自分の姿をネットに晒すと死ぬのは、インターネッツ老人会の面々くらいになっている。それか自分が嫌いな人たち。
サイバーハラスメントは現実でもネットでも、ちょっと有名な人が対象になりやすい。それは妬みからくる陰湿なイジメである。この手は「心無い一言」がよく取り上げられるけど、それを対面でぶつけられる勇気は持っているのだろうか。名前もわからず姿も見えず、匿名が守られているからこそ言える言葉ではないだろうか。なぜ人は、仮面をかぶると攻撃的になってしまうのだろうか……。
「言葉の暴力」を法律で”無くす”ことは不可能。
もしもの例を考えるなら、”相手を不快にさせる一言”が入るでしょうね。もしそうなったとしても、不快になるレベルは人それぞれだから、次は特定の単語に制定するしかない。放送禁止用語など、ピー音が入る言葉は使うなって言われても、伏せられた言葉を知ることで、それが中傷、または隠語な用語だと気づくこともあります。
……そう考えると、沈黙が正解でしょ?言論の自由が失われるわけだし、友人同士の会話で「ちょお前氏ねよ!(笑)」とふざけた会話でも、本人たちの意志とは反して罰せられる可能性が出てくる。
ネット上の犯罪を取り締まるのを難しいのは、犯人の特定が難しいところ。なんだか「IPアドレスを知れば相手を特定できる!」みたいな風潮があるけど、頭に血が昇った言語直感バカでなければ、アクセスルートを幾重に隠蔽して偽装する。それでも本気で探れば辿り着くわけだけど──。犯人が偽装でも接続したAPから開示してもらう手続きをいちいちしなければならないため、労力と結果が釣り合わない。おまけに警察関係者も、ひいてはサイバーセキュリティ課にも「よくわかんない」人もいたりする。これは世界共通の問題点。
なので本著では、以下を特に重要視するべしと捉えている。
1.被害者の通報、そして声に耳を傾けること
2.法整備は迅速に。そして世界中で
3.通報から逮捕まで迅速にするには警察のスキルアップが重要
サイバー犯罪は、まあとにかく、面倒な問題なのである。
ここ数ヶ月を遡っても、ネット上の誹謗中傷で自殺した有名人は存在する。もともとはファンであるはずが、如キバを剥いて攻撃を扇動したりするから、匿名パワーは恐ろしい。やっていることは「デモ」と変わらない。だけど、中継で顔が割れやすい国会前デモよりかは、ネット上の誹謗中傷へ加わるメンツは”軽い気持ち”で入力していると思う。
それは「こんなことじゃ人は死なないし、捕まることもないだろう」と思い込んでいるセーフティーがあるから。まあとにかく、「口は災いの元という名言を知らないのかよ」と覚えておいて欲しい。
サイバーハラスメントをやる側の人間がこの本を読むとは思えないが……
ほぼ学術書といっていいので、字がみっちりあるから読み切るのは時間がかかる。専門用語も多く出てくるものの、普段からネットをやっていれば「あーうんそーね」と理解できるレベル。問題は法律関係かな。
本著は序盤で「サイバーハラスメントとは何か?」を提起し、事例を持って読者へ「これどう思う?」と語りかける。中盤からは試行錯誤の法廷回となり、法が出来ていく過程を知ることもできる。終盤は「結局いたちごっこになるけど……なるようにするしか、ないヨネ!」という感じで終わる。
実例はアメリカで実際起きた事件を扱っているし、ネット犯罪の黎明期だから、警察のあわわわで無能な対応を赤裸々に記録している。この辺は無能ネット警察日本と大差ないし、向こうが提起したからこそ、今の日本があるといえる。
悲しみは二度と繰り返してはならないの考えから、ネットを介したハラスメント・誹謗中傷・言葉の暴力などを、法律でどう抑制するか──についての議論が始まる。これは世界中で同時進行している問題である。某社の噂のように、端末に無許可でトラッキングアプリを埋め込んでいれば、どこの誰がネット上で何をしているのかが、ハッキリ把握できるようにはなる──。
まあそれを実現するなら、ネットに接続する全ての人が、ある1つの巨大国家に掌握される感じになるのでは?
サイバー犯罪で逮捕されているのは、全体からすればほんの一握り。わかりやすいバカか、元凶となる重要人物を優先しているので、”見せしめ”の狙いが強いでしょう。個人が使用する端末を警察が把握することができれば、犯罪は減るでしょうけど、反発が強いんだろうなぁ。悪いことを一切しなければいいだけなのにね。
頂いたサポート費は活動費にあてさせていただきます!カフェイン飲みたい。
