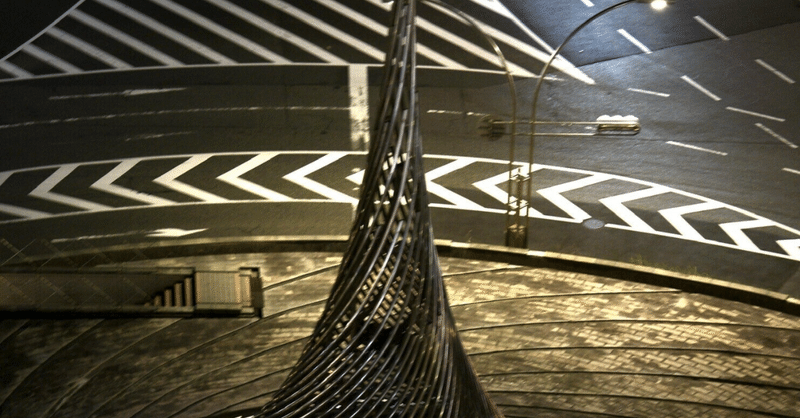
「音楽・平和・学び合い」(18)
◆【実践報告】
中学校における臨床教育学的生徒理解(4)
-生徒のナラティヴを引き出す音楽科授業-
4.「5分間鑑賞」が引き出した生徒のリアリティー
-『ギルド』のエピソード
2009年(前任校最後の年)2学期最初の授業でのことである。バンプ・オブ・チキンの『ギルド』という曲が3年生のあるクラスで紹介された。この曲はその前年(2008年)に起きた秋葉原無差別殺傷事件において、犯行に及んだ男が事件の直前に、その歌詞をサイトに書き込んでいたという曲である。紹介した生徒はこのエピソードを知らなかったが、私は北海道大学の中島岳志氏(公共政策大学院准教授)の講演12)を通して、この話を知っていた。
このクラスはその覇気や反応のなさから、1学期には随分語ったり叱ったりとエネルギーを使う学級だった。グループ間でのいじめやトラブルが続き、居場所を失った生徒が転校したり、クラスに入れない生徒が交互に休んだりと、落ち着かない日々が続いていた。2年次までは前向きに発言したり行動できていた生徒でさえ、KY文化に絡め取られ何も言えないような雰囲気がクラスを支配していた。
この曲が紹介された日の朝、私が担任に代わって短学活に行った時、彼らは暗く死んだような挨拶しかできなかった。「この空気のまま、音楽室には来ないでね」とは言ったものの、案の定覇気のない状態で授業が始まり、曲紹介のスピーチも小さな声でほとんど聞こえない。ふと中島氏の講演内容を思い出し、「彼らに自分たちの問題点を感じてもらうには、このタイミングしかない」と急いで職員室に行き、中島氏の講演記録を手にして音楽室に戻った。曲の最後に入っているハンマーの金属音を取り上げ「何の音に聞こえる?」と問いかけるも、最初はいつも通り何の反応もなかった。その後、この曲の歌詞「その場しのぎで笑って、鏡の前で泣いて、当たり前だろう、隠してるから気づかれないんだよ」を取り上げ、この曲と秋葉原事件との接点を紹介した。その上で中島氏の講演内容をそのまま読み上げた。
「そういう自分とやっぱり向き合うしかないじゃないか、そういうものをかかえこんでも、他者と関わりながら生きていくという、そういう意志をもたないといけないんじゃないか」との中島氏の言葉に生徒たちは反応し、顔を上げて現状に満足していないという感覚を表現してくれた。一通り話し終えた後、「もう一度この曲を、今の自分たちと重ねて聴いてみて欲しい」と伝え、紙を配り再度音楽を流し始めると、1回目とは打って変わったように、あふれる思いや感情、思考を皆が書き始めた。
以下、2人の生徒のナラティヴを抜粋して紹介したい。
==================================
1-(前略)私はBUMP OF CHICKENがとてつもなく好きで、多くの曲をもっていますけれど、こんなに自分が思っているより強いメッセージがあるんだと思いました。歌詞を見て、人間の捉え方の違いがものすごくわかった気がする。「気がする」というのはおかしいかもしれないけれど、「よくわからないもの」が頭の中に浮かびました。「人間という仕事」という出だしがこんなに重要だと、たくさんの人に伝わっているんだなと、最初は思いませんでした。(中略)BUMP OF CHICKENのデビュー曲「ダイヤモンド」の歌詞の中に「何回転んだっていいさ」という歌詞がある。この歌詞と「ギルド」はつながっているような気がしました。どうして私が、この曲が、このBUMPOF CHICKENが好きなのか、今日の音楽でわかりました。自分が言われたことだけやって…。本当のこというと、私はもともと、人とあまり話さないです。こんなシナリオ通りの人生を生きているから、この曲を選んだんだと思いました。人間はイヤなことは何でも「自分だけだ」と思いがちですが、広く考えれば、原因は周りにも自分にもあるんだと、あらためて思いました。最後の音は、新しく歩き出した足音、そしてそれを応援する音にも聴こえました。
==================================
2-必ずしも自分に落ち度がなかったとは言えない。拒まれ、クビになるのは、自分の力が至らなかっただけ。社会にぶつけても逆恨みでしかない。「お前は生まれたばかりの、うじゃうじゃいる子蜘蛛より下にいるんだ。そんな素人が糸の出し方すっ飛ばして巣作ろうなんざ、1兆年早いんだよ。生まれ直してこい!」厳しい言葉だが当たり前だろう。自分の母親は派遣切りで仕事がない。職を失うことがどういうことなのかはわからないが、自分の母親ではあるのだが、ああはなりたくない。新たな職を手に入れられないのを、他人のせいにしたくないのだ。少なくともこの社会には失業者も含まれる。だからここまで悲惨になったのは、社会のせいだ!と訴えたところで、回り回って自分のせい。自分の落ち度を認め、前向きに生きようとする者は、周りの人の輪からは外れる。自ずとそうなるだろう。
==================================
一人目の生徒は、この曲を持って来てくれた女子生徒である。まじめだが自己表現の得意ではない子で、2年になったときに合唱部を辞めた生徒だった。彼女は「シナリオ通りの人生を生きているからこの曲を選んだんだ」と気づき、最後のハンマーの音を「新しく歩き出した足音」と肯定的に再解釈している。坦々と聞いているだけでは生成しないイマジナリーなストーリーが、作品を自らの物語に重ねて深く味わうことを通して生まれている。
二人目の母子家庭男子生徒は、自らの母親が派遣切りにあったという複雑な心境を書いている。蜘蛛のメタファーは、世知辛い「自己責任論」の影響を強く感じさせるが、そこに漂う「生きづらさ」に抗おうとする彼の心性を行間から読みとることができるだろう。他の生徒たちの文章にも、様々に彼らの「生きづらさ」が色濃く表現されており、同時にそれを乗り越えて前向きな未来をつかみたいという意志があふれていた。
中島氏は講演において「もしかして書き込みを次の所に展開して、最後の方の歌詞まで書き込んでいたら、彼はそこの所で立ち止まったかもしれない」と指摘し、その上で彼に足りなかったのは「社会的包摂(social inclusion)」であったと言う13)。さらにこれは決して彼に限ったことではなく、様々な場面で承認されず、湯浅誠氏の言う「溜め」を失った人々がこの社会には無数に存在しており、そういった人間関係のつながりを再構築することこそ現代人の課題なのだとまとめていた。フェイストゥフェイスで関係を編みなおすオルタナティブなつながりが、もっと様々な場所で生まれる必要があるとも主張していた様に思う。ここには一人ひとりのナラティヴ(物語)に耳を澄まし、個人の当事者性に立脚しながら、それぞれが各々のストーリーを生きることを可能とする、新たな社会像への志向性が表明されている様に思われた。
中島氏が語る「つながりからも排除されてしまって(中略)社会的包摂というものがはたらかなかった」14)状態が、過去も現在もこの国の至る所に現出しているのではないか。そしてさらに悲しいことには、そのようなつながりを感じられない、殺伐とした空虚な空間として、学校や教室が子どもたちの前に立ち現れているのではないか。思い返せば、私が向き合ったこのクラスは、そういった「社会的排除(social exclusion)」の雰囲気が支配する場所となっていたのではないか。
今回紹介した『ギルド』のエピソードを通して子どもたちと確認できたのは、音楽にはこういった社会的な関係性に気づいたり、承認を与えて孤独を癒したりする包摂力があるということだった。この取り組みは私にとって、「音楽は人の心に深く届く」ということを再確認する、たいへん貴重な機会となった。この授業の後、彼らは受け身であることを意識的に脱して、積極的に声を出し仲間と支え合う雰囲気を作るようになっていった。その後の合唱の取り組みでは、特に男声パートが意欲的な取り組みを見せ、アカペラの混声四部曲を見事に歌いこなすところまで成長を見せた。あの時の「5分間鑑賞」のおかげでクラスが好転したとまでは言わないが、確実に彼らが変わるきっかけとなったことは間違いない。このケースは、音楽がその人の内面の語り(セルフ・ナラティヴ)を触発し、自己認識を変える力となることを証明する一つの機会となったのではないだろうか。
【注】
12)中島岳志・雨宮処凛「貧困と教育、経済格差と教育格差問題を考える」北海道教職員組合編『北海道の教育』第43集 第58次合同教育研究全道集会(夕張)報告(2009)pp.73-105
13)前掲書p.105
14)前掲書p.104
===編集日記===
皆様に支えられて「日刊・中高MM」第3325号です。
笹木陽一さんの「音楽・平和・学び合い」、お届けします。
前号の続きです。
・一人目の生徒は、この曲を持って来てくれた女子生徒である。まじめだが自己表現の得意ではない子で、2年になったときに合唱部を辞めた生徒だった。彼女は「シナリオ通りの人生を生きているからこの曲を選んだんだ」と気づき、最後のハンマーの音を「新しく歩き出した足音」と肯定的に再解釈している。
・二人目の母子家庭男子生徒は、自らの母親が派遣切りにあったという複雑な心境を書いている。蜘蛛のメタファーは、世知辛い「自己責任論」の影響を強く感じさせるが、そこに漂う「生きづらさ」に抗おうとする彼の心性を行間から読みとることができるだろう。
見当違いな話になるが、「食」について、「何を食べるか、ではなく、
誰とどこで食べるか」が重要。そんなことを思いだした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
