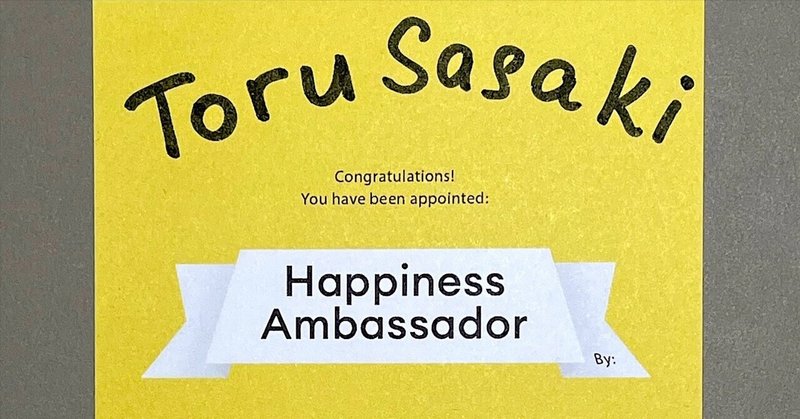
#99 「好き!」 は嘘をつかない〜100番目の記事を目前に、大おさらい会
今年4月にアカウント開設、6月にスタートした note が次の記事で100投稿目になる。明後日に投稿する100番目の記事は、『未来の日本へ、10の提言』と題して、僕が教師時代から今まで、「日本は□□を〇〇すれば、もっとしあわせな国になるのにな〜」と思いついた提案を10項目書こうと思う。今日は一歩手前の99番目ということで、これまでの記事の大おさらい会をしたい。
たくさんスキをいただいた記事
大切なのは自分の思いと、それが読者にどう届いたかということは充分に承知しているが、それでもたくさんスキをいただけるとやはり嬉しい。この記事を書いている時まででいただいたスキ数トップ10の記事と、その思いを振り返りたい。ここでの順位はダッシュボードの情報を元にしているので、実際の数と若干違う場合があることをご容赦願いたい。
* * *
第1位:「#51 あの選択をしたから〜年収3分の1の転職〜」🎖️
この記事は、マイナビ × note のコラボコンテスト「あの選択をしたから」で賞をいただいた。この記事をきっかけに知り合えた方もいて、感謝の気持ちでいっぱいだ。読み直すと、文章が下手だなあ、稚拙だなあ、と思う。賞品として頂いた2万円で、日本の自宅のコーヒーメーカーを新調した☕️
◇ ◇ ◇
第2位:「#80 全部落ちた、オンライン英語教師」
この記事が第2位に入ったのは、かなり意外だった。一見、いろいろスムーズに進んでいそうな僕が、実は自分の最も得意分野の「英語を教える」という分野で全敗したという事実が多くを語ってくれた。でも、英語を教えることには今後も何らかの形で携わりたいと思っている。
◇ ◇ ◇
第3位:「#70 北欧に想いを馳せた、ロヒケイット」
この記事は、note の特集3つに同時期に掲載していただき、ビュー数では2位に2000ビュー以上の差をつけて、ダントツ1位の記事だ。1日に1000以上のビューがついた日もあり、書いた方がびっくりだった。ロヒケイットは妻の大好物、年末に帰省したら真っ先に作る約束をしている🇫🇮
◇ ◇ ◇
第4位:「#58 未来のためにできること 〜幸せの意味を99%まで考えること〜」
文藝春秋 × note のコンテストに応募した作品。「未来」を50億年後に設定して書いてみた。1000字という短い制限の中で書くのはいい経験だった。コンテスト受賞は逃したが、実はこの作品は終わっていない。続編が年明けに意外な形で登場するので、乞うご期待〜みなさんのご期待を上回る自信があるぞ😎
◇ ◇ ◇
第5位:「【号外#5】KANさんありがとう 〜よければ一緒に、バトンを引きつごう〜」
KANさんの訃報にふれて急いで書いたが、思いのほか多くの人に読んでいただけた。同時に、長年連絡が取れずにいた旧友とのやりとりが復活したのも、この記事のおかげだった。KANさんは亡くなったあとも人と人を繋いでいる。いつの日か、ヨーロッパのどこかの駅のストリートピアノで、KANさんの「1989」のピアノ・アレンジを弾く、と決めた。
◇ ◇ ◇
第6位:「#82 ワクワク人生のための、学修歴プラン」
これはとても意外だった。かなりとんがった意見だと思うし、今の日本の価値観とは全く違うことを書いたので、こんなに反響があるとは思っていなかった。なんといっても、「大学なんて大の字がついていればどこでもいい。入学後徹底的に成績にこだわって GPA 3.7 を取り、30歳前後で海外の大学院へ行って一花咲かせよう」という内容は、やはりぶっ飛んでいる。
◇ ◇ ◇
第7位:「#43 ドイツ留学、ふりだしから始めよう」
これは上の記事以上に意外だった。47歳まで「純粋文系」だった僕が、理転後3年で海外の大学の博士課程へ進学し、研究員としてフルタイムのお給料をいただいているというストーリーが、やはり斬新だったのだろう。実際はかなりきついので、早く続編を涼しい顔で書けるようになりたい。
◇ ◇ ◇
第8位:「#67 勉強して叱られるのは、納得がいかない」
この記事が上位に入ったことは心から嬉しく、この記事に書いたことが自分だけの感情でないことがわかってホッとした。どうしても音楽理論をちゃんと理解したい。ここで言う「音楽理論」はクラシックの理論のことではなく、いわゆる「バークリーメソッド」のことだ。少なくとも、Available note scale に基づいたインプロヴィゼーションを理解して実践できるようになりたい。サックスとフルートで。
◇ ◇ ◇
第9位:「#79 やりたいことは、全部やる」
この記事はとても個人的な内容で、ひっそりと忘れられる記事になるかな、と思っていたので、上位に入ってどちらかというとキツネにつままれた思いだ。でも、僕と同じように、今はできていなくても、「やりたいことは、たくさんある」人が多いのだろうな、と思った。「生まれ変わる保証ないよ」という友人の言葉は、大きな気付きをくれた。
◇ ◇ ◇
第10位:「#66 もう一度、「ぶらいと珈琲」一緒にやりませんか?」
この記事を出したのが10月で、なんと先日、この記事を読んだある方から、「私もカフェをやるのが夢でした。「ぶらいと珈琲」として、二人の夢を合わせたカフェをやりませんか」とお誘いをいただいた✨実際にはすぐにとはいかないが、思いは発信してみるものだと思った出来事だった。つくばにあった小さい喫茶店の思い出は、これからもきちんと生き続ける。
たくさん読んでいただいた記事
僕の記事は、スキ数とビュー数が比例しない記事が結構あった。つまり、スキは押さないが多くの人に読んでもらえたということだ。こちらもビュー数トップ10の記事について、スキ数トップ10に入っていないものを紹介したい。
第1位:「#70 北欧に想いを馳せた、ロヒケイット」
(7386ビュー)スキ数第3位
第2位:「#51 あの選択をしたから〜年収3分の1の転職〜」
(5023ビュー)スキ数第1位
第3位:「#18 デスクトップPCを飛行機で持っていく!」
たくさん写真を入れて、iMac 27インチを安全に飛行機の預け入れ荷物として運ぶ方法を説明した記事だ。この記事を通して、オーストラリア時代に留学していた大学に現在留学している方と知り合えた。同じ学生寮に入っているという嬉しい共通点もあった!(1545ビュー)
第4位:「【号外#5】KANさんありがとう 〜よければ一緒に、バトンを引きつごう〜」
(1421ビュー)スキ数第5位
第5位:「#32 ダルムシュタット工科大学」
ドイツの大学は日本ではあまりなじみがないと思うので、やはり好奇心で多くの人に読んでいただけたのだろう。(1185ビュー)
◇ ◇ ◇
第6位:「#10 “Don't think, just do.” の本当の意味」
映画『トップガン マーヴェリック』をハッシュタグに入れたので、多くの人が読んでくださったようだ。僕の信じるところを書いたつもりだが、内容的にはあまり共感を得られなかったか?僕は、Don't think, just do. は、充分に考え抜いた人にだけ許される特権だと信じている。(903ビュー)
第7位:「#80 全部落ちた、オンライン英語教師」
(775ビュー)スキ数第2位
第8位:「#64 朝と夕方は、宮殿にいます」
これは、note の旅行記事に取り上げてもらったので、多くの人に読んでもらえたようだ。お気に入りの図書館があって、そこにいる時間を宝物のように感じられるというのは、大きなしあわせに違いない。今の季節は、この宮殿の目の前がダルムシュタット・クリスマスマーケットの主会場になっていて、とても華やかだ。(683ビュー)
第9位:「#43 ドイツ留学、ふりだしから始めよう」
(641ビュー)スキ数第7位
第10位:「#38 ダルムシュタットの役所と教会を『ブラタモリ』」
ハッシュタグ「ブラタモリ」が効いたのだと思う。僕がこれまでに書いた記事の中で、数少ない観光案内的な記事。実際はダルムシュタットには世界遺産が一つあるので、年明けにはそちらを紹介する記事を書こうと思う。恥ずかしながら、まだ一度も行っていないのだ。(632ビュー)
結果からみえてくるもの
ここではあくまで note ダッシュボードに現れた「数字」のみに基づいて、98本+号外6本、合計104本の記事をふりかえった。実際には、数字では上位に来なかったが思い出深い記事もたくさんある。いつか、数字ではない軸でのふりかえりもしてみたい。それでも、上の2種類の結果を見て気付いたことが3つあるので、最後にまとめておきたい。
「好き!」は嘘をつかない
スキをたくさん頂いたり、ビュー数が多かったりする記事をよく見てみると、一つの共通項があった。それは、自分の「好き!」なものについて書いた記事だったということだ。コンテストで賞を頂いた記事は、2000年からこれまでの20数年間を「好きを羅針盤として」生きてきたことの記録であり、多くの人にこの、「好きを羅針盤として」というフレーズが響きましたと言ってもらえた。
それ以外にも、英語、好きな料理のロヒケイット、KANさんの音楽と、受け入れてもらえた記事の多くは「好き!」がベースにあるものだった。この結果を見て、本当に嬉しかったし、安心した。僕はこれからも、「好き!」に原点がある内容を発信していこうと思う。
「情報提供」には伸び代がある
同時に、自分ではあまりピンときていないながら、「情報提供」を主とする記事も、それなりに受け入れてもらえた。日本人にはあまり馴染みのないフィンランド料理ロヒケイットの作り方や、大型モニタをスーツケースで運ぶ方法、在籍している大学や住んでいる街の紹介などの記事は多くの人に読んでもらえた。note の公式マガジンにも多数登録して頂いた。
自分では、「情報提供」系の記事はあまり得意分野ではなかったが、今後は少し力を入れてもいいかもしれない。専門家でない人が近寄りがたい、最近の AI の内部構造などを、わかりやすく説明するのも得意だ。そういう技術系の記事も増やしていければ、と思う。
一番の財産は、「人」
たった半年間の note 生活で、たくさんの新しい友人を得た。その中でも、将来の生活や仕事に大きく関わる3人を、名前は挙げずに紹介したい。
一人目は、「#58 未来のためにできること 〜幸せの意味を99%まで考えること〜」に関連が深く、来年1月あるいは2月開始の新プロジェクトの共同運営者。上では、「乞うご期待〜みなさんのご期待を上回る自信があるぞ」と書いた。この人と知り合って以来、毎日の生活や研究の意味がはっきりしてきた☀️
二人目は、「#66 もう一度、「ぶらいと珈琲」一緒にやりませんか?」に関連が深く、食べ物の話題をきっかけとして知り合った人。来年すぐに、とはいかないが、何らかの形で、自分たちの問題意識を形にする活動をしようと話している☕️
三人目は、とても具体的な形の夢を掲げていて、その夢を応援したい!と思わせてくれる人。現実的に一緒に何かをすることはないかもしれないが、日々の活動の大きな指針となってくれるに違いない。ひょっとすると、来年開始するプロジェクトで接点があるかもしれない🌙
一年の計は 穀を植うるにあり
十年の計は 木を植うるにあり
百年の計は 人を植うるにあり
原文:一年之計莫如樹穀、十年之計莫如樹木、終身之計莫如樹人
中国の格言は上のとおりで、年齢的にも一年よりも十年よりも百年が近くなってしまった。やはり何より、人との縁を大切にしようと思う。そして、思い出してみると、上の3つの格言は、昔学んだ甲陽学院の設立趣旨でもあった。
* * *
今日もお読みくださって、ありがとうございました。明後日の100番目の投稿、どうぞご期待&よろしくお願いいたします☕️🍩🕯️
(2023年12月11日)
サポートってどういうものなのだろう?もしいただけたら、金額の多少に関わらず、うーんと使い道を考えて、そのお金をどう使ったかを note 記事にします☕️
