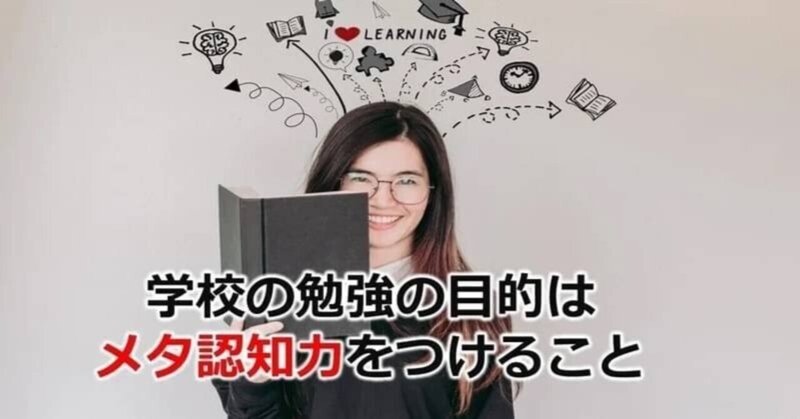
「何のために学校で勉強するの?」の答えとは?
いつも読んでいただき
ありがとうございます。
さおりんです。
今回は、あるコミュニティで
ご紹介されていた内容が
LGBTQのジェンダー種族や
ADHD・HSPなどの繊細敏感種族、
いわゆる繊細感覚派の方々が
生きやすくなるためのヒントになるな
と感じたのでご紹介していきます。
「何のために勉強するの?」
「なぜテストをするの?」
誰もが学生の頃に思う疑問です。
テストができなければ惨めですし
そもそも勉強内容が社会でそのまま
役立つ例はあまりありません。
しかし、学校は勉強やテストを通して
あるとても大事な能力をトレーニング
していたのです。
海外の大学の研究結果を
ご紹介していきます。
1. 試験の最後に自己評価をしてもらう
2017年イリノイ大学の研究チームは
同大学の「栄養学」コースの学生79名の
協力のもとに、こんな実験をしました。
合計3回の中間試験の終わりに、
追加課題として次のアンケートに
答えてもらいます。
すなわち自己評価と改善案を
記入してもらうのです。
その他にも
「何日前から勉強したか?」
「何時間勉強したか?」
「(前回の)予想得点と実際の得点」
などをたずねる欄もありました。
さらに2回目、3回目については
自分の学習戦略を自由記述で振り返る
欄も設けられました。
これに答えるだけで
次の試験に何か影響はあるのか?
結果は驚くべきものでした。
2. 学生たちに現れた
驚くべき4つの変化
研究チームは、3回の調査の結果を
分析して次のことを発見しました。
1)中間レベルの学力の学生が特に
成績が上がっだ。
このような試験ごとの学習戦略の
見直しで
最も成績を上昇させたのは
A~Cの学力レベルの中の【B層】
でした。
2)試験の平均点が低い学生ほど、
自分の成績を過大評価していた。
逆に平均点の高い学生は、
過小評価していました。
この現象はダニング=クルーガー効果
とよばれています。
3)試験の準備が前倒しになり、
勉強時間が増えた
実に85%の学生が最終的には勉強時間
を増やしたと回答しました。
特に試験1週間以上前から
準備をする学生の割合は
2回目の試験では3倍に
3回目の試験では7倍になりました。
また平均学習時間も
5時間→7時間→8時間と
試験ごとに増えていきました。
4)88%の学生が、すべての回で
試験の解き直しを行った。
復習としては最適なことです。
3.メタ認知スキルを磨いていこう
いかがでしたか?
最終的には実に72%の学生が
この試験用紙を使った振り返りが
役立ったと証言しました。
このように何かの結果について
自己評価し、戦略目標を設定しなおし
実行していく一連のプロセスを
「メタ認知スキル」といいます。
自分で自分を客観的に評価し
戦略を練り直すことは
学校のみならず、社会に出ても
必要とされることです。
学校の授業やテストは
このメタ認知スキルを
トレーニングする大事なチャンス
だったのです。

もっともメタ認知スキルの訓練は
別に何歳からでも遅くはありません。
むしろ生活のための仕事の場面こそ
より真剣に取り組めるはずです。
1)今回の仕事では何に注意したか?
2)今回の仕事は何が問題だったか?
3)次に何をするか?
これだけを日々
チェックしていきましょう。
できれば1冊のノートに記録
していくのがおすすです。
(「ジャーナリング」といいます)
本実験ではこの3点を確認するだけで
教材や教師を変えることなく
あるいはご褒美をあげるわけでもなく
学生たちの向学心が劇的に増えたのです。
忙しい大人こそやってみるべきです。
とはいえ、自分を振り返るにも
心の余白が必要です。
いつでもどんなときも
周囲の雑音ではなく
自分の内面に向き合える方法が
大事になってきます。

さらに、感情論にも当てはまります。
『感情にうったえる』
『感情の機微にふれる』
『感情が顔にあらわれる』
感情というのは常に制御が必要です。
特に交渉ごとの感情は
マイナスに作用します。
日々の生活の中でも感情的な人は
知らず知らずのうちに損してしまう事
が多いです。
損してさらに感情的になったり。
もう、しっちゃかめっちゃかです。
泣いたり怒ったり笑ったりの
感情があるからドラマが生まれます。
どのようなドラマを生み出すかを
少し考えて行動しましょう。
そのためにもこの
メタ認知&ジャーナリングを
有効に利用してみてくださいね。
ここまで読んでいただき
ありがとうございました。
さおりんでした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
