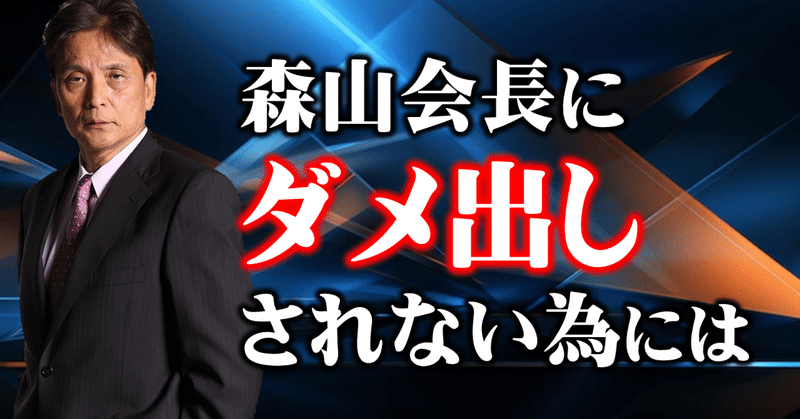
森山会長にダメ出しされない為には①
今から約10年前の2013年8月30日、日本プロ麻雀連盟で新たな番組がスタートした。
その番組は「ダメ出し麻雀」。
挑戦者は森山会長と藤原隆弘プロの解説のもと1半荘打ち、良くない打牌があるたびにダメ出しを受ける。
そのダメ出しは「ダメポイント」として貯まり、対局終了後に
1ダメポイント=1円
に換算され、挑戦者が被災地へその合計を寄付する、という番組である。
第2回は2015年8月15日に行われた。
それから9年の時が経ち…
ダメ出し麻雀の復活が決定した。
放送日程は2024年4月19日(金)14:00~
応募者多数の中、選考して頂いた結果有り難いことに出演できることが決まったので、過去のデータを分析するとともに、森山茂和会長と藤原隆弘プロの思考を解明し、ダメ出し無しのパーフェクトクリアを目指して頑張りたいと思う。
・ダメ出しされた項目の全貌
映像データが見れる範囲で番組を確認し、データにまとめてみた。

・1位 序盤の手順(26回)
・2位 立直を受けた後の手順(8回)
・3位 中盤の手順(5回)
・4位 降りるときの手順(4回)
・5位 立直の選択(2回)
森山会長と藤原プロが行ったダメ出し回数は、
計45回 合計96700ダメポイント
であった。
なお森山会長と藤原プロのダメ出しした回数の内訳はこちらである。

・1位 森山茂和会長(17回)
・2位 藤原隆弘プロ(2回)
そして残りの大半を占めるのが「二人の意見の一致」(26回)である。
この数字だけ見ると、森山会長の思考をターゲットにしぼることがクリアへの近道のように見える。
しかし実際は逆である。
番組をよく見てみると、ダメ出しを多く出しているのは森山会長だが、そのダメ出しの前に藤原プロが会長に「この打牌はどうですかね」と投げかけるシーンが多く見受けられる。
その結果ダメポイントが加算されることになるという流れはかなり多い。
藤原プロは言わずもしれた「守備型」の雀士である。
序盤の手組・牌の持ち方は誰よりも繊細といっても過言ではない。
つまり挑戦者は、藤原プロが安心してみていられるような繊細な打ち回し、が求められるのだろう。
今回のNoteでは一番ダメ出しされた回数が多かった「序盤の手順」にフォーカスしていきたいと思う。
序盤の手順の内訳はこちらである。

・1位 字牌を残すべき(9回)
・2位 手役を見るべき(5回)
・3位 字牌を持ちすぎ(5回)
・4位 手を広げすぎ(3回)
・5位 手を狭くしすぎ(2回)
・6位 その他(2回)
1位の「字牌を残すべき」と3位の「字牌を持ちすぎ」は対であり、
4位の「手を広げすぎ」と5位の「手を狭くしすぎ」も対である。
字牌を残しながら進行すればいいという事でなければ、ブクブクに構えて進行すればいいという事でもない。バランスが大事ということだ。
実際に行われた映像を使って振り返っていきたいと思う。

ここで福光プロは字牌に手をかけ、1000ダメポイントとなった。
⑨のみセーフの牌となる。
このくらいの手牌だと真っ直ぐ字牌から切っていきたくもなりそうだが、藤原プロの心がざわつかない打牌をしたいと思う。
このダメ出し麻雀の恐ろしいところは、対局中はどの打牌がどんな理由でダメポイントがついたのか選手に知らされない点である。
上の画像と似たような序盤の手牌で全て字牌から徹底して切り出していった福光プロは、その都度ダメポイントがゴリゴリ加算されていき、気づいたら序盤の手順だけで18000ダメポイントが溜まることとなった。
その負のスパイラルに陥ってしまった際の回避方法は未だ思いつかない。
とにかく序盤は特に慎重に打つことが鍵になりそうだ。
例外も紹介しておこう。

ここから北を切ったら「字牌を残すべき」でダメポイントをもらうように見える。
実際ここで三戸プロは2を切った。
が、2000ダメポイントを喰らうこととなった。
それはなぜか。
1枚の画像だけでは分からないが、実は前局に三戸プロは良いアガリをしていた。
なのでここでは手を最大限に広げる「北」のみセーフなのであった。
半荘を立体的に捉える打ち方も、ダメ出し麻雀攻略には必要なのである。
言うまでもないが内容が良くなかった次局、がむしゃらにただ手を広げていくとダメポイントを喰らうことになるので注意が必要だ。
次のNoteではリーチを受けた後の押し引きのバランスについて考えていきたいと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
