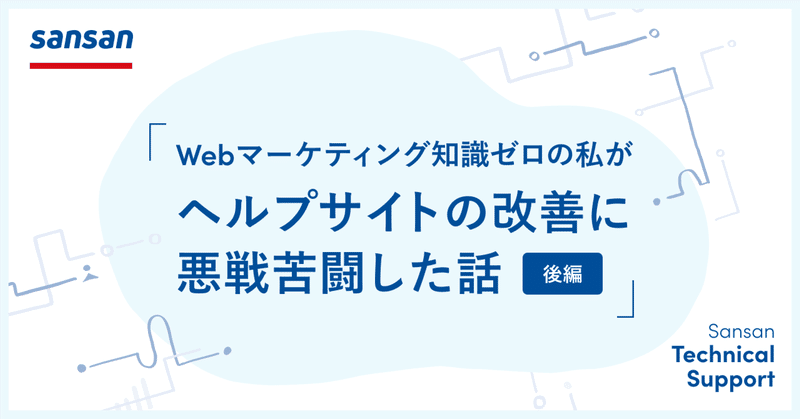
Webマーケティング知識ゼロの私が、ヘルプサイトの改善に悪戦苦闘した話 後編
こんにちは。Technical Supportの尾崎です。
この記事は「Webマーケティング知識ゼロの私が、ヘルプサイトの改善に悪戦苦闘した話 前編」の続きです。
前編をご覧いただいていない方は、ぜひご覧ください。
Webマーケティング知識ゼロの私が、ヘルプサイトの改善に悪戦苦闘した話 前編
前編に続き、以下の章立てで取り組みの詳細を紹介します。
ファクトの取得
他社を知る:ヘルプサイトの「あるべき姿」を考えるイベントを開催
内容は過去に投稿した記事「ヘルプサイトの「あるべき姿」を考えるイベントを初開催【Sansanイベントレポート】」で紹介されているため、本記事では割愛します。
よろしければご覧ください。
ヘルプサイトを知る:Google Analyticsを用いたアクセス解析
まずは、ヘルプサイトのアクセス状況を把握することから始めました。
幸いにも、SansanのヘルプサイトにはGoogle Analyticsが導入されていたため、まずはそこから解析しようと考えました。
開くだけでなんだか賢くなったような気にさせてくれるダッシュボードに浸りつつも、専門用語の多さに「これは勉強しなければ…」と思ったことを覚えています。
Google AnalyticsはGoogleアカウントさえあれば利用が可能なため、解析したい内容をWebで検索すれば実現方法を紹介したブログがヒットしたり、また自社のマーケティング部門に達人のような社員がいたりと、先駆者が多く存在することが利点でした。
また、SNS上にコミュニティーなども存在します。
まずは泥臭く簡単な情報でもいいので抽出方法を調べ、実行してみることで、徐々に専門用語の意味などの理解が深まり、必要な情報が抽出できるようになりました。
解析の結果、以下のような事実が浮かび上がりました。
お問い合わせに至ったセッションにおけるランディングページ(ヘルプサイトの中で最初に訪れたページ)は以下の通り
1位:トップページ
ランディングした直後の行動は、「トップページ上部の検索窓からの検索」や「トップページに表示しているFAQ記事の閲覧」を大きく上回り、「記事を閲覧することなくお問合せフォームへ直行する」が最多
2位:個別のヘルプ記事
アクセス元はプロダクト側でのサジェストが最多(Sansanではプロダクト上で、開いている機能に関連したヘルプ記事をサジェストしています)
3位:お問い合わせフォーム
上記の現状を踏まえて、以下のような仮説を構築しました。
仮説A
お客様自身が抱える問題を端的に表現しにくい状態のため、検索やFAQ記事の閲覧ではなく、お問い合わせをせざるを得ないのではないか
仮説B
サジェストされたヘルプ記事にはアクセスできるが、コンテンツの内容が不十分なために、お問い合わせをせざるを得ないのではないか
これらの仮説をさらに確かなものにするために、実際のお問い合わせ内容を俯瞰的に確認してみることにしました。
お問い合わせを知る:お問い合わせ内容の俯瞰
お客様がお問い合わせの際に使った言葉でヘルプ記事を検索し、その課題を解決できるヘルプ記事が検索結果の上位3つに表示されるかを調べてみました。
プロジェクトメンバー3人で、1人100件超のお問い合わせを読み込み、かつ判断が偏らないように相互チェックを行いました。
ファクトを取得するための作業の中ではこの作業に最も時間を要しましたが、実情に対する解像度が上がりメンバー間の認識がより揃ったという副次的な効果もあり、価値のあるものになりました。
その結果から、以下のことがわかりました。
お問い合わせの約8割は既存のヘルプ記事の内容で解決するものだった
ただし、そのうちの約7割は、お客様が使った単語で検索しても解決できる記事が検索結果の上位3つに表示されなかった
上記を踏まえると、仮説A・仮説Bともに確からしく、ヘルプサイトを有益にするには「読みたい記事を検索でヒットさせることによる効果が大きいのではないか」という優先的に解決すべき仮説も得られました。
一方で先に書いたイベントの際に、「検索の改善」は検討・実装ともにコストが高いと伺っており、慎重に仕様を策定すべく、実際のお客様の体験を調査することにしました。
お客様を知る:お客様の実体験の想像・調査
私たちは「お困りごとの内容とその解決策」に対してプロフェッショナルであると自負していますが、「お困りごとがあった際に、お客様はどういう行動をするのか」といった体験の解像度が低い状態でした。
餅は餅屋で、体験については体験の専門家に相談しよう!という発想のもと、「Sansanのプロダクトデザイナー」に相談をしました。
プロダクトデザイナーからは、お客様に見立てた人に対して具体的な状況を含めたお題を出し、どこで躓くかを観察する、いわゆる「ウォークスルー」をしてみてはどうかと提案してもらいました。
一例として、以下のような設定でウォークスルーを行いました。
あなたは企業においてメール配信を行う立場である。
先日、2,000人に対しSansanのメール配信機能からセミナーの案内メールを配信した。
配信したメールの開封率を確認するために、配信一覧画面を開いたところ、なぜか「不達」の数字が「10」と表示されていた。
不達の理由は「ユーザー不明」「その他」とあるが、どういった場合にそのようなエラーとなるかの詳細や、不達にならないようにするにはどうすれば良いか、確認したい。
その結果、複数の被験者が次のような体験をしていることを確認しました。
サポートに問い合わせると回答を待たなければならないが、すぐに知りたいのでヘルプサイトに訪れ、「ユーザー不明」というワードで記事を検索した
ヒットした記事のうち上から3番目の記事に答えがあったが、以下の理由から検索結果の羅列を見ても3番目の記事まで開こうとは思わず、解決に至らなかった
そもそも目に入らなかった
タイトルは読んだが、自分が調べたい「不達となった理由」であると思えなかった
言語化できる自信がないため検索はせずに、お問い合わせ窓口を探すことにした
上記を踏まえ、「読みたい記事が上位にヒットしない」「情報はあるが、それが自分が求める記事だとわからない」「検索するための言語化が難しいため探すことを諦めてしまう」の3点を課題として定めました。
得られたファクトを元に打ち手を考える
ここまでの情報を踏まえ、「お客様が検索した言葉に対し、自分が求めるものとわかる記事をヒットさせることができる状態の実現」が打ち手として制定されました。
ではどのようにその状態を実現するのか…については、現在まさに企画進行中のため、またの機会に記事にできればと思います。
最後に
いかがでしたでしょうか。
文字数の関係もあり、なかなか悪戦苦闘した様子を表現できなかったのですが、どのファクトも何度も関係者間の擦り合わせやPDCAを回した結果ようやく得られたものであり、泥臭い側面が多々ありました。
一方で、Webを取り巻くツール類の奥深さや、お問い合わせをする前のお客様の体験に触れ、知識・見解を深めていくことは、とてもやりがいのある面白い作業だったことも書き添えておきます。
「これからヘルプサイトの改善に着手したいが難しい」「今着手しているが煮詰まっている」といった方、ぜひ一緒に楽しみながらヘルプサイト界隈を盛り上げていきましょう!
※ Google、Google Analytics は Google LLC の商標です。
Sansan Technical Support と意見交換していただける方がいればお気軽にご連絡ください。
Sansan Technical Support 大谷・野口
sg@sansan.com
